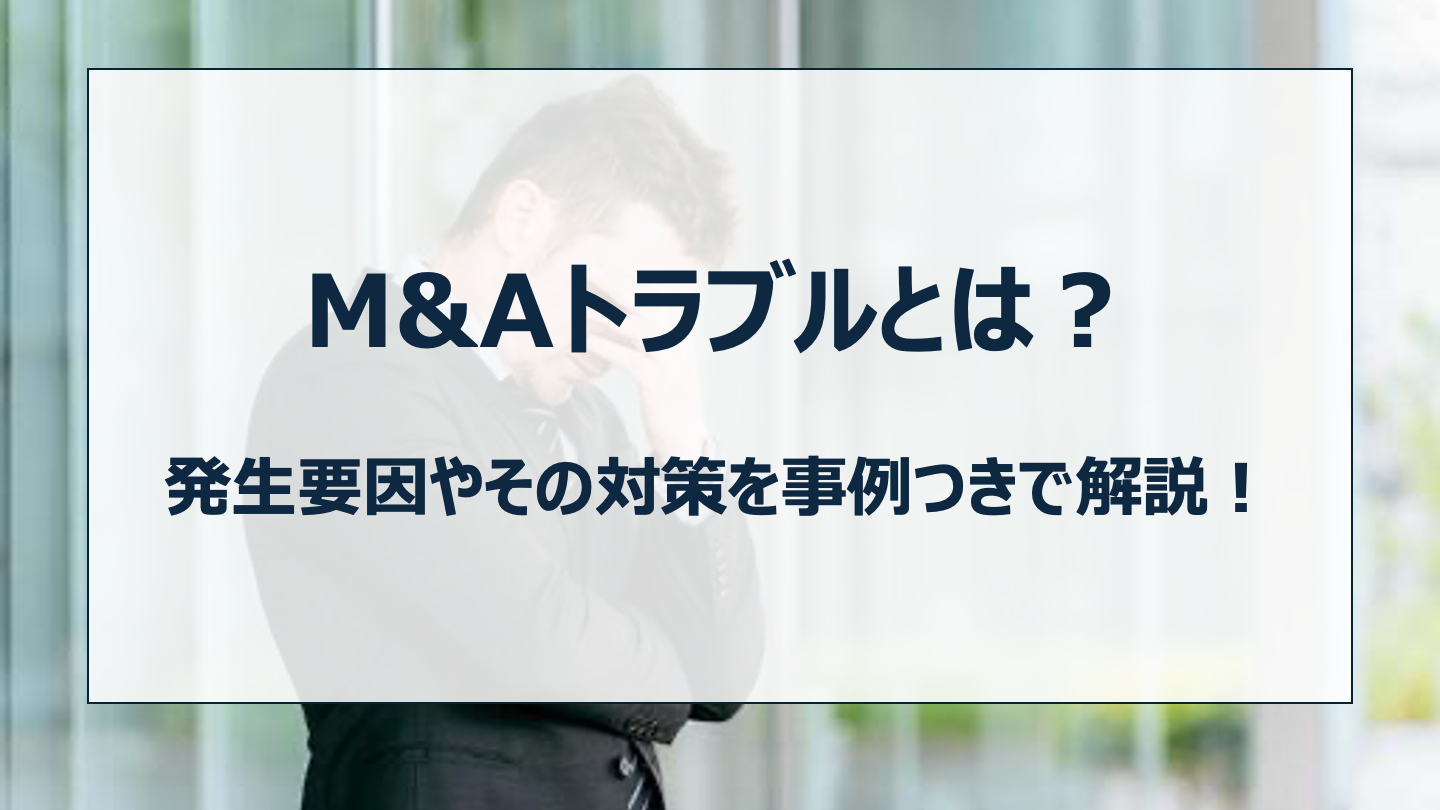
- M&Aでどのようなトラブルが起こるのか分からない。
- M&Aトラブルの要因やそのための対策を知りたい
- M&Aトラブルの具体例を教えて欲しい
このようなお悩みをお抱えではないでしょうか。
M&Aのプロが、売り手と買い手の間で発生しやすいM&Aトラブルの事例、主な原因、対策さらには相談先について解説します。
この記事を読むことで、M&Aトラブルの原因とその対策が分かり、トラブルの発生を未然に防ぐことができるようになります。
1. 主なM&Aトラブル
M&Aトラブルとは、企業同士の合併や買収の過程で発生するさまざまな問題を指し、経営全体に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
こうした問題は、手続きの不備、情報の誤認、契約条件の曖昧さなどが原因で生じることが多く、注意が必要です。
たとえば、十分な事前調査(デューデリジェンス)が行われなかった結果、後日予期せぬリスクが明らかになるケースがあります。
実際には、情報開示の不足により訴訟に発展した企業もあり、その影響は企業のブランド価値や将来の成長戦略にも大きく関わるといえます。
このようなリスクを回避するため、M&Aの初期段階から慎重な検討を重ね、準備と万全の対策を講じる必要があると考えられます。
2. M&Aトラブルの事例
| 事例項目 | 内容 |
| 表明保証条項違反 | 開示内容と実態の不一致が原因で紛争に発展した事例 |
| 少数株主から株式を購入できない | 敵対的な少数株主から株式を購入できず、買収プロセスが滞った事例 |
| 粉飾決算の発覚 | 買収後に企業の内部不正(過去の粉飾決算)が発覚し、財務リスクとなった事例 |
| 知的財産権を侵害 | 買収した会社が第三者の知的財産権を無断使用しており法的トラブルに発展した事例 |
| 従業員への未払給与 | 統合後、従業員への未払いなど労務管理不足により労務トラブルが発生した事例 |
M&Aトラブルの事例は多岐にわたり、実際の現場ではその深刻さが明らかになっています。
このような具体的な事例を学ぶことで、同様のリスクを未然に防ぐための対策が見えてきます。
たとえば、過去の事例では表明保証条項の違反や、買収後の粉飾決算などが大きな問題となったケースがあり、複数の企業でトラブル後に和解や契約条件の再交渉が必要となることもあります。
このような事例からは、事前調査と契約の明確化、そしてトラブル発生時の迅速な対応が不可欠であることが分かります。
2-1. 表明保証条項違反トラブル
合併・買収契約における「表明保証条項」の違反は、双方にとって大きな法的リスクを伴う問題です。
表明保証条項とは、最終契約書に規定される主要な条項であり、M&Aの当事者が相手方に対して、一定の事実を表明し保証するものです。
この条項に定められた内容と実態が一致していた場合、後に大きなトラブルや紛争に発展する可能性が高くなります。
M&Aでは、買い手側が売り手側に対して、「デューデリジェンス」を行いますが、貸借対照表には載っていない内容など、リスクを全て把握できるとは限りません。
そのため、表明保証条項を結び、買い手は一定のリスクから保護される仕組みとなっています。
実際に、ある企業では、売り手の表明保証違反が原因で買い手が巨額の賠償請求を行なったケースがあります。
たとえば、契約締結時に明記されたリスク情報が後に事実と異なり、裁判沙汰となった事例もあります。具体的には、未払い残業代はないと表明しておきながら、実際には未払い残業代があるケースや、売り手企業の設備(工場など)が故障していて、業務を行うために補修するには多額の費用が必要だったケースなどがあります。
このように表明保証条項と実態が異なる場合、損害賠償請求に発展するリスクがあります
そのため、契約締結前の徹底したリスクの検証と双方での合意形成が不可欠です。
2-2. 少数株主から株式を購入できない
M&Aのプロセスにおいて、「敵対的な少数株主」が存在する場合、計画通りの株式取得が難航し、買収プロセスに混乱が生じることがあります。
例えば、少数株主との交渉が決裂し、計画していた買収が頓挫した事例があります。交渉段階での合意形成が不十分であったために、予定していたスケジュールが大幅に遅延したケースも確認されています。さらに、買い手側の足元を見た少数株主から高い株式価格を提示されるケースもあります。
このようなケースでは、敵対的少数株主に対しては「スクイーズアウト(少数株主排除)」の方法を使って、株式を強制買取する方法もありますが、反対株主には株式買取請求権(※)が認められます。つまりこの場合、株式買取価格決定申立を提起されるため、裁判を起こされることも多く、問題が長期化する可能性があります。
※株式買取請求権とは、株主が保有する株式を公正な価格で買い取るように請求できる権利を指します。会社法にて、少数株主の権利を保護するために定められています。
2-3. 粉飾決算の発覚
買収後に売り手企業の粉飾決算をしていた事実が発覚すると、買収企業にとっては深刻な問題となります。
不正な財務情報が明るみに出ると、企業の信用が失墜するためです。
通常、M&Aを締結するまでに、買い手は、対象会社に対してデューデリジェンスを行いますが、事実関係の調査には限界があり、全てのリスクを完全に明らかにすることは困難です。
特に中小企業の場合、会計基準は比較的柔軟です。例えば、大企業であれば粉飾決算となるケースでも、中小企業では粉飾決算とはならないケースがあります。
また、国際会計基準(IFRS)などに従っていない場合であっても、税金の過少申告などの重大な不正がない限り、税務署が指摘するケースは多くありません。
実際の事例として、ある企業では、買収後の内部監査で粉飾決算が発覚し、経営再建を余儀なくされました。このケースでは、退職給付債務や減価償却費が正しく計上されていないというものでした。
事前のデューデリジェンスが不十分であったことが問題の原因と考えられます。
中小企業の場合、決算書を見ているだけでは、売り手企業の実態を完全に把握することは難しいため、M&Aの経験が豊富な税理士や公認会計士に参画してもらい、デューデリジェンスを徹底的に行うことが、リスク回避のために非常に重要です。
2-4. 知的財産権を侵害
買収先企業が第三者の知的財産権を侵害していた場合、重大な法的リスクに直面します。
権利関係の不備があると、訴訟や賠償問題に発展する可能性があります。
たとえば、ある企業は、M&A買収後に著作権侵害で訴えられ、多額の損害賠償を支払う結果となりました。
実際に、第三者から著作権侵害の通知がきた場合、まず、契約書に表明保証条項として、「売り手側が第三者の権利を侵害していないこと」の文言が記載されているか確認してください。
その上で、著作権侵害があったのかどうか専門機関に調査を依頼すべきです。著作権侵害が事実であれば、表明保証に基づき売り手に補償を求めることが可能ですが、買い手側がデューデリジェンスを怠っていた場合は、損害賠償を請求できない可能性もあります。
つまり、売り手会社において著作権侵害があり、損害を被った場合は、買い手が売り手に対して契約書の表明保証の規定に基づいた補償責任を求めることができます。
つまり、事前に知的財産権の状況を把握しなかったことが原因でトラブルが発生した場合、買い手は自己責任を問われる可能性が高くなります。
このようなトラブルを避けるためにも、デューデリジェンスの段階で、知的財産権に関する十分な調査を行うことが重要です。
2-5. 従業員への未払給与
買収後に未払給与問題が明らかになると、従業員の士気が低下し、労務トラブルを引き起こす可能性が高くなります。
給与の未払いが発覚すると、従業員の信頼が損なわれ、企業全体の運営に悪影響を与えるため、非常に重要です。
従業員への未払給与がある場合、買い手は売り手に対して補償や損害賠償を請求できる可能性があります。
まずは、売り手と締結したM&A契約書等を確認しましょう。買い手が損失を被った場合に、売り手に対して補償や損害賠償を請求できる規定があるか、確認する必要があります。
例えば、契約書内に、「売り手は、従業員等に対する給与の未払いによって買い手に経済的な負担が生じた場合、直ちに補償する。」という旨の記載があれば、買い手は売り手に対して、補償請求や損害賠償請求を行うことが可能です。
一方で、M&A後に発生した未払給与は、売り手に請求できないことがあります。M&Aで買収後、買い手が経営を行っている中で、従業員との関係が悪化し、未払給与を請求されるという買い手に責任がある場合、売り手に対して、補償請求や損害賠償請求が行えないことがあります。
また、買い手側がデューデリジェンスを適切に実施していなかった場合も注意が必要です。M&Aプロセスにて気付けなかった場合も、例え表明保証条項があったとしても損害賠償を受けられない可能性があります。
このようなトラブルを回避するためには、買収前のデューデリジェンスにおいて、労務面、特に給与支払状況の確認を徹底することが重要です。
3. M&Aトラブルの原因
| 原因 | 説明 |
| デューデリジェンス(DD)の不十分さ | 事前調査不足により隠れたリスクが見逃される。 |
| 情報開示が不正確 | 重要事項の誤情報により、後のトラブルの種となる。 |
| 契約条件が不明確 | 契約の曖昧さが後の解釈違いや争議を引き起こす。 |
| PMIの不備・遅延 | 統合計画の遅れがシナジー効果の発現を阻害する。 |
| 人事・労務トラブルの顕在化 | 組織再編に伴う労務管理の不備が従業員の不満に繋がる。 |
| 法令違反・コンプライアンス不備 | 法令遵守の甘さが法的リスクを増大させる。 |
| 利害関係者との調整不足 | 株主や取引先との交渉不足が、統合後の混乱を招く。 |
M&Aトラブルの発生原因は多岐にわたり、事前の準備不足がその根本にあることが多いです。
各要因が作用することで、合併・買収後に大きな混乱を招いてしまいます。
たとえば、デューデリジェンスの不十分さからくる情報の誤認や契約条件の曖昧さが、後のトラブルの発端となるケースが確認されています。具体例として、初期段階でのリスク評価が甘かったために、統合プロセスが遅延し、結果として経営全体に悪影響を及ぼした事例があります。
このため、各原因を正確に把握し、対策を講じることがトラブル回避の鍵となると考えられます。
3-1. デューデリジェンス(DD)の不十分さ
M&Aにおいては、事前調査(デューデリジェンス)が十分に実施されないと、後に重大なリスクが顕在化する可能性があります。
たとえば、ある買収案件では、財務状況や法的リスクの調査が不十分であった結果、後日予期せぬ負債が発覚し、全体の評価が大きく下がった事例があります。具体例として、現地調査や専門家による評価が不十分であったために、交渉後に重大な不具合が明らかになったケースが確認されています。
そのため、信頼のおける公認会計士や税理士などの士業に依頼するのが良いといえます。
このように、徹底したデューデリジェンスの実施は、トラブル回避のための基本対策といえるでしょう。
3-2. 情報開示が不正確
正確な情報開示は、M&A成功の基盤であり、不正確な情報は後のトラブルを引き起こす大きな要因となります。情報の誤りがあれば、買い手側が予想外のリスクを抱え込む結果となるためです。
実例として、ある企業では、重要な財務情報の誤記載により、交渉後に大きな見直しを迫られたケースがあります。具体的には、開示内容が不完全であったために、後日訴訟問題に発展し、双方にとって大きなコスト負担となった事例が報告されています。
したがって、正確かつ詳細な情報開示が、M&Aプロセス全体の信頼性を保つ上で不可欠であると考えられます。
3-3. 契約条件が不明確
契約条件の不明確さは、M&A後の解釈の違いや争議の原因となり、企業間の信頼関係を損なうリスクがあります。曖昧な条項が残ると、後のトラブル発生時に双方で認識のずれが生じやすいためです。
たとえば、実際の事例では、契約書の不備が原因で、買収後に責任の所在が明確にならず、紛争に発展したケースが確認されています。具体例として、条項の具体性に欠けた契約が、後日の交渉で解釈の相違を生み、双方にとって大きな損失となった事例があります。
このため、契約書作成時には詳細な記述と明確な合意形成が求められ、トラブルの未然防止につながるといえるでしょう。
3-4. PMI(Post Merger Integration)の不備・遅延
統合プロセスであるPMIが不備または遅延すると、予定していた買収後のシナジー効果が発揮されず、企業全体の業績に悪影響を及ぼします。統合計画が不十分であれば、組織間の連携が取れず、運営上の混乱が生じるためです。
実例として、ある企業では、PMI計画が不十分だったことが原因で、合併後の組織再編が長期化し、収益改善が遅れた事例が見受けられました。具体的には、事前に策定された統合計画が十分に実行されず、現場レベルでの調整不足が顕在化したケースが報告されています。
このように、PMIの計画と実行の両面を徹底することが、M&A成功のために非常に重要になるでしょう。
3-5. 人事・労務トラブルの顕在化
M&Aでは、従業員の配置転換や労務条件の変更が生じるため、人事・労務トラブルが発生しやすくなります。
適切な対応がなされないと、従業員の不満が増大し、企業全体の士気低下に直結するためです。実例として、統合初期に労務管理の調整が不十分だったため、労働争議が発生し、業務に支障をきたした企業があります。
具体例では、従業員への十分な説明が行われなかった結果、内部からの離職が相次ぎ、統合プロセスに大きな混乱を招いた事例が確認されています。このため、事前の人事戦略の策定と、統合後の迅速な労務対応が求められます。
3-6. 法令違反・コンプライアンス不備
M&Aの過程で法令やコンプライアンスを軽視すると、後日法的制裁や社会的信用の失墜に繋がる危険性があります。
法令遵守が不十分であれば、企業全体に対する監視の目が厳しくなり、罰則が科せられるリスクが高まります。
たとえば、ある事例では、内部統制が不十分であったために、法令違反が発覚し、莫大な罰金を支払う結果となったケースがあります。具体的な補足として、コンプライアンス体制の整備がなされていなかったことで、従業員からM&Aに関する情報が外部に漏れてしまい、取引先や株主からの信頼を失った事例が報告されています。
このため、M&Aプロセスにおいては、初期段階から法令遵守の徹底と内部統制の強化が不可欠であるといえるでしょう。
3-7. 利害関係者(株主・取引先・金融機関等)との調整不足
M&Aは多くの利害関係者が関与するため、事前の調整が不十分だと後の混乱に直結します。
各ステークホルダーとの十分なコミュニケーションが取れなければ、誤解や不信感が生じ、全体のプロジェクト進行に影響を及ぼすためです。
実際、ある企業では、株主や金融機関との連携不足が原因で、合併後に資金調達や取引条件の再調整を迫られた事例があります。具体例として、交渉段階での情報共有が不足していたために、各方面からの異議申し立てが相次ぎ、プロジェクトの進行が大幅に遅延したケースが確認されています。
したがって、関係者全員との緊密な調整とコミュニケーションが、M&A成功のための基本戦略となります。
4. M&Aトラブルの対策
M&Aトラブルを未然に防ぐためには、初期段階からの万全な対策が不可欠であり、各段階での注意が求められます。
適切な情報開示や詳細な契約書の作成、さらにはPMI計画の策定が重要な役割を果たすためです。
たとえば、事前に正確な情報を提供し、リスクを十分に評価することで、後のトラブル発生を大幅に低減できたケースがあります。具体的な補足として、各対策が実施された結果、実際の統合プロセスが円滑に進み、予期せぬリスクが回避された事例が多数報告されています。
このように、各対策を着実に実行することが、M&A成功のための重要な要素となるでしょう。
| 対策項目 | 内容 |
| 初期段階での正確な情報開示 | 事前に全てのリスクや情報を正確に提示する。 |
| デューデリジェンス(DD)の徹底 | 徹底した調査によりリスクを洗い出し、対策を講じる。 |
| 適切な契約書の作成・法的チェック | 明確な契約条件と専門家によるチェックでトラブルを回避する。 |
| PMI計画の事前策定 | 統合計画を詳細に策定し、スムーズな実行を図る。 |
| 利害関係者への丁寧な説明・交渉 | すべての関係者と十分なコミュニケーションを図る。 |
| コンプライアンスと法令遵守の徹底 | 法令遵守を徹底し、内部統制を強化する。 |
4-1. 初期段階での正確な情報開示
M&Aプロセスの初期段階で正確な情報を開示することは、トラブル回避の第一歩となります。初期の段階でリスクを明確にすることで、後々の誤解や不信感を防ぐ効果が期待できるためです。
たとえば、ある企業では、初動で詳細な財務情報や事業リスクを共有することで、買収後の不測の事態を未然に防いだ事例があります。具体例として、透明性の高い情報開示により、関係者全体の信頼を獲得し、スムーズな交渉が進んだケースが報告されています。
このように、初期段階から正確な情報提供を徹底することが、M&A成功のための重要な対策となります。
4-2. デューデリジェンス(DD)の徹底
デューデリジェンスを徹底することは、M&Aにおけるリスクの発見と対策に直結します。詳細な調査が行われなければ、隠れたリスクが後になって見つかる可能性を生み、大きな問題に発展するためです。
実際、ある買収案件では、徹底したDD調査により潜在的な問題点を早期に発見し、交渉条件の見直しが行われた事例があります。具体例として、外部専門家を起用して各分野のリスクを洗い出し、事前に改善策を講じたケースが成功の要因となりました。
したがって、DDの徹底は、M&Aプロセスにおける信頼性確保とリスク軽減のために不可欠な要素であるといえます。
4-3. 適切な契約書の作成・法的チェック
契約書の内容が明確であれば、後々の解釈違いや争議を未然に防ぐことが可能となります。専門家による法的チェックが行われることで、契約条件の不明瞭さが原因となるリスクが大幅に低減されるためです。
たとえば、ある企業は、契約締結前に専門の法律事務所に依頼して詳細なチェックを実施し、その結果、後のトラブルを回避した事例があります。
具体例として、契約書に明確な条項を盛り込み、双方が合意した内容を文書化することで、後日の紛争発生を防いだケースが報告されています。このため、適切な契約書作成と法的チェックは、M&Aプロセスの安全性を高めるための重要な施策であると認識されます。
4-4. PMI(Post Merger Integration)計画の事前策定
買収後の統合計画を事前に策定することは、スムーズな組織統合を実現するために不可欠です。統合計画が整備されることで、各部署間の連携が強化され、シナジー効果が最大限に引き出されるためです。
実例として、ある企業は、事前に詳細なPMI計画を策定し、買収後の組織再編を円滑に進めた結果、業績向上に成功した事例があります。
具体例として、計画段階で各部門の役割分担やスケジュールを明確に定めたことで、統合に伴う混乱が最小限に抑えられたケースが確認されています。このように、PMI計画の事前策定は、M&A後の統合プロセスを成功に導くための必須対策であるといえます。
4-5. 利害関係者への丁寧な説明・交渉
M&Aにおいては、株主や取引先などの利害関係者への説明が十分でなければ、信頼関係が損なわれるリスクが高まります。適切なコミュニケーションと交渉を行うことで、各関係者の不安を払拭し、円滑なプロセス進行が期待できます。
実際に、ある企業では、定期的な説明会や個別面談を実施することで、関係者からの理解を得た事例があります。具体例として、買収前後の情報共有を密に行い、各ステークホルダーと協議を重ねた結果、トラブル発生を未然に防いだケースが報告されています。
このため、利害関係者への丁寧な説明と交渉は、M&Aプロセス全体の成功に直結すると考えられます。
4-6. コンプライアンスと法令遵守の徹底
コンプライアンスの徹底は、M&Aにおける法的リスクを回避するための最も重要な対策です。法令遵守が徹底されれば、将来的な法的トラブルや社会的信用の失墜を防ぐことが可能になります。
たとえば、ある企業は、内部統制の強化と定期的な監査を実施することで、法令違反のリスクを大幅に低減した事例があります。具体的には、コンプライアンス体制を整えた結果、取引先や金融機関からの信頼を維持し、安定した経営基盤を確立したケースが確認されています。
このように、法令遵守と内部統制の強化は、M&A全プロセスにおいて必ず実施すべき重要な対策であるといえます。
5. M&Aトラブルに巻き込まれないためのM&Aの相談先
M&Aに関するトラブルを未然に防ぐためには、専門機関や相談窓口を活用することが有効です。信頼できるパートナーと連携することで、複雑な案件にも的確な助言を受けることができます。
たとえば、実際に事業承継支援センターや弁護士事務所と連携することで、リスク回避に成功した企業の事例があります。各専門機関が持つ豊富な経験と専門知識により、M&Aプロセスの初期段階からリスク管理が徹底されるためです。
以下に代表的な相談先を紹介します。
| 相談先 | 内容 |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 経営者向けの事業承継や引継ぎの専門相談を提供 |
| 弁護士・税理士・会計事務所 | 法務、税務、会計の観点からリスク管理をサポートする |
| M&Aマッチングサイト | 買い手と売り手のマッチングを支援し、情報提供をサポートする |
| M&A仲介会社 | M&A全体をサポートし、交渉や契約の調整を支援する専門業者 |
| 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA) | 中立的立場から戦略立案や資金調達について助言を行う |
5-1. 事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、企業の円滑な引継ぎとリスク管理を支援する公的機関です。各分野の専門家が連携し、経営者に対して具体的なアドバイスを行います。
たとえば、実際にこのセンターのサポートを受けた企業では、事前のリスク評価が徹底され、M&A後のトラブルが回避された事例があります。事業承継計画の策定と同時に、経営戦略の再構築がスムーズに進んだ好例です。このように、事業承継・引継ぎ支援センターの活用は、経営者にとって大きな安心材料となるといえるでしょう。
5-2. 弁護士・税理士・会計事務所
法務、税務、会計といった専門領域は、M&Aにおいて不可欠な専門家です。専門家の助言があれば、契約書の作成やリスク管理をより正確に行うことができます。
実例として、ある企業では、複数の専門事務所と連携することで、情報開示や契約内容の精査が徹底され、トラブル回避に成功したケースがあります。法的チェックや財務調査が十分に行われた結果、買収後の統合が円滑に進んだ好例です。
信頼できる専門家のネットワークは、M&A成功のために欠かせません。会社と普段から取引のある事務所があれば、まずは相談してみるのも良いでしょう。
5-3. M&Aマッチングサイト
M&Aマッチングサイトは、売り手と買い手を効率的に結びつけるプラットフォームです。
情報の透明性が高く、迅速なマッチングが可能なため、双方にとって有益な環境が整えられています。
たとえば、ある事例では、マッチングサイトを通じて適切な相手先が見つかり、交渉が円滑に進んだケースがあります。サイト上での事前審査や評価システムが、双方の信頼性向上に寄与した好例です。M&Aを検討する際は、こうしたマッチングサイトの活用がリスク低減に大いに役立つといえるでしょう。
5-4. M&A仲介会社
M&A仲介会社は、M&A専門家として買収・売却の交渉から契約締結までをサポートする専門のパートナーです。煩雑な手続きやリスク管理を行なってくれるので、経営者の負担を軽減できます。
ある企業では、仲介会社のサポートにより、問題発生前に迅速な対策を講じることができました。仲介会社が持つ豊富な実績と専門知識を活かし、交渉過程での不明点を解消した好例です。
M&A仲介会社の支援は、プロジェクトの成功とリスク回避において非常に重要であると評価されています。
5-5. 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
独立系ファイナンシャルアドバイザーは、中立的な立場から買収・売却戦略の策定や資金調達のアドバイスを提供します。
客観的な視点でリスクを評価し、最適な戦略を提示するため、企業の経営判断に大きなプラス効果をもたらすのです。
たとえば、ある企業では、IFAの助言により、最適な買収条件が整い、資金計画も安定した事例があります。具体例として、特定の金融機関に属さない独立した専門家の助言が、経営者の判断材料として重視され、交渉力の向上に寄与したケースが報告されています。
したがって、IFAの活用は、M&Aプロセス全体の安全性と効率性を高めるために有効な手段であるといえます。
6. まとめ
M&Aトラブルは、情報開示の不備や契約条件の曖昧さ、統合プロセスの遅延など、さまざまな要因によって引き起こされる重大なリスクです。
これらを防ぐには、各段階でのリスク管理や専門家のサポートが不可欠です。事前の徹底した調査と透明性のある情報開示が成功の鍵となります。
具体的な事例や対策、相談先の活用方法を学ぶことで、経営者は万全の備えを講じることが可能です。
今後、企業間の信頼関係や経営戦略の成功を実現するためにも、M&A専門家の知識を活用し、慎重かつ計画的なM&Aの推進に努めることが求められるでしょう。
IFAのファーストパートナーズでは、経営者の引退後の資産運用も見据えた、ワントップでのM&Aサポートを提供しています。万が一M&Aトラブルが起こった際にも、対応できるサポート体制が整っておりますので、後継者問題を抱える経営者の方は、この機会に是非一度相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。

