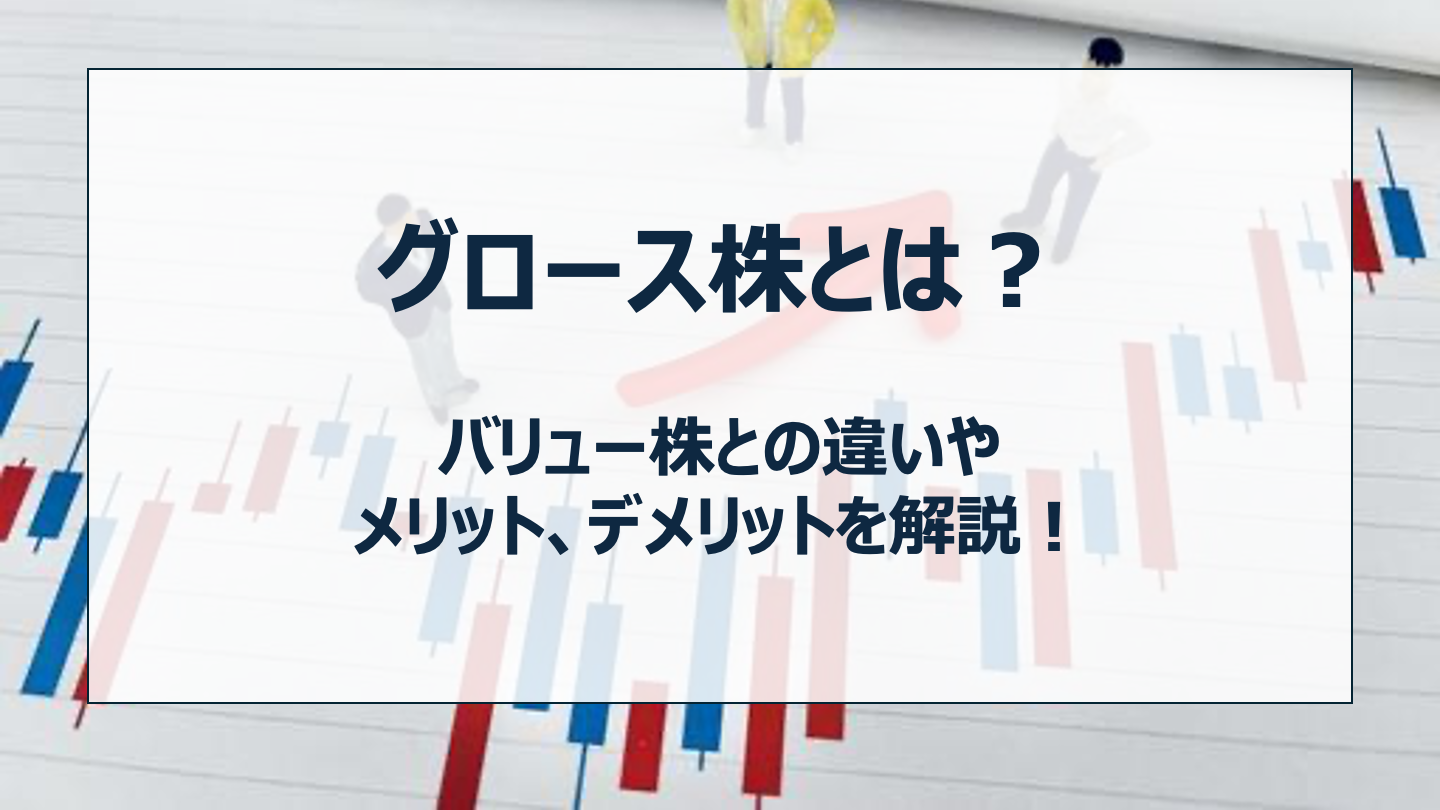
- グロース株の特徴がよく分からない
- バリュー株との違いを整理したい
- メリットやリスクを理解したうえで投資判断したい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
資産運用のプロが、グロース株投資について解説します。
この記事を読むと、グロース株投資のメリットやデメリットが分かり、グロース株投資をするべきかどうか判断できるはずです。
1. グロース株とは?
グロース株の一般的な意味やグロース株が注目されている理由について解説します。
1-1. 一般的な意味
グロース株とは、革新的なビジネスモデルを展開し、今後の売上や利益の大幅な拡大が期待される企業の株式を指します。
例えば、ITやバイオテクノロジー分野の企業が挙げられ、これらの企業は積極的な研究開発やグローバル展開により業績の向上が期待される場合が多く、投資家の注目を集めています。
また、2024年に生成AIブームが到来し、生成AIを開発する企業や生成AIを提供する企業の取り組みが注目されました。
このような企業は、業績の急成長や将来の収益性への期待から株価が上昇する傾向があります。
このように、グロース株は将来の成長性と革新性を兼ね備えた企業への投資機会として認識され、今後の市場展開に大きな期待が寄せられています。
1-2. なぜグロース株が注目されているのか
グロース株が注目されるのは、企業の成長期待が株価上昇に直結する可能性が高いからです。
成長企業は新規事業の拡大や技術革新を通じて、既存市場に革新をもたらすと期待されています。
実際に、近年ではインターネットサービスやフィンテック関連の企業が市場で急速にシェアを拡大しており、業界全体さらには株式市場全体で大きな影響力を持つ存在となっています。
2. グロース株とバリュー株の違い
| 観点 | グロース株 | バリュー株 |
| 定義 | 将来的な成長性が高く、業績の急拡大が期待できる銘柄 | 現在の企業価値に対して市場価格が割安と評価される銘柄 |
| 売上高成長率 | 今後の急激な売上高拡大が見込まれるため、短期間での大きな成長が期待される | 急激な伸びよりも持続的な売上高の安定性が重視される |
| 営業利益成長率 | 経営基盤の安定化、事業効率性の向上により、営業利益急増が見込まれる | 堅実な成長を示す傾向がある |
| PER(株価収益率) | PERが高くなる傾向にある。 | 現在の収益水準に対し株価が割安に評価されるため、PERが低くなる傾向にある |
| PBR(株価純資産倍率) | PBRが高くなる傾向にある | 現在の資産価値に対し株価が割安に評価されるため、PBRが低くなる傾向にある |
それぞれ以下で解説します。
2-1. バリュー株とは?
バリュー株は、実際の企業価値に比べて市場価格が割安と判断される銘柄を指します。
業績や企業価値に対して株価が低く評価されている場合が多く、投資家は潜在的な割安感に魅力を感じます。
例えば、成熟期に属する企業では、安定した収益基盤がありながらも株価が低迷した場合、財務情報を基に評価される株価指標からも割安感が見出されることがあります。
さらに、こうした企業は将来的な回復や業績改善期待から、特に慎重に銘柄選択をしたい人にとって魅力的な投資先になるでしょう。
このように、バリュー株は企業の実態に基づく投資戦略として理解されています。
2-2. 売上高成長率
グロース株と呼ばれる企業の売上高は、その急激な伸び率が特徴です。
新製品や新サービスを次々と市場に投入し、需要の拡大に努めるためです。
例えば、急成長中のIT企業やスタートアップ企業が爆発的な売上高を記録することで、投資家は将来の収益拡大を期待します。
さらに、売上高の伸び率が高い企業は、資金調達や事業拡大に有利な環境を享受できるため、今後の持続的な成長が期待されるようになります。
このように、売上高成長率はグロース株の魅力を示す重要な指標です。
2-3. 営業利益成長率
グロース株と呼ばれる企業は、営業利益成長率が高い点も評価できます。
これは、企業が効率的な経営を実践し、収益構造の改善に注力していることが背景にあります。
このような企業は、さらなる市場シェア獲得、ビジネス拡大を優先した多額の先行投資を行っているケースが多く、営業利益が出ていない(赤字である)ことも珍しくありません。
しかし、伝統的な経営手法に捉われず、先進的な経営手法やコスト削減策を取り入れることで、短期間で大幅な利益成長を実現する可能性があります。
また、利益成長率が高い企業は、さらなる研究開発費や設備投資の拡大に伴う事業拡大が期待されるため、株式市場でも評価されるでしょう。
さらに、この指標は企業の経営効率や競争力を示す重要な根拠となります。
2-4. PER(株価収益率)(₌株価÷1株当たり利益(EPS))
グロース株は、一般的にPERが高くなる傾向があります。
理由は、株価が企業の将来的な成長期待を強く織り込んでいるためです。この場合、現在の利益に対して割高と評価がされる場合があります。
この指標は企業の収益性と株価のバランスを図る上で欠かせない要素です。
※投資判断の際には、割安感や割高感だけではなく企業の実態や将来の見通しなどを総合的に分析することが大切です
※PERは、同業種や業界平均と比較することで、相対的な割安・割高を判断する材料となります
2-5. PBR(株価純資産倍率)(₌株価÷1株当たり純資産(BPS))
グロース株は、PBRが相対的に高くなる傾向があります。
前述のPER同様に、株価が企業の将来的な資産価値や成長ポテンシャルを高く評価しているために起こります。そのため、現在の純資産に対して割高と評価される場合があります。
一方で、PBRの高さは企業の成長力と今後の資産形成能力を示す指標としても有益な情報です。
※投資判断の際には、割安感や割高感だけではなく企業の実態や将来の見通しなどを総合的に分析することが大切です
※PBRが高ければ高いほど割高、低ければ低いほど割安と判断できます。一般的にPBRが1倍未満の場合、株価は割安と考えられます。
3. グロース株投資のメリット
| No. | メリット |
| 1 | 株価の値上がりによる大きな売却益を期待できる |
| 2 | 成長期待を背景に、中長期の資産形成にも活用できる可能性がある |
| 3 | 未来の社会やビジネスを学べる |
それぞれ以下で解説します。
3-1. 株価の値上がりによる大きな売却益を期待できる
グロース株投資の最大の魅力は、株価の急上昇による大きな売却益を期待できる点にあります。
企業の急速な成長が株価に反映されるため、投資タイミングを捉えることで高いリターンを期待することができます
成長企業が新規事業やグローバル展開を成功させた結果、短期間で株価が大幅に上昇するケースもあります。投資家がリスクを取ってグロース株に資金を投じる理由のひとつです。
グロース株投資はタイミングさえ見極められれば大きな利益を生む可能性が高く、その点で非常に魅力的な投資対象となります。
3-2. 成長期待を背景に、中長期の資産形成にも活用できる可能性がある
グロース株の中には、将来の業績拡大が期待されている企業が多く存在します。
そのため、企業の成長性に賭けるという意味で中長期投資に用いられることもあります。例えば、クラウドサービスやAIなど将来の社会インフラを担うと目される企業に対しては、長期的な株価上昇を見込んで投資がなされる傾向があります。
ただし、「好業績=グロース株」という単純な構図ではありません。グロース株には、現在の業績が赤字でも、将来的な飛躍が見込まれて株価が上昇しているケースもあります。
そのため、例えばFANG銘柄のように結果的に中長期投資として成功した事例ばかりではなく、予想に反して株価が大幅に下落してしまうケースもあることには注意が必要です。中長期で保有する場合には、定期的な株価動向をチェックし、リスク管理することが不可欠です。
3-3. 未来の社会やビジネスを学べる
グロース株への投資は、将来の値上がり益を狙うだけではなく、これからの社会やビジネスの変化を知るきっかけにもなります。
グロース株の多くは、AI、再生可能エネルギー、クラウドサービス、バイオテクノロジーなど、最先端の分野で急成長している企業です。これらの企業がどのような技術やサービスで社会課題を解決しようとしているのかを知ることで、時代の流れや今後注目されるであろう産業を学ぶことができます。
また、成長企業の事業内容や戦略を調べる過程で、財務情報の見方や市場トレンドの捉え方など、投資の基礎知識を自然に身につけることができます。
つまり、グロース株投資は「お金を増やすための行動」であると同時に、未来を見据える目を養う“学びの場”にもなるのです。
4. グロース株投資のデメリット
| No. | デメリット |
| 1 | リスクが高い |
| 2 | 配当性向が低い |
以下でそれぞれについて解説します。
4-1. リスクが高い
グロース株は、将来の成長性を期待され投資される企業が多いため、株価の変動幅(ボラティリティ)が大きくなる傾向があります。
この「変動幅の大きさ」が、投資におけるリスクの高さを意味します。
例えば、ある企業に対して多くの投資家が将来の業績拡大を期待し、結果として株価が急上昇したとしても、ひとたび業績予想を下回る決算が出たり、社会情勢が不安定になったりすると、失望売りを誘発し、株価が急落することがあります。
特にグロース株は、実績よりも期待が先行して株価が形成されることが多いため、期待と現実のギャップに大きく左右されやすいのです。
大きな利益を期待できる可能性がある反面、損失も大きくなる可能性があるという点を理解しておくことが重要です。
4-2. 配当性向が低い
グロース株は、成長戦略を重視するため、配当性向が低い傾向にあります。配当利回りが低かったり(配当金の支払い方針がなかったり)、株主還元を重視しないなどが挙げられます。これは、企業が内部留保を確保し、事業への再投資に注力し将来の成長を優先するためです。
具体的には、研究開発や設備投資に資金を充て、一時的な配当政策を後回しにすることで、結果的に将来の株主還元に繋がると考えられています。
5. まとめ
グロース株は、企業の革新性と将来性を重視した投資対象として、多くの投資家から注目を集めています。
その成長力は、売上高や利益に表れますが、その魅力と同時にリスクも内包している点には注意が必要です。
投資戦略の選択には十分な知識と慎重な判断が求められます。資産形成の一部としてグロース株投資を戦略的に活用する際には、各株価指標や市場動向などの理解を深め、投資リスクの低減とリターンの最大化を図ることが大切です。

