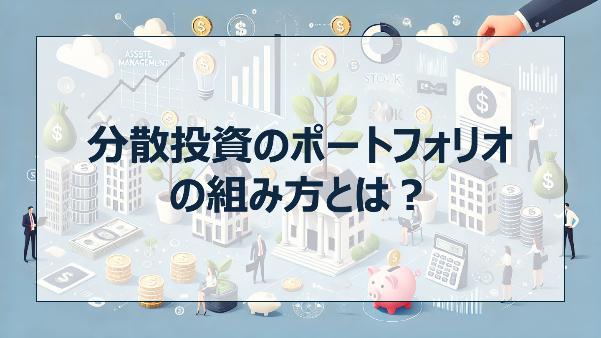
- 分散投資のポートフォリオの組み方が分からない
- 具体的な分散投資のポートフォリオが知りたい
- 少額からできる分散投資について知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
資産運用のプロが、分散投資のポートフォリオの組み方について解説します。
この記事を読むと、分散投資に関する不安を解消でき、ポートフォリオの設計に役立つでしょう。
1. 分散投資のポートフォリオの組み方
分散投資によるポートフォリオ構築は、
以下の4つのポイントを押さえることで、自分に合った効率的な運用がしやすくなります。
- 投資の目的と期間を決める
- リスク許容度を確認する
- 異なる資産クラスに投資する
- 分散投資の基本的な考え方を理解する
以下で、それぞれについて解説します。
1-1. 投資の目的と期間を決める

資産運用を始める際には、まず投資の目的と期間を明確にしましょう。
目的が老後資金の準備であれば、長期的な視点での運用が求められます。一方、住宅購入の頭金を貯めるなど使途の決まった短期的な目標であれば、リスクを抑えた運用が適している可能性があります。
例えば老後資金の準備を目的とする場合、20年後に必要な金額を設定し、期待リターンを考慮して逆算することで、毎月の積立額や、具体的な運用計画を決めることができるでしょう。
このように、目的と期間を明確にすることで、自分に合った投資戦略を選択しやすくなります。
1-2. リスク許容度を確認する
投資においては、自分がどれだけのリスクを許容できるかを理解することが不可欠となります。
リスク許容度は、年齢、収入、資産状況、性格などによって異なります。
例えば、安定した収入があり、長期的な運用が可能な30代の方は、株式の比率を高めたポートフォリオを選択することができます。
一方、退職が近い60代の方は、元本割れのリスクを避けるために、安定資産である国内債券や預金の比率を高めることが望ましいでしょう。
自分のリスク許容度を正しく把握することで、無理のない投資を継続することが可能になります。
1-3. 異なる資産クラスに投資する
分散投資を効果的に行うためには、資金を異なる資産クラスに分けて投資することが重要です。
主な資産クラスには、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、不動産(不動産投資信託)、金などがあります。これらの資産は、それぞれ異なるリスクとリターンの特性を持っており、組み合わせることで全体のリスクを抑えることができます。
例えば、株式と債券は一般的に逆の値動きをする傾向があるため、両者を組み合わせることでポートフォリオの安定性が高まるでしょう。
このように、資産クラスを分けて考えることで、リスクを分散しながらリターンを追求することが可能となります。
1-4. 分散投資の基本的な考え方を理解する
分散投資の基本は、「卵を一つのかごに盛るな」という投資の格言に象徴されます。
これは、特定の資産に集中投資することで、特定資産の影響が大きくなることを防ぐためです。
例えば、国内株式だけに投資していた場合、日本経済の不調が直撃し、資産全体が大きく目減りする可能性があります。
一方、国内外の株式や債券、不動産などに分散して投資していれば、ある資産の損失を他の資産の利益で補うことができるでしょう。
このように、分散投資はリスクを抑えながら安定したリターンを目指すための有効な手段となります。
1-5. ポートフォリオを組む
ポートフォリオを組む際には、前述のリスク許容度や投資目的、資産クラスの特性を踏まえて、それぞれにあった資産配分を決定します。
例えば、リスクを抑えたい場合は、債券の比率を高めることで安定性を確保できます。一方、高いリターンを目指す場合は、株式の比率を増やすことで成長性を追求できるでしょう。
また、定期的にポートフォリオを見直し、市場環境やライフステージの変化に応じて資産配分を調整することも重要です。このように、自分に合ったポートフォリオを組むことで、長期的な資産形成を実現することができます。
2. 【年齢別】分散投資のポートフォリオ例
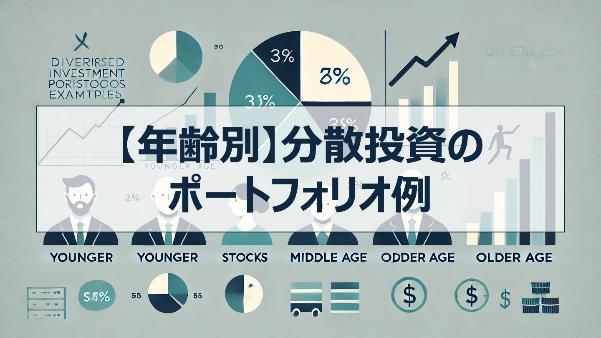
年齢やライフステージに応じてリスク許容度や運用期間が変わるため、それぞれに適したポートフォリオを組むことが重要です。
以下の3つの年代別プランを参考に、自分の状況に合う資産配分を検討することをおすすめします。
- 20代〜30代
- 40代〜50代
- 60代〜70代
以下でそれぞれの年代について解説します。
2-1. 20代〜30代
若い世代は、時間を味方につけて積極的な投資戦略を採ることが可能です。
長期的な視点でリスクを取り、成長性の高い資産に重点を置くことで、資産形成を加速させられる可能性があります。
例えば、米国株式型インデックス投資信託を40%、新興国インデックス投資信託を30%、国内株を30%、としたポートフォリオにすると、リスク投資対象を分散しながら高リターンを狙います。
若いうちから積極的に投資を行うことで、将来的な資産形成に大きな差が生まれる可能性があります。
2-2. 40代〜50代
中年期は、老後資金の準備を本格化させる時期です。
リスクとリターンのバランスを取りながら、安定した資産運用を目指すことが重要です。
例えば、全世界株式型インデックス投資信託を40%、日本株式型インデックス投資信託を20%、東証REIT指数型インデックス投資信託を20%、国内債券を20%といったポートフォリオにすると、成長性と安定性を両立させることが期待できます。
将来の生活資金を確保するためにも、安定性にも重点を置いた計画的な資産運用が求められます。
2-3. 60代〜70代
60代以降は、資産の保全や安定的な収入の確保がより重視される時期です。リスクを最小限に抑えつつ、生活資金を確保するためのポートフォリオが求められるでしょう。
例えば、国内債券50%、日本もしくは米国の高配当ETFを30%、東証REIT指数型インデックス投資信託を20%といったポートフォリオにすると資産の目減りを防ぎつつ、安定的な収入が期待できるでしょう。
老後の生活を安心して送るためにも、慎重な資産運用が必要です。
3. 【初心者向け】少額から始める分散投資の方法
少額から始める分散投資は、リスクを抑えながら投資に慣れていくのに有効な方法です。最初は小さな金額から始め、相場の動きや自分の投資スタイルに慣れていくことで、安心感を持ちながら資産形成を進められます。
具体的には、以下の方法を組み合わせると効果的でしょう。
- NISAを活用する
- 投資信託を活用する
以下で、それぞれについて解説します。
3-1. NISAを活用する
少額から投資を始める際には、NISAの活用をおすすめします。
NISAとは、年間一定額までの投資に対して、配当や売却益が非課税(通常は配当や売却益に20.315%税金がかかります)となる制度であり、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの枠があります。
つみたて投資枠は、年間120万円(成長投資枠を使わなければ最大1,800万円・成長投資枠を上限まで利用すれば600万円)までの投資が非課税となり、長期的な資産形成に適しています。
また、成長投資枠としては、年間240万円(上限1,200万円)の非課税枠があります。この制度を利用することで税負担を軽減しながら運用できるため、
初心者でも始めやすい制度として、多くの人に利用されています。
3-2. 投資信託を活用する
投資信託は、少額からでも始められる分散投資の手段の一つです。
投資信託自体が複数の資産に分散投資されているため、個別銘柄のリスクを軽減できる特徴があります。
100円から購入できる投資信託もあり、初心者でも手軽に始めることができます。
また、プロの運用によって資産が管理されるため、自分で銘柄選定を行う必要がありません。NISAの非課税枠を使って投資することもできるため、投資信託は初心者にとって魅力的な選択肢となっています。
4. ポートフォリオの定期的な見直しとリバランス

ポートフォリオを決めて運用を始めても、時間の経過や市場環境、ライフステージの変化に合わせて定期的に見直したり、必要に応じてリバランスすることが重要です。
リバランスとは、ポートフォリオ内の資産の比率が目標から乖離した際に、売買などを通じて元の比率に調整する作業を指します。
見直しとリバランスによって、想定外のリスク上昇を抑えつつ、中長期の目標達成に向けた最適なポートフォリオを維持しましょう。
ここでは、具体的な見直しとリバランスのポイントを解説します。
- 年に1〜2回はポートフォリオをチェックする
- 配分が崩れたらリバランスする
- ライフイベントや市場の変化に応じて見直す
以下で、それぞれについて解説します。
4-1. 年に1〜2回は資産配分をチェックする
資産運用を続けるうえで、定期的なポートフォリオの見直しは欠かせません。
市場の変動や資産の増減により、当初の配分比率から乖離することがあるからです。
例えば、株式市場の上昇により、株式の比率が高くなりすぎると、リスクが増大する可能性があります。このような場合、年に1〜2回の頻度でポートフォリオを確認し、必要に応じて調整を行うことが推奨されます。
定期的に見直すことで、リスクを適切に管理し、目標とする資産運用を継続することが可能です。
4-2. 配分が崩れたらリバランスする
資産配分が当初の計画から乖離した場合、リバランスが必要になります。
例えば、株価の上昇等で株式の比率が高くなりすぎた場合、株式の一部を売却して債券を購入することで、配分比率を当初目標に整えることができます。
このような調整により、リスクを適切に管理し、安定した資産運用を継続することができるでしょう。
4-3. ライフイベントや市場の変化に応じて見直す
ライフイベントや市場の変化に応じて、ポートフォリオの見直しを行うことも重要です。
例えば、結婚や出産、退職などの大きなライフイベントが発生した場合、資産運用の目的やリスク許容度が変化することがあります。
また、市場の大きな変動や経済環境の変化も、ポートフォリオの見直しを検討するきっかけとなります。このような状況に応じて、柔軟にポートフォリオを調整することで、長期的な資産形成を行えます。
5. まとめ
分散投資によるポートフォリオの構築は、リスクを抑えながら安定したリターンを目指すための基本戦略です。投資の目的や期間、リスク許容度を明確にし、それぞれが自分に合ったポートフォリオを組むことができます。
また、運用開始後は定期的な見直しとリバランスを通じて、資産配分の維持、ライフイベントや市場の変化に対応することが重要です。少額から始められるNISAや投資信託を活用することで、初心者でも手軽に分散投資を始めることができます。
これらのポイントを意識しながら、無理のないペースで資産運用を継続することが、将来の目標達成への確かな一歩となるでしょう。
IFAのファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案をしております。分散投資のポートフォリオについて、お客様のライフスタイルやリスク許容度を鑑みながら、的確にサポートいたします。
これを機に一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
