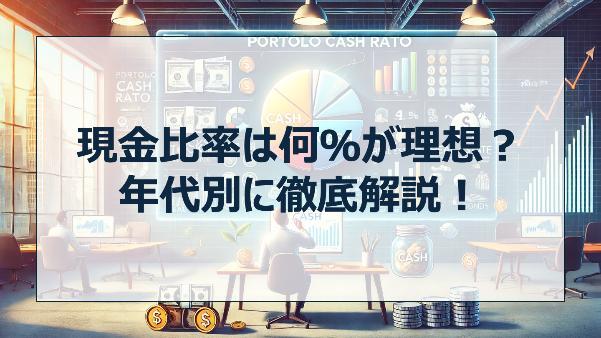
- 資産の現金比率はどれくらいが良いのか分からない
- 現金比率が高すぎる場合や低すぎる場合のリスクと対処法を教えて欲しい
- 資産配分で困った時、誰に相談したらいいか分からない
このようなお悩みで困ることはないでしょうか。
資産運用のプロが、「現金比率」について解説します。
この記事を読むと、自分にとって最適な現金比率に関する不安を解消でき、リスクに備えた安定的な資産運用に繋がるでしょう。
1. そもそも現金比率とは?

「現金比率」を正しく理解するため、本記事では以下のポイントを順に解説します。
- 現金比率の定義とは|資産全体における現金の割合
- なぜ現金比率が注目されるのか
以上の構成で、現金比率の基本概念から、その注目される背景までを丁寧に押さえていきます。
1-1. 現金比率の定義とは|資産全体における現金の割合
「現金比率」は、保有する資産全体のうち、現金が占める割合であり、個人や企業の財務状況を示す指標です。定義上、現金や預貯金は最も流動性の高い資産です。
例えば、総資産が1,000万円で現貯金が300万円であれば、現金比率は30%となります。この値は、投資を行う際にどれだけの安全資産を保有しているかを表し、リスク管理の一環として欠かせません。
また、企業や個人は現金比率を基に資産運用戦略を検討します。例えば、リスク許容度が低い場合には現金比率を高めに設定し、市場の価格変動に対する備えを強化する必要があります。
すなわち、現金比率は、安定した資産運用の実現のために非常に有用な指標であると言えます。
1-2. なぜ現金比率が注目されるのか
現金比率が注目される理由は、現金比率が高ければ、相場の変動に関わらず支払い能力が維持でき、資金繰りのリスクを軽減することができるためです。
また、現金比率は資産ポートフォリオの安定性を示すバロメーターとしても機能します。経済の不透明感が増す状況の中では、一定の現金保有が長期的な資産形成の成功に寄与すると考えられます。
例えば、相場の下落局面では、現金比率が高い投資家は有利なポジションで買い増しをすることもできます。現金比率は、リスク管理にとって非常に重要です。
2. 一般的な現金比率の目安
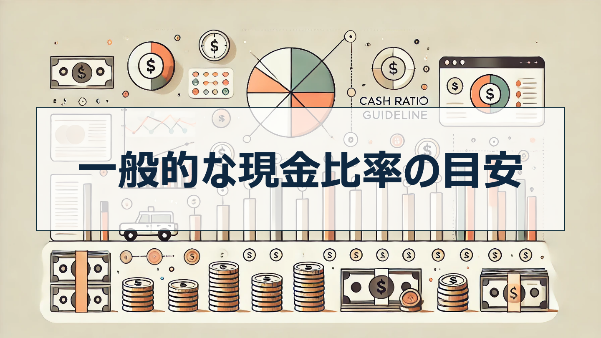
一般的に、個人投資家の場合、資産全体に占める「現金比率=年齢」と同じにするべきとされることが多いです。
資産運用において、ある程度の安全性と流動性を維持しながら、十分なリターンが期待できる資産配分が重要です。
現金比率が低すぎると、急な出費に対応できなかったり、市場急落時の買い増し機会を逃したりするリスクがあります。逆に現金比率が高すぎると、投資資産の期待リターンが低くなってしまいます。
ただし、あくまで目安であるため、それぞれの投資家のリスク許容度やライフプランによって調整する必要があります。
3. 年代別の理想的な現金比率
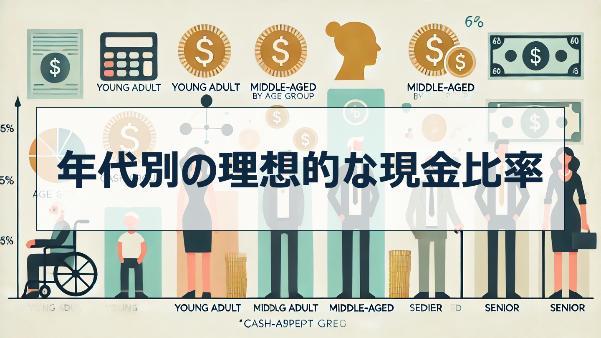
各年代に応じた理想的な現金比率は、年齢やライフステージの変化により異なります。
ここでは、以下の年代それぞれについて現金比率の例を解説します。
- 20代:少額からでも貯蓄習慣を意識する
- 30代:家族構成の変化・住宅購入などの支出増に備える
- 40代:教育資金や老後資金の準備
- 50代:定年直前、現金比率をやや高めにシフト
- 60代以降:取り崩しを見据えた現金比率を意識
3-1. 20代:少額からでも貯蓄習慣を意識する
20代は資産形成の初期段階のため、少額からでも貯蓄や投資の習慣を身につけることができれば、将来に向けた大きなメリットとなるでしょう。
現金比率を一定割合に保つことで、株式市場の上昇局面では大きなリターンを狙いながら、万が一の相場下落時には、必要に応じた買い増し資金として現金を活用できます。
20代では、例えば現金比率を20%前後に設定することで、より積極的な運用が可能になります。生活費数ヶ月分の貯蓄を確保した上で、リスクを取りながら、積立投資など少額からでも資産形成を始めると効果的です。
3-2. 30代:家族構成の変化・住宅購入などの支出増に備える
30代は、家族構成の変化や住宅購入、教育資金の準備など将来の大きな支出が予測されるため、リスク管理の観点から20代に比べて現金比率をやや高めに設定しましょう。
30代では、例えば現金比率を25%〜30%前後に設定することで、予期せぬ出費や将来の大きな支出に備えつつ、投資によるさらなる資産成長を狙えるでしょう。
家計の中で急な支出があった際にも、銀行預金や手持ち現金が十分に確保されていれば、安心して資産運用を継続することができます。
30代は、将来に向けた資産成長に加えて、家計の安定を意識した現金比率のバランスが重要です。
3-3. 40代:教育資金増加や老後資金の準備
40代は、収入が安定し資産形成が本格化する一方、ライフプランの変化に伴うリスクが増大します。40代では、支出に占める子供の教育資金の増加や自身の老後資金準備について考慮する必要があります。
40代では、例えば現金比率を35〜40%前後にすることで、十分な流動性資金を確保しながら、投資資金としてさらなる資産運用も可能になるでしょう。
一方で、投資資金が減少してしまうと運用効率が低下するため、実際の資産運用額を考慮し、適度なリスクとリターンのバランスを見極めた資産配分が求められます。40代は、目の前の支出や間近に迫った将来への不安に備えて、慎重さと攻めの資産運用との両立が鍵となるでしょう。
3-4. 50代:定年直前、現金比率をやや高めにシフト
50代は、定年までの期間が短くなり、急な資金需要のリスクが増すため、現金比率をやや高めに見直すことが理想的です。
50代では、例えば現金比率を45〜50%前後に設定し、万が一のリスク回避に重点を置きつつ、市場の変動に柔軟に対応するための備えを整えることが望ましいでしょう。50代は、教育ローンや住宅ローンの返済など、定年退職後を見据えた資金管理が重要です。
3-5. 60代以降:取り崩しを見据えた現金比率を意識
60代以降は、生活資金の確保や、長期的な資産保全が最優先となり、現金比率をさらに高める必要があります。
60代では、例えば50〜60%、70代では、例えば60〜70%前後を目安に、資産の急な変動リスクを回避しながら、安定した生活資金を確保することが求められるでしょう。
さらに、退職後に十分な収入が見込めない場合、退職金の運用においては、流動性が非常に重要です。60代以降は、リスク資産は必要最低限に抑え、資産の安全性を第一に考えた資産配分が理想的です。
4. 現金比率が高すぎる・低すぎる場合のリスクと対処法
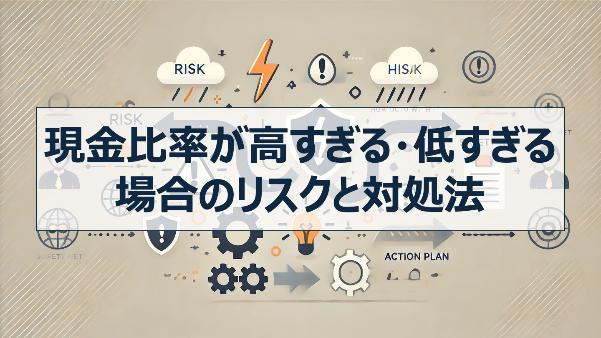
現金比率が適正でない場合、さまざまなリスクが発生します。
以下に、2つの場合のリスクについて解説します。
- 高すぎる場合:インフレによる資産の目減り
- 低すぎる場合:急な出費に対応できない
4-1. 高すぎる場合:インフレによる資産の目減り
現金比率が高すぎると、インフレが進行する局面では現金価値が目減りし、結果として実質的価値が低下してしまう恐れがあります。
例えば、預金の金利が1%/年に対し、物価上昇率が2%/年の場合、現金価値は実質的に低下します。この際に現金比率が高すぎる場合、資産運用によるリターンも限定的となり、結果的にインフレによる資産価値の低下を避けることができません。
現金比率が高すぎる場合は、経済環境におけるインフレリスクに晒されるため、計画的な資産配分の見直しが必要です。
4-2. 低すぎる場合:急な出費に対応できない
現金比率が低すぎると、急な出費や予期せぬ資金需要に柔軟に対応できなくなるリスクがあります。
例えば、多くの資産を株式や債券に投資してしまい、現金比率が低すぎると、無理な資金調達や不利なタイミングで投資資産の売却を強いられることがあります。
その結果、損失を被るケースもあり、予定通りの生活資金が確保できなくなる恐れがあります。現金比率が低すぎる場合は、現預金は安全資産としての役割を果たせず、急な資金需要に対応できないリスクがあるため、資産配分の見直しが必要です。
5. 困った時の相談先
ライフプランや現金比率の見直しで悩んだ際は、専門家に相談することで、客観的かつ実践的なアドバイスを得ることができます。
相談先として、銀行、証券会社、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が挙げられます。
投資のプロフェッショナルに相談することで、現金比率に限らず自分に合った最適な資産運用プランを見つけることができるかもしれません。
IFAに相談するならファーストパートナーズへ
IFAに相談するなら株式会社ファーストパートナーズをおすすめします。
〈ファーストパートナーズの強み〉
①証券会社や銀行など金融機関出身者が多く在籍しており、豊富な知識と経験を活かしてお客様に的確なアドバイスをご提供します
②資産運用のみならず、事業承継、M&A、不動産など多岐にわたる金融サービスをご提供しています
③ヘッジファンドや外資系プライベートバンクと提携し、幅広い選択肢をご提供可能です
6. まとめ
現金比率は、リスク管理の観点から資産ポートフォリオにおいて重要な指標です。
一般的には「現金比率=年齢」とされることが多いですが、それぞれの年代やライフプランによって適切な現金比率は異なります。
また、現金比率が極端に高すぎる・低すぎる場合は、計画的な見直しが必要です。
困った時には、銀行、証券会社、そしてIFAといった専門家に相談し、戦略的な資産運用を行いましょう。
IFAのファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案をしております。資産ポートフォリオにおける現金比率について、お客様のライフステージに合わせて、的確にアドバイスいたします。
これを機に、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談はこちらから。
