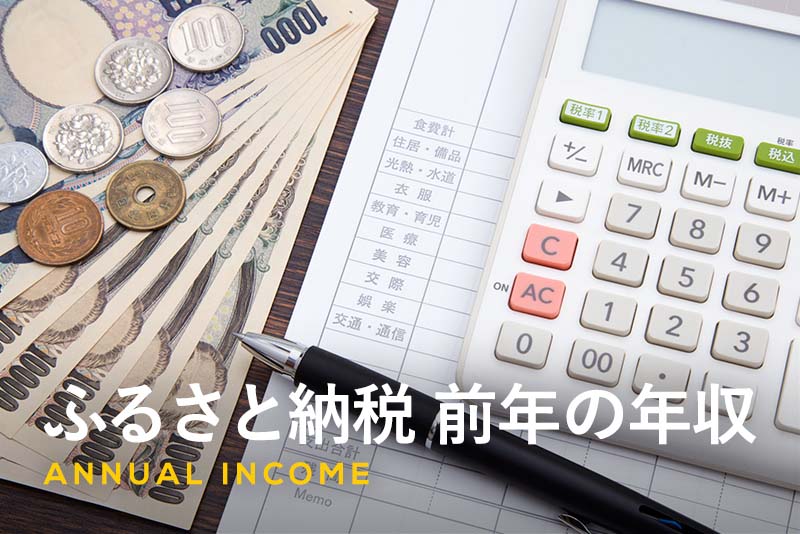
(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
| この記事は2025年6月17日にふるさと納税DISCOVERYで公開された「ふるさと納税の限度額は「前年の年収」「今年の年収」どちらで決まる?その仕組みを徹底解説」を転載したものです。 掲載記事:ふるさと納税の限度額は「前年の年収」「今年の年収」どちらで決まる?その仕組みを徹底解説 |
※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。
ふるさと納税の控除上限額が「前年の年収」と「今年の年収」どちらで決まるのか、疑問に思っている方もいることでしょう。
この記事では、この疑問を解消し、正確な控除上限額の算出方法とその仕組みをわかりやすく解説します。
ふるさと納税の控除上限額の基本

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附を行うことで、寄附金額から自己負担分の2,000円を引いた金額が翌年の所得税・住民税から控除される制度です。
この税金控除には上限があり、その上限額は個人の所得や家族構成によって異なります。
上限額を超えて寄附をしてしまうと、その分は税金控除の対象外となり、自己負担額が増えてしまい、ふるさと納税のメリットを十分に享受できなくなります。
そのため、ご自身の正確な控除上限額を把握しておくことは、ふるさと納税を最大限に活用するために不可欠です。
ふるさと納税の控除上限額は、寄附を行った年の年収を基準にして算出されます。
これは、税金の計算が、原則としてその年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて行われるためです。
ふるさと納税による税額控除もこの考え方に基づいているため、前年の年収はあくまで目安であり、今年の年収見込みを正確に把握することが重要です。
今年の年収の確認方法

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
ふるさと納税の控除上限額を算出するためには、まず「今年の年収」を正確に把握することが第一歩です。
ご自身の雇用形態や所得の種類によって、確認方法は異なります。
給与所得者の場合
給与所得者の場合、毎月の給与明細や賞与明細で、現時点までの総支給額を確認できます。
より正確な今年の年収(所得)を把握するためには、年末に会社から発行される源泉徴収票が最も確実な情報源となります。
源泉徴収票には、その年の1月1日から12月31日までの給与や賞与の合計額、各種所得控除額などが記載されており、これによって確定した年収(所得)を確認できます。
年の途中で転職をしたり、昇給や降給があったりした場合は、給与明細をこまめに確認し、年末の年収見込みを随時更新していくことが大切です。
特に、年末に近づくにつれて、より正確な年収が把握できるようになるため、ふるさと納税の最終的な寄附時期を決める際の参考にしてください。
自営業者やその他所得がある場合
自営業者やフリーランスの方、不動産所得や副業所得がある場合は、ご自身で年収(所得)を計算する必要があります。
事業の売上や経費を日頃から記帳し、ご自身の所得額を把握することが重要です。
所得額は、「収入-必要経費」で計算されます。
確定申告を行うことで、その年の所得額が最終的に確定します。
そのため、年の途中でふるさと納税を行う場合は、これまでの収入と支出、そして年末までの事業計画や見込み収入・支出を考慮し、慎重に所得額を予測する必要があります。
正確な所得予測は、ふるさと納税の控除上限額を計算する上で非常に重要となるため、税理士に相談するなど専門家の意見を求めることも検討しましょう。
控除上限額の目安とシミュレーション活用

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
ご自身の今年の年収が把握できたら、次に控除上限額の目安を確認し、シミュレーションツールを活用しましょう。
控除上限額は、年収以外にも様々な要素によって変動します。
控除上限額は、年収だけでなく、家族構成や扶養親族の有無によっても異なります。
例えば、配偶者控除や扶養控除の対象となる家族がいる場合、いない場合とでは控除上限額が変わってきます。
さらに、社会保険料控除、生命保険料控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金、医療費控除、住宅ローン控除など、個々人が受けている各種所得控除の金額も控除上限額に影響を与えます。
これらの控除が多いほど、所得が少なくなるため、控除上限額も低くなる傾向があります。
正確な控除上限額を知るには、各ふるさと納税サイトが提供しているシミュレーションツールの活用が便利です。
これらのツールは、年収、家族構成、その他の所得控除などの情報を入力することで、おおよその控除上限額を算出してくれます。
参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」
シミュレーション結果はあくまで目安です。
実際の控除額は最終的な所得や、その年の各種控除(例えば、急な医療費が発生して医療費控除が増えるなど)によって変動する可能性があります。
特に、年の途中で所得状況に変化があった場合や、シミュレーションツールでは考慮しきれない個別の税制上の事情がある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
シミュレーションツールは、あくまで計画の参考として活用し、過信しないように注意しましょう。
ふるさと納税の控除手続きについて
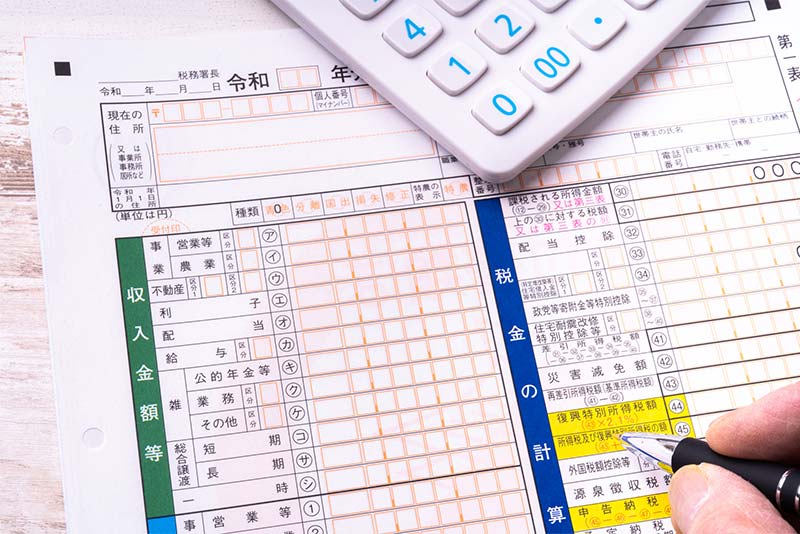
(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
ふるさと納税で寄附した金額の控除を受けるためには、適切な手続きを行う必要があります。
主な手続き方法は「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つです。
ご自身の状況に合わせて、適切な方法を選択してください。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者で、年間5自治体以内の寄附の場合に利用できます。
この制度を利用すると、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられます。
手続きは非常に簡単で、寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と「本人確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)」を郵送またはオンラインで提出します。
提出期限は、寄附を行った翌年の1月10日必着です。
この期限を過ぎてしまうと、ワンストップ特例制度の適用を受けられなくなるため、注意が必要です。
その場合は、確定申告を行うことで控除を受けることになります。
確定申告
確定申告は、自営業者や、年間6自治体以上に寄附した場合、医療費控除などで確定申告を行う場合に選択します。
また、ワンストップ特例制度の条件を満たさない場合も、確定申告が必要です。
確定申告を行う場合は、寄附金受領証明書を添付し、税務署に確定申告書を提出します。
寄附金受領証明書は、寄附先の自治体から送られてくる書類で、寄附を行った証明となります。
確定申告の期間は、原則として寄附翌年の2月中旬から3月中旬までです。
e-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで申告することも可能です。
今年の年収が大きく変動した場合の注意点

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
年の途中で転職や退職、副業の開始などで年収が大きく変わると、ふるさと納税の控除上限額も変動します。
このような年収変動は、ふるさと納税の計画に大きな影響を与える可能性があります。
年収が大幅に増減すると、控除上限額を超過して自己負担が増えたり、上限額を十分に活用できなかったりする可能性があります。
例えば、年の初めに「今年の年収は500万円になるだろう」と見込んでふるさと納税を行ったとします。
しかし、年の途中で予期せぬ転職や休業により年収が300万円に下がってしまった場合、当初計算した控除上限額よりも実際の控除上限額が低くなり、超過分の寄附が自己負担となってしまいます。
逆に、年収が想定より大きく増えた場合は、もっと多くの寄附ができたはずなのに、その機会を逃してしまうことになります。
寄附は1月1日から12月31日の間に行われます。
年間の所得見込みを立て、年収の変動が見込まれる場合は、年末に近い時期に最終的な年収を確認してから寄附を行うなど、計画的な進め方がおすすめです。
年の早い段階で多額の寄附を集中させるのではなく、複数回に分けて寄附を行う「分散寄附」も有効な戦略です。
これにより、年収変動のリスクを軽減し、年末の最終的な年収に基づいて調整を行うことが可能になります。
まとめ
ふるさと納税の控除上限額は、寄附を行った年の年収に基づいて決定されます。
ご自身の年収を正しく把握し、シミュレーションツールなどを活用して、賢くふるさと納税を活用しましょう。
特に、年の途中で年収が変動する可能性がある方は、年末の年収見込みを考慮し、計画的に寄附を行うことが大切です。
この記事を通じて、ふるさと納税の仕組みを深く理解し、ご自身の状況に合わせた最適な寄附計画を立てる一助となれば幸いです。
