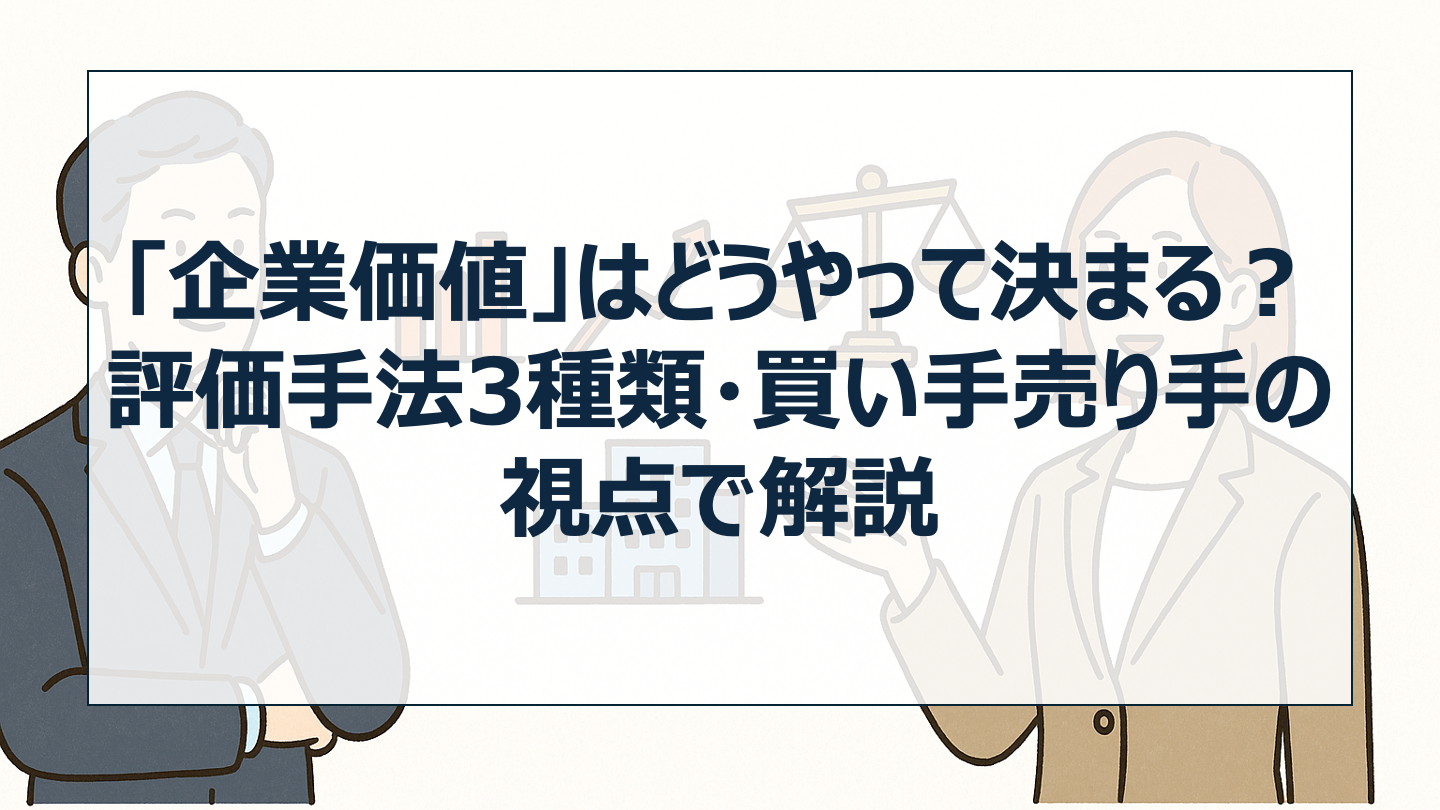
- 企業価値を計算する方法が分からない
- 何を基準に企業価値が決まるのか?
- どのタイミングで企業価値評価をすればいいのか分からない
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
M&Aのプロが、企業価値の算定方法について解説します。
この記事を読むと、企業価値に関する疑問や不安が解消され、M&Aや資金調達の場面等で意思決定に役立つでしょう。
1. 「企業価値評価」とは?
企業価値評価とは、会社全体の価値を算出するための手法を指します。
この評価はM&Aや資金調達の交渉で基準となり、取引の透明性を高める役割を果たします。
上場企業の場合、時価総額が企業価値の目安になります。一般的には、企業価値=時価総額+有利子負債−現預金という形で計算されます。
一方、非上場企業の場合、帳簿上の数値だけでは実態を反映しにくいため、市場性や成長性を考慮した調整が必要です。
こうして算出された企業価値が、売り手・買い手双方の交渉材料として使われます。
2. 企業価値を評価する3つの代表的な手法
企業価値評価は、大きく分けて以下の3つのアプローチで行われます。
- コストアプローチ(純資産ベース)
- マーケットアプローチ(比較ベース)
- インカムアプローチ(収益ベース・DCF法など)
以下で、それぞれについて解説します。
2-1. コストアプローチ(純資産ベース)
この手法は、帳簿上の総資産から負債を差いた純資産を基準に、企業価値を算定します。
ただし、帳簿価額の資産には実際の市場価値が反映されない点に注意が必要となります。
たとえば、遊休地や不要設備は市場価格との差が大きく、含み損益が生じることがあります。そのため、資産の時価評価を別途行い、帳簿価額とのギャップを調整することが一般的です。
このアプローチは企業の清算価値やネットアセットを把握する用途で活用されるケースが多く見られます。
2-2. マーケットアプローチ(比較ベース)
こちらは、類似した上場企業や過去のM&A取引事例をベンチマークとして企業価値を算出する方法です。対象会社と同じ市場に属する他社の株価や類似した取引事例などに着目した評価をします。代表的なものには、「市場株価平均法」「類似会社比準法」「類似取引比較法」などがあります。
類似取引比較法(マルチプル法)では同業他社のEV/EBITDA倍率が8倍で、自社のEBITDAが5億円なら、40億円が目安となります。ただし、市場環境や企業特性によって倍率は変動するため、交渉余地が大きいのが特徴です。
このアプローチは企業価値を短時間で概算を得たい場合や市場に近い水準の価値を把握したいときに適していますが、業種や企業ごとに倍率が異なるため、調整が必要です。
2-3. インカムアプローチ(収益ベース・DCF法など)
こちらでは、将来のフリーキャッシュフローを現在価値に割り引いて計算するDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)を紹介します。
まずはフリーキャッシュフロー(FCF)を予測します。FCFとは経営者の判断で自由に使えるお金を指します。次に残存価値(TV)を求めます。TVとは事業計画の期末時点における買収対象企業の事業価値のことです。
算出したFCFとTVを現在価値に割り引きます。DCF法における割引率は加重平均資本コスト(WACC)を使うのが一般的です。最後に事業用資産を加えると企業価値が算出できます。また、有利子負債を差し引くことで株主価値を算出することができます。
3. 「企業価値」=「売買価格」ではない?その違いと注意点
理論上の企業価値と実際のM&A成立価格は、必ずしも一致するとは限りません。
- 企業価値は理論値|実際の売買価格とは乖離があることも
- 価格を左右する交渉力・競争環境・取引条件
以下で、それぞれについて解説します。
3-1. 企業価値は理論値|実際の売買価格とは乖離があることも
理論的な企業価値は将来のキャッシュフローや市場データに基づいて数式で算出する一方で、実際の売買価格は交渉力や取引のタイミング、買い手の事情などによって大きく価格が変動します。
例えば、売り手側が複数の買い手候補を集めて競争環境を作れば価格は上昇しやすく、一方で急いで売却したい事情があれば、理論値を下回る価格での売買もあり得ます。
また、財務デューデリジェンスで想定外の負債やリスクが発覚すると、提示額が大幅に減額されることもあるでしょう。
このような乖離を理解せず評価額だけを過信すると、不利な条件での取引につながるリスクがあります。
3-2. 価格を左右する交渉力・競争環境・取引条件
実際の価格交渉では、売り手側の交渉力が価格を大きく左右します。
例えば、競合する買い手が多いほど売り手優位となり、理論価格以上のオファーが出やすいです。
逆に、買い手が一人しかいない場合は買い手主導で金額が抑えられることがあります。
また、契約条件(公開範囲、保証条項、アーンアウト等)によって実効価格は変動するため、金額面だけでなく契約条件も含めて交渉の枠組みを広く検討する必要があります。
4. 買い手・売り手、それぞれの視点で見る企業価値評価
ここでは、企業価値の評価において買い手と売り手が重視するポイントを比較します。
- 売り手は「できるだけ高く売る」、買い手は「将来の収益性を見極める」
- M&A後のシナジーやコスト構造まで考慮すべき
以下で、それぞれについて解説します。
4-1. 売り手は「できるだけ高く売る」、買い手は「将来の収益性を見極める」
売り手は、自社を可能な限り高い金額で譲渡したいため、資産の含み益やブランド価値などを強調します。
一方、買い手は将来のキャッシュフローや事業成長率、買収後のROI(投資回収率)を厳しく検証するでしょう。
具体的には、売り手は無形資産(特許やブランド)の価値を定量化して理論価格を引き上げ、買い手は業界成長率や競合状況を勘案して保守的な見積もりを行います。
このような視点の違いを認識し理解をした上で、双方がどう折り合いをつけるかが交渉戦略において重要な鍵となるでしょう。
4-2. M&A後のシナジーやコスト構造まで考慮すべき
買い手は、買収後のコスト削減や売上拡大によるシナジー効果も評価に加味します。
例えば、重複する管理部門の統合で年間数億円のコスト削減が見込めれば、その分を買収価格に上乗せしても十分な投資回収が期待できるでしょう。
逆に、組織文化の違いや人材流出リスクが高いと判断された場合は、統合後のコスト増を見越して買収価格を低く見積もることもあります。
このように、M&Aは単なる買収ではなく、統合後の事業計画まで含めて全体評価することが買い手側の一般的な手段です。
5. 企業価値評価を行うタイミングとは?
適切なタイミングで評価を実施することもM&Aや資金調達成功の鍵のひとつになるでしょう。
- M&A・資金調達の場面
- フェアバリューや経営判断の根拠資料としても活用
以下で、それぞれについて解説します。
5-1. M&A・資金調達の場面
M&Aの検討を始める段階や資金調達ラウンドに入る前に、事前評価を済ませておくことが一般的です。
これにより、売り手は必要資金や希望譲渡価格を明確に把握でき、買い手は出資の可否や買収規模を判断しやすくなります。
スタートアップ企業の場合は、プレIPOフェーズでDCF法や類似企業比較を行い、資本政策や企業価値向上の根拠にします。
5-2. フェアバリューや経営判断の根拠資料としても活用
上場企業では、四半期決算や決算説明資料などでフェアバリュー評価を定期的に開示することが求められます。
また、事業再編や新規投資の意思決定では企業価値のシミュレーションが経営判断の重要なレポートとなります。
こうした内部資料を活用して、経営陣が資本効率やROIをモニタリングし、戦略的に意思決定を行うのが望ましいでしょう。
6. まとめ
企業価値評価は、資産ベース、比較ベース、収益ベースの3つの評価手法を使い分け、市場動向や交渉力、シナジー効果なども踏まえて総合的に算定するプロセスです。
理論値と実際の売買価格は乖離することが多いため、売り手・買い手双方が自社の目的に応じた評価視点を明確化することが重要です。
特に、M&Aや資金調達のタイミングでは適切な企業価値評価を行うことで、経営判断や交渉戦略の根拠となり、より有利な取引や資本効率向上を実現できるでしょう。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添ったM&Aや資金調達のサポートをしております。企業価値の計算方法について、お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
