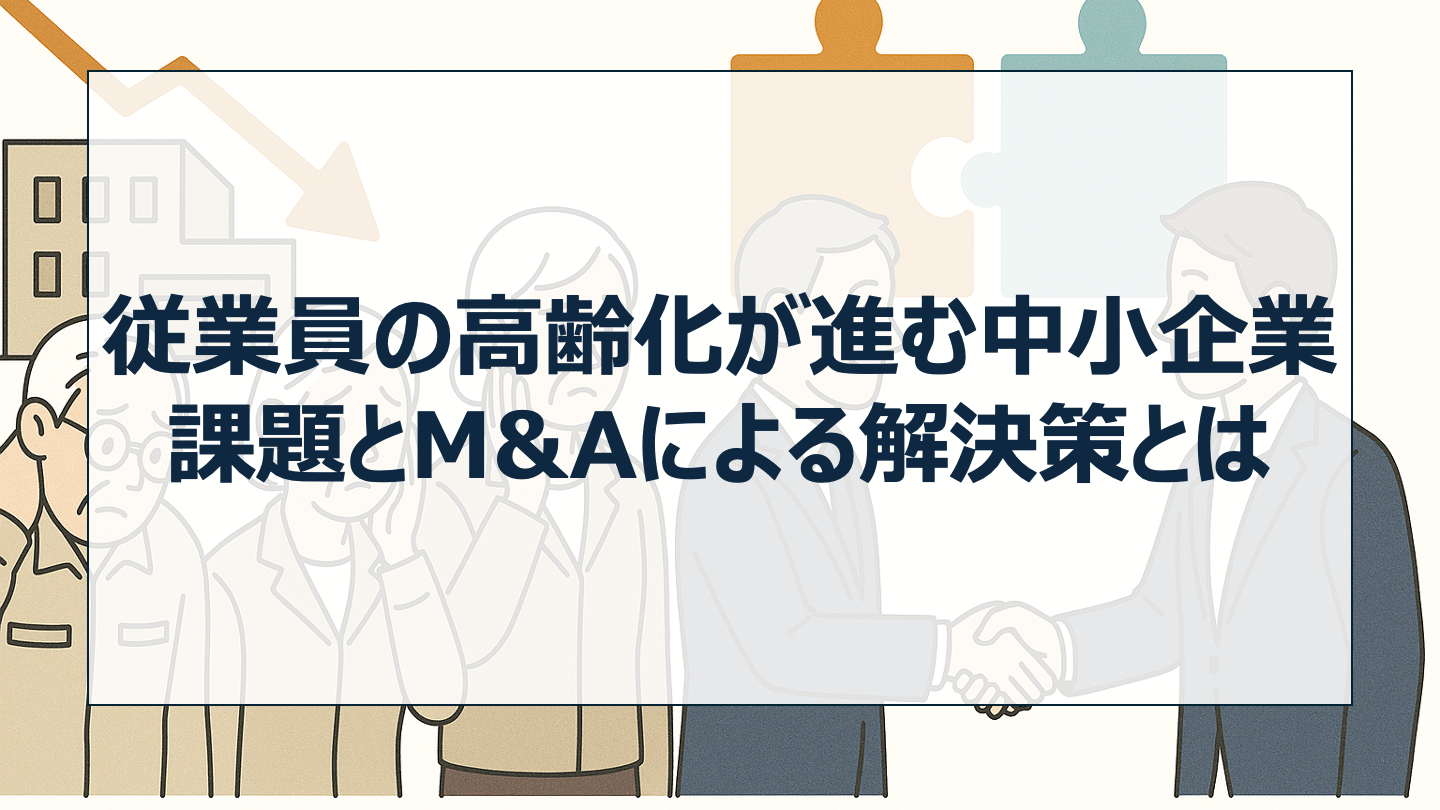
- 従業員が高齢化しており、どうすれば良いか分からない
- 従業員の高齢化が会社に与える影響が分からない
- 従業員の高齢化への対策として、M&Aを行うメリットを知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
M&Aのプロが、従業員の高齢化が及ぼす影響と解決策について解説します。
この記事を読むと、従業員の高齢化に関する不安を解消でき、将来を見据えた会社経営に役立つでしょう。
1. 日本企業で深刻化する従業員の高齢化問題
従業員の高齢化は、総務省のデータによると2004年以降一貫して進展し、2017年からは70歳以上の層が増加していることが分かっています。
このような状況は若手人材の確保が難しいことに繋がっており、中小企業の持続的な成長や事業継続に大きなリスクをもたらす要因となっているのです。
2. 数字で見る従業員の高齢化の現状
前述のような状況であるため、従業員21人以上の企業のうち99.9%が高年齢者雇用確保措置を実施済みであり、さらに、70歳までの就業確保措置をとっている企業も29.7%あります。一方、国内の労働力人口構成は、40歳以上が半数を超えるなど世代間のバランスが大きく変化しています。
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となってくることで、人手不足や業績低迷、事業承継問題などが深刻化すると指摘されていることを、2025年問題と呼ばれています。
たとえば、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)がピーク時1995年の8,700万人から7,100万人と減少が進むとされており、地域や業界による差はあるとはいえ、具体的な対策を講じる必要性がある場合があることがわかります。
3. 従業員の高齢化が企業にもたらす3つの影響
上述した従業員の高齢化が企業にもたらす影響は、以下の3つあります。
- 労働生産性の低下|身体的負担とスキルアップ機会の減少
- 人手不足の常態化|若手採用の難化、売り手市場
- 後継者が見つからず、廃業リスクが現実化
以下で、それぞれについて解説します。
3-1. 労働生産性の低下|身体的負担とスキルアップ機会の減少
従業員の高齢化が進むと、身体的負担の増加により労働生産性が低下しやすくなります。
高齢者は慢性的な疲労や健康リスクを抱えやすく、従来のペースで長時間働くことが難しくなります。また、若手に比べて新しい技術やデジタルスキルの習得機会が限られ、スキルアップに遅れが出ることもあります。
具体的には、建設業界でのデジタル施工技術導入が進まないケースなど、現場での効率化が停滞する事例が挙げられます。
こうした要因が重なると、労働時間あたりのアウトプットが減少し、全体の事業パフォーマンスに影響を及ぼすのです。
3-2. 人手不足の常態化|若手採用の難化、売り手市場
高齢化が進むほど若手人材の採用競争が激しくなり、中小企業では売り手市場が常態化します。
若手労働人口の減少と転職志向の高まりにより、定着率が低いことも採用難の要因です。さらに、少子化の影響で労働力人口全体が縮小し、求人数に対して応募数が減少する状況が続いています。
例えば、中小規模の製造業で定期的な欠員補充が困難になると、生産ラインが一時停止するケースも考えられます。
このように、人手不足が慢性化すると企業活動の継続に支障をきたし、成長戦略の実行が難しくなるのです。
3-3. 後継者が見つからず、廃業リスクが現実化
従業員の高齢化は後継者問題を深刻化させ、特にオーナー経営の中小企業では廃業リスクが現実味を帯びます。
後継者候補が少なく、かつ高齢化による技能継承が進まないと、事業の継続が困難になります。実際に、事業承継問題は2025年問題の主要課題の一つとして指摘されています。
例えば、創業数十年以上の会社で技能伝承が打ち切られ廃業を余儀なくされる、といったケースが考えられます。
これらの要因が重なることで、企業の存続そのものが危うくなるのです。
4. 「従業員高齢化」が進む会社がM&Aを行うメリット
従業員の高齢化が進む会社が取る措置の一つとして、M&Aがあります。
M&Aを実施するメリットは以下の通りです。
- 技術承継:蓄積された技術が買収企業へ引き継がれることによる事業シナジー創出
- 廃業回避:取引先や顧客への負担なく事業を継続できる
- オーナーの利益:M&Aにて売却することにより譲渡対価を受け取れる
以下で、それぞれについて解説します。
4-1. 技術承継・蓄積された技術が買収企業へ引き継がれることによる事業シナジー創出
M&Aでは、先代経営者や高齢社員が培ったノウハウや技術が買収先に継承され、事業シナジーを生み出せます。
これにより、新規顧客開拓や製品の高度化が可能になり、成長戦略と効率化策の両立が可能となる場合があります。
例えば、製造業のM&Aでは、長年蓄積された技術が組み合わさって新製品開発が加速した事例が挙げられます。このような技術資産の共有は、買収企業の競争力にも直結します。M&Aを通じて技術承継がスムーズに行われると、組織全体のスキルアップも促せるでしょう。
4-2. 廃業回避・取引先や顧客への負担なく事業を継続できる
M&Aを選択することで、廃業による取引先や顧客への影響を最小限に抑えつつ事業を継続できます。
取引停止や顧客離れを防ぎ、従業員や取引先の負担を軽減できる点が大きなメリットです。
特に長期にわたり取引関係を築いてきた企業間では、事業継続が信頼維持につながります。
例えば、地域密着型のサービス業ではM&A後も旧経営者が顧問として支援することで顧客の安心感を保てるでしょう。
こうした備えが、廃業による社会的損失を防ぐ役割を果たします。
4-3. オーナーの利益・M&Aにて売却することにより譲渡対価を受け取れる
オーナーはM&Aを通じて企業価値に見合った譲渡対価を得ることができます。
これにより引退後の資金計画が立てやすくなるうえ、経営者個人のリスクも軽減できます。
また、相続や贈与に伴う税務リスクを抑えるための事前対策としても活用可能です。
具体的な事例では、飲食店オーナーがM&Aにより数千万円の対価を得て、退職金や年金の不足を補った例が挙げられます。
オーナーにとって、M&Aは自社を活かしながら財務的メリットを享受できる有力な選択肢と言えるでしょう。
5. 従業員の高齢化を背景にM&Aを進める際の2つの注意点
従業員の高齢化を解決するために、M&Aを実施する際の注意点は以下です。
- M&A後の従業員ケアが重要|不安感の払拭とモチベーション維持
- 成功の鍵は準備とタイミング|早期準備とプロセス設計
以下で、それぞれについて解説します。
5-1. M&A後の従業員ケアが重要|不安感の払拭とモチベーション維持
M&A後も従業員が安心して働ける環境を整備し、不安感を払拭することは、最も大切なことの1つです。
健康診断や職場環境の改善といった健康経営の視点を取り入れることで、従業員ケアが促進されるでしょうし、研修プログラムの充実は、新旧両世代の知識共有とモチベーション維持に有効となるでしょう。
M&A発表時には適切なタイミングで情報共有を行い、噂や誤解を防ぐことも重要です。
これらを計画的に実施することで、M&A後の組織統合をスムーズに進められるでしょう。
5-2. 成功の鍵は準備とタイミング|早期準備とプロセス設計
M&Aの成否を分けるのは、早期の準備と適切なタイミングです。
事前に財務・法務・人事面のデューデリジェンスを行い、リスクを洗い出しておくことが欠かせません。
特に従業員の高齢化が進む企業では、人員配置や退職金の計算などを綿密に検討する必要があります。
また、市場環境を見極め、ベストなタイミングでM&Aを検討しましょう。
こうしたプロセス設計を整えていけば、交渉も円滑に進み、統合後のトラブルを防げるでしょう。
6. まとめ
従業員の高齢化は、中小企業にとって労働生産性低下や人手不足、後継者不在といった深刻な課題を生み出しています。
一方でM&Aは技術承継や事業継続、オーナー利益の獲得など複数のメリットをもたらします。
ただし、従業員ケアと準備・タイミングが成功の鍵となるため、早期の検討と計画立案が不可欠です。
従業員の高齢化を背景に、M&Aを活用した戦略的な事業継承を検討することで、中小企業は持続可能な成長を実現できるでしょう。
まずは自社の高齢化状況を数値で再確認し、最適な解決策としてM&Aを視野に入れてはいかがでしょうか。ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添ったM&Aのサポートをしております。従業員の高齢化問題について、お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度相談を検討ください。
ご相談はこちらから。
