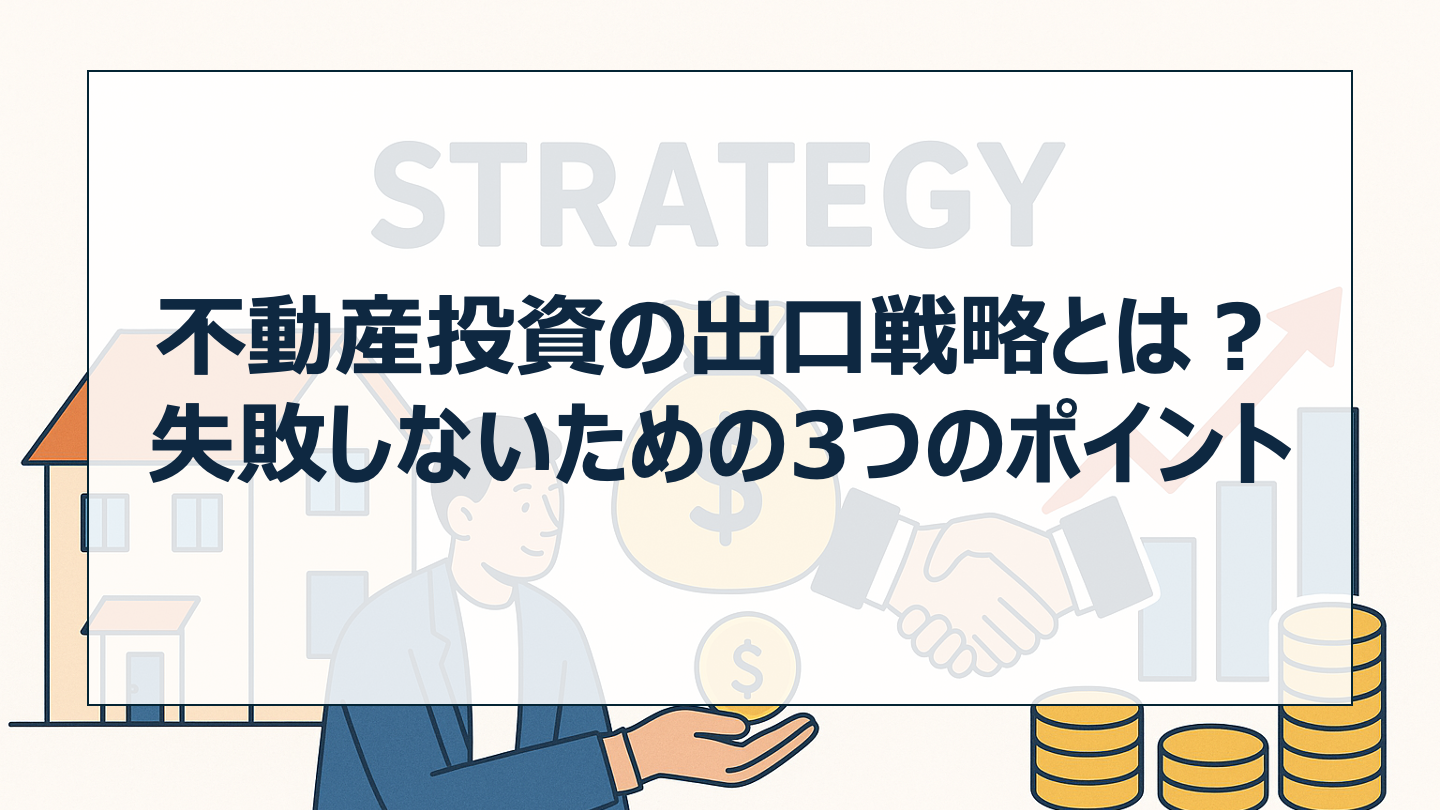
- 不動産投資の出口戦略がよく分からない
- 不動産の売却タイミングの見極め方について知りたい
- 不動産投資で失敗しないためのポイントが知りたい
このようなお悩みを抱えていませんか?
本記事では、不動産のプロが、不動産投資の出口戦略について解説します。
この記事を読むと、ご自身の投資計画にあった戦略を検討するのに役立つでしょう。
1. 不動産投資における「出口戦略」とは?
出口戦略とは、保有している不動産を投資による利益を損なわず手放すために、売却や継承の方法をあらかじめ計画することを指します。
不動産は株式や債券のようにすぐ現金化できるわけではないため、売却タイミングや資産価値の変動が利益に直結するリスクがあります。。
例えば、築年数が進んだ物件を長期保有したまま売却時期を逃すと、資産価値の下落や空室増加で期待した利益が得られない可能性があります。
一方、物件購入時から出口戦略をしっかり計画することで、利回りの維持や税制面での工夫がしやすくなります。
出口戦略の計画は、出来るかぎり早い段階から検討しておきたい重要なポイントです。
次に、具体的な出口戦略パターンを見ていきます。
2. 収益物件の代表的な出口戦略パターン
収益物件の出口戦略は投資家の目的や市場需要に合わせて3つの主要パターンに大別できます。各パターンの特徴を理解することが適切な手法選択に繋がります。
- 収益物件のまま売却(利回り重視の投資家向け)
- 更地にして売却(建て替え需要を狙う)
- 自己居住用として売却(実需層へ転用)
各パターンの具体的な内容を詳しく説明します。
2-1. 収益物件のまま売却(利回り重視の投資家向け)
現在の入居者との賃貸借契約を引き継いだ状態で売却する「オーナーチェンジ」は収は、安定した利回りを重視する投資家にとって検討するとよい選択肢でしょう。
賃料収入が継続して得られる点や、物件の収益性が可視化されている点が評価されやすく、買主にとっても投資判断がしやすいといえます。例えば、築年数の浅いマンションを、賃料水準が高い状態を維持したまま売却できれば、利益率の改善が期待できるでしょう。
その結果、売却時の利回り計算に基づく適正価格設定が容易になり、買主を見つけやすくなります。
一方で賃貸需要が低下すると家賃収入が減るリスクがある点には注意が必要です。
以上のように収益物件のまま売却は需要と収益性を両立させたい投資家に向く戦略といえます。
2-2. 更地にして売却(建て替え需要を狙う)
更地にして売却する方法は、建替え需要が高い地域や再開発が進むエリアで有効とされるケースがあります。
建物を取り壊すことで買主は自由なプランニングが可能になり、敷地価値を最大化できます。
実際に都心部再開発地区では築古戸建てを更地化後に転売し、土地価格の高騰で購入価格を大きく上回る利益を上げた事例があります。
さらに、建物解体費用を売却価格に織り込むことで収支計画を正確に立てやすくなるメリットもあります。一方で解体リスクや費用負担を考慮しないと利益が圧迫される可能性がある点に留意が必要です。
このように更地化売却は土地需要と収益性を両立させる有効な手法です。
2-3. 自己居住用として売却(実需層へ転用)
自己居住用として売却する手法は、実需層への訴求力が高い点が特徴です。
賃貸経営という枠を外し、マイホーム需要に合わせた価格設定が可能になるためです。
たとえば郊外のファミリー向けマンションを自己居住用に転用した結果、住宅ローン利用者が買主となり早期の売却が期待できるでしょう。
上記のケースでは立地と間取りがファミリー層のニーズにマッチしたことで売却期間が短縮できた点が良かったと考えられます。
ただし価格交渉の際に投資家利回り目線と相違があると交渉が難航する点には注意が必要です。
3. 収益物件の価格はどう決まるのか?
収益物件の価格は主に収益性と資産性という二つの軸で評価されます。
収益性は利回りや稼働率、賃料水準など投資判断に直結する指標で、資産性は立地や築年数、管理状態を総合的に見て将来の価格維持や売却可能性を示す指標です。
- 収益性(利回り・稼働率・賃料水準)
- 資産性(立地・築年数・管理状態)
以下でそれぞれについて解説します。
3-1. 収益性(利回り・稼働率・賃料水準)
収益性とは利回り・稼働率・賃料水準を総合した投資効率の指標です。
高い利回りと安定した稼働率、適切な賃料設定が揃うほど投資家に魅力的と評価されます。
例えば、満室稼働率95%以上のマンションなどは高い収益性が見込まれることから、買い手の関心を集めやすい傾向があります。
こうした物件は一定の収益が見込めるとされ、、市場価格にもその魅力が反映されやすくなります。
ただし賃料下落リスクを考慮しないと収益性評価が過大になるので注意が必要となるでしょう。
以上のように収益性の評価は不動産投資判断の指標となります。
3-2. 資産性(立地・築年数・管理状態)
資産性は立地・築年数・管理状態で将来の価値維持力を示す要素です。
駅近や商業施設周辺といった好立地の物件は資産価値が下がりにくい傾向があります。
また築浅物件は設備の劣化が少なく、修繕費用負担が軽減されるため資産性が評価されます。
具体的には築数年以内の駅徒歩数分のマンションは市場で高い資産性評価が付きやすく、売却時に有利な価格で取引される可能性が高いでしょう。
ただ、管理状態が悪い物件は修繕負担が増え、資産性評価が下がる可能性があります。
このように資産性の見極めは長期的な投資判断や出口戦略を考えるうえでも、重要な指標の一つとなります。
4. 売却タイミングの見極めポイント
不動産の売却タイミングを見極めるには、税制や市場環境の変化を踏まえた戦略的判断が求められます。
重要なポイントとしては長期譲渡税制への移行時期や減価償却の終了、デッドクロス発生時、市場価格の高騰などが挙げられます。
- 所有期間が5年を超えたタイミング
- 減価償却期間が終了するタイミング
- 「デッドクロス」が発生する時期
- 市場価格の高騰・融資条件の好転時
以下で各ポイントを順に説明します。
4-1. 所有期間が5年を超えたタイミング
不動産の譲渡所得にかかる税率は、所有期間が5年以下か5年超かで大きく異なります。
具体的には、所有期間5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、所得税・住民税を合わせて約39%の税率がかかります。一方、5年を超えると「長期譲渡所得」として、税率は約20%に軽減されます。このため、5年の保有期間を経過した「6年目以降」に売却することで、税負担が抑えられる可能性があり、譲渡益が大きい物件ほど税率差によるインパクトも大きくなります。
たとえば同じ売却益であっても、短期と長期で数十万~数百万円単位の差が生じるケースも見られます。ただし物件価値が下落していないかも確認しないと利益が縮小する恐れがあります。
こうした税制メリットを活かすかどうかは売却計画の早期設計が大切となるでしょう。
4-2. 減価償却期間が終了するタイミング
建物部分の減価償却期間が終了すると帳簿上の経費として計上できる減価償却費が無くなります。これにより、同じ収入であっても経費が減る分課税所得が増加し、結果として所得税・住民税の負担が増す可能性があります。
例えば、築数十年の建物を所有していた投資家が減価償却終了後に売却を検討し、税負担増加を回避できるケースが挙げられます。
このケースでは売却益を減価償却終了前に確定させることで手取りを最大化しました。
ただし資産性や市場環境も併せて判断しないと機会損失になる恐れがあります。
減価償却終了をタイミングに含めた売却計画の立案が重要です。
4-3. 「デッドクロス」が発生する時
不動産投資における「デッドクロス」とは減価償却費を含む経費の総額が賃料収入を上回り帳簿上のキャッシュフローが赤字に転換する現象を指します。
赤字化前に売却を検討することで資金不足リスクを回避できるため重要な判断ポイントとなります。
例えば、築数十年の物件でデッドクロスが発生した際、売却によって赤字転換を免れることがあります。この場合、その後の修繕費負担を軽減し、資金繰り悪化を防ぐことが可能でしょう。
一方で慌てた不動産売却は価格交渉力を弱めるため注意が必要です。
デッドクロスの発生タイミングを把握し、売却戦略を練ることを意識しましょう。
4-4. 市場価格の高騰・融資条件の好転時
市場価格が高騰し金融機関による融資条件が緩和されている局面は売却を検討するよいタイミングになります。
買い手の資金調達が容易になると物件の売却期間も短縮されやすいためです。
例えば金利低下局面で融資が付きやすくなり、多くの投資家が都心部中古マンションに殺到することが考えられるでしょう。
この結果、期待以上の価格で不動産売却できる可能性もあります。
ただし、その後の金利上昇局面には注意しないと買い手不足に陥る恐れがあります。
市場環境と融資動向を見極めた売却検討が成功に繋がるでしょう。
5. 売却で失敗しないための3つの出口戦略
売却で失敗しないためには家賃下落リスクの少ない物件選定、自己資金の確保、融資の付きやすさを重視した戦略が不可欠です。
これらの要素を抑えることで売却時に価格崩れや買い手不在のリスクを減らせる可能性があります。
- 家賃の下がりにくいエリア・物件を選ぶ
- 自己資金を一定額入れておく
- 融資の付きやすい物件を選ぶ
以下で各ポイントを詳しく見ていきましょう。
5-1. 家賃の下がりにくいエリア・物件を選ぶ
家賃の下がりにくいエリアや物件は安定的な収益を生み出し、売却時にも価格維持が期待できます。
特に都心の利便性が高い地域や人気の沿線沿いは賃貸需要が旺盛です。
実際に駅徒歩数分圏内の築浅ワンルームは賃料下落が小さく、買い手が途切れにくい傾向があります。このようなエリアの物件は市場での流動性も高く、スムーズな売却を実現しやすいでしょう。
一方で築年数が古い地域では一般的に賃料下落リスクが大きいため選別が必要と考えられます。
家賃下落リスクを抑えられる物件選びを実施することで、不動産投資成功に繋がりやすいです。
5-2. 自己資金を一定額入れておく
物件購入時に自己資金を一定額投入しておくことで、借入比率を抑えられ、売却時に手元に残る利益を確保しやすくなります。
借入額が少ないほど金利負担も軽減されるためキャッシュフローが安定しやすいからです。
例えば、購入価格の20%を頭金として拠出した投資家は、元本の返済が進みやすく、数年後の売却時にローン残債と売却価格との差額が大きくなり、手取りが増える可能性があります。このケースでは金利上昇リスクにも耐性を持った資金構成が功を奏しました。
一方で自己資金を入れすぎるとレバレッジ効果が薄れる点には注意が必要となるでしょう。
適切な自己資金比率が投資収益性とリスク許容度のバランスを保つことに繋がります。
5-3. 融資の付きやすい物件=次の買主がつきやすい物件を選ぶ
融資の付きやすい物件は次の買主にも融資が下りやすく、早期売却に繋がります。
金融機関が評価しやすい物件は立地や築年数、収益性が安定しているものです。
例えば、金融機関が積極的に融資を行った物件は市場に出ると短期間で成約した事例が見られます。こうした物件は買い手側の審査も通りやすいため価格交渉力が高まりやすいです。
一方で過度に金融機関依存になると金利変動リスクを受けやすくなる点には留意が必要です。
融資付きやすさを重視した物件選びが売却成功への確実なステップとなるでしょう。
6. まとめ
本記事では不動産投資の出口戦略の定義から具体的な売却パターン、価格決定要因、タイミングの見極め、失敗回避のポイントまで幅広く解説しました。
収益物件のまま売却や更地化、自己居住用転用など目的に応じた手法選択が重要となるでしょう。
価格評価は収益性と資産性の両面から行い、タイミングは税制メリットや市場環境を考慮しましょう。
家賃下落リスクを抑えたエリア選定、適切な自己資金比率、融資付きやすい物件選びが不動産投資成功に繋がるでしょう。
ぜひ本記事のポイントを踏まえて出口戦略を練り、失敗しない不動産投資を実現していただければと思います。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添った不動産投資のご提案をしております。不動産投資の出口戦略について、お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機に一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
