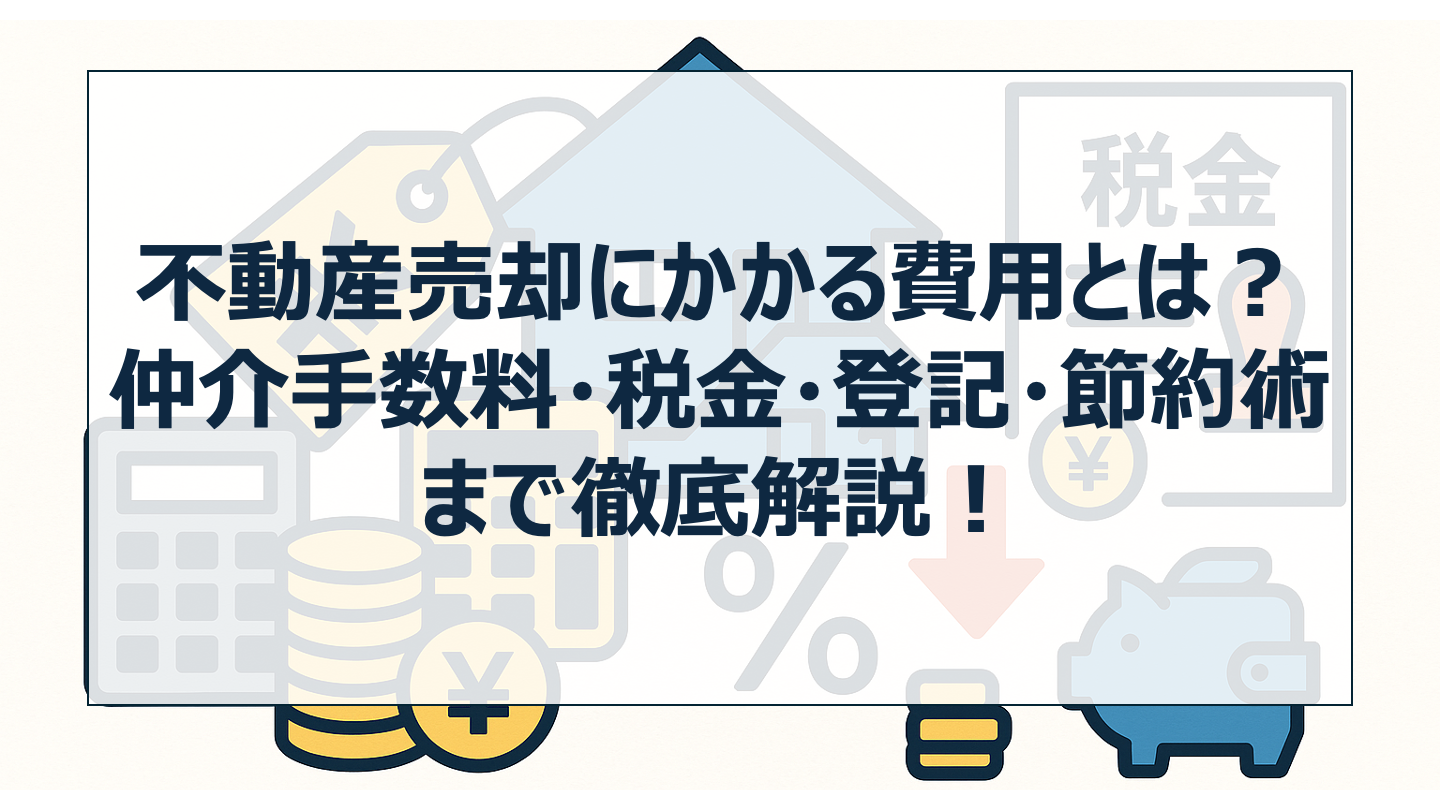
- 不動産売却にかかる費用が分からない
- 不動産売却での費用を抑えるやり方が分からない
- 不動産売却費用の想定外を避けるためのポイントを知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
不動産のプロが、不動産売却にかかる費用について解説します。
この記事を読むと、不動産売却に伴う費用への不安を解消でき、諸費用を抑えた不動産売却に繋がることでしょう。
1. 不動産売却でかかる3つの基本費用
不動産を売却する際、必ず発生する費用は主に「仲介手数料」「印紙税」「譲渡所得税」の3つに絞られます。
これらは売却プロセスの根幹を成す費用として、金額規模や計算方法を理解しておく必要があるでしょう。
仲介手数料は売却価格に連動して増減し、印紙税は契約書に貼付する収入印紙代として、譲渡所得税は利益に対して課税されます。
これらを把握しておかないと、手取り金額の見込みが大きくずれてしまう可能性があります。
まずは三大基本費用の全体像を押さえたうえで、それぞれの詳細を確認していきましょう。
それではまず、最も大きなウェイトを占める仲介手数料について詳しく見ていきましょう。
1-1. 仲介手数料(売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税)
仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬で、売買価格が400万円を超える場合「売却価格×3%+6万円」に消費税(現在10%)を加えた額が上限と定められています。
たとえば3,000万円の物件を売却した場合、「3,000万円×3%+6万円=96万円」に消費税を乗せて105万6,000円となります。この計算式によって、売却価格の約3.3%前後が手数料として発生しやすいです。見込みを立てる際には、必ずこの計算式をもとにシミュレーションすると安心です。
続いて、契約書にかかる印紙税について見ていきましょう。
1-2. 印紙税(契約書に貼付/売買金額によって異なる)
印紙税は売買契約書を作成する際に貼付する収入印紙の代金で、売買金額に応じて1,000円~6万円が課税されます。
たとえば売買金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円超~1億円以下なら6万円と区分されています(国税庁の不動産売買契約書の印紙税の軽減措置より)。売買契約締結時に買主・売主双方で半額ずつ負担する方法が一般的ですが、どちらか一方の負担にするケースもあり得ます。
また、軽減税率が適用される契約書もあるため、適用条件を事前に確認しておくと節約につながるでしょう。
契約書作成のタイミングで必ず発生する費用なので、見落としがないよう注意が必要です。
さらに、売却で利益が出た場合に必要になる譲渡所得税について見ていきましょう。
1-3. 譲渡所得税(所得税+住民税)
譲渡所得税は売却価格から「取得費用(購入代金や改良費など)+譲渡費用(仲介手数料・印紙税など)(※)」を差し引いた利益部分に対して課税される税金です。
国税庁によると譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」、5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、それぞれ以下の税率が適用されます:
- 長期譲渡所得:所得税15%+住民税5%=合計約20%
- 短期譲渡所得:所得税30%+住民税9%=合計約39%
たとえば3年前に3,000万円で購入した住宅を3,500万円で売却し、取得費用等を含めた譲渡費用が200万円だった場合、譲渡所得は300万円となり、約117万円の税金が発生します。
利益が膨らむほど税負担も大きくなる点にはくれぐれも注意しましょう。
※厳密には、特別控除も存在します。例えば、「3,000万円の特別控除」では、マイホームを売って譲渡益がある場合、譲渡所得を最大3,000万円控除できます。
2. 売却の状況によって発生する7つの追加費用
基本費用に加えて、売却の状況次第では以下のような費用が追加で発生します。
これらはケースバイケースで必要性が変わるため、事前のチェックが重要といえます。
- ローン残債がある場合:繰上返済手数料
- 抵当権抹消登記費用(司法書士報酬含む)
- ハウスクリーニングや簡易リフォーム費用
- 測量・境界確定費用(土地売却時に必要)
- 建物の解体費用(更地渡しの場合)
- 引越し・移転費用
- 税理士報酬(譲渡所得の申告が必要な場合)
それでは、一つずつ見ていきましょう。
2-1. ローン残債がある場合:繰上返済手数料
ローンが残っている不動産を売却する際は、ローンを一括返済したうえで抵当権抹消が必要になります。
たとえば残債2,000万円を返済するときに一括返済手数料が2万円かかった場合、手取り金額はその分だけ減少します。期間変更型か全額繰上型かによって手数料率が変わるため、事前に金利プランや返済方法の違いを確認しておくとよいでしょう。
返済後に抵当権抹消登記費用も別途必要になる点も押さえておきたいですね。
2-2. 抵当権抹消登記費用(司法書士報酬含む)
ローン完済後、登記所での抵当権抹消手続きを行うためには登録免許税(1件あたり1,000円)と司法書士への報酬(5,000円~2万円程度)が必要となります。
司法書士に依頼すると、書類作成から申請代行まで一括で任せられるため手間は省けますが、その分報酬額が発生します。
たとえば3件の抵当権抹消が必要な物件では登録免許税3,000円+司法書士報酬2万円で合計2万3,000円前後となるケースも挙げられます。自分で手続きをすることで出費を抑えることもできますが、書類不備のリスクもあるため判断が分かれるところです。
2-3. ハウスクリーニングや簡易リフォーム費用
購入検討者の印象を向上させるため、売却前にハウスクリーニングや簡易リフォームを行うケースがあります。
おおよそ費用相場は3万~10万円程度で、クロス張替えや網戸補修、キッチン周りのクリーニングなどが中心となることが多いです。
たとえば20年経過したマンションなら、浴室やキッチンを中心にリフォーム依頼をすると購入意欲が高まりやすく、売却スピードが上がる可能性があります。
ただし高額な大規模リフォームは費用回収が難しい場合もあるため、相見積もりを取って必要最小限に抑えることが大切となるでしょう。
2-4. 測量・境界確定費用(土地売却時に必要)
土地を売却する場合、正確な面積を示すための測量費用は一般的に35万~80万円程度かかります。
公図だけでは境界が曖昧になるケースが多いため、土地家屋調査士に依頼して境界確定を行うと安心です。
費用は、たとえば200坪程度の土地なら50万円前後、複雑な形状や官民立会いが必要な場合には80万円を超えることもありますが、
境界トラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引を実現する上で重要なステップといえます。
2-5. 建物の解体費用(更地渡しの場合)
古い建物を含めて売却するのではなく、更地で引き渡す場合は解体工事が必要です。
木造戸建ての平均的な解体費用は50万~100万円程度で、規模や構造によって変動します。
たとえば築30年の木造家屋(延床面積100㎡)を解体すると70万円前後が相場となることが多いです。解体に伴う廃材処分費用や足場設置費用も含めると、さらにコストがかさむ点に注意が必要です。
価格交渉をする前に、必ず複数業者から見積もりを取るようにしましょう。
2-6. 引越し・移転費用
売却に伴って転居が必要な場合、引越し業者への支払いが発生します。
単身なら5万~10万円、ファミリー世帯なら10万~30万円が相場です。
距離や荷物量、繁忙期か否かで大きく変わるため、早めに日程を確定して、相見積もりを取ると安く抑えられる可能性があります。
荷物の量を減らしたり、オフシーズンを狙うことで数万円単位で節約できるケースもあります。
新居の初期費用も合わせてシミュレーションしておきましょう。
2-7. 税理士報酬(譲渡所得の申告が必要な場合)
譲渡所得が発生した場合、確定申告の際に税理士へ依頼すると報酬が10万~30万円程度かかります。
譲渡所得の計算や節税対策、書類作成をプロに任せられる一方で、報酬額が発生する点には注意が必要です。
申告期限(売却翌年の3月15日)までに余裕をもって相談すれば、修正申告リスクや追加費用を避けることができるでしょう。
費用を抑えるために自分で申告書を作成する方法もありますが、ミスによるペナルティのリスクを考慮しましょう。
3. 不動産売却費用を安く抑える10の工夫
追加費用の発生を最小限に抑え、手取り額を増やすには様々な工夫があります。
- 所有期間5年超なら長期譲渡所得税率を適用
- 3,000万円特別控除などの特例を活用
- 譲渡損と他の利益を損益通算
- リフォーム・クリーニングは必要最小限に
- 不要品を処分・フリマで売却してコスト圧縮
- 売却前提でローン商品を選択
- 相見積もりで各コストを比較
- 早めに不動産会社や税理士に相談
3-1. 所有期間5年超なら長期譲渡所得税率を適用
所有期間が5年を超えていると、譲渡所得税の税率が約20%(所得税15%+住民税5%)となり、短期の約39%と比べて負担が大幅に軽減します。
そのため、売却タイミングを調整できれば節税効果は非常に大きいといえます。売却予定がまだ先なら、5年超えを待つだけで手取りが増える可能性があります。
税率差を意識した売却タイミング戦略は有効な節約術といえるでしょう。
3-2. 3,000万円特別控除などの特例を活用
居住用不動産の売却で譲渡益が出た場合、3,000万円までの特別控除を受けられる制度があります。
たとえば譲渡益が3,500万円の場合、3,000万円まで非課税となり、課税対象は残りの500万円だけとなるため、税額負担を大幅に減らせます。
ただし居住用要件や所有期間などの適用条件があり、住み替え特例など他の制度との併用制限にも注意が必要です。
適用可否は専門家に相談すると安心でしょう。
3-3. 譲渡損と他の利益を損益通算
マイホームを譲渡して損失(譲渡損)が出た場合、給与所得など他の所得と損益通算できるケースがあります。
たとえば売却価格が取得費用に満たず損失が生じた場合、その損失額を他の所得から差し引くことで節税効果を得られます。ただしマイホームに限られる特例があるため、適用対象や申告手続きに注意が必要です。
譲渡損が発生しそうな場合は、早めに税務署や税理士に確認しておくとよいでしょう。
3-4. リフォーム・クリーニングは必要最小限に
見栄え向上のためのリフォームやクリーニングは効果的ですが、過度な投資は費用倒れの原因になります。
小規模な補修や汚れ落としにとどめることで、費用を抑えつつ、購入検討者には清潔感をアピールできます。
たとえばクロス張替え1面だけを行う、キッチン周りのみ専門クリーニング業者に依頼するといった節約術があります。
効果とコストのバランスを見極めることが重要です。
3-5. 不用品を処分・フリマで売却してコスト圧縮
売却に伴う引越し費用を減らすには、不用品を早めに処分したり、フリーマーケットを活用して現金化する方法があります。
荷物量が減ればトラックサイズを小さくでき、引越し費用が数万円単位で安くなる可能性があります。
また、フリマで得たお金をリフォーム費用などに充当できるメリットもあります。
3-6. 売却前提でローン商品を選択
マイホーム購入時に「売却時の繰上返済手数料無料」などの特典があるローン商品を選んでおくと、将来の売却費用を削減できます。
金融機関によっては特別プランがあり、手数料無料の代わりに金利が若干高めに設定されるものもあります。
ライフプランに応じて金利差と手数料メリットを比較検討し、総返済コストが最小限となる商品を選ぶようにしましょう。
3-7. 相見積もりで各コストを比較
仲介手数料・リフォーム・解体・測量・引越しといった業者コストは、必ず複数社で見積もりを取り比較検討しましょう。
数社間で数万円から十万円単位の差が出ることも珍しくありません。
オンライン査定や一括見積もりサービスを活用すると、手間をかけずに見積もりを取ることが可能です。コスト削減の基本は「比較」と「交渉」にあると心得ましょう。
3-8. 早めに不動産会社や税理士に相談
売却を決めた段階で早めに専門家に相談すると、適用可能な制度や交渉余地を見逃さずに済みます。
不動産会社は市場動向を踏まえた価格設定や販売戦略を提案し、税理士は節税スキームをアドバイスしてくれます。
売却活動中でも相談窓口を確保しておけば、急なトラブルや税務上の不明点を迅速に解消できるでしょう。
情報の鮮度が高いほど、コスト削減効果も大きくなります。
4. 不動産売却費用は“想定外”が多い|事前準備がカギ
売却費用には予期せぬ支出が紛れ込みやすく、想定外の出費で手取りが大きく減るリスクがあります。
事前に費用項目を洗い出し、逆算することで安心して取引を進められるでしょう。
それでは、手取り額を確保するための逆算方法から見ていきます。
4-1. 売却価格から“手取り額”を逆算しておく
最初に希望する手取り額を設定し、そこから必要費用を差し引いた逆算シミュレーションを行うと、売り出し価格の目安が明確になります。
たとえば「手取りで2,000万円を確保したい」場合、仲介手数料・印紙税・譲渡所得税などを合計すると、売却価格は2,200万円以上に設定する必要があるといった具合です。
事前に不動産会社とも数字を共有しておくことで認識齟齬が防げるでしょう。
価格交渉や値下げ対応にも落ち着いて臨めるよう、シミュレーションをしておきましょう。
4-2. 「見えないコスト」を洗い出す
測量費用や解体費用、ハウスクリーニング費など、契約書に明記されない「見えないコスト」をあらかじめ洗い出しておくことも成功のポイントです。
土地の境界トラブル対策や設備故障リスクまで想定しておくと、追加出費のショックを避けることができるかもしれません。
たとえば隣地所有者との境界協議に費用や時間がかかるケース、老朽化した給排水管の修繕費用など、実際の取引で必須になる支出を想定しておきましょう。
取引経験が豊富な宅建士や司法書士にも相談し、見落としリスクを最小化しましょう。
5. まとめ
不動産売却にかかる費用は、基本費用3項目に加えて、状況に応じてかかる追加費用が多岐にわたります。
事前準備として各費用の計算式を理解し、節約の工夫を取り入れることで手取り額を最大化できるでしょう。
最後に、専門家へ早めに相談して想定外のコストを洗い出し、シミュレーションを徹底することで、安心かつ効率的な不動産売却に繋がるでしょう。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案をしております。お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機に一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
