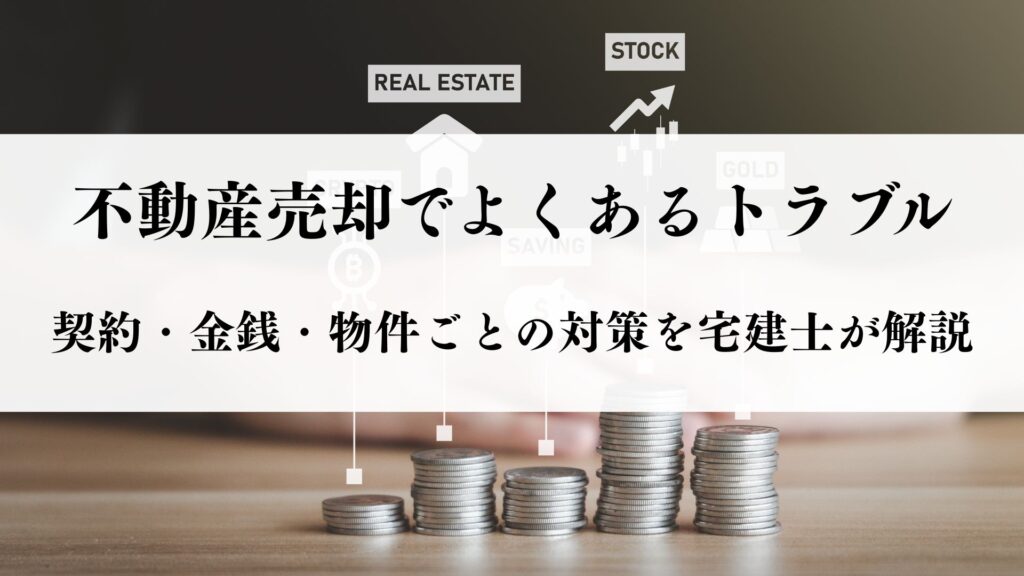
- 不動産売却でよく起こるトラブルについて知りたい
- トラブルを未然に防ぐために、どのような対策を取ればよいか分からない
- 万が一トラブルが発生した場合、どこに相談すればよいか分からない
不動産売却にあたって、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。不動産のプロが、不動産売却のトラブル例を契約・金銭・物件ごとに解説します。
この記事を読むことで、不動産売却に関する不安を解消し、トラブルを最小限に抑えたスムーズな売却を実現するためのヒントが得られるでしょう。
1. 契約に関するトラブル例
まずは、不動産売却において契約段階で起こりやすいトラブルについて見ていきましょう。
事前に実際のトラブル事例を知っておくことで、同じようなトラブルに巻き込まれるリスクを減らすことができます。
ここでは、以下の2つの代表的なトラブルについて解説します。
- 媒介契約を結んだ不動産会社による「囲い込み」
- 買主からの一方的な契約解除
1-1. 媒介契約を結んだ不動産会社による「囲い込み」
「囲い込み」とは、不動産会社が売り出し中の物件情報を自社内に留め、他社に紹介しないことで、自社での成約を優先する行為です。
売主は買い手候補が十分に集まらず、適正な売却価格での取引機会を逃す可能性があります。また、売却期間が長引き、余分な維持コストが膨らむことも考えられます。
例えば、あるケースではA社が自社サイトのみで物件に掲載し、数百万円高く購入希望を出していた買い手を取り逃した事例が挙げられます。囲い込みを防ぐ対策として、媒介契約の種類(一般媒介・専任媒介・専属選任媒介)と情報公開の範囲を事前に確認することが重要となるでしょう。
複数の不動産会社に査定依頼し、広く情報を出してもらうと安心です。
1-2. 買主からの一方的な契約解除
契約締結後に、買主が手付金を放棄して契約不適合を理由に契約を解除するケースがあります。
これは、買主の資金計画変更や住宅ローン審査の不承認といった事情が背景にあることが多いです。
例えば、買主であるBさんがローン審査に通らず、手付金を放棄して契約を解除した事例では、売主にとって大きな精神的負担がかかりました。また、契約書には解除手続きや書類提出の期限が定められており、確認が不十分だとトラブルが生じる可能性が高いです。
また、契約書には解除条件や手付金の取り扱いが明記されているかを確認し、リスクを把握して進めましょう。
不安がある場合は、宅建士や弁護士など専門家のアドバイスを受けると、解除後の対応がスムーズになります。
次に、金銭面で起こりやすいトラブルについて見ていきましょう。
2. 物件に関するトラブル例
不動産売却では、物件そのものに関するトラブルも多く発生します。
- 瑕疵の申告漏れ(物理的・環境的・心理的・法的)
- 土地の境界線をめぐるトラブル
- 地中埋設物の発見による責任問題
- 引き渡し後の残置物トラブル
- 管理規約や重要事項説明の不備(マンション等)
以下で、それぞれについて解説します。
2-1. 瑕疵の申告漏れ(物理的・環境的・心理的・法的)
物理的な欠陥だけでなく、騒音や近隣トラブルといった心理的・法的瑕疵も、申告漏れがあるとトラブルの原因になります。
申告が不十分だと、引き渡し後に買主から修繕費や損害賠償を請求される可能性があります。
例えば、マンションで過去に給排水トラブルがあったにも関わらず未申告だったため、買主から雨漏り修繕費を請求された事例があります。その対策としては、法的瑕疵として、騒音や近隣トラブルの履歴も含める必要があります。
正確な情報開示を心がけ、インスペクション(建物状況調査)結果も契約書に添付しましょう。
2-2. 土地の境界線をめぐるトラブル
隣地との境界が不明確な場合、売却後に立会いや境界確定作業が必要になることがあります。
これは、登記簿上の境界と現地の筆界が一致していない場合に起こりやすいです。
例えば、隣家所有者の同意が得られず、売主が追加で境界確定作業を実施した事例がありました。その対策としては、筆界確認書や立会書を作成し、買主・隣地所有者双方の合意を記録しておくことが有効です。
境界明示を含む契約プランも検討しましょう。
2-3. 地中埋設物の発見による責任問題
地中に埋まった廃材や古い擁壁などが売却後に見つかると、売主に契約不適合責任が問われることがあります。事前調査を怠ると、多額の撤去費用を請求されることがあります。
例えば、所有地で古いボイラー室基礎が地下埋設物として見つかり、売主が撤去費用を全額負担した事例が報告されています。その対策としては、告知書に埋設物の有無を正確に記載し、専門業者による地中調査を実施し、報告書を添付すると安心です。
瑕疵保険への加入も検討しましょう。
2-4. 引き渡し後の残置物トラブル
引き渡し後に家具や家電などの残置物があると、買主とのトラブルに発展することがあります。約束された状態での引き渡しが守られないと、損害賠償や撤去費用の請求を受ける可能性があります。
例えば、大型家電が残されたまま引き渡され、買主が撤去費用を請求した事例があります。その対策としては、契約書に残置物処理の範囲や撤去費用負担者を明記し、引渡し前に現地確認を徹底しましょう。
引き渡し前のチェックリスト作成も効果的です。
2-5. 管理規約や重要事項説明の不備(マンション等)
マンション売却では、管理規約違反や重要事項説明書の誤記載や説明不足がトラブルを招きます。説明が不足した場合、買主が契約後に約款違反や修繕積立金未納を理由に契約解除を検討する場合があります。
例えば、マンションでペット規約の改定履歴を記載漏れし、買主にとって重要な情報が抜けていると、契約解除のリスクもあります。その対策としては、最新の管理規約や会計状況を開示し、重要事項説明書の内容を専門家に確認してもらいましょう。
瑕疵保険加入時に契約不備のチェックリストを活用することが重要です。
次に、不動産売却に伴うトラブルを防ぐための基本的な対策について確認していきましょう。
3. 不動産売却トラブルを最小限に抑えるには
不動産売却におけるトラブルは、事前の対策によってスムーズな不動産売却が実現しやすくなります。
- 物件の不具合・心理的要因があれば正直に伝える
- 重要なやりとりは必ず書面やメールで残す
- 悪質な不動産会社を見抜くポイント
以下で、それぞれについて解説します。
3-1. 物件の不具合・心理的要因があれば正直に伝える
小さな不具合でも隠さず伝えることで、後々の契約不適合責任を軽減できます。
心理的瑕疵も同様に開示すると、買主の信用を得るだけでなく、契約不適合責任のリスク軽減にもつながります。
例えば、ある物件では過去に騒音問題があったことを事前に伝えたことで、買主が納得して成約したケースがあります。インスペクション結果を契約書に添付し、買主側にも現状理解を促しましょう。
誠実な対応は信頼関係の構築につながり、トラブル抑制に有効です。
3-2. 重要なやりとりは必ず書面やメールで残す
口頭でのやりとりは証拠として残りにくく、後で認識のズレが生じ、トラブルにつながる可能性があります。
契約内容や費用、スケジュールはメールや書面で記録し、双方が確認できるようにしましょう。
たとえば、打ち合わせ内容をメールで詳細に残したことで、後の費用請求トラブルを回避できた事例があります。保存したやりとりは定期的にバックアップし、必要に応じて専門家に確認してもらうと安心です。
3-3. 悪質な不動産会社を見抜くポイント
強引な営業だったり、説明が不透明だったりする業者には注意が必要です。
不明瞭な費用や契約条項の早期提示を避け、複数社の比較を行いましょう。
過去のクレーム情報や口コミを調べ、都道府県宅建協会の相談窓口で業者情報を確認すると安心です。信頼できる担当者かどうか、人柄や回答内容で判断しましょう。
次に、万が一トラブルが発生した場合の相談先について、確認しておきましょう。。
4. トラブルが起きた時の相談先
様々な対策を講じたとしても、トラブルが起きてしまう可能性はあります。
そんな時に備えて、トラブル時の相談先を事前に把握しておきましょう。
- 宅建業者の相談窓口(都道府県の宅建協会など)
- 消費生活センターや国民生活センター
- 弁護士・司法書士・ADR(裁判外紛争解決手続
以下で、それぞれについて解説します。
4-1. 宅建業者の相談窓口(都道府県の宅建協会など)
各都道府県の宅建協会では、加盟業者に対する苦情や相談窓口があります。
無料で相談でき、業者調査や指導を依頼できることが特徴です。
例えば、協会窓口に相談したことで業者への調査が行われ、迅速に問題解決した事例があります。窓口の連絡先は都道府県別パンフレットやウェブサイトで確認可能です。正式な苦情申請には、問題の証拠となる書類や記録を用意しましょう。
4-2. 消費生活センターや国民生活センター
消費生活センターや国民生活センターは、消費者トラブル全般に関する相談が可能です。
不動産取引も対象で、助言や仲介によって解決を図ります。
例えば、広告費請求のトラブルを相談し、返金調整が行われたケースがあります。電話相談のほか、オンライン窓口や持ち込み相談も利用できるため、まずは最寄りのセンターへ問い合わせるとよいでしょう。
4-3. 弁護士・司法書士・ADR(裁判外紛争解決手続)
法的対応が必要な場合は、弁護士や司法書士、ADR機関の利用が有効です。ADRは裁判を伴わない紛争解決手続で、迅速かつ低コストでの解決が期待できます。
例えば、ある人がADRを利用し、業者との賠償金支払いで合意に至った事例があります。専門家の初回相談は無料のケースもあるため、早めに法律専門家へ相談すると安心でしょう。
5. まとめ
ここまで、不動産売却で起きやすいトラブルと対策、相談先を解説しました。
不動産売却におけるトラブルは、早めに問題点を把握し、適切な対策を取ることでリスクを抑えられます。
まずは信頼できる不動産会社選びと契約書の内容確認を徹底し、物件情報は正確かつ誠実に開示しましょう。
また、金銭や物件状態のやりとりは必ず書面やメールで記録し、疑問点は専門家へ相談してください。
万が一問題が起きた場合、都道府県宅建協会や消費生活センター、ADRなど、公的機関を活用し、解決に向けて進めてください。
これらを意識すすることで、スムーズで安心な不動産売却が実現できるでしょう。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案をしております。インフレ対策を含めた資産運用について、お客様の状況を鑑みながら、的確なアドバイスを提供いたします。
これを機に一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
