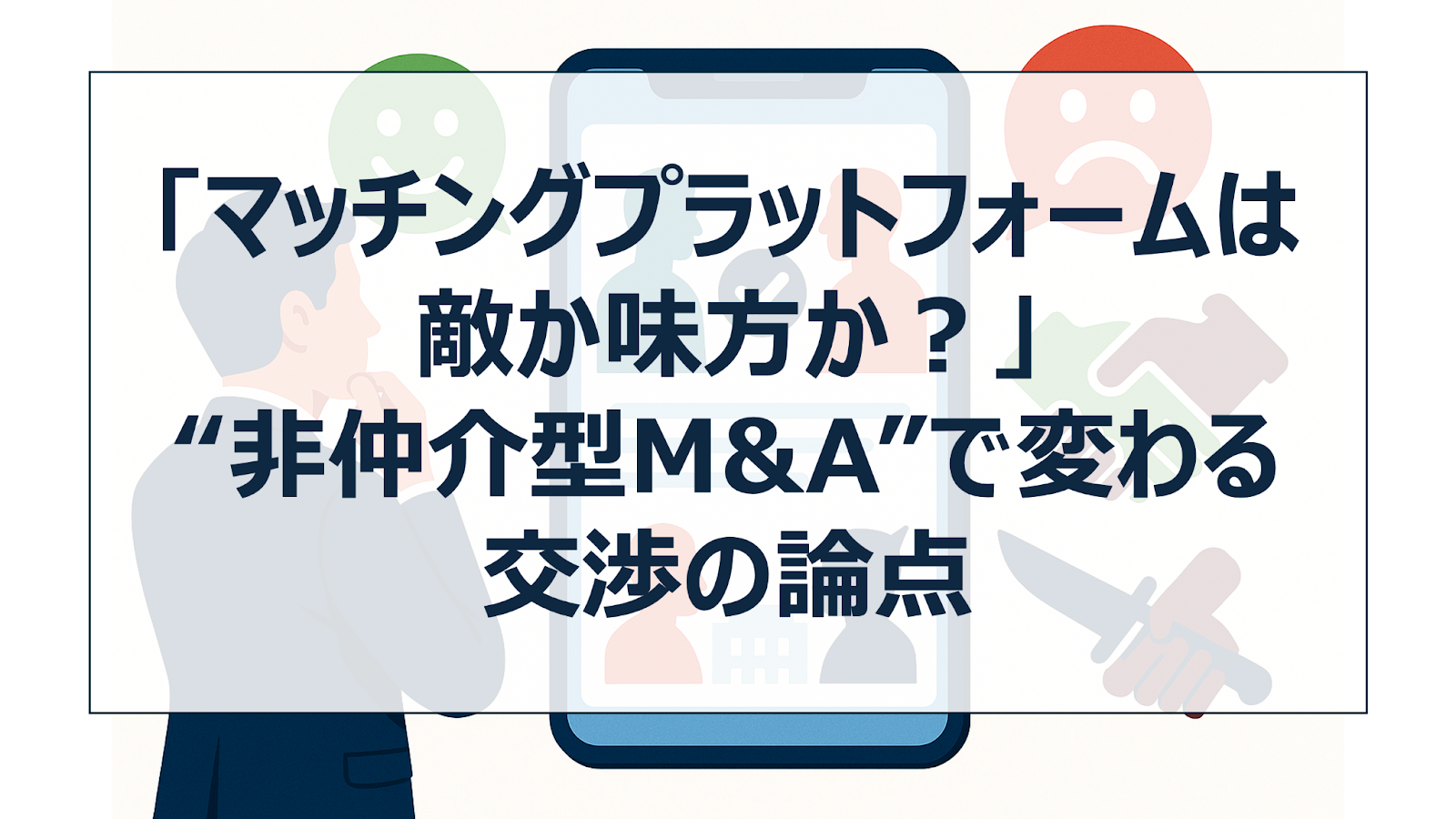
- 非仲介型M&A市場の実態とは?
- M&Aマッチングプラットフォームの強みと限界とは?
- 仲介なしでM&A成功しやすい企業について知りたい
このような疑問をお持ちではないでしょうか。本記事では、M&Aのプロが「非仲介型M&A市場の実態」について解説します。
この記事を読むことで、M&Aマッチングプラットフォームに関する不安を整理し、効率的なM&A交渉に役立てることができるでしょう。
目次
1. 急成長する“非仲介型M&A”市場の実態
1-1. バトンズ・TRANBIが広げた「個人間M&A」の裾野
1-2. マッチングプラットフォームが支持される理由
2. プラットフォーム型M&Aの“強み”
2-1. 情報の対称性が高まり、初心者でも交渉に入れる
2-2. 案件データベース化で「探しやすさ」「スピード感」が向上
3. プラットフォーム型M&Aの“3つの限界”
3-1. 表面情報しか見えないことで起こる誤解
3-2. 対面の“温度感”や空気が伝わらないまま進む危うさ
3-3. 「誰が責任を取るのか」が曖昧になりがち
4. 仲介なしでも成立しやすい企業とそうでない企業の違い
4-1. スキームがシンプルなスモールM&Aは成立しやすい
4-2. 利害が複雑な事業譲渡・一部売却は難易度が高い
5. まとめ
1. 急成長する“非仲介型M&A”市場の実態
非仲介型M&A市場は近年急速に拡大しています。その背景には、案件探索のオンライン化と、M&A全体の活況があります。
1-1. バトンズ・TRANBIが広げた「個人間M&A」の裾野
非仲介型M&Aは、案件探索のオンライン化により裾野が一気に広がりました。
国内大手の「バトンズ」は常時数万件規模の売り案件を掲載し、買い手候補からの申込みも集まりやすい仕組みを整備しています。
「TRANBI」も会員数の拡大や安全対策の強化を進め、初心者でも安心して検索・接点づくりに取り組める環境を提供しています。
プラットフォーム台頭の背景には、M&A全体の活況もあります。日本全体でも大規模ディールの増加で、アジアのM&Aをけん引する場面も見られ、市場での存在感が増しています。こうした裾野拡大とマクロ環境の追い風が重なり、個人や中小企業がM&A市場に参加しやすくなったと考えられます。
特に重要なのは、数字や機能だけでなく「アクセスのしやすさ」です。登録や検索がオンラインで完結し、初期の情報収集コストが大幅に下がり、従来は参入しづらかった層まで市場に入れるようになりました。
1-2. マッチングプラットフォームが支持される理由
プラットフォームが支持を集める理由は大きく3つに整理できます。
・選択肢の広さ
・スピード
・コスト透明性
案件を横断検索できるため、従来の「紹介待ち」に比べて初期母集団が増えます。
問い合わせやメッセージ機能で一次接点までの時間が短縮されることも評価されています。
行政のガイドライン整備が進み、手数料や役割の説明が求められるようになったことも安心材料です。これにより、利用者は「どの段階を自分で、どこから専門家に頼るか」を比較しやすくなっています。
その結果、まずはプラットフォームで案件を探索し、必要に応じて専門家を加えるという段階的アプローチが一般化しつつあります。
2. プラットフォーム型M&Aの“強み”
プラットフォーム型M&Aには、従来の仲介型にはなかった独自のメリットがあります。ここでは主に次の2点について解説します。
・情報の対称性が高まり、初心者でも交渉に入れる
・案件データベース化で「探しやすさ」「スピード感」が向上
