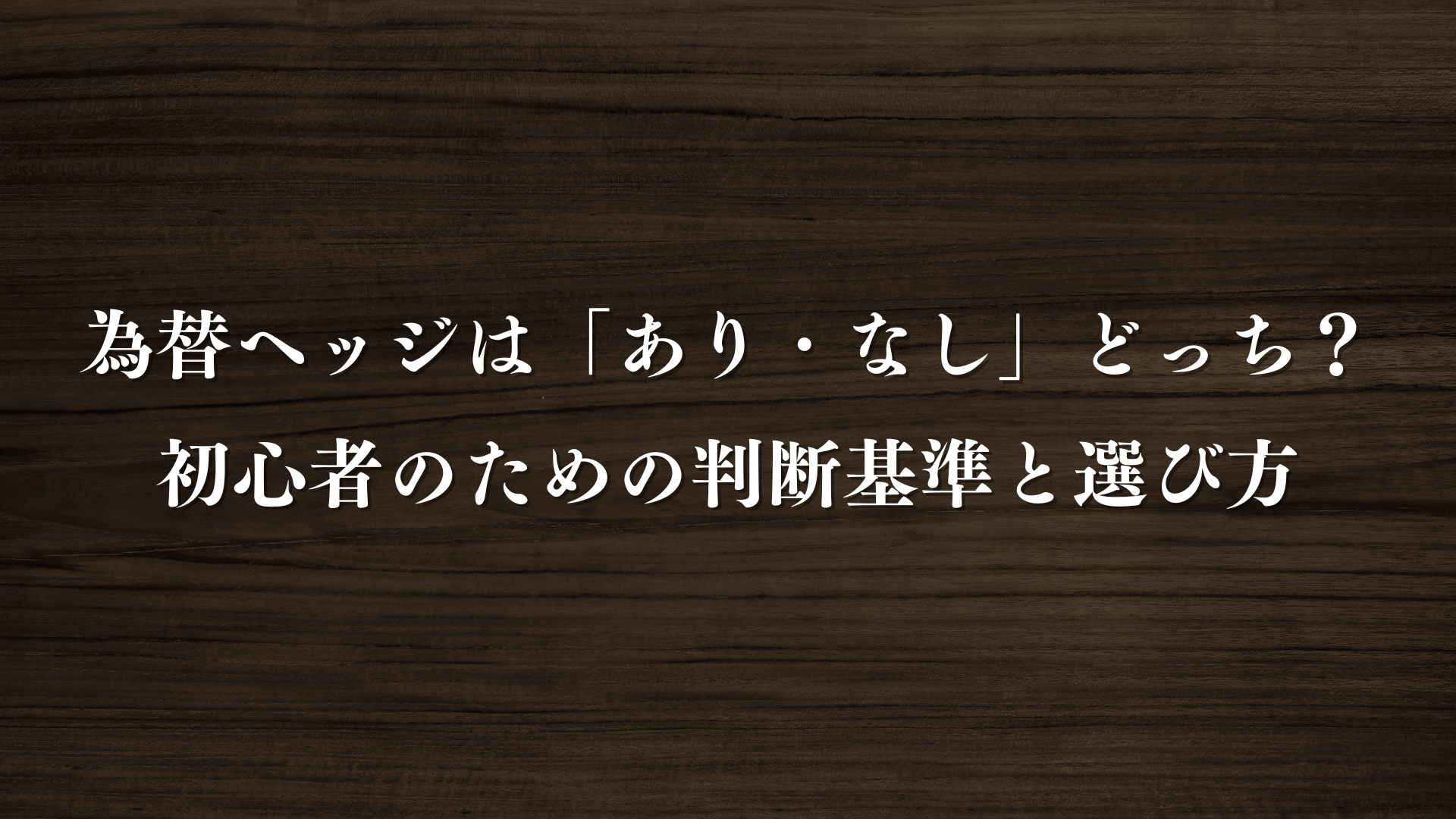
海外の株式や債券に投資する際、多くの初心者が悩むのが「為替ヘッジを付けるべきかどうか」という選択です。
為替ヘッジは円高リスクを抑えられる一方で、コストが発生し円安のメリットを享受できなくなる可能性があります。
本記事では、為替ヘッジの基本的な仕組みやメリット・デメリットを整理し、初心者が判断する際の基準や投資信託の選び方をわかりやすく解説します。
1.為替ヘッジとは?初心者がまず知っておきたい基礎知識
1-1.為替リスクとは何か
1-2.為替ヘッジの基本的な仕組み
2. 為替ヘッジ付き投資信託の仕組みとコストの考え方
2-1. 為替ヘッジにかかる主なコストとは?
2-2. ヘッジコストが運用成績に与える影響とは?
3. 為替ヘッジ「あり」「なし」それぞれの特徴を比較
3-1. ヘッジなしのメリット・デメリット
3-2. ヘッジありのメリット・デメリット
4. 為替と投資の関係 円高・円安が運用にどう影響する?
4-1. 円高・円安で投資信託の評価額はどう動く?
4-2. 為替ヘッジの有無でリターンはどう変わるのか
5. 初心者が投資信託を選ぶときのチェックリスト
6.まとめ
1.為替ヘッジとは?初心者がまず知っておきたい基礎知識
海外の株式や債券、投資信託に投資するとき、多くの人が気になるのが「為替の影響」ではないでしょうか。
投資先の値動きだけでなく、為替の変動によっても運用成績が大きく左右されるためです。この為替リスクを軽減するために活用されるのが「為替ヘッジ」という仕組みです。
初心者の方にとっては少し難しく聞こえるかもしれませんが、基本的な考え方を押さえれば理解はそれほど難しくありません。ここでは、為替リスクと、為替ヘッジの基礎知識をわかりやすく解説します。
1-1.為替リスクとは何か
為替リスクとは、外貨建ての資産を保有する際に生じる「為替相場の変動による損益」のことです。
たとえば米国株に投資した場合、株価が上昇しても円高が進めば、円に換算したときのリターンは目減りしてしまいます。逆に株価が横ばいでも円安が進めば、為替差益によって円換算の評価額が増えることもあります。
つまり、日本の投資家にとっては「投資先の値動き」と「為替の値動き」という2つの変動要因が運用成績に影響を与えるのです。
1-2.為替ヘッジの基本的な仕組み
為替ヘッジとは、将来の為替変動による影響をできるだけ抑えるための仕組みです。
具体的には、金融機関が「先物取引」や「スワップ取引」といった手法を用いて、将来の為替レートをあらかじめ固定することで実現されます。
たとえば、投資信託で米ドル建て資産に投資するとします。為替ヘッジをかけると、円高になってもあらかじめ決めたレートで円に換算できるため、為替による損失を防ぐ効果が期待できます。
言い換えると、投資の成果をできるだけ「純粋に資産の値動き」だけで判断できるようになるのがヘッジの役割です。
ヘッジあり・なしの違い
初心者が混乱しやすいのは「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」という表記の違いです。
・為替ヘッジあり :ヘッジをかける、つまり、為替変動による損益を抑えられる。ただし完全にゼロになるわけではなく、ヘッジコストが発生する。
・為替ヘッジなし :ヘッジをかけずに為替の変動をそのまま受ける。円安のときは有利に働くが、円高のときは損失要因になる。
このように、どちらにもメリット・デメリットがあるため、一概に「どちらが正解」とは言えません。投資する通貨や時期、そして投資家自身がどの程度のリスクを許容できるかによって選択が変わってきます。
初心者が理解しておきたいポイント
為替ヘッジを理解するうえで重要なのは、「為替リスクを取るか取らないか」というシンプルな視点です。
リスクを避けたいならヘッジありを、円安によるリターン拡大の可能性を取りにいきたいならヘッジなしを選ぶ、という考え方が基本になります。
ただし、為替ヘッジにはコストがかかるため、必ずしもリスクを抑えた分だけ有利になるとは限りません。この点は次章以降で詳しく触れていきます。
2. 為替ヘッジ付き投資信託の仕組みとコストの考え方
為替ヘッジ付きの投資信託は、海外資産に投資する際に「為替変動による影響を抑えたい」と考える投資家に向けた仕組みを持っています。
