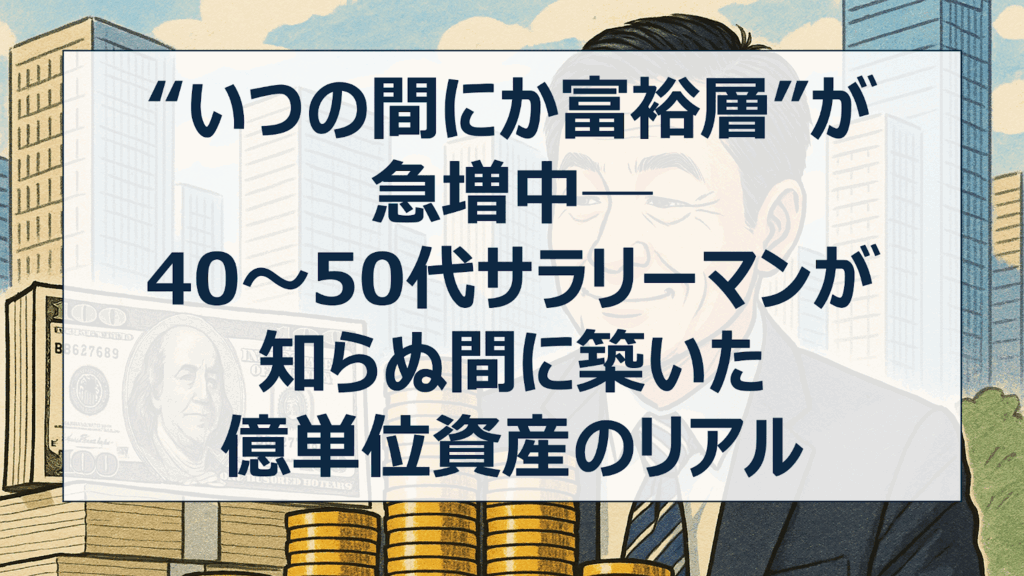
- 今の40〜50代サラリーマンがどのように資産形成したかを知りたい
- 富裕層予備軍が今後意識した方が良いことについて知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
資産運用のプロが、いつの間にか富裕層の実態と特徴について解説します。
この記事を読むと、富裕層に関する疑問を解消でき、安定的な資産運用に役立つでしょう。
1. 「いつの間にか富裕層」とは
近年、日本において「富裕層」の定義が広がり、これまでとは異なるタイプの資産家が増えています。特に、野村総合研究所(NRI)が提唱する「いつの間にか富裕層」は、その代表的な存在と言えるでしょう。
本章では「いつの間にか富裕層」とは何かを、以下の観点から解説します。
- 日本最大手のシンクタンクが定義する「富裕層」と「準富裕層」の基準
- 「いつの間にか」型が増える社会的背景
1-1. 日本最大手のシンクタンクが定義する「富裕層」と「準富裕層」の基準
野村総合研究所(NRI)の推計では、日本における富裕層と準富裕層に明確な基準が設けられています。この基準を知ることで、自分がどの階層に属するのか、また目標とする資産額を具体的にイメージしやすくなります。
NRIでは、純金融資産の合計額から負債を差し引いた額に基づいて、世帯を5つの階層に分類しています。
- 超富裕層:純金融資産が5億円以上
- 富裕層:純金融資産が1億円以上5億円未満
- 準富裕層:純金融資産が5千万円以上1億円未満
- アッパーマス層:純金融資産が3千万円以上5千万円未満
- マス層:純金融資産が3千万円未満
例えば、現在の純金融資産が7千万円であれば、「準富裕層」に分類されます。この定義は、預貯金だけでなく、株式、債券、投資信託、一時払い生命保険や年金保険など、世帯全体で保有する金融資産の合計額から、不動産購入に伴う借入金などの負債を差し引いた純粋な金額で判断されるものです。
これらの基準を踏まえると、2023年時点では、富裕層と超富裕層を合わせた世帯数は165万世帯に達し、前回の2021年時点と比較して11%も増加しました。また、純金融資産が5千万円以上1億円未満の準富裕層も、2023年時点で403万世帯となり、2021年と比較して24%増加していることがわかります。
このように、富裕層や準富裕層の定義を理解することは、自身の資産状況を客観的に把握し、今後の資産形成計画を立てる上で非常に重要だと言えるでしょう。
1-2. 「いつの間にか」型が増える社会的背景
「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人々が増加している背景には、主に近年の社会経済環境の変化、特に金融市場の動向と相続の増加などの理由があります。
主な増加要因として、好調な株式市場が挙げられます。実際、東証株価指数(TOPIX)は2017年末の1,818ポイントから、2023年末には2,366ポイントへと約30%も上昇しました。
例えば、株式や投資信託などリスク性金融資産を保有していた投資家は、この株価上昇によって、特別な行動をせずとも保有資産の価値が大幅に上昇したケースが考えられます。この傾向は、特にリスク性資産の比率が高い準富裕層以上の保有資産額を増加させ、準富裕層の一部が富裕層へ、富裕層の一部が超富裕層へと移行するきっかけとなりました。
また、相続の増加も準富裕層以上の世帯が増加している一因と考えられています。国税庁の相続統計によると、課税価格が3億円以上の被相続人数は2017年の8,039名から2022年には10,098名に増加しており、それに伴い法定相続人の数も27,395名から33,045名へと増えています。
例えば、親から受け継いだ資産が、本人の給与所得やこれまでの貯蓄と合わさることで、一気に富裕層の定義を満たす純金融資産額に達するケースが想定されます。このように、市場の好調と相続という二つの大きな流れが、「いつの間にか富裕層」の増加を後押ししていると言えるでしょう。
2. 富裕層入りした40~50代サラリーマンの特徴
「いつの間にか富裕層」として資産を築いた40~50代のサラリーマンは、従来の富裕層とは異なる独自の特性を持っています。
ここでは富裕層入りした彼らの特徴について、以下の2つの観点から解説します。
- 投資スタイルとリスク許容度
- 家計管理と支出の傾向
2-1. 投資スタイルとリスク許容度
「いつの間にか富裕層」に分類される40~50代の現役サラリーマンは、株式や投資信託といったリスク性資産を高い割合で保有している傾向があります。彼らは金融リテラシーやネットリテラシーが高く、情報収集や投資取引にデジタルツールを積極的に活用しています。
近年では、AI技術を活用して、個々の投資家の資産状況や行動履歴に基づいた投資情報を提供する金融サービスが増えています。こうしたサービスには、顧客の関心や取引傾向を分析し、重要な市場動向をリアルタイムで通知する機能が備えられています。
また、単に情報を一律に提供するのではなく、過去の取引時間や反応パターンに応じて、通知のタイミングや手段を最適化するなど、行動パターンに合わせたサポートが行われるのが特徴です。これにより、投資家は自身のペースで情報を受け取り、より自発的かつ効率的な投資行動につなげることができます。
しかし、このようなデジタル活用に長けている彼らも、複雑な金融商品や高額な取引を行う際には、対面でのアドバイスを求める傾向が見られます。
例えば、普段はスマートフォンのアプリで手軽に投資を行っているものの、数千万円単位の取引や、専門的な知識が必要な金融商品の検討の際には、金融機関の担当者との対面相談に切り替えるケースが想定されます。これは、デジタルサービスでの利便性を享受しつつも、重要な局面では専門家に任せる安心感や深い知識に基づいた提案を重視しているためと言えるでしょう。
彼らの特徴として、企業オーナーや地主といった従来の富裕層とは異なり、自身の資産を「家族全体の共有物」として捉える傾向が弱いことが挙げられます。そのため、金融機関の担当者との面談時に家族同席に消極的なケースも見られます。
例えば、相続や贈与といった将来の資産承継に関わる話をする際にも、家族を巻き込むことに抵抗を感じるサラリーマンが一定数存在すると考えられます。
2-2. 家計管理と支出の傾向
「いつの間にか富裕層」となったサラリーマンは、資産が1億円を超えても、生活様式や消費嗜好がマス層に近いという特徴が見られます。
彼らは給与収入の範囲内でこれまでの生活スタイルを維持していることが多く、金融資産が増えても、生活水準や金融行動に大きな変化があまりありません。
例えば、ある現役世代の富裕層は、資産が1億円を超えたタイミングで高額なゴルフセットを購入したり、家族旅行に出かけたりはしたものの、普段の家計は給料の範囲内でやりくりをしているといったケースもあります。このように衝動的な消費を避け、堅実な家計管理を続ける姿勢が見られるのが特徴です。
また、資産運用を金融機関の担当者や親族・知人の勧めに任せ、自らはあまり関与していない人も一定数存在します。
例えば、NISA(少額投資非課税制度)や確定拠出年金(iDeCo)など、税制優遇のある制度を積極的に活用しつつも、具体的な商品の選択や売買のタイミングについては専門家に任せたいと考えているケースが想定されます。この背景には、従来の富裕層に比べて金融知識が十分でないことや、多忙な日常の中で資産運用に時間を割けない事情があると考えられます。
3. 資産を築いたプロセス
40~50代のサラリーマンが「いつの間にか富裕層」と呼ばれるまでに資産を築けたのは、偶然の要因だけではありません。そこには、給与収入以外の収入源の活用や、長期的な視点での投資戦略が深く関わっています。
資産を築いたプロセスについて、以下に沿って解説します。
- 給与収入+副収入による資産形成
- 長期投資と複利効果の活用
3-1. 給与収入+副収入による資産形成
「いつの間にか富裕層」の多くは、本業である給与収入に加えて、資産運用による利益を効果的に組み合わせることで資産を増やしています。特に、確定拠出年金(DC)や従業員持株制度、NISA(少額投資非課税制度)などを活用した長期投資が、その成功の鍵を握っていることが多いです。
例えば、毎月の給与から一定額を積立投資に回すだけでなく、ボーナスの一部をリスク性資産に投入するなど、給与以外の資金も積極的に資産運用に充てるケースが考えられます。これにより、給与収入だけでは難しいスピードで資産を積み上げることが可能になるでしょう。
中でも従業員持株制度は、自社の株を定期的に購入し、会社からの奨励金が上乗せされることで、効率的な資産形成を促す側面があります。確定拠出年金やNISA枠の活用を通じて、運用資産が1億円を超えたケースが多く見られると野村総合研究所は推察しています。
このように、給与収入を着実に確保しながら、それ以外の収入源や制度を賢く利用することで、資産形成のスピードを加速させることが、彼らの成功の要因の一つと言えるでしょう。
3-2. 長期投資と複利効果の活用
「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人々、特に50代後半以降の現役サラリーマンは、確定拠出年金(DC)や従業員持株制度などを活用した長期投資によって、複利効果を最大限に享受している層が多く見られます。
※複利効果とは、投資で得た利益を再び投資に回すことで、元本だけでなく利益にも利息がつき、時間と共に資産が増えていく効果のこと。
例えば、若いうちから少額でも定期的に投資を始め、それを長期間にわたって継続することで、たとえ毎月の積立額が少額であっても、20年、30年といった長い期間をかけることで、複利の力が働き、想像以上の資産額になる可能性があります。
しかし、この層の中には、長期投資の仕組みを活用しているものの、必ずしも自身の資産状況を正確に把握しているわけではない人も存在すると言われています。多くの企業で確定拠出年金や持株制度が整備されていますが、制度があるからと「とりあえず利用してきた」という受動的な姿勢の加入者もおり、退職後に自分で運用を継続することに不安を感じるケースが見られます。
例えば、自分がどの銘柄に、どれくらいの割合で投資しているのかを定期的に確認せず、運用報告書などもあまり見ていないというケースが想定されます。年金シニアプラン総合研究機構の調査によれば、企業型DC加入者のうち、継続的な金融教育を受けたと認識している人の割合は約1割にとどまると報告されています。
このような背景から、金融機関はセミナーなどを通じて制度加入者との接点を確保し、退職前後の相談につながるきっかけを創出することが、顧客獲得に向けた重要な取り組みになるでしょう。
4. 投資パフォーマンスを維持するポイント
「いつの間にか富裕層」入りした人々は、これまでの投資戦略によって大きな資産を築き上げました。しかし、今後もそのパフォーマンスを維持し、さらに資産を増やしていくためには、継続的な努力と適切な知識が不可欠です。
投資パフォーマンスを維持するポイントについて、以下に沿って解説します。
- 忙しくても続けられる資産運用ルーティン
- 税制優遇制度の活用(NISA・iDeCo)
- 資産分散とリスク管理の徹底
4-1. 忙しくても続けられる資産運用ルーティン
「いつの間にか富裕層」の多くは、本業で多忙なサラリーマンです。そのため、彼らにとって重要なのは、手間をかけずに継続できる資産運用ルーティンを確立することにあります。
例えば、毎月特定の日に定額を自動で積み立てる「積立投資」の仕組みを活用するケースが考えられます。これにより、市場の動向に一喜一憂することなく、感情に左右されない安定した投資を続けることができます。一度設定してしまえば、あとは自動で運用が進むため、忙しい日々の中でも資産形成を着実に進めることができるでしょう。
また、デジタルツールを積極的に活用することも、効率的な資産運用ルーティンには不可欠です。投資アプリや資産管理ツールを利用することで、自身の資産状況をリアルタイムで把握し、必要に応じて迅速な対応が可能です。
例えば、日常的にスマートフォンアプリで投資情報を収集・管理し、市場の動向や自身のポートフォリオの状況を簡単にチェックすることで、手軽に運用を行うことができます。デジタルツールは、情報強者である「いつの間にか富裕層」が、お得さや便利さを求めて金融機関を選ぶ際にも重視するポイントであり、これを活用しない手はないでしょう。
ただし、金額の大きさや取引の複雑性によっては、デジタルチャネルだけでなく対面チャネルの活用も検討することが大切です。
4-2. 税制優遇制度の活用(NISA・iDeCo)
資産運用を効率的に進める上で、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇制度の活用は欠かせません。これらの制度は、投資で得られた利益に対して税金がかからない、あるいは軽減される仕組みであり、手元に残る資産を最大化できます。
例えば、NISAでは、一定額までの投資で得た利益が非課税となるため、通常であれば利益の約20%が税金として引かれるところ、全額手元に残すことが可能です。新しいNISA制度では非課税投資枠が大幅に拡充され、より多くの資金を非課税で運用できるようになりました。
iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税、さらに受け取る際にも税制優遇があるという、三重のメリットがある私的年金制度です。
例えば、毎月iDeCoに掛金を拠出することで、所得税や住民税の負担を軽減しつつ、長期的に老後資金を形成するケースが想定されます。特に、40代、50代のサラリーマンにとって、これらの制度を最大限に活用することは、将来の資産形成を加速させる上で非常に効果的だと言えるでしょう。
「いつの間にか富裕層」の多くは、これらの制度を積極的に活用して資産を増やしています。税制優遇制度のメリットを理解し、自身のライフプランに合わせて賢く利用することが、持続的な投資パフォーマンス維持の鍵となるでしょう。
4-3. 資産分散とリスク管理の徹底
投資パフォーマンスを維持し、資産を守る上で最も重要なのは、資産分散とリスク管理を徹底することです。株価の急騰を背景に富裕層入りした「いつの間にか富裕層」の中には、リスク性資産の比率が高まっている人も少なくないと考えられます。
例えば、特定の銘柄や資産クラスに偏って投資している場合、その市場が下落すると資産全体に大きな影響が出てしまうケースが考えられます。これは「集中投資」のリスクです。
資産分散とは、株式、債券、不動産、投資信託など、異なる種類の資産に投資をすることです。さらに、国内だけでなく海外の資産にも投資することで、地域的なリスクも分散できます。
例えば、日本株と米国株、さらには先進国債券や新興国投資信託など、複数の資産にバランス良く資金を配分することで、どれか一つの資産の価値が下がったとしても、他の資産がカバーし、全体としての下落幅を抑える効果が期待できるでしょう。
また、「いつの間にか富裕層」の中には、急増した保有金融資産の適切な分散投資方針や、富裕層向けの金融商品特性に関する知識が十分でないケースも見られます。そのため、定期的に自身のポートフォリオを見直し、リスクが偏っていないか確認することが大切です。必要であれば、金融機関の専門家と相談し、アドバイスを受けることも有効なリスク管理の一つと言えるでしょう。
5. 「富裕層予備軍」が今後意識すべきこと
すでに「いつの間にか富裕層」になった方々や、これから富裕層入りを目指す「富裕層予備軍」にとって、今後の資産運用は新たなステージに入ります。これまでのような資産形成だけでなく、築いた資産を守り、さらに次世代へと引き継ぐ視点も重要になります。
「富裕層予備軍」が今後意識すべきことについて、以下に沿って解説します。
- 資産防衛の重要性
- インフレ・金利上昇への備え
- ライフプランと資産運用の定期的アップデート
5-1. 資産防衛の重要性
資産が一定の水準に達すると、これまでの資産形成だけでなく、築いた資産をいかに守っていくかという「資産防衛」の視点が非常に重要になります。
特に「いつの間にか富裕層」となった方々は、給与所得者であることが多く、法人オーナーや地主といった従来の富裕層とは資産に対する意識が異なる傾向が見られます。彼らは自身の資産を「家族全体の共有物」として捉える意識が弱いことがあり、そのため、相続や贈与といった資産承継への関心が薄い場合があるようです。
さらに、金融機関との面談時に家族同席に消極的なケースも見られることから、家族間の情報共有の重要性を啓発し、家族会議の開催や資産目録の作成・共有を促すことが効果的なアプローチとなるでしょう。
これは、急な病気や介護など、予期せぬ事態が発生した際に、家族が資産の状況を把握しておらず、手続きに手間取るケースを避けるためにも重要です。資産防衛は、将来にわたって家族の安心を守るための大切な取り組みだと言えるでしょう。
5-2. インフレ・金利上昇への備え
資産を中長期的に維持・増加させていく上で、インフレ(物価上昇)や金利上昇への備えは不可欠です。これらは資産の実質価値を減少させたり、投資戦略に影響を与えたりする可能性があるからです。
例えば、インフレが進むと、現金の価値が目減りするケースが考えられます。100万円で買えたものが、インフレによって120万円必要になる、といった状況です。このような事態に備えるためには、現金だけでなく、物価上昇に強いとされる資産への投資を検討することが有効でしょう。
金利上昇も同様に重要ですし、金利が上昇すると、一般的に債券価格は下落する傾向にあります。また、住宅ローンなどの借入金がある場合は、金利負担が増える可能性もあります。
例えば、変動金利型の住宅ローンを組んでいる場合、金利が上昇すると毎月の返済額が増加し、家計を圧迫するケースが想定されます。そのため、金利上昇リスクに対応できるよう、固定金利型への借り換えや、繰り上げ返済を検討するなどの対策を講じることが重要になります。
これらのリスクに対応するためには、資産分散を徹底し、インフレヘッジとなる資産(例:不動産、株式の一部、金など)をポートフォリオに組み入れることを検討すべきでしょう。また、定期的に経済情勢をチェックし、自身の資産配分を見直す柔軟な姿勢も求められます。
5-3. ライフプランと資産運用の定期的アップデート
富裕層として、あるいは富裕層を目指す上で、ライフプランの変化に合わせて資産運用戦略を定期的に見直し、アップデートしていくことは非常に重要です。人生のステージが変われば、必要な資金やリスク許容度も変化するからです。
例えば、結婚、子どもの誕生、住宅の購入、転職、退職など、人生にはさまざまな転機があります。これらのイベントが発生するたびに、資産運用の目標や計画を見直すケースが想定されます。
具体的には、子どもの教育資金が必要になる時期には、リスクを抑えた運用にシフトしたり、住宅ローンの返済が進んだら、新たな投資資金を捻出したりといった調整が考えられます。
「いつの間にか富裕層」の中には、自身の資産状況を正確に把握していない層も存在すると言われています。そのため、定期的な資産状況の確認と、ライフプランに合わせた見直しが、特に重要になります。
例えば、年に一度は資産全体を棚卸しし、当初の目標と比較して運用状況がどうなっているか、ライフプランに変更はないかなどを確認するルーティンを取り入れるべきでしょう。これにより、予期せぬ市場の変動や個人の状況変化にも柔軟に対応し、長期的に安定した資産運用を続けることが可能になります。
6. まとめ
日本における富裕層および準富裕層の世帯数は、好調な株式市場と高額な相続の増加を背景に、過去最高の水準に達し、富裕層市場が拡大・多様化しています。
野村総合研究所(NRI)の推計によると、2023年時点で純金融資産1億円以上の「富裕層」と「超富裕層」は合計165万世帯となり、2021年から11%増加しました。また、純金融資産5千万円以上1億円未満の「準富裕層」も403万世帯に達し、24%増加しています。これは、東証株価指数(TOPIX)の約30%上昇や、課税価格3億円以上の被相続人数の増加などが主な要因です。
この富裕層市場の拡大に伴い、従来の富裕層とは異なる新しいタイプが出現しています。
- 「いつの間にか富裕層」は、株価上昇により資産が急増した一般の給与所得者やその出身者で、生活様式や消費嗜好がマス層に近いという特徴があります。彼らは金融知識が十分でない場合や、資産運用を人に任せているケースも存在します。
- 「スーパーパワーファミリー」は、都市部に居住し、世帯年収3,000万円以上の大企業共働き世帯に代表される層で、情報強者としてデジタルを活用し、タイムパフォーマンスを重視する傾向があります。 これらの新しい富裕層はデジタル親和性が高い一方で、高額で複雑な取引には専門家による対面サービスも求めるという二面性を持っています。
したがって、金融機関は、デジタルアプローチの強化、資産防衛や承継への関心に対応したサービス、そして金融教育の提供を通じて、これら多様化する富裕層のニーズに応じたパーソナライズされたサービスを提供していくことが重要です。
ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案を行っております。安定的に資産を増やしたい40~50代の方に対して、状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
