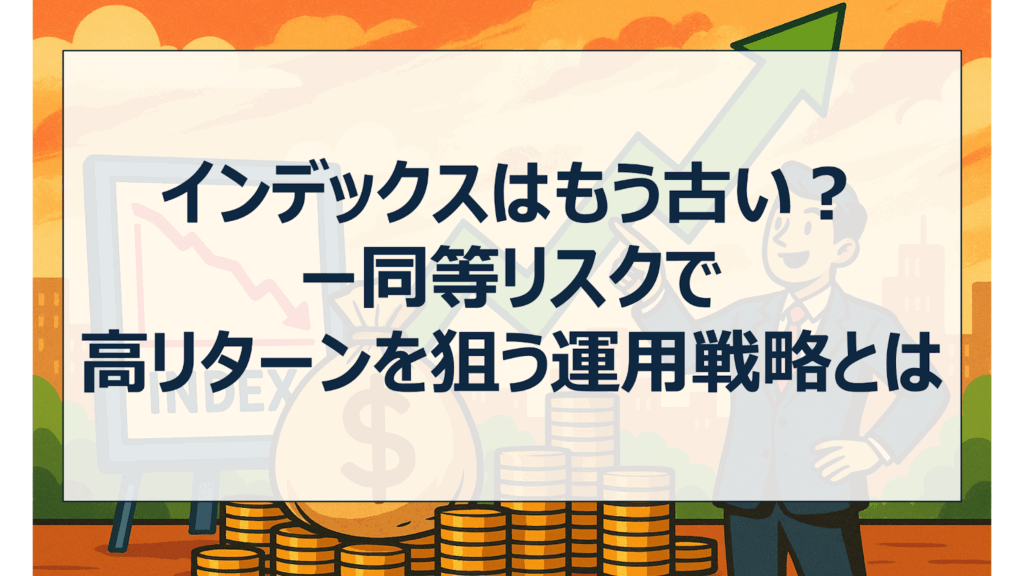
- インデックスはもう古いのか?その背景について知りたい
- インデックスと同等のリスクで、より高いリターンを狙える戦略を知りたい
- アクティブ運用を成功させるための条件を知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
資産運用のプロが、インデックスと同等のリスクで成果を狙えるアクティブ運用について解説します。
1. 「インデックスはもう古い?」論争の背景
1-1. 過去10年の市場環境とインデックスの推移(米大型株集中と世界株の動き)
近年、特に米国大型株に集中した市場の好調により、インデックス投資の優位性について再考を促す声が高まっています。これは、特定の市場が突出した成長を見せたことで、その市場に連動するインデックスが非常に高いリターンを示したためと考えられます。
米国株式市場は、過去10年間で非常に力強い成長を遂げています。例えば、主要な株価指数S&P500種株価指数は23年通年で24%高、24年も23%高と、連続して高いパフォーマンスを記録しました。このような環境下では、S&P500のような特定の大型株指数に連動するインデックスファンドが目覚ましいリターンをもたらすことがあり、実際に多くの投資家が恩恵を受けました。
ただし、こうした一極集中とも言える好成績が今後も続くのか、あるいは、他の市場と比較して過度にリスクを取っているのではないかという懸念も生じています。このような特定の市場動向が、インデックス投資の将来性やリスクについて議論を深めるきっかけになっているのです。
1-2. インデックス投資の強みと弱点(集中リスクとコスト優位性)
インデックス投資は、低コストで分散投資ができるという利点を持っています。特定の市場指数に連動する仕組みのため、運用にかかる手数料(信託報酬)が低い点が魅力といえるでしょう。
しかし一方で、そのインデックスが構成する銘柄が特定の地域や大型株に集中している場合、集中リスクを抱える可能性があります。
例えば、S&P500のような米国の大型株指数に連動するファンドは、米国経済全体に手軽に投資できる半面、もし米国経済が停滞したり、主要な大型株の成長が鈍化したりすれば、そのインデックスファンドのリターンにも大きな影響を及ぼす集中リスクが想定されます。実際に、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が出しているSPIVAレポートによれば、日本国内で販売されている米国株ファンドのアンダーパフォーマンス率は非常に高く、これは米国市場の効率性の高さとアクティブ運用の難しさを同時に示唆しているといえるでしょう。
低コストでリターンを享受できるインデックス投資ですが、その構成内容による集中リスクを適切に理解し、自身の投資目標に合致しているかを見極めることが、より賢明な判断に繋がります。
1-3. アクティブ運用側の主張と実績
アクティブ運用は、市場平均(インデックス)を上回る超過リターンを目指す投資手法です。ファンドマネージャーが独自の分析や調査に基づいて銘柄を選定し、市場平均を上回る運用成果を目指すため、理論上はインデックスファンドよりも高いリターンを期待できる可能性があります。
しかし、このような運用を行うには、アナリストなどの専門的なリサーチ部隊を抱える必要があり、その結果としてインデックスファンドよりも運用コストが高く設定されることが一般的です。この高コストこそが、アクティブファンドがインデックスファンドに勝ちにくいという構造的なハンディキャップとなることが多いでしょう。
例えば、SPIVA日本版2024年のデータを見ると、日本大型株ファンドの62%がベンチマーク(S&P/TOPIX 150)に劣後していますが、日本の中小型株ファンドでは57%がベンチマークを下回ったと報告されており、他のカテゴリーに比べて比較的健闘している様子がうかがえます。これは、中小型株市場のように情報が行き渡りにくく、比較的非効率とされる市場では、アクティブ運用が優位性を見出す余地があると考えられるからです。一方で、海外株式ファンド、特に米国株ファンドでは、10年以上の長期スパンで91%ものファンドがベンチマークに勝てていないなど、依然として厳しい現実が示されています。
アクティブ運用は特定の市場環境や運用の質によってはインデックスを上回る可能性も秘めていますが、全体としては高コストと市場の情報効率性の高さが、インデックスファンドに勝ちにくい構造的な理由となっていることを理解しておく必要があるでしょう。
2. 同等リスクでインデックスのリターンを上回る可能性のある戦略
「同等リスクでインデックスのリターンを上回る可能性のある戦略」として、以下の3つの戦略について解説します。
- ファクター投資(バリュー・クオリティ・モメンタム)
- セクター・テーマ型投資(AI・脱炭素・インフラ)
- オルタナティブ資産(REIT・プライベートエクイティ・ヘッジファンド)
2-1. ファクター投資(バリュー・クオリティ・モメンタム)
ファクター投資は、特定の企業特性(ファクター)に着目することで、インデックスと同等、またはそれ以下のリスク水準で超過リターンを狙う戦略の一つです。このアプローチは、市場の非効率性から生まれるリターンの源泉(ファクター)を体系的に活用しようとする考え方に基づいているため、伝統的な時価総額加重型インデックスでは捉えきれない収益機会を追求できる可能性があります。
代表的なファクターとしては、割安性を示す「バリュー」、企業の優良性を示す「クオリティ」、株価の勢いを示す「モメンタム」などが知られています。
例えば、割安な株式に投資する「バリューファクター」は、市場が一時的に過小評価している企業はやがてその本質的価値に見合った評価を受けるという考えに基づいています。具体的には、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)が市場平均よりも低いにもかかわらず、堅実な業績を上げている銘柄を厳選して投資するケースが考えられます。また、利益成長率が高く、財務が健全な企業に投資する「クオリティファクター」や、過去数ヶ月間にわたって株価が上昇傾向にある銘柄に投資する「モメンタムファクター」も存在します。
これらのファクターは、過去の市場データから、長期的に市場平均を上回るリターンをもたらす傾向があることが統計から確認できます。ファクター投資は、市場の非効率性に着目し、統計的に優位性が確認されている特性を持つ銘柄群に投資することで、インデックスを超えるリターンを目指す有望なアプローチの一つといえるでしょう。
2-2. セクター・テーマ型投資(AI・脱炭素・インフラ)
セクター・テーマ型投資は、将来の成長が期待される特定の産業分野や社会的トレンドに焦点を当てることで、市場全体の成長を上回る高いリターンを追求する戦略です。これらの投資は、技術革新や政府の政策支援、あるいは社会的な意識の変化によって加速されることが多いでしょう。
例えば、AI(人工知能)分野への投資は、AI技術の飛躍的な発展と社会全体への浸透により、関連企業の収益が爆発的に伸びるケースが考えられます。NVIDIAのようなAI関連企業が近年急成長を遂げたのは、このテーマ型投資の代表的な事例の一つといえるかもしれません。また、世界的な脱炭素社会への移行を背景とした再生可能エネルギー関連企業や、老朽化した社会インフラの更新・拡充に貢献する企業への投資も、長期的な成長トレンドに乗るための有効な戦略でしょう。このようなテーマ型投資は、特定の産業に特化するため、一般的なインデックスファンドよりも高いリターンを目指せる可能性があります。しかしその一方で、テーマが期待通りに進まなかった場合や、すでに株価に織り込まれてしまっている場合のリスクも考慮する必要があります。
セクター・テーマ型投資は、将来性のある分野を早期に見極め、集中投資することで高いリターンを目指す一方で、そのテーマの動向を注意深く見守る必要があります。
2-3. オルタナティブ資産(REIT・プライベートエクイティ・ヘッジファンド)
オルタナティブ資産は、伝統的な株式や債券とは異なる値動きをする特性を持つため、ポートフォリオ全体のリスクを分散しつつ、インデックスを上回るリターンを狙える可能性があります。また、情報やアクセスに優位性がある場合に、高い超過リターンが期待できる分野でもあります。
例えば、REIT(不動産投資信託)は、商業施設やオフィスビルなどの不動産を小口化して投資できる商品であり、賃料収入や不動産価格の上昇から収益を得るケースが考えられます。特に安定したキャッシュフローが期待できるため、株式市場との相関が低く、ポートフォリオの安定化に寄与することもあるでしょう。また、プライベートエクイティ(未公開株)投資は、成長初期段階の企業に投資し、企業価値の向上を通じて高いリターンを目指すもので、上場株式市場では得られない大きな成長を享受できる可能性があります。さらに、ヘッジファンドは、多様な投資戦略を用いて市場リスクを抑制しつつリターンを追求するため、市場が下落する局面でも利益を出すことを目的としています。ただし、これらのオルタナティブ資産は、一般的に流動性が低い、最低投資額が高い、情報開示が少ないといった特徴があるため、投資には十分な理解と専門知識が必要となります。
オルタナティブ資産は、伝統的な資産クラスと組み合わせることでポートフォリオの多様性を高め、長期的に安定した高リターンを目指す上で重要な役割を果たす可能性があるといえるでしょう。
3. アクティブ運用を成功させる条件
アクティブ運用を成功させるためには、以下の3つの条件が重要になります。
- コスト管理とアクティブシェア
- コア・サテライト戦略
- 情報優位性の確保と運用者の選定
3-1. コスト管理とアクティブシェア
アクティブ運用で成果を出すためには、コストを厳しく管理するとともに、インデックスとの乖離度合いを示す「アクティブシェア」が高いファンドを選ぶことが不可欠です。
アクティブファンドは、インデックスファンドに比べて信託報酬などの運用コストが高い傾向にあります。そのため、仮に同等の運用成績を上げたとしても、コスト控除後にはインデックスを下回る要因となるため、コストの低減は非常に重要な要素となります。
また、実際の運用がインデックスと大きく変わらないにも関わらず高いコストを課している「隠れインデックスファンド」を避けるためにも、運用方針の独自性を示すアクティブシェアに着目することが有効です。
例えば、あるアクティブファンドが年率1%の信託報酬を徴収しているとしましょう。市場平均が年5%のリターンだった場合、このファンドは最低でも年6%のリターンを上げなければ、コスト控除後にインデックスを上回ることはできません。もしファンドの実質的な運用がインデックスと大差ない「隠れインデックスファンド」であれば、その高コスト分だけリターンを押し下げる可能性があります。そのため、投資家は、運用報告書などでファンドのアクティブシェアを確認し、真に独自性のある運用が行われているかを見極めることが求められるでしょう。
アクティブ運用を成功させるには、高すぎるコストを避けつつ、独自のポートフォリオを構築しているかどうかが鍵となるでしょう。
3-2. コア・サテライト戦略
コア・サテライト戦略は、ポートフォリオの大部分を低コストのインデックスファンド(コア資産)で運用し、残りの一部をアクティブファンド(サテライト資産)に投資する方法です。これにより、安定性と成長性の両立を図ることができます。
SPIVAデータが示すように、多くのアクティブファンドが長期的にインデックスを上回ることが難しいという現実があるため、堅実な資産形成のためにはインデックスファンドを軸に据えることが合理的といえます。
一方で、厳選されたアクティブファンドは、特定の市場やテーマにおいて高いリターンをもたらす可能性を秘めているため、結果として、バランスの取れたポートフォリオの構築につながり、全体のパフォーマンス向上を狙えるでしょう。
例えば、資産の8割を全世界株式やS&P500といった低コストのインデックスファンドに投資することで、市場全体の平均的な成長を捉え、長期的な資産の土台を築きます。残りの2割を、日本の成長が見込まれる中小型株に特化したアクティブファンドや、AIのような特定のテーマに投資するアクティブファンドに配分することで、インデックスを上回るリターンを追求するイメージです。
このように、コア・サテライト戦略では、コア部分で市場平均リターンの安定性を確保しつつ、サテライト部分でリスクを取りながら高いリターンを目指すという、バランスの取れた運用が可能となります。
インデックス投資の堅実さとアクティブ運用の成長性を組み合わせることで、リスクを抑えながらも効率的な資産成長を目指す有効なアプローチといえるでしょう。
3-3. 情報優位性の確保と運用者の選定
アクティブ運用で継続的に安定した成果を上げるためには一般に出回っていない情報や独自の分析力に基づいた「情報優位性」が不可欠です。この情報優位性を持つ優秀な運用者を選ぶことが成功の鍵となります。
現代の市場は情報の透明性が高く、企業の決算情報やマクロ指標などの公開情報は即座に株価に反映されるため、一般的な情報に基づく銘柄選定だけではインデックスを上回るリターンを継続的に生み出すことは難しいのが実情です。
そのため、ファンドマネージャーは、独自のリサーチや分析、あるいは市場に歪みが生じる場面での投資機会を見出すことで、他の投資家よりも有利な情報を得られるかどうかが重要になります。
例えば、金融庁のデータによれば、日本株式のアクティブファンドのうち、統計的に有意な超過リターンをあげられるファンドは約1割に限られます。これは、ごく一部の優秀なファンドマネージャーや運用チームだけが、市場に先駆けた情報収集や、独自の深い企業分析を通じて、投資機会を見出していると考えられます。特に、中小型株市場や特定のテーマ型投資において、質の高いリサーチ力や企業との対話を通じて企業の本質的な価値を発掘できる運用者は、インデックスを上回る成果を出す期待ができます。このように、アクティブファンドを選ぶ際には、ファンドの過去成績だけでなく、運用チームの哲学、リサーチ体制、ポートフォリオの独自性などを総合的に評価し、真に優れた運用者を選ぶことが大切です。
4. 投資タイプ別おすすめアプローチ
「投資タイプ別おすすめアプローチ」として、以下の3つのアプローチについて解説します。
- 投資初心者・時間が取れない人:低コストインデックス+少額アクティブ
- 情報収集が得意で市場に関心が高い人:ファクター投資・セクター型アクティブ
- 資産拡大を狙う人:インデックス+オルタナティブ分散
4-1. 投資初心者・時間が取れない人:低コストインデックス+少額アクティブ
投資初心者や日々の情報収集に時間を割けない方は、まずは低コストのインデックスファンドを資産形成の中心とすることが基本となります。インデックスファンドは、市場全体に分散投資ができ、個別の銘柄分析の手間もかからず、運用コストも非常に低いことから、長期的な資産形成の土台として非常に優れています。
さらに、そこに厳選したアクティブファンドを、少額でも組み合わせることで、インデックスを上回る成果も期待できるでしょう。
例えば、NISAのつみたて投資枠を活用し、全世界株式インデックスファンドやS&P500インデックスファンドを毎月積立で購入。さらに、成長投資枠を活用し、少額だけ日本の成長企業に特化したアクティブファンドを購入するケースが考えられます。これにより、特別な知識がなくても市場の成長の恩恵を享受しつつ、アクティブ運用の魅力も残すことができます。
低コストインデックスを主軸に据え、少額のアクティブファンドで運用の経験を積みながら、自身の投資スタイルを確立していくことが、無理なく長期的な資産形成を進めるための方法といえるでしょう。
4-2. 情報収集が得意で市場に関心が高い人:ファクター投資・セクター型アクティブ
市場への関心が高く、情報収集に長けている方は、ファクター投資やセクター・テーマ型のアクティブファンドを積極的に活用することで、インデックスを上回る成果を追求できる可能性があります。これらの投資戦略は、特定分野の成長トレンドを見極める分析力、そしてタイムリーな情報収集能力が成果に直結しやすいのが特徴です。
インデックス投資が市場全体を広くカバーするのに対し、ファクターやセクターに絞ったアクティブファンドでは、深掘りした情報に基づいて「勝てる」可能性のある領域に集中して投資することができます。
例えば、企業の決算情報や業界ニュースを丹念に分析し、特定のファクター(例:バリュー、モメンタム)が現在、市場で過小評価されていると判断した場合、そのファクターに特化したETFやアクティブファンドに投資するケースが考えられます。また、AI技術の進展や脱炭素化の潮流といった大きなテーマを見据え、関連するセクターの成長性が高いと判断すれば、その分野に特化したテーマ型アクティブファンドを選択するケースも有効でしょう。
このようなアプローチは、市場の動向を常にウォッチし、自身の見立てに基づいて積極的に投資判断を下したいと考える投資家に向いているといえます。情報収集と分析に自信がある方は、インデックス投資では得られない超過リターンを目指せるでしょう。
4-3. 資産拡大を狙う人:インデックス+オルタナティブ分散
資産のさらなる拡大を目指す方は、インデックス投資を基盤としつつ、オルタナティブ資産を取り入れる戦略が考えられます。オルタナティブ資産は、伝統的な株式や債券とは異なる値動きをするものが多いため、ポートフォリオ全体のリスクを抑えながら、同時に新たなリターンの源泉を獲得できる可能性があります。
特に、流動性は低いものの、長期的な視点で高いリターンを期待できる資産としてプライベートエクイティなどが挙げられます。
例えば、主要な資産の大部分をS&P500や全世界株式などのインデックスファンドで安定的に運用し、市場平均のリターンを確保し、これに加えて、ポートフォリオの一部をREIT(不動産投資信託)に投資することで、不動産市場の恩恵を受けながら、株式市場との相関が比較的低い収益源を確保できます。
さらに、資金に余裕があれば、プライベートエクイティやヘッジファンドといったオルタナティブ資産を組み入れることで、市場の動きに左右されにくいリターンを追求することができるでしょう。
ただし、これらのオルタナティブ資産は専門的な知識や高額な投資資金が必要になることが多く、投資家は自身のリスク許容度や投資目標に合わせて慎重に検討する必要があります。
インデックス投資で市場全体の成長を捉えつつ、オルタナティブ資産を戦略的に組み込むことで、資産の分散効果を高め、より積極的に資産拡大を目指すことができるでしょう。
5. まとめ
インデックス投資は低コストで市場平均のリターンを捉える堅実な方法で、長期的な資産形成の基盤として多くの投資家が実践しています。
一方で、特定の市場環境や個人の投資目標によっては、アクティブ運用やオルタナティブ資産も有効な選択肢となりえます。SPIVAデータは、アクティブ運用が「長期的にインデックスを上回ることは難しい」という内容を示しているものの、一部の情報効率が低い市場や分析力が高い運用者、また特定の成長テーマに注目することで、インデックスを超える成果を目指せる可能性があります。
例えば、SPIVA日本版では、日本の中小型株ファンドが他のカテゴリーに比べて比較的健闘していることが報告されています。これは、情報が行き渡りにくい中小型株市場において、優れた運用者が価値を見出す余地があることを示唆しています。
また、AIや脱炭素といった成長テーマに特化したファンドや、株式・債券とは異なる値動きをするREITなどのオルタナティブ資産をポートフォリオに組み入れることで、リスク分散を図りつつ、新たなリターンの源泉を追求することも可能です。
最終的には、自身の投資目標、リスク許容度、そして情報収集への意欲などに応じて、インデックスファンド・アクティブファンド・オルタナティブ資産をバランスよく組み合わせることが、長期的な資産形成を成功させる鍵となるでしょう。
ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案を行っております。安定的に資産を増やしたい方に対して、状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
