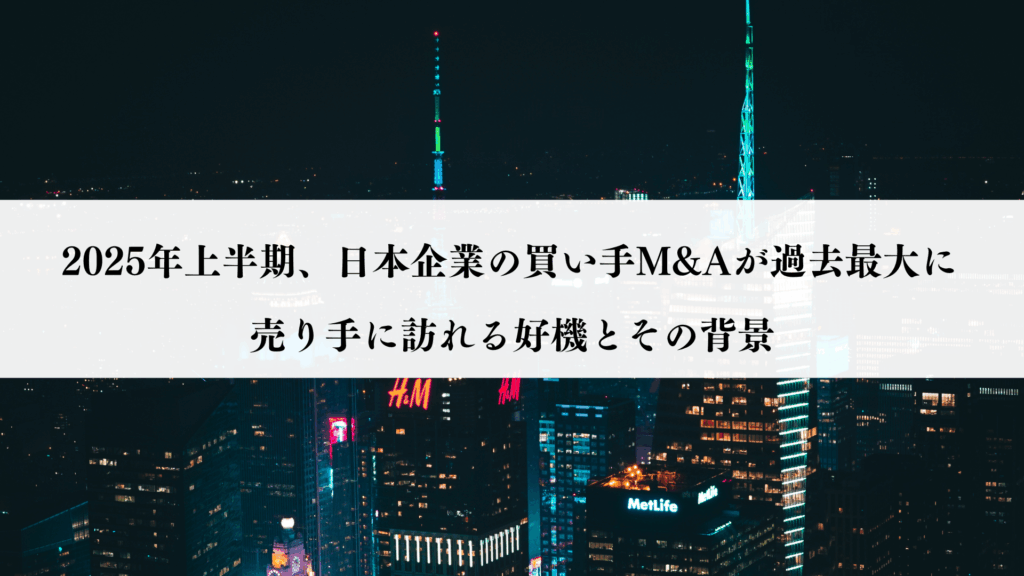
- 2025年上半期、日本企業によるM&Aが過去最大になった理由が知りたい
- 買い手企業が積極化する背景を理解したい
- 売却を検討する際の有利なタイミングや準備方法を知りたい
このようなご関心をお持ちではないでしょうか。
本記事では、資産運用のプロの視点から、M&A市場の最新動向と売却戦略について解説します。
この記事を読むと、日本企業のM&Aの現状に関する不安を払拭し、売却機会を最大限に活かす判断に繋がるでしょう。
1.2025年上半期のM&A市場概況
1-1. 国内企業による買い手M&A件数の過去最大化(前年比・件数データ)
2025年上半期のM&A市場は、国内企業による買収が件数ベースで過去最大を更新しました。
これは、国内外の経済不確実性の中でも、日本企業が成長機会を積極的に模索している姿勢を示しています。件数の増加は前年比でも顕著であり、特に中堅企業や上場企業による買収意欲の高まりが背景にあります。
こうした傾向が見られる理由は、低金利環境や投資余力を持つ企業が多いことが挙げられます。資金調達が比較的容易であるため、成長を外部から取り込もうとする動きが高まっていきました。
例えば、国内製造業の中には、海外市場の不透明感を回避するために国内企業の買収を選択するケースが考えられます。こうした選択はリスク分散にもつながり、結果として件数増加の一因となりました。
総じて、2025年上半期は企業の投資マインドが強く働いた時期であり、売却を検討する企業にとっても追い風となったでしょう。
1-2. 業種別(製造業・IT・サービス等)および取引規模別の動向
業種別では、IT・サービス分野のM&Aが引き続き活発でした。デジタル化やDX推進に伴い、成長分野の企業を取り込む動きが強まっています。
製造業においても事業承継を背景とした買収が増加しており、後継者不足が顕在化する中で、安定した技術基盤を維持するためのM&Aが進んでいます。
取引規模別では、数十億円から数百億円規模の中型案件が中心でした。これは中小企業による売却の増加と、買い手がリスクを抑えた投資を志向していることが合致した結果といえます。
例えば、地域の老舗製造業が後継者不在を理由に売却し、大手企業が技術や販路を吸収する事例が想定されます。こうした案件は、規模は大きくなくても、戦略的価値が高い傾向にあります。
このように業種別・規模別の特徴は、買収戦略の多様化を示しており、売却側にとって幅広い買い手候補が存在する環境といえます。
1-3. クロスボーダーM&Aとの比較(国内案件比率の変化・特徴)
クロスボーダーM&Aと比較すると、国内案件の比率が増加しています。
海外市場では地政学リスクや為替変動が大きな懸念材料となり、企業はより安定性の高い国内案件を選択する傾向を強めています。。
この変化の背景には、円安による海外買収コストの上昇があります。。国内企業を買収する場合、為替リスクを回避できるほか、、買収後の統合作業も比較的スムーズに進めやすいという利点があります。
例えば、アジア市場への進出を計画していた企業が、為替変動や現地規制の影響を回避するために、国内IT企業を買収し、デジタルシフトを強化するケースが考えられます。こうした動きは、特に中堅企業で顕著です。
このように、クロスボーダー案件よりも国内案件の相対的な魅力が高まっており、売却側にとって買い手を見つけやすい状況が広がっています。
2.買い手が積極化する背景
買い手が積極化する理由について、解説します。
2-1. 金利環境と企業の資金調達コストの変化
2025年は依然として低金利が続いており、企業の資金調達は良好な状況にあります。借入コストが抑えられることから、成長戦略を外部資源に依存する動きが後押しされました。
金利水準が安定していることから、企業は大型案件にも積極的に取り組みやすくなっています。さらに、内部留保の積み上げにより、、余剰資金をM&Aに投じやすい環境も整いつつあります。
例えば、製造業の上場企業が国内で資金調達を行い、競合他社を吸収して市場シェアを拡大するケースが考えられます。こうした動きは、低金利による借入コストの低さが前提条件となっています。
このような環境は、買い手企業の増加につながっており、売却側にとっても交渉の選択肢や余地を広げる要因になっています。
2-2. 中小企業における事業承継案件の増加と後継者不足統計
中小企業では後継者不足が深刻化しており、事業承継案件が急増しています。
経済産業省の統計によれば、経営者の高齢化が進み、後継者不在率は依然として高い水準にあります。
後継者が見つからない企業は、廃業かM&Aといった限られた選択をせざるを得ません。この現状が売却案件の増加につながり、買い手側にとっては優良な企業を獲得できる機会となっています。
例えば、地域の医療法人や建設業の中小企業が、後継者不在を理由に大手グループ企業に売却されるケースが想定されます。こうした取引は、雇用の維持や地域経済の安定にも直結します。
この動きは市場全体に多くの案件を供給しており、買い手企業の選択肢を広げる形で市場を活性化させています。
2-3. 成長戦略としての事業多角化・海外市場進出事例
買い手のM&Aは単なる規模拡大ではなく、事業多角化や海外進出を狙う戦略的な動きが多く見られます。
国内市場が成熟している中で、新分野への投資が求められているからです。
例えば、サービス業によるIT企業の買収を通じた事業基盤のデジタル化や、製造業による海外市場進出のための現地法人買収と言った動きも増えています。
このような動きは、買い手が積極的にM&Aを進める理由を一層確かなものにしており、売却側も成長分野への寄与や海外展開につながる強みを持っていれば、高く評価されやすくなります。
つまり、成長戦略を反映したM&Aは、買い手の意欲を引き出す重要な要素になっています。
3.売却側にとってのチャンス
売却側にとってのメリットについて、解説します。
3-1. 買い手競争による企業評価額上昇の可能性
買い手が増えることで、売却企業の評価額が上昇する可能性があります。複数の買い手が同時に関心を示すと、競争入札の形となり、価格が押し上げられるためです。
実際、過去のデータでも、買い手間の競争が激しい市場環境では、売却価格が高止まりする傾向が見られます。これは特に、独自技術や市場シェアを有する企業においては、その傾向が顕著です。
例えば、地域で独占的なポジションを持つサービス業が、複数の上場企業から入札を受け、当初の想定を上回る価格で売却されるケースが考えられます。こうした状況は、売却側にとって大きなメリットとなります。
したがって、現在のように買い手意欲が強い時期は、売却を検討する上で有利なタイミングであるといえるでしょう。
3-2. 高値売却を狙うタイミング判断(株価・為替・金利動向と連動)
売却価格は、株価や為替、金利といった外部要因と密接に関連します。
特に株式市場が堅調であれば、企業の将来性が高く評価されやすくなり、それが買収額にも反映されます。
為替の影響も見逃せません。円安が続けば海外からの投資は減少しますが、国内買い手にとっては、資金調達面での優位性が高まりやすくなります。
例えば、株価が高水準で維持し、金利が低く安定しているタイミングで売却すれば、より高い評価を得やすい可能性があります。このような外部環境を把握することは、売却戦略をたてる上で極めて重要となります。
つまり、外部環境の変動を注視しながら、売却タイミングを見極めることで高値売却の可能性が広がります。
3-3. 売却準備で重視すべき3つのポイント(財務デューデリジェンス、法務整理、事業ポートフォリオ見直し)
売却を成功させるには、入念な事前準備が欠かせません。特に重要なのは、財務・法務・事業の整理です。
財務面では、透明性の高い決算書やキャッシュフローの健全性を示すことが求められます。法務面では、契約関係の整理やリスク要因の解消が必要です。さらに、事業ポートフォリオの見直しを行い、買い手にとって魅力ある資産構成を示すことが重要です。
例えば、子会社の整理や不採算事業の切り離しを事前に済ませておくケースが考えられます。これにより、買い手は統合後の負担を減らせるため、評価額が増加する可能性があります。
このように、事前準備を整えることで、交渉において有利な立場を築くことができます。
4.今後の市場見通しと戦略
今後の見通しについて、解説します。
4-1. 下半期以降のM&Aトレンド予測(業種別・国内外別)
2025年下半期以降もM&A市場は堅調に推移する見込みとなります。特に、IT・サービス分野は引き続き成長の牽引役となり、製造業においても事業承継型の案件が増加すると予測されます。
国内案件は安定した動きを見せる一方、クロスボーダーM&Aは為替リスク・地政学リスクといった影響を受けやすく、国内案件中心の動きが継続する可能性が高いです。
例えば、地方の医療・介護関連企業を大手が買収するケースや、AI関連スタートアップの買収が加速するケースが考えられます。これらは業界構造の変化にも直結します。
市場全体として、案件数は引き続き高水準で推移することが期待されます。
4-2. 売り手・買い手双方に求められる戦略の変化(PMI対応・資金調達戦略・海外提携)
今後は、売り手・買い手双方に戦略的な変化が求められます。特に重要になるのは、PMI(統合プロセス)の円滑化です。
買収後のシナジーを早期に実現できなければ、期待された価値を享受できません。
また、資金調達戦略の多様化も課題です。従来の銀行融資に加え、社債や投資ファンドとの連携が進む可能性があります。海外提携においては、地政学リスクを踏まえた慎重な選別が必要となるでしょう。
例えば、IT企業が買収後の従業員統合を円滑に進めるために、文化融合を重視したPMIを導入するケースが考えられます。こうした工夫は、今後さらに重要性を高めます。
このように、売り手・買い手双方が戦略を高度化させることで、M&A市場は持続的に拡大していくことが見込まれます。
5.まとめ
2025年上半期、日本企業による買い手M&Aは過去最大の件数を記録しました。
その背景には、継続する低金利環境に加え、中小企業における後継者不足、そして事業の多角化や成長加速を狙うニーズが挙げられます。売却側にとっては、買い手企業が増えることにより競争が生まれ、企業価値が高まりやすい状況となっています。そのため、的確な準備と売却タイミングの見極めが一層重要となります。
下半期以降も、引き続き高水準のM&A市場が続くと見られており、売り手・買い手双方にとって一層戦略的な判断が求められる局面となります。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様の状況や業界動向に応じた最適なM&A戦略をご提案しております。
売却をご検討の企業様には、市場環境を踏まえた売却タイミングの見極めや事前準備の進め方について、実践的かつ丁寧にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
