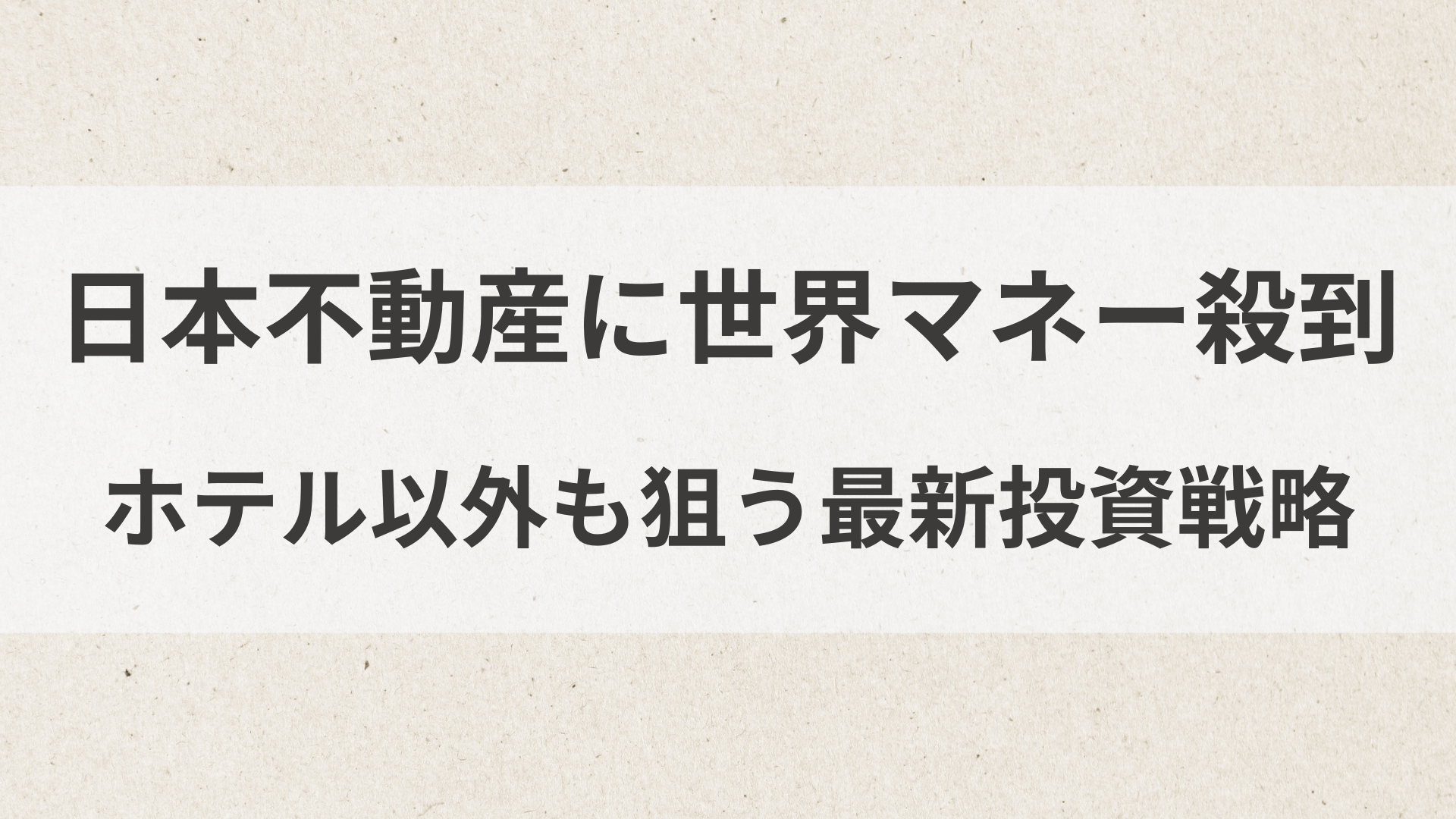
モルガン・スタンレーが約1,000億円規模の不動産ファンドを設立しました。地価上昇や利上げ後の環境を踏まえ、ホテル以外のオフィス・住宅・物流への投資拡大を目指しています。
1. 世界の投資家が注目する日本不動産の現状
2024年以降、日本の不動産市場には海外投資家からの関心が高まっています。背景には地価の上昇や円安の進行、日米金利差の拡大などがあります。
さらに、観光需要の回復を追い風にホテル投資が注目されてきましたが、近年は物流施設や住宅、オフィスといった多様な分野への資金流入も見られます。本章では、こうした動きを地価データや海外ファンドの事例を交えながら整理していきます。
1-1. 2024年の公示地価全国平均+2.3%の上昇とその背景
国土交通省の発表によれば、2024年の公示地価は全国平均で前年比+2.3%の上昇となりました。コロナ禍を経て、都市部を中心に地価の回復傾向が鮮明になったことが要因のひとつです。
特に商業地では、観光需要の回復や再開発の進展が評価され、東京・大阪・名古屋といった大都市圏で顕著な地価の上昇が確認されました。また、住宅地も安定した需要を背景に堅調であり、インフレ局面での実物資産への需要が影響していると考えられます。
地方圏についても、観光地やリゾートエリアを中心に上昇幅が広がりました。特に、北海道のニセコや沖縄などは、海外投資家や富裕層の購買意欲に支えられており、国際的なリゾート市場としての認知が高まっています。背景には、グローバルに見ても日本の地価が依然として割安に映ることや、長期的なインバウンド需要への期待感があります。
もちろん、地価の上昇は一律ではなく、用途やエリアによって差があります。都心部のオフィス街ではテレワーク普及による空室率上昇の影響で地価が下落しているケースがある一方、再開発プロジェクトが進むエリアではむしろ資産価値が上がっているケースもあります。つまり、地価上昇は単純な一方向ではなく、投資家にとっては物件選定力が試される局面となっています。
1-2. 円安・日米金利差・インフレ環境が生む相対的割安感による資金流入
海外資金が日本不動産に注目する大きな理由の一つが「為替と金利環境」です。2024年から2025年にかけて円安が進行し、1ドル=160円前後で推移する時期もありました。この水準は、海外投資家にとって日本の不動産を割安に見せる効果があります。
さらに、日米間の金利差も影響しています。米国が高金利政策を維持する一方、日本は段階的な利上げを行ってもなお低金利環境にあります。そのため、為替ヘッジを考慮しても日本不動産は相対的に魅力的な利回りを提供できる可能性があります。
インフレ率が上昇している中、実物資産である不動産は購買力の目減りを回避する「インフレヘッジ」としても注目されています。
こうしたマクロ環境は、特に長期運用を志向する海外年金基金やソブリンウェルスファンドにとって投資判断を後押しする要素になっています。また、短期的なキャピタルゲインではなく、安定した賃料収入を重視する動きが広がっていることから、堅実なインカムゲインを得られる日本不動産が好まれる傾向にあると考えられます。
1-3. 外資系ファンドの参入事例(物流・住宅・オフィスなど、ホテル以外にも拡大)
従来、海外資金による日本不動産への投資というと、「ホテル」セクターへの投資が目立っていました。
インバウンド需要の拡大や観光需要の回復が追い風となり、2022年以降は大手外資系ファンドが都市ホテルやリゾート施設を積極的に取得する動きが報じられています。しかし、2024年以降は投資対象がホテルにとどまらず、物流施設や住宅、オフィスへと広がっている点が注目されます。
物流分野では、EC市場の拡大やサプライチェーンの見直しが追い風となっています。大都市圏では最新設備を備えた大型物流施設が開発され、外資系ファンドの買収案件も増加しました。こうした物件は安定した賃貸契約を背景に、長期的なインカム収益を見込める点で人気があります。
住宅分野では、賃貸住宅の需要が底堅いことから投資が進んでいます。特に都市部のマンションやレジデンスは、人口集中や単身世帯の増加を背景に安定的な賃料収入が期待されます。海外投資家にとって、住宅はホテルに比べて需要変動が小さく、安定志向の資産として位置づけられやすいと言われております。
オフィス市場についても、コロナ禍後のテレワーク定着で「オフィス不要論」が語られた一方、ハイグレードビルや再開発エリアでは需要が底堅いことが確認されています。実際に、東京の丸の内や虎ノ門などでは、外資系ファンドによるオフィスビル投資が続いており、テナント需要を見極めた上での選別投資が進んでいます。
このように、ホテル偏重から多様なセクターへの分散が進むことで、日本不動産は投資対象としての魅力が増しています。投資家にとっては、複数セクターに分散することでリスクを抑えつつ収益機会を広げることが可能となります。
2.モルガン・スタンレーの新ファンド概要
モルガン・スタンレーが日本市場に向け、約1,000億円規模の新しい不動産ファンドを立ち上げました。
背景には、円安や日米金利差による資金流入の加速があります。本章では、このファンドの目的や資金調達の状況、投資対象となるオフィス・住宅・物流・ホテルなどのセクター、さらに利回りや運用期間の一般的な水準を整理して解説します。
2-1. 約1,000億円規模の不動産ファンドを組成した目的と資金調達状況(報道ベース)
2025年4月、モルガン・スタンレーが日本市場向けに新たな不動産ファンドを立ち上げたと複数の報道で伝えられました。規模はおよそ1,000億円とされ、国内外の機関投資家や富裕層からの資金を調達して組成されたものです。
背景には、日本不動産が持つ「相対的な投資妙味」があります。円安や日米金利差により海外投資家にとって日本資産は割安に見えやすく、さらにインフレ環境のなかで安定した実物資産への需要が高まっています。
モルガン・スタンレーとしても、この資金流入の波を逃さず、成長が見込まれる不動産セクターを幅広く取り込む狙いがあると考えられます。
資金調達の詳細は非公表ですが、報道ベースでは欧米の年金基金や中東のソブリン・ウェルス・ファンドが出資者として参加している可能性が指摘されています。また、日本国内の機関投資家や事業法人が一部関与しているケースも想定され、グローバル資金と国内資金の双方を取り込む形で組成されたファンドといえるでしょう。
こうした規模感のファンドは、日本市場における外資系プレーヤーの影響力をさらに強める可能性があります。特に1,000億円クラスとなると、個別物件だけでなく複数セクターにわたる分散投資を可能にし、都市部の大型案件や地方の成長エリアにも手を広げられるとみられます。
2-2. 投資対象セクター:オフィス・住宅・物流・ホテル(比率は非公表)
新ファンドの投資対象は、オフィス・住宅・物流・ホテルと報じられています。ただし、各セクターへの投資比率は公表されていません。外資系ファンドがセクターを複数に分ける背景には、以下のような考え方があります。
- オフィス
東京や大阪など大都市圏のオフィス市場は、テレワーク普及の影響で一部空室率が上昇しました。しかし、再開発地区やグレードの高いビルには需要が集中し、安定した賃料収入が見込まれるケースがあります。ファンドとしては、選別投資を行うことでリスクを抑えつつリターンを確保する戦略が想定されます。 - 住宅
都市部の賃貸住宅は、単身世帯の増加や住宅需要の底堅さから安定的な収益源とされます。海外ファンドにとっては、景気変動の影響を受けにくいセクターとして重視される傾向にあります。 - 物流施設
EC市場の拡大やサプライチェーン再編を背景に、最新設備を備えた物流施設への需要は高止まりしています。長期契約による賃料収入が期待できるため、ファンドにとっては「安定配当の柱」として位置づけられる分野です。 - ホテル
インバウンド需要の回復を背景に引き続き注目されていますが、コロナ禍を経て投資が集中しすぎるリスクも指摘されます。今回のファンドでは、ホテルに偏重せず他の資産と組み合わせることで、よりバランスの取れたポートフォリオを形成しようとしていると考えられます。
このように、比率は明らかではないものの、複数セクターを組み合わせることは投資リスクを分散し、市場環境の変化に対応する狙いがあると推察されます。
2-3. 想定利回り・運用期間:公表有無の確認と市場水準の目安(参考)
モルガン・スタンレーの新ファンドにおける利回りや運用期間については、現時点で公表されていません。したがって、ここでは市場一般の水準を参考として確認しておきます。
日本の不動産ファンドにおける想定利回り(ネットキャッシュフロー利回り)は、セクターや立地によって差があります。
一般的に、東京のプライムオフィスは3〜4%前後、物流施設は4%程度、住宅は3%台半ば、ホテルは稼働率や立地によって変動が大きく、4〜6%程度の幅が見られます。海外投資家が円安環境で投資する場合、為替要因を加味すると実質的なリターンはさらに高くなることもあります。
運用期間については、外資系不動産ファンドでは7〜10年程度の中長期を基本とすることが多いです。これは、不動産投資の特性上、短期的な売却益を狙うよりも、一定期間の賃料収入を安定的に享受し、その後に出口戦略を取る方が合理的とされるためです。ただし、市場環境が急速に変化した場合は、想定よりも早期の売却に踏み切るケースもあり得ます。
こうした市場水準を踏まえると、今回のファンドも複数セクターに分散しつつ、安定的なインカム収益と適切なタイミングでのキャピタルゲイン獲得を両立させる方針で運用される可能性があります。
3. 投資先多様化の戦略的意義
日本の不動産市場に流入する海外資金は、かつてホテル分野に集中していました。しかし、近年は物流施設や賃貸住宅、オフィスといった多様なセクターへと広がりを見せています。
投資先を分散することで、景気変動リスクを抑えつつ安定的な収益を確保できる可能性があるためです。本章では、それぞれの成長ドライバーや市場の再評価、そして分散投資がもたらすポートフォリオ効果について整理します。
3-1. 物流施設・賃貸住宅の成長ドライバー
近年、日本の不動産市場における物流施設と賃貸住宅は、特に注目を集めている分野です。
物流施設は、EC市場の拡大やサプライチェーン再編の影響を強く受けています。コロナ禍をきっかけにオンライン購買の浸透が一段と進み、都市近郊に効率的な配送拠点を構えるニーズが高まりました。
その結果、最新設備を備えた大型物流施設は空室率が低く、長期契約に基づく安定した賃料収入が期待できる物件として評価されています。また、自動化や省人化への投資余地が大きく、テナント側のニーズが多様化している点も特徴です。
ファンドにとっては単なる不動産収益だけでなく、成長産業と結びついた長期的なキャッシュフロー確保が可能になるため、戦略的な投資先とされています。
一方、賃貸住宅市場も安定した成長ドライバーです。都市部では単身世帯や共働き世帯が増加しており、賃貸住宅の需要は底堅く推移しています。
日本の人口全体は減少傾向にあるものの、東京や大阪など大都市圏への人口集中は続いており、立地条件の良い住宅物件は長期的に稼働率を維持できる可能性があります。海外投資家にとって、住宅は景気変動の影響を受けにくく、安定収益型の資産として魅力があると考えられます。
物流と住宅は、ともに「生活・産業インフラ」としての性格を持つため、景気循環に左右されにくいという点でポートフォリオの安定性を高める要素となっています。
3-2. オフィス市場の再評価とアフターコロナにおける需要動向
コロナ禍以降、リモートワークやハイブリッド勤務の普及により、オフィス市場には大きな変化が訪れました。一時は「オフィス不要論」が広がり、空室率上昇が懸念されましたが、2024年以降は「再評価」の動きが見られます。
特に、都心部の再開発エリアに建設されたハイグレードビルや環境認証を取得した最新オフィスは、需要が底堅く推移しています。企業にとっては単なる執務スペースではなく、人材確保や企業ブランディングに直結する場として、オフィスの質を重視する傾向が強まっています。結果として、築年数の古い物件と新築・高機能物件との二極化が進んでいます。
また、外資系企業の日本進出やスタートアップの成長により、柔軟な契約形態を求める動きも広がっています。コワーキングスペースやフレキシブルオフィスの需要は、テナント構成の多様化を促し、オフィス市場に新しい価値をもたらしています。
このように、オフィス市場は単純に縮小するのではなく、用途や機能の再定義が進んでいるといえます。投資家にとっては、従来の「面積で稼ぐ」発想から「質と用途の多様性で稼ぐ」視点に転換することが重要となり、多様化戦略に組み込む意義が増しているのです。
3-3. ホテル偏重傾向から投資先分散がもたらすポートフォリオ効果
ここ数年、日本の不動産投資で特に注目されてきたのはホテルでした。円安と観光需要の回復が重なり、2023〜2024年にかけては外資系ファンドがホテル物件を次々に取得しました。
しかし、ホテル市場は観光需要や国際情勢の影響を受けやすく、稼働率や客室単価が大きく変動するリスクを抱えています。
こうした状況を踏まえ、投資先を物流・住宅・オフィスへと分散させる動きが広がっています。ポートフォリオ効果として期待できるのは、リスク低減と安定収益の確保です。
ホテルは高収益が見込める一方で景気に敏感な性格を持ちますが、物流や住宅は安定的なインカムを生み出しやすいため、組み合わせることで全体の収益変動を抑えることができます。
さらに、異なるセクターに分散することで、市場環境の変化に対する耐性も高まります。例えば、観光需要が低迷してホテル収益が落ち込んでも、物流や住宅からの安定収益で全体をカバーできるといった具合です。ファンドにとっては、投資家へ安定した配当を継続するうえで大きな意義を持つ戦略といえるでしょう。
また、セクターを組み合わせることで、景気拡大局面ではホテルやオフィスの上振れを享受しつつ、景気後退局面では住宅や物流による底支えを確保する、といった柔軟な運用が可能になります。このような「景気サイクル耐性」を持つポートフォリオは、海外投資家だけでなく国内の富裕層や機関投資家にとっても魅力的なモデルとなり得ます。
4.利上げ後の市場変化と投資家の行動
日本銀行が段階的に利上げへ転じたことで、不動産市場にも新たな局面が訪れています。これまで低金利を背景に資金が流入してきた不動産投資は、金利上昇を受けて価格や賃料の調整局面に入りつつあります。
投資家はより慎重に投資対象を選別し、安定収益を重視する傾向を強めています。本章では、金利上昇が市場に与える影響、プライベートウェルスを含む投資家の行動変化、そしてインカム型とキャピタル型の戦略比較を整理します。
4-1. 金利上昇が価格・賃料・キャップレートに与える影響
金利が上昇すると、不動産市場にはいくつかの波及効果が生じます。最も直接的なのは「資金調達コストの上昇」です。融資金利が高まれば、不動産取得のためのレバレッジ効果は低下し、投資家は物件購入時により厳しい採算ラインを求めるようになります。
この結果、不動産価格には調整圧力がかかります。特に、利回りの低いプライムオフィスや都心住宅では、想定リターンが金利上昇に見合わないと判断される場合、価格の下方修正が起きやすいとされます。
一方で、地方都市や物流施設のように比較的高いキャッシュフローを生み出せる物件は、影響を受けにくいと考えられます。
キャップレート(還元利回り)についても金利と密接に連動します。一般に、金利が上がれば投資家はより高いリターンを求めるため、キャップレートは上昇方向に動きます。これにより不動産価格は下がる圧力がかかる一方、賃料収入の増加や安定的な稼働率が確保できれば、価格調整は限定的にとどまる可能性もあります。
賃料動向も重要です。金利上昇局面では景気動向に左右されやすく、企業業績が堅調であれば賃料上昇が価格下落を相殺するケースも考えられます。逆に景気が減速すれば、賃料の伸び悩みと価格調整が重なり、投資リスクが増す構図となります。
4-2. インカム重視(安定配当)志向とプライベートウェルスの動き
金利上昇下では、短期的な売却益を狙う戦略よりも、安定した賃料収入(インカムゲイン)を重視する姿勢が強まります。
特にプライベートバンキング顧客やファミリーオフィス、富裕層投資家は、相続や資産承継を意識した長期運用を志向するため、キャッシュフローの安定性を最優先に据える傾向があります。
このような層は、分配金を安定的に提供するJ-REITや私募リート、あるいは物流施設や住宅を対象とした共同投資案件を選好するケースが増えています。彼らにとって重要なのは「資産を減らさない」ことと「定期的に収益を得る」ことであり、変動リスクの大きいセクターよりも安定性を重視する判断が多くみられます。
また、プライベートウェルス層は独自のライフプランに基づき投資を行うため、短期的な市場変動に左右されにくい特徴があります。利上げ局面でも、不動産を長期保有してインカムゲインを得る戦略は、債券や株式といった他資産とのバランスを取りやすい点で魅力的に映っていると考えられます。
4-3. 長期保有vs 売却益狙い戦略の比較
不動産投資には大きく分けて「長期保有でのインカムゲイン重視」と「売却益を狙うキャピタルゲイン重視」の二つの戦略があります。利上げ局面では、この二つの戦略のメリット・デメリットがより鮮明になります。
- 長期保有(インカムゲイン重視)
定期的な賃料収入により、金利上昇や価格変動があってもキャッシュフローを維持しやすい点が強みです。特に物流施設や住宅は稼働率が高く、景気変動の影響を比較的受けにくいため、安定的な運用が可能とみられます。ただし、金利上昇により調達コストが増すことで、ネット収益が圧迫されるリスクには注意が必要です。 - 売却益狙い(キャピタルゲイン重視)
再開発エリアのオフィスや観光地のホテルなど、将来的な資産価値上昇を見込んで投資する戦略です。景気回復局面やインバウンド拡大局面では大きなリターンを得られる可能性がありますが、利上げ局面では価格下落リスクが高まりやすく、出口戦略のタイミングが難しくなります。
結果として、利上げ後の市場ではインカムゲイン重視が相対的に優位になりやすいとされますが、景気循環やセクター特性に応じてキャピタルゲイン重視の戦略を組み合わせる柔軟性も求められます。
5.富裕層、個人投資家が取るべきアクション
世界からの資金流入が続く日本不動産市場では、個人投資家や富裕層にとっても新しいチャンスとリスクが混在しています。外資系ファンドの大規模参入は市場全体の流動性を高める一方で、物件価格や利回りに影響を及ぼす可能性もあります。
本章では、こうした環境下で投資家が意識すべきチェックポイントや、実務的な資産分散の方法、さらに外資系ファンドと関わるための具体的な参加手段について整理していきます。
5-1. グローバル資金流入局面での国内投資チェックポイント
海外資金が積極的に日本不動産に投資する局面では、個人投資家もいくつかの点に留意する必要があります。
まず重要なのは 、価格水準の見極め です。海外からの資金流入によって特定エリアの地価や不動産価格が急上昇する場合、短期的な過熱感が生じることがあります。
例えば都市部のホテルや再開発エリアのオフィスは、国際的な競争の対象となりやすく、取得価格が高止まりする傾向があります。個人投資家は、市場全体の平均利回りや賃料動向を確認し、割高感がないか慎重に見極めることが大切です。
次に、 為替リスク にも注意が必要です。円安局面では海外投資家に有利な状況が続きますが、将来的な円高局面に転じれば、投資妙味が一時的に薄れる可能性があります。国内投資家にとっては、為替の影響を直接受けない強みがある反面、海外資金の動向によって市場が揺れる点を理解しておくことが求められます。
さらに、流動性の確認 も欠かせません。外資系ファンドが投資するような大型案件は、取引規模が大きく個人投資家には直接参入が難しいケースもあります。その場合は、J-REITや私募リートを通じて間接的に参加する方法を検討すると、流動性リスクを抑えやすくなります。
5-2. 資産クラス分散(住宅・物流・オフィス・ホテル・インフラ等)の実務ベストプラクティス
資産運用の基本原則は「分散投資」です。不動産投資においても同様で、住宅・物流・オフィス・ホテルといったセクターを組み合わせることで、安定性と成長性をバランスよく取り込むことが可能です。
- 住宅:都市部の賃貸住宅は長期的な需要があり、安定的なインカム収入を確保しやすい分野です。特に立地条件の良いマンションやレジデンスは、空室リスクが低くポートフォリオの安定要素となります。
- 物流:EC需要の高まりを背景に安定成長が見込まれるセクターで、長期契約に基づく安定収益が期待できます。富裕層投資家が共同投資案件として参加するケースも増えています。
- オフィス:テレワーク普及で調整を受けた一方、再開発エリアや高グレード物件は依然として強い需要があります。セレクティブに選定すれば、キャピタルゲインも狙える分野です。
- ホテル:インバウンド需要の回復によって収益性は高いですが、景気変動に敏感です。全体のポートフォリオの一部として組み込むと、リターンを押し上げる効果があります。
- インフラ関連不動産(データセンターや再エネ施設など):近年注目が高まっており、長期の賃貸契約が多いため、ポートフォリオの安定性を高める役割を担います。
実務的には、J-REITや不動産クラウドファンディング、私募リートなどを活用して、セクター分散を実現するのが現実的です。特に個人投資家にとっては、少額から分散効果を得られる仕組みを利用することでリスクを抑えることが可能になります。
5-3. 外資系ファンドとの協業・参加手段(共同投資、J-REIT/私募リートなどの活用)
外資系ファンドは、豊富な資金力とグローバルな運用ノウハウを持っています。個人投資家や富裕層が直接同じ土俵で競うのは難しいですが、協業や間接的な参加手段を活用することは可能です。
代表的なのが J-REITへの投資 です。東証に上場するREITは、外資系ファンドと共同で物件を保有・運用しているケースが多く、間接的にグローバル資金の動きに参加できます。また、流動性が高く少額から投資できる点も魅力です。
私募リート や 共同投資スキーム も有力な選択肢です。金融機関や証券会社を通じて富裕層向けに案内される案件では、外資系ファンドがスポンサーとなることもあり、国内投資家が協調して参加できる枠組みが整いつつあります。
さらに、不動産クラウドファンディング は小口化によって外資が関与する大型案件に個人投資家が間接参加できる手段として広がりを見せています。リスクを限定しつつ、多様な物件やセクターに分散投資できる点で注目されています。
このように、直接競争するのではなく、外資系ファンドの存在をむしろ「市場参加のチャンス」と捉え、適切なスキームを通じて協業・参加することが現実的なアプローチといえるでしょう。
6.まとめ
2025年、モルガン・スタンレーが1,000億円規模の日本不動産ファンドを組成し、従来のホテル偏重からオフィス・住宅・物流への投資先多様化が進んでいます。背景には円安・日米金利差・地価上昇(全国平均+2.3%)による相対的割安感があります。利上げ局面でキャピタルゲイン重視からインカムゲイン重視へシフトし、安定配当を求める投資家が増加しています。
個人投資家は価格水準を見極めつつ、J-REITや私募リートを活用した資産分散と外資系ファンドとの協業が有効な戦略となるでしょう。
ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。富裕層の方に対して、状況に応じた最適なアドバイスをいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
