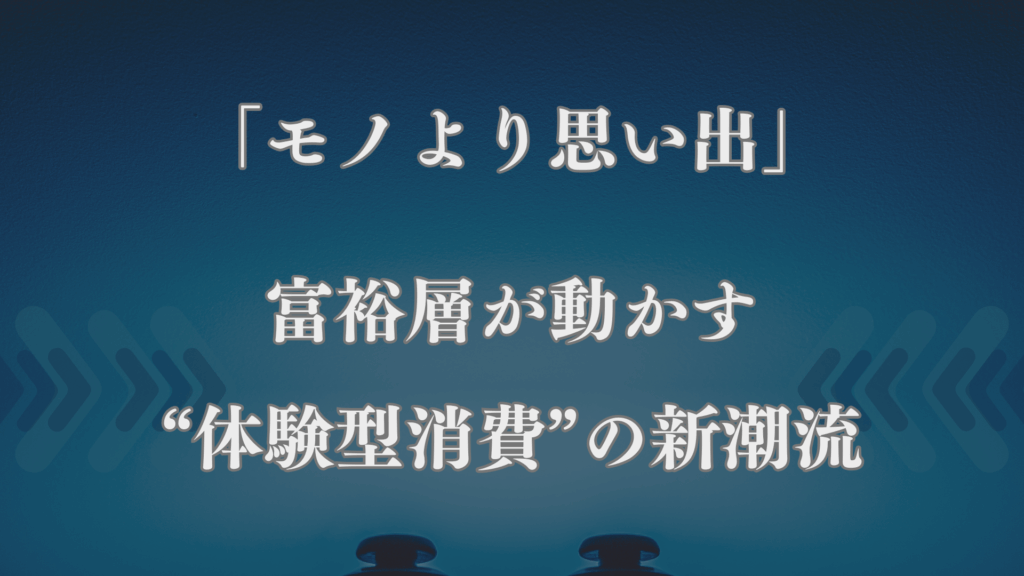
- 富裕層は本当に体験型へシフトしているのか
- 伸びている体験領域(旅行/食/文化)はどこか
- 金融・サービス業は何を設計すれば選ばれるのか
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
本記事では、資産運用のプロの視点から、富裕層消費の潮流と“体験型”の勝ち筋を解説します。
この記事を読むことで、富裕層の最新消費動向と、それに連動して拡大する高付加価値サービス市場の全体像が把握できます。
さらに、自社の提供価値をどう磨くかのヒントも得られるでしょう。
1. 富裕層消費の新潮流:「モノより思い出」
富裕層消費の動向について、以下の観点から解説します。
- 高額所得者は体験支出が一般層の約9倍
- 従来型消費(ブランド品・資産形成)との比較
- 心理的背景:経験がもたらす長期的満足感と心の豊かさへの投資傾向
1-1. 高額所得者は体験支出が一般層の約9倍
富裕層は“体験”への支出比重が一般層と比べて突出しており、エンタメ・旅行・趣味分野では約9倍の差があります。※
さらに、物価高の局面でも「価格が高くても価値があれば買う」と回答する割合が高く、需要の底堅さがうかがえます。
こうした値ごろ感より価値重視の姿勢が、体験型消費の伸びを後押ししています。
背景には、所有そのものよりも「どのような意味を持つ体験か」という判断軸があります。価格は単なる負担ではなく、品質や体験の意味を裏付ける“安心材料”として働いています。
具体的には、旅行・余暇・趣味への継続的な支出や、体験の前後を含むプロセスに投資する傾向があります。
したがって、企業は“体験の設計”を提案の核に据える必要があるでしょう。
※出所:BCG Japan | ボストン コンサルティング グループ 日本
1-2. 従来型消費(ブランド品・資産形成)との比較
富裕層はブランド品の購入もしますが、その選定基準は“価格”ではなく“物語”にあります。
特に、同一ブランドを継続して選ぶ傾向が強く、新規ブランドや新しい店舗に対してのハードルは高めです。
つまり、重視されるのは商品単体の価値よりも、購買体験や空間演出を含む“記憶価値”ということがわかります。買い物のプロセス自体が物語化され、ブランドへのロイヤルティにつながります。
例えば、世界観に没入できる導線設計や、一貫した体験設計を持つ空間づくりがその事例です。
結果として、資産形成や所有中心の発想に加え、体験価値を磨くことが企業競争力の源泉になるといえるでしょう。
1-3. 心理的背景:経験がもたらす長期的満足感と心の豊かさへの投資傾向
国内富裕層は、人生の価値を高める特別な体験やウェルビーイングの追求に積極的で、自分の好きなことには支出を惜しまない傾向が強いことが示されています。※
特に、購入過程でのサポートやパーソナライズへの期待値が高いため、品質と“自分向け”の提案が選定基準になっています。こうした価値観の変化が、所有から体験へのシフトを後押ししています。
その根拠として、ECの活用や店舗での品質・好み重視、旅行支出への高い意欲など、行動面のデータも挙げられます。
例えば、同じ旅行でも世代ごとに重視する点は異なるものの、旅行そのものへの意欲は一貫して高い傾向が見られます。
長期的な満足と”語りたくなる記憶”を生む体験への投資が選ばれやすいのです。
※出所: Deloitte
2. 代表的な体験投資の領域
代表的な体験投資の領域について、以下に沿って解説します。
- バケットリスト型の海外・国内旅行
- プレミアムダイニング、ガストロノミーツアー
- 芸術・文化・スポーツ観戦などの没入体験
2-1. バケットリスト型の海外・国内旅行
体験型消費の中心は旅行で、非日常を味わうことで満足度を押し上げます。富裕層は旅行関連支出への意欲が高く、世代ごとに重視する点が異なるという傾向も見られます。
特徴的なのは、旅程のカスタマイズや事前・事後のサポートまでを含む“体験全体”が評価対象になりやすい点です。
なぜなら、パーソナライズ志向とサポート重視、そして”時間対効果”への意識といった要素があり、効率的に上質な体験を得たいという動機があるためです。
例えば、プライベートツアーや特別アクセスを伴う滞在、静かな空間でのテイスティングといった事例が考えられます。
旅行は今後も体験型消費の“核”として最適化が進むでしょう。
2-2. プレミアムダイニング、ガストロノミーツアー
食体験は“味”だけでなく、場の演出や学びが加わることで価値が高まるのが特徴です。
富裕層は「自分に合う提案」や「丁寧なサポート」を重視するため、予約・案内・ストーリー共有までの設計が満足度を大きく左右します。
価格訴求よりも、情緒・象徴価値が響きやすい点も特徴です。これは富裕層は、購入前から始まるプロセスそのものを重んじ、記憶に残る体験を価値とするからです。
例えば、少人数の解説付きコース、産地とつながるガストロノミーツアー、招待制のペアリング会という事例が想定されます。
食体験の“物語化”は再訪や紹介につながりやすいでしょう。
2-3. 芸術・文化・スポーツ観戦などの没入体験
芸術・文化・スポーツ観戦は、ブランドの世界観への没入感と、個人の自己表現の双方を満たします。
富裕層の消費傾向には、憧れの世界に近づく「没入型」と、自己表現の手段として活用する「自己表現型」があり、どちらにおいても体験の物語化が重要な役割を果たします。
理由として、視覚や身体感覚を総合的に刺激する体験は、長期的満足や語りたくなる記憶を生み出しやすいからです。
例えば、開館前のプライベートビューイング、解説付きの特別観戦席、制作現場への限定アクセスといった事例が考えられます。
こうした所有では得にくい“時間価値”が、ロイヤルティを高める要因となるでしょう。
3. 金融・サービス業界の対応
金融・サービス業界が体験型消費に対応するためのポイントについて、以下の3つの観点で解説します。
- 富裕層向けカード特典における体験型サービスの拡充
- 富裕層専用カードの囲い込み
- 情緒価値と希少性を活用したブランディング
3-1. 富裕層向けカード特典における体験型サービスの拡充
カード会社にとっては、体験を起点とした特典の設計が有効です。富裕層の中には、旅行・高級店での飲食、学びやネットワークにつながるコミュニティ参加といった体験領域への投資意欲が強い人がいるため、このような分野への訴求は利用活性化に直結します。
特に、年収帯が上がるほど体験・関係性への支出傾向が強まる点は、特典編成における重要な示唆になります。理由として、カード会員の調査でも、“体験”や“関係性”への投資が強調され、国内旅行や外食の積極利用が報告されているためです。
例えば、限定イベントへの優先招待、旅の前後をサポートするコンシェルジュサービス、コミュニティ連携型の特典プログラムといった取り組みが考えられます。
体験価値を軸にした特典設計は、会員満足度を高めるだけでなく、カードの継続利用を後押しするでしょう。
3-2. 富裕層専用カードの囲い込み
富裕層マーケティングにおいて囲い込みの中核となるのは、“信頼”と“関係性”です。
富裕層は「誰が紹介したか」を重視する傾向があり、価格主導の大量訴求は逆効果となるリスクがあります。
効果的なのは、紹介や人脈を起点とした少人数で深い体験を設計することです。紹介や誠実な応対が強い説得力を持ち、長期的な関係構築が選好の決め手になるからです。
例えば、紹介者同伴の限定イベント、担当者による個別設計サービス、会員制スペースの活用という取り組みが想定されます。これにより、“選ばれた感”を得やすく、自然な希少性を演出することで、囲い込みを強化する効果があります。
3-3. 情緒価値と希少性を活用したブランディング
ブランディングでは、機能価値よりも情緒的・象徴的な価値を際立たせることが重要です。“信頼・体験・希少性”の三位一体で世界観を統合し、数量限定や紹介制、ストーリー性のある提案を通じて、“語りたくなる文脈”をつくることが差別化につながります。
富裕層は「限られた人だけが知っている」と感じられるものに強い魅力を覚え、入手のハードルや背景ストーリーが付加価値を増幅させるからです。
例えば、受注生産や招待制イベント、創業者哲学を体験に織り込む設計といったアプローチが考えられます。
これにより、価格競争に陥りにくい差別化資産を形成できるでしょう。
4. 投資家視点での意義
投資家視点での意義について、以下に沿って解説します。
- 体験重視型富裕層とのマーケティング機会
- 高付加価値サービス市場の成長性
- 事業ポートフォリオにおける体験型事業の位置づけ
4-1. 体験重視型富裕層とのマーケティング機会
富裕層は体験領域での支出が顕著で、一般層との支出差が約9倍になります。※ したがって、価値観ベースのターゲティングが有効であり、旅行・食・文化といった複数領域を横断した“編集型”による提案は、LTV(顧客生涯価値)の向上が狙えます。
富裕層はインフレ環境下においても価値で選ぶ姿勢は持続しており、体験設計を軸としたマーケティングは効果的です。例えば、旅行×文化×食の統合パッケージや、コミュニティ連動型プログラムというケースが考えられます。
これにより、既存顧客の深耕と新規VIP層の開拓の両面で機会が広がるでしょう。
※出所:BCG Japan | ボストン コンサルティング グループ 日本
4-2. 高付加価値サービス市場の成長性
富裕層の消費傾向には「ウェルビーイング志向」「パーソナライズ志向」「サポート重視」が明確で、体験価値の最大化が選好に直結します。
特に富裕層の6割前後が自分向けの提案・カスタマイズ・サポートを重視し、健康や心の豊かさへの投資意欲も確認されています。
このことから、旅行・食・文化と金融サービスをつなぐ体験設計には大きく拡張余地があります。例えば、資産・嗜好データに基づく“思い出投資”の年間計画や、旅×カード×コミュニティの統合サービスは、高付加価値市場の成長を後押しするでしょう。
4-3. 事業ポートフォリオにおける体験型事業の位置づけ
体験型事業は価格競争に陥りにくく、差別化資産として有効です。
価値観によるセグメントや、物語を紡ぐ人材の育成、外部データやAIの活用によるVIP顧客の先読みなどは、全社的なマーケティング再設計につながります。行動を分ける基準は年齢や年収ではなく“価値観”であり、物語化が選ばれる理由を生み出します。
例えば、価値観クラスタごとに“旅行・食・文化”の編集軸とするユニットを設置することで、“選ばれ続ける力”を備えたポートフォリオが構築できるでしょう。
5. まとめ
体験型消費は、富裕層の持つ「価格より意味」という価値観を背景に拡大しています。旅行・食・文化の文脈で購買プロセスを物語化し、信頼・体験・希少性を軸にブランディングすることが重要です。
カード事業や金融サービスは、体験特典やコンシェルジュによってサービス利用の前後工程まで支援し、紹介を起点に関係性を深めることで効果を発揮します。
今後も体験カテゴリーは支出差が最大化する分野であり、事業の中核として投資検討する価値が高いといえるでしょう。
ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。富裕層の方に対して、状況に応じた最適なアドバイスをいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
