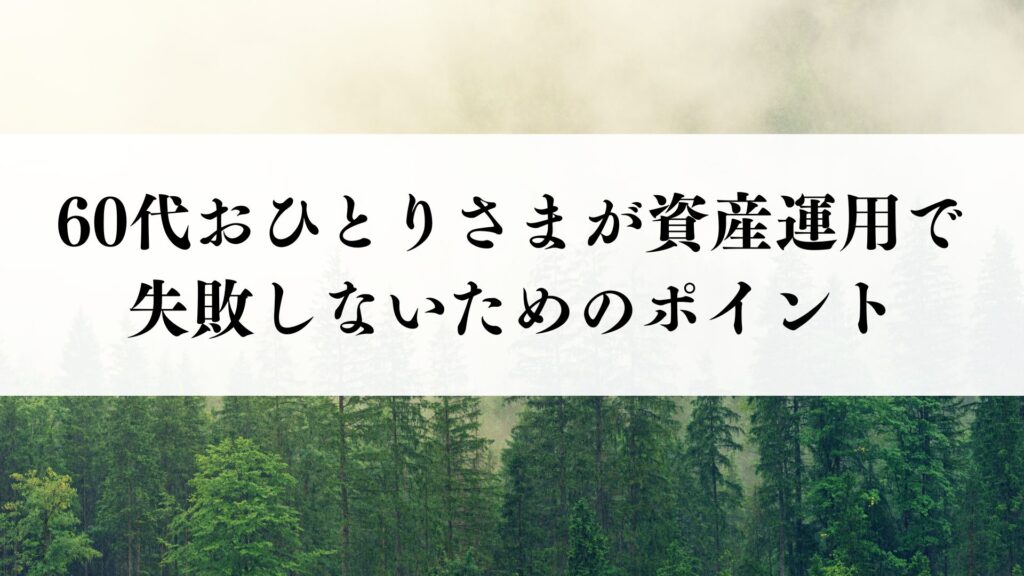
人生100年時代を迎え、資産運用はこれからの生活を守るために不可欠な選択となっています。
特におひとりさまにとって、配偶者や家族に頼ることが難しい分、老後の生活を支える経済基盤は自分自身で築く必要があります。
年金だけでは不十分な現実を踏まえ、判断力の低下や詐欺リスクなど、高齢期特有の課題を理解しながら、安全で効果的な資産運用を始めることが重要です。今からでも遅くない、賢い資産運用のポイントをご紹介します。
1. なぜ今、60代おひとりさまが資産運用を考えるべきなのか?
60代を迎えると、仕事や生活のペースが落ち着く一方で、「老後」という言葉がより身近になります。特におひとりさまの場合、経済面・生活面の両面において、自分一人が頼りとなるため、将来の備えはより重要です。
ここでは、あらためて資産運用を考えるべき理由を整理します。
1-1. 平均寿命の延びがもたらす「老後30年時代」
日本は世界でも有数の長寿国です。厚生労働省の統計によると、2024年時点での平均寿命は男性が約81歳、女性が約87歳とされています。しかしこれはあくまで平均値であり、健康状態や生活習慣によっては、さらに長生きする人も少なくありません。
たとえば、60歳で定年退職し、90歳まで生きるとすれば、老後の生活は30年間に及びます。しかも、老後は収入が限られる中で生活を続ける必要があるため、長寿は喜ばしい一方で「お金が足りなくなるリスク」も高まります。
さらに、医療技術の進歩により、介護や治療を受けながら長生きするケースも増えています。介護費用や医療費は年齢とともに増加する傾向があり、こうした将来の支出をカバーするためにも、運用によって資産を増やす工夫が求められます。
1-2. 年金だけでは心許ない生活費の実態
老後の主な収入源は公的年金ですが、必ずしも生活費のすべてをまかなうのは難しいのが現状です。
総務省の「家計調査」によれば、65歳以上の単身無職世帯の平均的な消費支出は月約14.9万円です。一方で、厚生労働省の公的年金の平均支給額は、国民年金のみの場合で月5〜6万円程度、厚生年金を含めても単身では月10万円前後にとどまるケースもあります。
つまり、月に数万円の不足が生じる可能性が高く、年間で考えると数十万円、20〜30年という老後期間では1,000万円以上の不足になることもあります。この差額をどう補うかが、老後の安心度を大きく左右します。
もし定期預金だけに資産を置いておくとすると、利息はほとんど増えず、物価上昇(インフレ)によって実質的な資産価値が目減りする恐れがあります。
少しでも資産を増やし、長期的に生活費を補うために、運用を取り入れることが現実的な選択肢となります。
1-3. おひとりさま特有の「頼れる人がいない」リスクとは
おひとりさまの場合、配偶者や子どもといった近しい家族がいないことも少なくありません。
家族がいれば、病気や介護が必要になった際に経済的・精神的な支えになってくれることがありますが、おひとりさまはその役割を自分の資産と制度の活用で補う必要があります。
特にリスクとなるのが、急な病気や事故による収入減少や出費増加です。
たとえば入院や長期療養になった場合、医療費や生活費を同時にまかなう必要があり、短期間でも大きな負担となります。また、判断能力が低下した際に、資産を適切に管理してくれる人がいないと、不正利用や詐欺被害に遭う危険も高まります。
こうした状況に備えるには、単に資産を貯めておくだけでなく、「使いやすい形」「守りやすい形」にしておくことが重要です。信託制度の活用や、分散投資による安定的な収益確保は、その一例です。
さらに、定期的に資産の状況を見直し、必要に応じて運用方針を変える柔軟さも求められます。
2. おひとりさまの資産運用での注意点
おひとりさまが資産運用を行う際は、資産を「増やす」視点と同じくらい、「守る」視点が重要です。
特に、年齢を重ねることで起こりうる判断力の低下、詐欺や悪質商法の被害、そして病気や入院時の資金凍結といったリスクは、早めに備えておくことで影響を最小限にできます。以下では、それぞれの注意点を解説します。
2-1. 判断力の低下に備えた仕組みづくり
加齢に伴い、判断力や記憶力が徐々に低下するのは自然なことです。
しかし、資産運用においてはその影響が大きく、誤った判断や遅れた対応が損失につながる場合があります。将来の自分を守るために、事前に準備をすることが大切です。
・運用の自動化
投資信託の積立設定の仕組みを活用すれば、日々の相場変動に左右されずに安定した運用を続けられるでしょう。あらかじめ金額と購入日を決めておくことで、感情的な判断を減らし、長期的な成果につなげやすくなります。
・運用方針の「見える化」
現在の資産配分、投資先の目的、売却条件などを紙やデジタルにまとめておくと、判断力が落ちたときや第三者が関与するときの指針になります。簡潔なメモ形式でも、記録があるだけで意思の確認ができるようになります。
・法的制度の活用
任意後見制度や家族信託は、判断能力が低下した場合に備える有効な手段です。おひとりさまの場合、後見人や受託者に専門職(司法書士・弁護士)を選任することもできます。資産の管理方針や支出の優先順位を契約で明確にしておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
・シンプルな資産構成への移行
高齢期には、管理が複雑な金融商品よりも、理解しやすく安全性の高い資産を中心に構成する方が安心です。商品数を絞ることで管理の負担を軽減し、判断ミスの可能性を抑えられます。
2-2. 高齢者を狙う詐欺や悪質商法から身を守るには
資産運用を行っている人は、詐欺グループから「お金を持っている」と見なされやすく、標的にされるリスクが高まります。特におひとりさまは相談相手が限られることもあり、被害が発覚しにくい傾向があります。
〈代表的な手口〉
- 未公開株詐欺:「まもなく上場予定」「大手企業が出資」などと偽り、実際には価値のない株式を高値で売りつける
- 高利回り保証型投資:「元本保証で年利10%以上」「損はしない」など、あきらかに非現実的な条件で資金を集める
- 還付金詐欺:「税金や医療費の還付がある」と偽って口座情報を聞き出す
- 名義貸し詐欺:「名義を貸せば謝礼がもらえる」と誘い、実際には犯罪や多額のローン契約に巻き込む
・即断即決しない習慣
詐欺は「今契約しないと損をする」と焦らせるケースが多いため、必ず一度持ち帰って冷静に判断することが重要です。不審な場合は、その場で返答せず、後日改めて検討するようにしましょう。
・公的機関の活用
消費生活センター(188)や警察相談専用窓口(#9110)は、怪しいと感じた段階で相談できます。被害に遭う前に第三者の意見を聞くことで、被害防止につながります。
・情報管理の徹底
資産状況や投資の詳細をSNSや知人に安易に話さないことも重要です。郵便物や契約書類は施錠できる場所で管理し、外部に漏れないように気を付けましょう。
・定期的な第三者チェック
年に一度など定期的に、信頼できる専門家に資産や契約の内容を確認してもらうと、不自然な動きや不要な契約を早期に発見できます。
2-3. 病気や入院時に「お金を引き出せない」リスクとは
おひとりさまが直面しやすいもう一つの大きなリスクが、病気や入院によって自分でお金を引き出せなくなる状況です。長期間の入院や意識障害、判断能力の低下が起こると、銀行口座や証券口座へのアクセスが制限され、資産を動かせなくなる可能性があります。
・口座凍結の可能性
本人が重病や認知症などで判断能力を失ったとみなされると、銀行は安全のため口座取引を制限することがあります。相続が発生した場合と同様に、一部の取引が停止され、生活費や医療費の支払いが滞るリスクがあります。
・キャッシュフローの確保
入院中でも必要な支払いを続けるため、生活費や医療費の半年〜1年分は、すぐに引き出せる普通預金口座やネット銀行に置いておくことが有効です。また、キャッシュカードやネットバンキングの暗証番号は安全な方法で管理しましょう。
・法的代理制度の利用
任意後見契約や家族信託を活用すれば、自分が意思表示できなくなった場合でも、あらかじめ指定した代理人が資産を管理・運用できます。おひとりさまの場合、専門家を代理人にすることで、法的に認められた範囲で資金を動かせる仕組みを作れます。
・代理人カード
金融機関によっては、代理人用キャッシュカードの発行が可能です。これにより、家族や信頼できる第三者が必要なときに引き出しや支払いを代行できます。
ただし、信頼性と管理ルールを明確にしないと、不正利用のリスクもあるため注意が必要です。また、銀行によって代理人に指名できる条件が異なりますので事前に調べておきましょう。
・長期入院に備えた保険
医療保険や入院保障を組み合わせておくことで、入院中の費用を保険金でカバーすることができます。これにより、資産を大きく崩さずに療養生活を送ることができます。
ただし、商品によって保障内容は多岐にわたります。自分に合った保障を選べているか、また月々の保険料負担は問題ないかなど、定期的に内容を見直すことが大切です。
3. 60代からの資産運用-3つの基本ルール
60代は、これまで築いてきた資産を「守りながら活かす」ことが求められる時期です。
現役時代のように積極的に資産を増やすよりも、リスクを抑えて安定した生活を維持する運用が重要になります。ここでは、60代からの資産運用で意識したい3つの基本ルールをご紹介します。
3-1. 「増やす」より「減らさない」を意識する
60代からの運用は、将来の収入増を目指すよりも、これまで蓄えた資産を減らさないことが大きな目的になります。なぜなら、退職後は給与収入がなくなるため、損失を取り戻すことが難しくなるからです。
特に株式やハイリスク商品に大きく資産を振り分けると、市場の下落局面で資産が減少し、その後の生活に影響が及ぶ可能性があります。
・元本の保全を優先
資産運用を考える際には、「安全資産」を中心に構成すると安心です。安全資産とは、元本割れのリスクが低い商品(定期預金、個人向け国債、短期国債、MMFなど)を指します。これらを生活資金のベースとして確保することで、市場の変動に左右されにくくなります。
・インフレへの対応も意識
元本保全を重視すると、定期預金や国債のように利回りが低い商品が多くなります。しかし、物価が上昇すると実質的な資産価値は目減りします。そのため、安全資産に加え、値上がりや配当収入が期待できる低リスクの投資信託や高格付け社債なども一部組み合わせると、バランスが取れるでしょう。
3-2. 「生活資金」と「運用資金」を明確に分ける
運用を始める前に大切なのは、手元資金を「生活資金」と「運用資金」に分けることです。この区分けが曖昧だと、予期せぬ出費のたびに投資商品を売却しなければならず、損失が発生するリスクが高まります。
・生活資金の目安
生活資金は、少なくとも1〜3年分の生活費を確保しておくと安心です。例えば、月20万円の生活費が必要なら、最低でも240万円〜720万円程度を、いつでも引き出せる普通預金や定期預金に置いておくのがひとつの目安となります。この生活資金には、医療費や介護費用、住宅の修繕費といった突発的な支出も含めておくと、さらに安心です。
・運用資金の活用方法
生活資金を確保した上で余裕がある分を運用資金として使います。運用資金は、中長期的に増やす目的で投資信託、ETF、社債、REITなどに分散投資する方法が考えられます。運用資金は「なくても生活に困らないお金」に限定することが、リスクを取りやすくするポイントです。
・資金の取り崩し計画
運用資金からの引き出しは計画的に行いましょう。たとえば「年間で資産の3〜4%を取り崩す」というルールを決めておくと、資産寿命を延ばしやすくなります。有名なのが「4%ルール」です。これは、老後資金を長期間持たせるための、資産引き出しの目安です。
退職時の総資産から毎年4%をインフレ調整しながら取り崩すと、過去の米国市場データでは約30年間資金が枯渇しにくいとされています。株式と債券を組み合わせた分散投資が前提で、日本では低金利や物価変動を考慮し、3%台に抑えるとより安全だと考えられます。
しかし、資産の構成や時代によっても変わるため、いつでもこのルールが当てはまるわけではないことは注意しておきましょう。
3-3. なるべくシンプルで管理しやすい運用を
高齢になるにつれて、金融商品の管理や運用判断が複雑になるとミスが増える可能性があります。そのため、商品や取引口座の数を絞り、管理の手間を減らすことが重要です。
・商品数を減らす
株式、債券、投資信託などを細かく分けて複数持つと、管理が難しくなります。60代以降は、複数の資産クラスに投資できるバランス型投資信託やETFなど、1つの商品で分散投資できるものを選ぶと管理がしやすいです。
・口座の整理
証券会社や銀行口座を複数使い分けている場合は、利用頻度の低い口座を整理しておくと、資産全体の把握がしやすくなります。運用資産を一元管理できる状態にしておくことで、判断や手続きがスムーズになります。
・自動化と定期見直し
積立や分配金の再投資設定など、運用を自動化できる仕組みを活用すれば、日々の相場を追わなくても運用が続けられます。加えて、年に1〜2回は運用状況を確認し、必要に応じて資産配分を見直すと、過度なリスク偏重を避けられます。
・相続や管理の引き継ぎを意識
おひとりさまの場合でも、資産を将来どのように使い切るか、または寄付や相続の形で引き継ぐかを決めておくと、終盤の資産管理がスムーズになります。さらに、遺言書を作成しておくと、後々の混乱を防げます。
4. 60代おひとりさまに向いている資産運用とは?リスク別に紹介
60代おひとりさまの資産運用では、「どの程度のリスクを取れるか」が運用方法を選ぶうえでの大きなポイントになります。
年齢的に大きな損失を取り返す時間は限られているため、資産の一部は安全性を重視しつつ、将来の生活費を補うために一定のリターンも確保したいところです。ここでは、リスクレベル別におすすめの運用方法を紹介します。
4-1. 安全性重視なら「定期預金」「個人向け国債」
・定期預金
定期預金は元本保証(元本1,000万円までと破綻日までの利息などが保護されている、外貨は対象外)があり、満期まで保有すれば元本割れの心配がほとんどない商品です。
預け入れ期間は1年、3年、5年などから選べ、満期ごとに利息が受け取れます。現在は低金利ですが、キャンペーン金利を活用すれば、普通預金よりも高い利息を得られる場合があります。また、高額資金を一時的に安全に保管する手段としても有効です。
・個人向け国債
国が発行する債券で、元本と利息の支払いが保証されているため、安全性は高いといえます。「固定3年」「固定5年」「変動10年」の3種類があり、中でも「変動10年型」は金利が半年ごとに見直され、将来的な金利上昇にも対応できます。
1万円から購入でき、途中解約も一定条件をクリアすれば可能なため、流動性も確保しやすい商品です。また、すべてのタイプ(固定・変動ともに)において、最低年0.05%の利率が保証されています。
・メリットと注意点
安全性重視の商品は、リスクが低い反面、得られる利息も小さくなります。そのため、全資産をこれらの安全資産にするとインフレに弱くなる点に注意が必要です。生活費の基盤部分として活用し、残りの資金は別の方法で運用するのがバランスの取れた使い方です。
4-2. リスクとリターンのバランスを重視した「バランス型ファンド」「分配型ファンド」
・バランス型ファンド
バランス型ファンドは、株式・債券・REIT(不動産投資信託)など複数の資産に分散投資できる投資信託です。
1つの商品で国内外の幅広い資産に投資できるため、手間をかけずに分散効果を得られます。価格変動はありますが、資産を分けて投資することで大きな下落リスクを緩和できます。
・分配型ファンド
分配型ファンドは、運用益や一部元本を定期的に分配金として受け取れる投資信託です。毎月・隔月・年数回など受け取り頻度を選べ、年金のように定期収入を得る感覚で利用できます。
ただし、分配金が必ずしも利益だけから支払われるわけではなく、元本が取り崩されている場合もあります。そのため、分配金の水準や元本の減少リスクを理解したうえで選ぶことが大切です。
・メリットと注意点
このカテゴリーの商品は、安全資産よりも利回りを期待できますが、価格変動リスクが伴います。一部をこの層に振り分け、残りを安全資産に置くことで、リスクとリターンのバランスをとることが可能です。特に「安定収入を確保しながら資産を減らさない」ことを目的とする場合に有効です。
4-3. 少額から無理なく始めたい方に「つみたて投資信託」
・つみたて投資信託の特徴
つみたて投資信託は、毎月一定額を自動的に投資信託に積み立てる仕組みです。
少額から始められるため、大きな資金を一度に投入せず、時間をかけて資産を形成できます。購入タイミングを分散できる「ドルコスト平均法」により、価格変動リスクを平準化できるのが特徴です。ドルコスト平均法は、価格変動のある金融商品を一定額ずつ定期的に購入する投資手法です。
価格が高い時は少なく、安い時は多く買うため、購入単価が平均化され、長期的には価格変動リスクを抑えやすくなります。このように、積立投資は初心者に適した方法ですが、相場が長期的に下落する局面では損失が出る可能性もあるため、投資目的や期間を明確にして活用するようにしましょう。
・対象商品の選び方
NISA対応の低コストインデックスファンドなど、信託報酬が低く、長期運用に向いた商品を選ぶと効率的です。例えば、国内外の株式や債券に連動するインデックスファンドは、幅広い市場に分散投資できるため、特定の銘柄リスクを抑えられます。
・メリットと注意点
少額から始められるため、資金に余裕がない場合や、これから運用を学びたい方にも向いています。一方で、短期間では元本割れの可能性もあるため、生活資金ではなく余裕資金で行うことが前提です。
また、60代から始める場合は、長期間の積立が難しい場合があるため、5〜10年程度の運用期間を想定して計画を立てるようにしましょう。
5. 安心して老後を過ごすために大切なこと
老後を安心して過ごすためには、資産運用や貯蓄だけでなく、生活全体を支える「知識」「制度」「環境」の3つの柱を整えることが大切です。
特におひとりさまの場合、頼れる人が限られる分、自分の判断と準備がより重要になります。ここでは、老後の安心のために意識しておきたい3つのポイントを紹介します。
5-1. 金融リテラシーを高めて“判断力の見える化”を
老後資産を守り、必要なときに適切な判断を下すためには、最低限の金融知識が欠かせません。金融リテラシーが高いほど、商品や制度のメリット・デメリットを理解し、自分に合った選択がしやすくなります。
・基本的な金融知識の習得
金利やインフレの意味、複利の効果、金融商品の仕組みといった基本的な概念を理解しておくと、資産運用や契約内容の判断に役立ちます。
・判断基準を明文化する
「どんな商品に投資するか」「何%損が出たら売却するか」といった判断基準を事前に明文化しておくと、感情に流されず冷静に判断できます。将来、自分の判断力が低下した場合でも、この基準が指針となるでしょう。
・情報源の選び方
インターネットやSNSには、正確性が不明な情報も多く流れています。金融商品の情報や制度改正については、金融庁・証券会社・銀行など信頼できる公的機関や大手金融機関の発信を確認することが大切です。
5-2. 公的支援制度や成年後見制度なども選択肢に
老後は、自分ひとりで生活や資産を管理することが難しくなる可能性があります。そんなとき、国や自治体の制度、法的な仕組みをうまく活用すれば、生活の安定と資産保全に役立ちます。
・公的支援制度の活用
介護保険制度、医療費の高額療養費制度、年金生活者支援給付金など、年齢や所得に応じて利用できる制度が複数あります。制度は改正されることも多いため、定期的に最新情報を確認することが必要です。地域の包括支援センターや市区町村役場の相談窓口では、制度の利用条件や申請方法を教えてもらえます。
・成年後見制度
判断能力が低下した際に、代理人(成年後見人)が財産管理や契約手続きを行う制度です。家庭裁判所が選任する「法定後見制度」と、自分であらかじめ後見人を決めて契約する「任意後見制度」があります。おひとりさまの場合、親族だけでなく司法書士や弁護士など専門家を後見人に選任することもできます。
・家族信託
こちらは比較的新しい仕組みで、信頼できる人(受託者)に資産を託し、契約内容に沿って管理・運用してもらう方法です。成年後見制度より柔軟な管理が可能で、相続や資産承継の計画にも活用できます。
5-3. 一人でも安心できる暮らしのインフラを整える
おひとりさまの老後は、日々の生活を支える「人・住まい・サービス」のインフラを整えることで安心感が大きく高まります。
・住まいの確保
持ち家の場合は、バリアフリー化や耐震補強などのリフォームを早めに行い、将来も安全に暮らせる環境を整えます。賃貸の場合は、高齢者向け住宅やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、年齢を重ねても入居しやすい物件を検討しておくと安心です。
・生活支援サービスの活用
買い物や家事、通院の付き添いなどをサポートしてくれる民間サービスや、自治体の高齢者支援事業を活用することで、体力や健康状態の変化に対応できます。特におひとりさまの場合は、緊急時に駆けつけてくれるサービスを契約しておくと安心です。
・人とのつながりづくり
孤独や緊急時の対応不足を防ぐため、地域のサークルや趣味の集まり、ボランティア活動などを通じて人とのつながりを持つことも大切です。連絡先や緊急連絡方法を信頼できる友人や知人と共有しておくことも、有事の安心につながります。
6.まとめ
60代おひとりさまの資産運用は「増やす」より「減らさない」ことを重視し、生活資金と運用資金を明確に分けることが基本です。
安全性重視なら定期預金や個人向け国債、バランスを求めるならバランス型ファンド、少額から始めるなら積立投資信託などの金融商品が考えられます。判断力低下や詐欺への備え、病気時の資金アクセス確保も重要な課題です。
金融リテラシーの向上、公的制度や成年後見制度の活用、生活インフラの整備を通じて、安心できる老後の基盤を築きましょう。
ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。富裕層の方に対して、状況に応じた最適なアドバイスをいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
