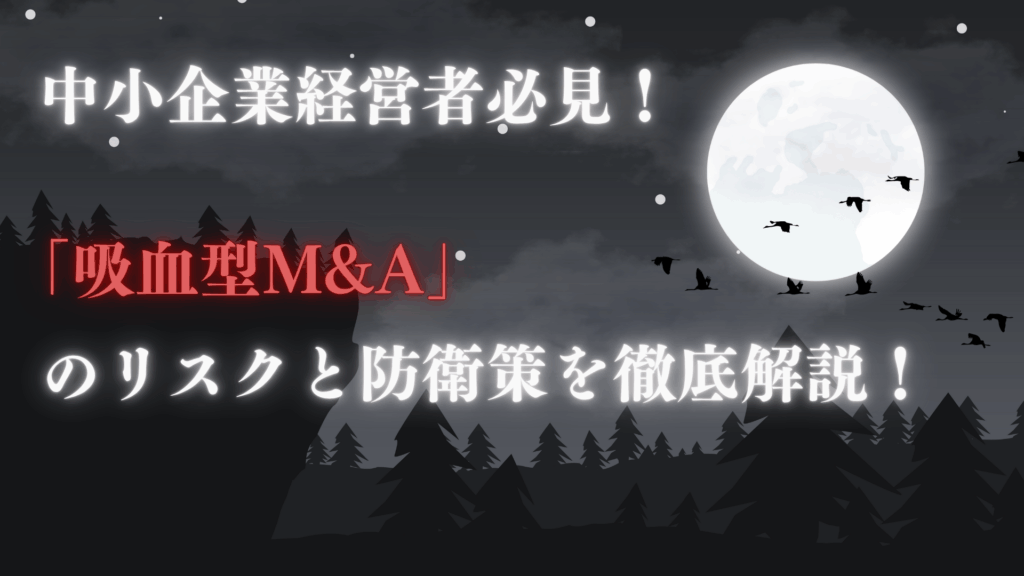M&A
中小企業経営者必見!「吸血型M&A」のリスクと防衛策を徹底解説
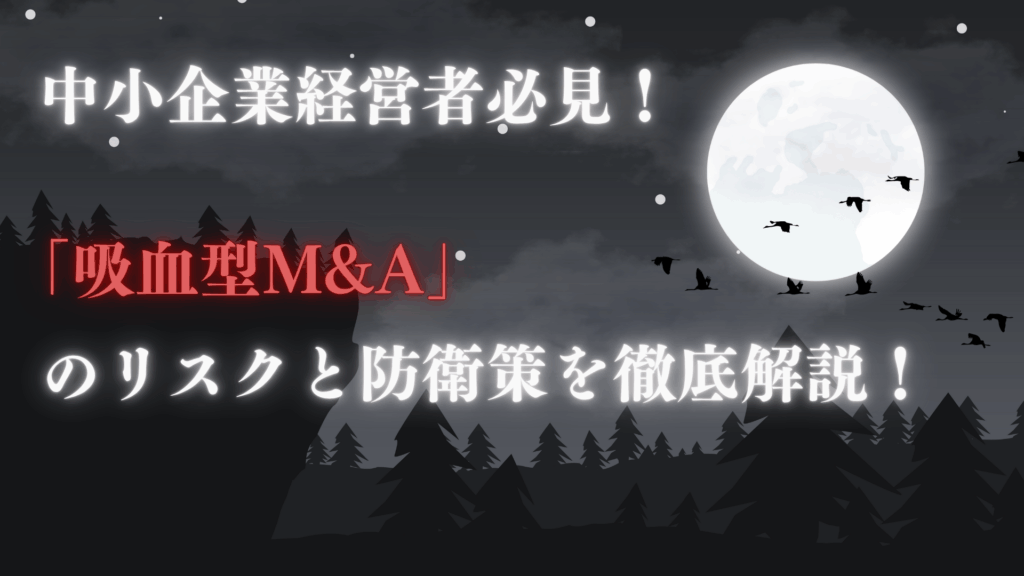
近年、中小企業を取り巻くM&A市場が活発化する一方で、「吸血型M&A」と呼ばれる危険な買収手法が問題視されています。
この手法は、経営者の知識不足や時間的制約につけ込み、まるで吸血鬼のように企業の資産をむしばむような悪質なものです。
本記事では、「吸血型M&A」の概要からその被害事例、そして企業がどのように防衛すべきかを、わかりやすく解説します。経営者の方々はもちろん、M&Aに関心があるすべての方にとって必見の内容です。
目次
1. 吸血型M&Aとは何か?
2. 吸血型M&Aに狙われやすい企業の特徴
2-1. 後継者不在の中小企業
2-2. 売却を急いでいる中小企業
2-3. M&Aが初めてで知識が薄い中小企業
3. 売却後に経営者が直面しやすいリスク
3-1. 財務基盤の弱体化
3-2. 企業の信用低下
3-3. 従業員の離職
4. 経営者が実行すべき5つの防衛策
4-1. M&Aに精通した仲介会社に相談する
4-2. 買い手企業の背景調査を徹底する
4-3. 正式なM&Aプロセスを踏む
4-4. 契約内容を慎重に精査する
4-5. M&Aのセカンドオピニオンを活用する
5. まとめ
1.吸血型M&Aとは何か?
「吸血型M&A」とは、ターゲット企業の現預金などの資産だけを吸い上げ、借入金や未払金といった負債は元オーナーに押しつけるという、悪質な買収手法です。
このようなM&Aは、買収側がターゲット企業の弱点や経営課題につけ込み、不当に安い価格で企業を買収し、価値のある資産だけを回収することを目的としています。
表面的には合法的なM&Aのように見えることもあり、特に知識や経験が不足している中小企業経営者が被害に遭いやすい傾向があります。
買収後、現金や売掛金、不動産といった流動性の高い資産はすぐに買収側に移される一方で、借入金や未払い金などの負債は買収前の法人にそのまま残されます。
その結果、企業は資産を失い、負債だけが残るという最悪の事態に陥り、経営の立て直しが極めて困難になるケースも少なくありません。
特に問題なのは、こうした買収が通常のM&Aと見分けがつきにくいため、被害に気づいた時にはすでに手遅れということもあるのです。
2.吸血型M&Aに狙われやすい企業の特徴
吸血型M&Aのターゲットにされやすい企業には、いくつかの共通した特徴があります。
この記事は会員限定の記事です。
会員限定コンテンツがすべて読み放題
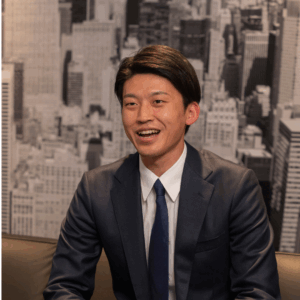
大学卒業後、新卒で銀行へ入行。支店業務(担当地域の個人・法人のお客様へ資産運用や融資の提案を主に実施)を経験後、本部へ異動し富裕層や相続・事業承継業務及び支店管理、提携先との連携や折衝を経験。頭取表彰や本部長表彰等受賞。銀行の求めるものとお客様の求めるものとのずれを感じ、株式会社ファーストパートナーズへ転職。現在は幅広いサービスや金融商品をお客様に案内できる環境にあり、お客様のニーズから真に求めるものを提案できるよう日々行動している。
保有資格:証券外務員一種、内部管理責任者、生命保険協会認定保険募集人、FP二級技能検定資格
';
window._nslWebViewNoticeElement.insertAdjacentHTML("afterbegin", webviewNoticeHTML);
document.body.appendChild(window._nslWebViewNoticeElement);
}
});
}
}
window._nslDOMReady(function () {
window.nslRedirect = function (url) {
if (scriptOptions._redirectOverlay) {
const overlay = document.createElement('div');
overlay.id = "nsl-redirect-overlay";
let overlayHTML = '';
const overlayContainer = "",
overlayContainerClose = "
",
overlaySpinner = "",
overlayTitle = "" + scriptOptions._localizedStrings.redirect_overlay_title + "
",
overlayText = "" + scriptOptions._localizedStrings.redirect_overlay_text + "
";
switch (scriptOptions._redirectOverlay) {
case "overlay-only":
break;
case "overlay-with-spinner":
overlayHTML = overlayContainer + overlaySpinner + overlayContainerClose;
break;
default:
overlayHTML = overlayContainer + overlaySpinner + overlayTitle + overlayText + overlayContainerClose;
break;
}
overlay.insertAdjacentHTML("afterbegin", overlayHTML);
document.body.appendChild(overlay);
}
window.location = url;
};
let targetWindow = scriptOptions._targetWindow || 'prefer-popup',
lastPopup = false;
document.addEventListener('click', function (e) {
if (e.target) {
const buttonLinkElement = e.target.closest('a[data-plugin="nsl"][data-action="connect"]') || e.target.closest('a[data-plugin="nsl"][data-action="link"]');
if (buttonLinkElement) {
if (lastPopup && !lastPopup.closed) {
e.preventDefault();
lastPopup.focus();
} else {
let href = buttonLinkElement.href,
success = false;
if (href.indexOf('?') !== -1) {
href += '&';
} else {
href += '?';
}
const redirectTo = buttonLinkElement.dataset.redirect;
if (redirectTo === 'current') {
href += 'redirect=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&';
} else if (redirectTo && redirectTo !== '') {
href += 'redirect=' + encodeURIComponent(redirectTo) + '&';
}
if (targetWindow !== 'prefer-same-window' && checkWebView()) {
targetWindow = 'prefer-same-window';
}
if (targetWindow === 'prefer-popup') {
lastPopup = NSLPopup(href + 'display=popup', 'nsl-social-connect', buttonLinkElement.dataset.popupwidth, buttonLinkElement.dataset.popupheight);
if (lastPopup) {
success = true;
e.preventDefault();
}
} else if (targetWindow === 'prefer-new-tab') {
const newTab = window.open(href + 'display=popup', '_blank');
if (newTab) {
if (window.focus) {
newTab.focus();
}
success = true;
window._nslHasOpenedPopup = true;
e.preventDefault();
}
}
if (!success) {
window.location = href;
e.preventDefault();
}
}
}
}
});
let buttonCountChanged = false;
const googleLoginButtons = document.querySelectorAll(' a[data-plugin="nsl"][data-provider="google"]');
if (googleLoginButtons.length && checkWebView()) {
googleLoginButtons.forEach(function (googleLoginButton) {
if (scriptOptions._unsupportedWebviewBehavior === 'disable-button') {
disableButtonInWebView(googleLoginButton);
} else {
googleLoginButton.remove();
buttonCountChanged = true;
}
});
}
const facebookLoginButtons = document.querySelectorAll(' a[data-plugin="nsl"][data-provider="facebook"]');
if (facebookLoginButtons.length && checkWebView() && /Android/.test(window.navigator.userAgent) && !isAllowedWebViewForUserAgent('facebook')) {
facebookLoginButtons.forEach(function (facebookLoginButton) {
if (scriptOptions._unsupportedWebviewBehavior === 'disable-button') {
disableButtonInWebView(facebookLoginButton);
} else {
facebookLoginButton.remove();
buttonCountChanged = true;
}
});
}
const separators = document.querySelectorAll('div.nsl-separator');
if (buttonCountChanged && separators.length) {
separators.forEach(function (separator) {
const separatorParentNode = separator.parentNode;
if (separatorParentNode) {
const separatorButtonContainer = separatorParentNode.querySelector('div.nsl-container-buttons');
if (separatorButtonContainer && !separatorButtonContainer.hasChildNodes()) {
separator.remove();
}
}
})
}
});})();