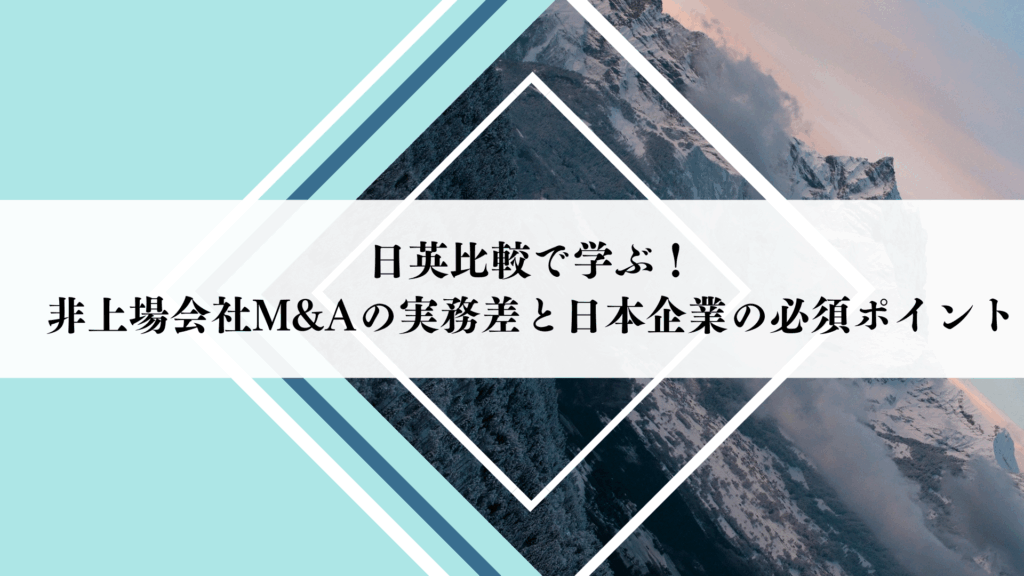
- 日本と英国のM&A実務の違いを知りたい
- クロージング条件やデューデリジェンス範囲の相違点を理解したい
- 日本企業が学ぶべき契約交渉術を押さえたい
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
本記事では、資産運用のプロの視点で、日英における非上場会社M&A実務の違いについて解説します。
この記事を読むことで、交渉や契約に関する不安が解消でき、国際M&Aを有利に進めるための実務力を高めることができるでしょう。
1. 日英の非上場会社M&Aの概観
日英の非上場会社M&Aの概観について、解説します。
1-1. 非上場会社M&Aの基本プロセス
非上場会社のM&Aは、上場会社と比べて開示義務が限定的であるため、買収側による調査と契約交渉が中心となります。
特に株式譲渡をベースとした取引が多く、価格算定、デューデリジェンス、契約書作成、クロージングといったプロセスが一般的です。
この背景には、株式市場を介さずに企業価値を評価する必要がある点があります。財務・税務に加え、労務や法務の調査も不可欠であり、情報の非対称性をいかに解消するかが重要です。
例えば、日本の中小企業M&Aでは、オーナー経営者に属人的な情報が集中しており、開示資料だけではリスクの全体像を把握しにくいケースが考えられます。そのため、交渉段階においては、追加質問や現場調査が不可欠となります。
このように、非上場会社のM&Aでは、公開情報が乏しい分、契約や調査の精度が極めて重要であると言えるでしょう。
1-2. 日本と英国の市場規模・動向
日本と英国では、非上場会社M&Aの市場規模に大きな違いがあります。
日本は近年、事業承継型M&Aが増加し、2025年には過去最高水準に達しました。一方、英国は中小企業からクロスボーダー案件まで幅広いM&Aが展開されており、国際金融センターとしての地位が、M&A市場の厚みを支える基盤となっています。
日本市場の特徴は、オーナー高齢化による後継者不足を背景に、譲渡件数が増加している点です。中小企業庁の調査でも、国内中小企業におけるM&A需要の高まりが明らかになっています。
一方で、英国ではプライベートエクイティの活発な投資により、非上場企業の買収が成長戦略の一部として根付いています。さらに規制環境や仲裁制度の整備が進んでおり、これが取引の流動性を高める要因となっています。
このように、日本は「事業承継ニーズ」が市場を牽引する一方、英国は「成長投資」や「国際的取引」に支えられた市場であると言えるでしょう。
2. クロージング条件の違い
クロージング条件について、解説します。
2-1. 日本のクロージング条件の特徴
日本では、クロージング時点の財務諸表を基に最終価格を調整する「クロージング口座方式」が一般的です。
これは取引成立時点の財務実態を反映するため、買収側のリスクを軽減できる点がメリットです。
ただし、この方式はクロージング後に調整作業が必要であり、価格確定までに時間がかかる点が課題です。売り手にとっては価格が確定しにくく、不確実性が残るというデメリットもあります。
例えば、中小企業の買収では、決算体制が整っていないケースが考えられ、クロージング後に大きな差異が出ることもあります。その結果、追加交渉や紛争に発展するリスクもあります。
したがって、日本のクロージング条件は、買い手に有利である一方、売り手には負担が大きい仕組みであると言えるでしょう。
2-2. 英国のクロージング条件の特徴
英国では「ロックドボックス方式」が広く利用されています。これは基準日を設定し、その時点の財務諸表を基に価格を確定する方法です。価格はクロージング前に固定されるため、売り手にとって高い確実性が得られます。
この仕組みにより、クロージング後の価格調整が不要となり、交渉コストや紛争リスクが低減します。ただし、買い手側は基準日以降の会社活動による価値変動を負担する可能性がある点がデメリットとなります。
例えば、基準日からクロージングまでに債務が増加するケースが想定され、そのリスクを契約条項や表明保証で補う必要が出てきます。
したがって、英国の方式は「価格確定性を重視しつつ、契約設計でリスクを調整する」仕組みといえるでしょう。
2-3. 両国比較から見えるポイント
日本と英国のクロージング条件の違いは、交渉の焦点やリスク配分に大きな影響を与えます。
日本は買い手保護を優先する設計が一般的であるのに対し、英国は売り手にとっての価格確実性が重視されます。
その背景には、企業文化や市場慣習の違いが存在します。日本は慎重な意思決定を好み、英国は効率的な契約履行を求める傾向が強いと言えます。
例えば、クロスボーダー案件では、日本企業が英国のロックドボックス方式に慣れていないため、価格確定方法を巡って交渉が長期化するケースも少なくありません。
このように、双方の特徴を理解することで、国際M&Aにおける交渉力を高められるでしょう。
3. デューデリジェンス範囲の違い
デューデリジェンス(DD)範囲について、解説します。
3-1. 日本のDD範囲と重点項目
日本の非上場会社M&Aでは、デューデリジェンスの重点が税務・株式評価・事業承継に置かれる傾向があります。
これは、オーナー企業が多く存在し、承継リスクを抑える必要があるからです。
調査内容は、財務諸表の精査、税務リスクの確認、株式の適正評価が中心となります。さらに、コンプライアンス体制や許認可の有無も重要視されます。
例えば、製造業のM&Aでは環境規制に関する許認可が不十分なケースが考えられ、買収後に追加投資が必要となる場合もあります。特に中小企業では内部管理が弱く、法令遵守体制が不十分足なケースも少なくありません。
したがって、日本のDDは事業承継を前提とした財務・税務・法令面の安全性確認を重視しているといえるでしょう。
3-2. 英国のDD範囲と重点項目
英国のDDでは、労働契約の移転や年金債務といった、人事・労務関連が大きなポイントとなります。特に「TUPE(事業譲渡に伴う従業員保護規制)」に基づく調査は不可欠です。
また、環境規制やデータ保護(GDPR)も重点項目として扱われます。これは、法規制違反が多額の制裁金につながるため、取引価格や契約条件に直結するからです。
例えば、IT企業の買収では、顧客データ管理が不十分なケースが想定され、GDPR違反による巨額の罰金リスクが発生する可能性があります。そのため、英国ではデータ管理体制を精緻に検証する文化が根付いています。
こうした点から、英国のDDは幅広い法規制を網羅的にカバーする体制が整っているといえるでしょう。
3-3. 両国比較から見えるポイント
日本と英国のDD範囲の違いは、取引コストや期間に直接影響を与えます。日本は比較的、財務・税務に集中する一方、英国は規制対応まで含めた広範囲な調査が求められます。
この違いは、制度や商慣習の違いに起因しています。日本では裁判や行政制裁が比較的限定的であるのに対し、英国は違反に対して厳格な制裁が行われるため、事前調査に時間とコストをかける傾向があります。
例えば、クロスボーダー案件で日本企業が英国企業を買収する場合、想定以上にDDコストがかかるケースが考えられます。調査期間も長引くケースが考えられるため、スケジュール管理とコスト見積もりの精度向上が重要になります。
両国の特徴を理解しておくことで、DDの計画を適切に立て、交渉を円滑に進められるでしょう。
4. 契約条項の違い
契約条項について、解説します。
4-1. 表明保証条項の比較
英国の表明保証条項は、日本と比べて範囲が広く、期間も長期に設定される傾向があります。さらに、免責条件や上限金額も詳細に規定されるのが特徴です。
一方、日本では比較的限定的な記載が多く、網羅性よりも基本的事項を押さえるにとどまります。そのため、買収後に予期せぬリスクが顕在化するケースもあります。
例えば、英国契約では知的財産権や環境規制遵守について明示的に保証を求めるケースが一般的です。これにより、後日発覚した違反でも補償請求が可能となります。
したがって、英国の方式はリスクコントロールに優れた仕組みであり、日本企業も応用する余地があるといえるでしょう。
4-2. 補償・違約金条項の比較
英国では、補償や違約金条項がクロージング条件や価格調整方式と密接に関連付けられているのが特徴です。これは、リスクの所在を契約全体で一貫して設計するという考え方に基づいています。
一方、日本の場合、補償条項は比較的抽象的に記載され、違約金も限定的です。その結果、トラブル発生時の金銭的回収が難しくなる可能性があります。
例えば、環境規制違反が後日発覚したケースでは、英国契約なら違約金と価格調整が連動して即時対応可能ですが、日本契約では長期の訴訟を経て解決するケースが考えられます。
したがって、英国式の詳細設計は、予期せぬ事態への実効性ある備えと言えるでしょう。
4-3. 紛争解決・準拠法の違い
日本では準拠法を日本法とし、紛争解決を国内裁判所に限定することが一般的です。これにより、手続きが分かりやすく、コストを抑えやすいという利点があります。
一方、英国では国際仲裁を選択するケースが多く、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)などが利用されます。これは国際的な執行力と中立性を確保するためです。
例えば、クロスボーダー案件で相手国に資産がある場合、国際仲裁判断は広範に執行可能なため、日本の国内判決よりも実効性が高い場合があるのです。
したがって、国際案件では英国式の紛争解決方法を学ぶ意義が大きいと言えるでしょう。
5. 日本企業が学ぶべき実務ポイント
日本企業が国際M&Aを進めるうえで参考とすべき実務ポイントについて、解説します。
5-1. 英国式から取り入れたい契約交渉術
日本企業は、英国の契約交渉スタイルから学べる点が多くあります。特に、価格調整方式と表明保証を組み合わせて、全体的なリスク配分を最適化する設計は参考になります。
英国では交渉の初期段階から弁護士・会計士が一体となってリスクを洗い出すため、契約条項に反映されやすいのです。日本企業も同様に、初期段階から専門家を積極的に活用する必要があります。
例えば、クロスボーダー案件で相手方がロックドボックス方式を希望する場合、契約交渉で補償条項を強化することで、買収側のリスクを抑制できるでしょう。
交渉力を高めるために、英国式のリスク分担思考を導入することが有効といえます。
5-2. DD精度を高めるための体制整備
DDの精度向上は、日本企業にとって重要な課題です。特に海外案件では、規制や制度の違いを把握しなければ重大なリスクを抱える可能性があります。
英国では、人事・環境・データ保護を含む幅広い視点を持つことが求められます。また、外部専門家の知見を取り入れる体制を構築することが欠かせません。
例えば、GDPR対応を怠れば、買収後に予期せぬ制裁を受けることも想定されます。このような事態を防ぐには、法務・IT・人事部門を横断的に組成したDDチームを構築することが有効です。
結果として、事前調査の精度が高まれば、価格交渉や契約内容の合理性も増すでしょう。
5-3. 国際M&A視点でのリスクマネジメント
国際M&Aに臨む際、日本企業はリスクマネジメントの枠組みを再考する必要があります。為替変動、法規制、文化的差異など複合的なリスクが存在するからです。
英国企業との取引においては、仲裁条項や表明保証を活用し、国際的に執行可能な契約を意識することが求められます。加えて、M&A保険や為替ヘッジを利用したリスク分散も効果的です。
例えば、環境規制に関わる潜在債務が後に顕在化するケースが想定されます。この場合、M&A保険を活用することで不測の損失を吸収できる可能性があります。
このように、総合的なリスクマネジメントを確率することが、国際M&Aを成功する鍵となるでしょう。
6. まとめ
日本と英国の非上場会社M&Aを比較すると、クロージング条件、デューデリジェンス範囲、契約条項に明確な違いが存在します。日本は承継リスクや財務重視の文化、英国は契約確実性や規制遵守の文化が色濃く反映されています。
両国の違いを理解し、日本企業は英国式のリスク分担やDD精度の高さを参考にすることで、より安全かつ効率的な取引を実現できるでしょう。今後の国際M&Aにおいては、これらの知見を実務に落とし込むことが不可欠です。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添ったM&A戦略のご提案を行っております。
事業承継や海外展開を検討されている経営者の方に対して、状況を鑑みながら最適なスキーム選択や契約交渉について的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
