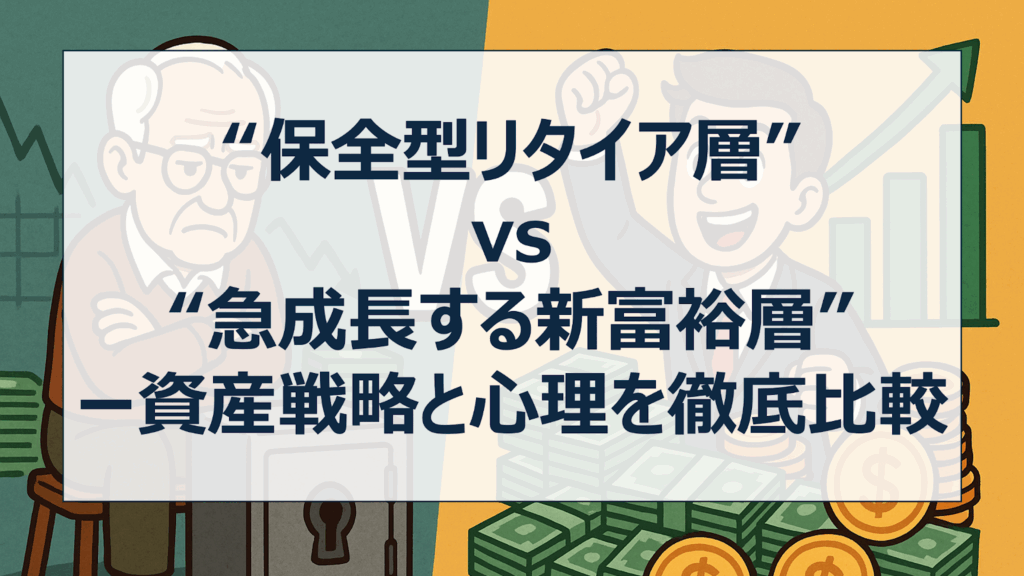
- 富裕層の「保全型リタイア層」と「新富裕層」とは?
- 富裕層2タイプの違いを詳しく知りたい
- 投資目的などの視点別に比較したい
このようなご関心をお持ちではないでしょうか。
本記事では、資産運用のプロが、富裕層2タイプの特徴と違いについて解説します。
この記事を読むと、それぞれのタイプの特徴や資産戦略の違いを理解し、ご自身に合った資産運用の参考にしていただけるでしょう。
1. 富裕層2タイプの概要
日本の富裕層は多様化が進んでいますが、大きく分けると「保全型リタイア層」と「急成長する中高年新富裕層」の2つのタイプが存在します。それぞれの特徴や資産形成の背景を見ていきましょう。
1-1. 「保全型リタイア層」とは?
「保全型リタイア層」とは、主に事業経営や長年の勤労を通じて、着実に資産を形成してきた高齢世代の富裕層を指します。
この層は高度経済成長期からバブル経済期にかけて、多様な資産を形成してきました。資産の「保全」と「次世代への承継」に強い関心を持っているのが特徴です。
この層の資産構成は、不動産、非上場企業の株式、そして長年にわたる預貯金や伝統的な金融商品が中心です。特に日本の家計資産が高齢世代に集中している傾向があり、2024年12月末時点で家計金融資産の約6割を60歳以上が保有していることからも、この層の存在感がうかがえます。
例えば、先祖代々受け継がれた土地や建物を賃貸経営することで収入を得ている地主の方や、長年経営してきた非上場企業の株式を保有している法人オーナーの方などがこの類型に多く見受けられます。自身の経験から、資産の目減りを避ける意識が強い点が大きな特徴です。
1-2. 「急成長する中高年新富裕層」とは?
一方、「急成長する中高年新富裕層」は、近年特に目覚ましい台頭を見せている新たな富裕層のタイプです。
従来の法人オーナーや地主といった富裕層とは異なり、多くは40代後半から50代の現役会社員や、給与所得者出身者で純金融資産1億円以上を短期間で達成した方層です。近年の好調な株式相場や、確定拠出年金(DC)や従業員持株会制度といった長期投資の仕組みを最大限に活用し、株式や投資信託などリスク資産へ積極的に運用をしています。
例えば、ネット証券などを活用して自ら積極的に投資を行い、高い金融リテラシーとデジタルツールを駆使して情報収集や取引を行う傾向が強い方が多数派を占めています。彼らは資産をさらに「成長」させることにも意欲的であり、デジタル化された利便性の高い金融サービスへの期待も高いと考えられます。
2. 富裕層2タイプを6つの視点で徹底比較
「保全型リタイア層」と「急成長する中高年新富裕層」は、資産形成の背景が異なるため、投資スタイルや心理にも大きな違いがあります。
ここではこの2つのタイプをより深く理解するために、6つの重要な視点から徹底比較します。
- 投資目的の違い
- リスク許容度の差
- 投資手法の比較
- 情報収集の方法
- 投資商品の嗜好性
- 意思決定のプロセス
2-1. 投資目的の違い
両者の投資目的は、ライフステージや資産形成の背景を色濃く反映しています。
・保全型リタイア層の主な投資目的は、
築き上げてきた資産を「保全」し、安定的なインカムゲインを確保しながら次世代へ「承継」することが最大の目的。老後の生活設計や医療・介護費用への備えも重視するため、資産の目減りを防ぐことを最優先とし、リスクの高い投機的な運用は避ける傾向が見られます。そのため、資産を減らさないための慎重な運用を金融機関に求めることでしょう。
・急成長する中高年新富裕層
資産をさらに「成長」させる意欲が強く、ポートフォリオの最適化や新たな投資機会に積極的。早期退職や転職、起業といったライフイベントに合わせた資産計画の柔軟な見直しや、資金使途に応じた最適な資金調達・運用方法に関するアドバイスを求めるケースが想定されます。資産の成長と効率的な管理を重視すると言えるでしょう。
2-2. リスク許容度の差
両タイプの富裕層は、資産運用におけるリスク許容度にも明確な違いがあります。
・保全型リタイア層
景気変動や金融危機を経験しており、資産の「保全」や「リスク回避」に対する意識が非常に高いです。彼らは、築き上げてきた大切な資産を減らさないことを最優先とし、安定した収入源の確保を重視します。例えば、リスクの高い投機的な運用は避け、米ドル建て国債や高格付けの社債、あるいは安定した不動産収入など、慎重な資産運用を好む傾向が見受けられます。
・急成長する中高年新富裕層
資産の「成長」を優先するため、一定程度のリスクを許容する傾向があります。株式や投資信託といったリスク性資産を保有し、市場の変動を成長の機会と捉える側面も持ち合わせています。例えば、暗号資産のようなハイリスクな商品に「遊び投資」として少額を投じるケースも見られており、より積極的なリスクテイクの姿勢が見られることがあります。
2-3. 投資手法の比較
両タイプの富裕層は、それぞれの投資目的とリスク許容度に基づき、異なる投資手法を採用しています。
・保全型リタイア層
比較的伝統的で安定性志向。不動産(自宅、賃貸物件など)や、自身の経営する非上場企業の株式、そして預貯金などを中心とした資産形成。相続税対策として不動産を活用したり、生命保険の非課税枠を利用したりするなど、資産を「守りながら次世代に引き継ぐ」ための戦略的な手法を選択します。
・急成長する中高年新富裕層
株式や投資信託などのリスク性資産を高い割合で保有し、積極的に市場を活用。確定拠出年金や従業員持株制度といった長期投資の仕組みを最大限に活用して、複利効果を享受。米国株ETFや海外インフラファンド、さらにはベンチャー投資など、多様なアセットクラスへのアクセス。資産運用の「攻め」と「守り」のバランスを意識しつつ、効率的な資産拡大を目指していると考えられます。
2-4. 情報収集の方法
両タイプの富裕層は、資産運用に関する情報収集の方法も大きく異なります。
・保全型リタイア層
金融に関する一定の知識や判断力を有していますが、近年の金融商品の多様化やデジタル化の急速な進展に対しては、必ずしも最新の情報に精通しているとは限りません。そのため、金融機関の担当者や親族・知人の助言を大いに参考にする傾向が見られます。例えば、複雑な商品の取引や多額の取引を行う際には、普段デジタルチャネルを利用していても、最終的には店舗での対面チャネルを選び、人との対話から安心感を得たいと考える傾向にあります。
・急成長する中高年新富裕層
金融やネットリテラシーが非常に高く、情報収集や投資取引にデジタルツールを駆使する傾向が強いです。インターネットのニュースや報道を最も重視し、専門家や投資家のインターネット・SNSでの発言を参考に投資判断を行うことがあります。例えば、シンガポールのDBS銀行がAIを活用して顧客の資産状況や取引履歴を分析し、最適な投資通知「ナッジ」を提供しているように、パーソナライズされたデジタルアドバイスに高い関心を寄せています。
2-5. 投資商品の嗜好性
それぞれの富裕層タイプは、投資目的とリスク許容度、そして情報収集の方法に合致した投資商品を好む傾向があります。
・保全型リタイア層
資産保全を最優先し、安定的なインカムゲインのある商品を好み、リスクの高い投機的な運用は避ける傾向があります。不動産賃料、株式の配当、債券の利息などが中心。米ドル建ての国債や社債、または高配当銘柄の国内株式など、比較的安全性が高く、中長期的に安定したリターンが期待できる商品を選好する傾向があります。・急成長する中高年新富裕層
資産の成長志向が強く、株式や投資信託といったリスク性資産を高い割合で保有する傾向にあります。ポートフォリオの最適化や新たな投資機会に強い関心を持っており、米国株ETF、海外インフラファンド、さらにはベンチャー投資といった、成長性が見込まれる幅広い商品を積極的に検討するなど、短期間での利益獲得を狙った投資などを好む傾向もあります。
2-6. 意思決定のプロセス
両タイプの富裕層は、資産運用に関する意思決定のプロセスも対照的な特徴を示します。
・保全型リタイア層
資産運用に対して受動的な傾向があり、意思決定には慎重です。そのため、金融機関の担当者や親族・知人の助言を大いに参考に進める傾向があります。例えば、相続・贈与といった複雑な手続きや、将来の財産管理に関する決定に際しては、家族同席での面談を避けつつも、金融機関が家族間の情報共有の重要性を啓発し、家族会議の開催や資産目録の作成・共有を促すことが効果的になるでしょう。
・急成長する中高年新富裕層
ビジネスや資産運用で即決を迫られる場を多く乗り越えてきた経験から、オンオフ問わず決断が非常に速い傾向があります。彼らは金融リテラシーとネットリテラシーが高く、情報収集から投資取引までデジタルツールを駆使しながら、迅速に判断を下すことを好みます。例えば、特定の株式の安値更新や外貨の価格変動といった市場動向に関するリアルタイムの通知「ナッジ」を受け取ることで、自発的かつ迅速に投資行動へ移し、スピーディーな情報に基づいた意思決定を重視していると言えます。
3. まとめ
本記事では、増加する富裕層の中でも特に注目される「保全型リタイア層」と「急成長する中高年新富裕層」に焦点を当て、その資産戦略と心理を6つの視点から比較しました。両者はいずれも「富裕層」という共通点を持ちながらも、資産形成の背景、投資目的、リスク許容度、投資手法、情報収集の方法、そして意思決定のプロセスにおいて、明確な違いが見られます。
「保全型リタイア層」は、長年の蓄積と伝統的な価値観を背景に、資産の保全と安定的なインカムゲイン、そして次世代への円滑な承継を重視する傾向があります。彼らは対面での丁寧なアドバイスや、信頼できる専門家による包括的なサポートを求めることでしょう。
一方、「急成長する中高年新富裕層」は、近年の市場の恩恵と高いデジタルリテラシーを活かし、資産のさらなる成長と効率的な管理を追求しています。彼らはデジタルチャネルを通じたリアルタイムの情報提供や、ライフイベントに合わせた柔軟なプランニングを期待しています。
金融機関にとって、お客様一人ひとりの多様なニーズを深く理解し、それぞれに合った最適なウェルスマネジメントサービスを提供することが、重要な課題になっています。単なる商品販売に留まらず、顧客一人ひとりの価値観、ライフプラン、リスク許容度に深く寄り添った「真のウェルスマネジメント」を提供することが求められます。
ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案を行っております。安定的に資産形成を目指す方に対して、状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
