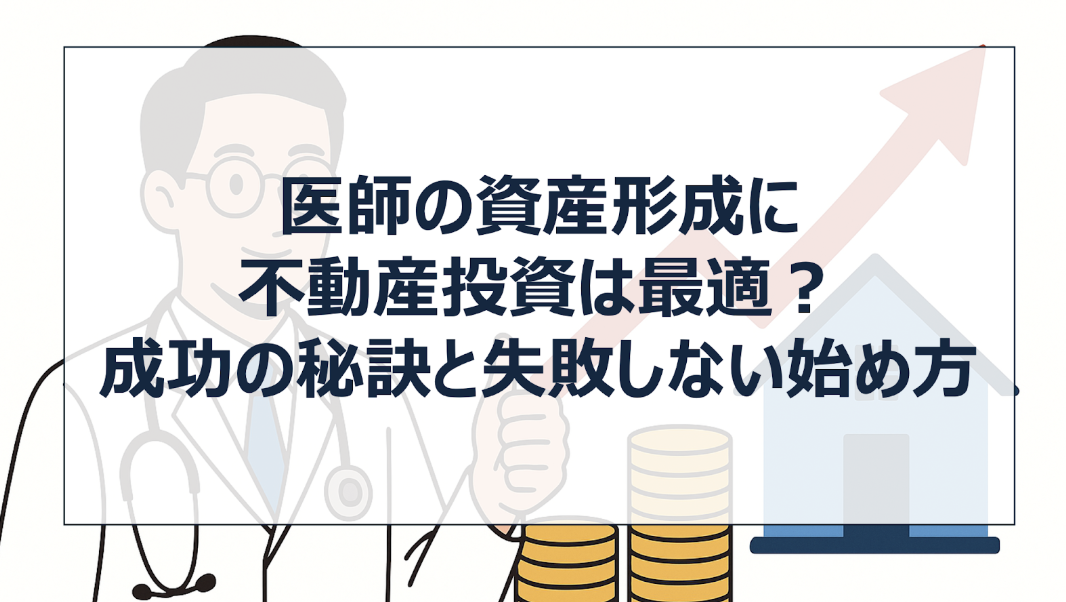
- 医者が不動産投資をすることは最適なのか分からない
- 医者の不動産投資のメリットや気をつけるべき落とし穴について知りたい
- 医者が不動産投資で選ぶべき物件が何か分からない
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。不動産投資のプロが、医者の不動産投資について解説します。
この記事を読むと、医者の不動産投資に関する疑問を解消し、資産形成において有益な情報を得られるでしょう。
1. 医者が不動産投資を始める「3つの理由」
医者が不動産投資を始める具体的な理由を順に見ていきましょう。
1-1. 高収入と安定職だからこそ実現できる融資の優位性
医者は収入の安定性と社会的信用力が高いため、金融機関から好条件で融資を受けやすい傾向にあります。
医者の平均年収が高いことは与信審査で評価され、低金利・高額融資を実現しやすいためです。
例えば、医者がワンルームマンション購入時に一般的なサラリーマンよりも低金利で融資を受けるケースが多く報告されています。
こうした融資の優位性が、不動産投資の第一歩を後押しする大きな要因でしょう。
1-2. 将来に備えた「本業外収入」の確保という考え方
医者は診療報酬に依存しがちですが、不動産収入を得ることで収入源を多様化できます。
収益物件からの家賃収入は、本業の変動リスクを緩和し、安定的な副収入として機能します。
具体的には、投資用アパートを持つ医者が本業での収入が減少している時でも月数十万円の家賃収入が確保できる例があります。
このように、本業以外の収入源を予め構築しておくことは、経済的な安心感につながるでしょう。
1-3. 多忙な医者でも可能な管理負担の少ない資産形成とは
多忙な医者でも、管理業務を専門会社に委託すれば手間を大幅に削減できます。
プロの管理会社に一任すれば、入居者対応や修繕手配などの日常業務を任せられます。
例えば、築古木造アパートを管理会社に丸投げし、本業に集中しながら資産を育てると言った事例が多数あります。
こうした仕組みによって、医者は診療に専念しつつ安定した資産形成が可能になります。
2. 医者にとっての不動産投資、その現実的なメリットとは
実際に医者が不動産投資を行う際に得られる具体的なメリットを以下に沿って解説します。
- 「守りと攻め」の資産運用
- 本業リスクを分散する副収入源の確保
- 相続対策や生命保険効果としての活用
- 時間や手間をかけない投資手法である理由
2-1. 「守りと攻め」の資産運用
不動産投資は守りの節税効果と攻めのインフレ対策を両立できます。
減価償却やローン利息控除で課税所得を圧縮しつつ、実物資産でインフレリスクをヘッジできるのです。
例えば、賃貸マンションの減価償却によって年数百万円の節税を実現し、同時に家賃収入でインフレを上回るリターンを狙う例があります。
このように、守りと攻めを兼ね備えた運用ができるのは不動産ならではでしょう。
2-2. 本業リスクを分散する副収入源の確保
医者は長時間労働や法改正等の影響を受けやすいため、副収入がリスク分散になります。
賃貸収入は本業の忙しさや医院経営リスクとは独立して得られるため、安心材料となります。
例えば、勤務医がクリニックの経営難に直面した際も、投資アパートの家賃収入で生活水準を維持した事例があります。
このように、本業以外の収入源を持つことで、収入不安を軽減できるのです。
2-3. 相続対策や生命保険効果としての活用
不動産は評価額が市場価格より低く算定されるため、相続税の節税に有効でしょう。
現金で相続するよりも不動産を所有するほうが課税評価額が下がり、相続税の負担を軽減できます。
具体的には、土地と建物の評価差を活用し、相続時の税額を数百万円単位で減らした医者の事例があります。
こうした相続対策としての不動産活用は、生命保険の代わりとしても一役買う可能性があります。
2-4. 時間や手間をかけない投資手法である理由
管理会社委託や定期点検契約によりメンテナンス負担を最小限にできます。
物件購入後の運営体制を整えることで、忙しい医者でも長期運用が可能になります。
例えば、入居率95%以上を維持する管理会社と契約した医者が、年間数回の報告を受けるだけで運営することができたケースがあります。
こうした仕組みにより、時間をかけずに安定収入を得られる投資手法といえます。
3. 医者だからこそ陥りやすい不動産投資の落とし穴とは
医者が特に注意すべきリスクや落とし穴を以下に沿って見ていきましょう。
- 情報不足と管理負担が「ストレス」になるリスク
- 医者を狙う詐欺や不適切な提案への注意
- 本当に必要な物件選びの視点
- 安定したキャッシュフローの重要性と物件選び
3-1. 情報不足と管理負担が「ストレス」になるリスク
知識不足で適切な物件選定ができないと、管理負担が大きくなってしまいます。
物件の老朽化や入居者トラブルにより、想定以上の手間やコストが発生する可能性があります。
例えば、築古木造アパートで修繕費が膨らみ、キャッシュフローが赤字化した事例があります。
こうしたストレスを回避するには、情報収集と管理会社選びが不可欠でしょう。
3-2. 医者を狙う詐欺や不適切な提案への注意
高収入の医者はターゲットになりやすいため、甘い条件を餌にした詐欺が存在します。
「節税が100%保証」や「空室リスクゼロ」といった過剰な謳い文句には警戒が必要です。
具体的には、高利回りだけを強調し、建物の状態説明が不十分なまま契約を迫る業者の事例があります。
こうした提案を見抜くためには、複数の専門家の意見を比較することが大切でしょう。
3-3. 本当に必要な物件選びの視点
利回りだけで選ぶと、空室や修繕費リスクを見落としがちです。
築年数や立地、管理体制など総合的に評価する視点が求められます。
例えば、駅徒歩10分以内の築15年以内の区分マンションは入居需要が安定しやすいと言われています。
こうした視点を持つことで、長期的に安定したキャッシュフローを実現しやすくなるでしょう。
3-4. 安定したキャッシュフローの重要性と物件選び
物件選定時に入居率や返済負担率を事前にシミュレーションすることが重要です。
返済額が家賃収入を上回る事態を避け、手元資金の余裕を確保できます。
具体的には、入居率90%でも黒字運用が可能となるよう、返済額を抑えた物件を選定した成功例もあります。
安定したキャッシュフローの確保は、投資継続の鍵となるでしょう。
4. 医者が選ぶべき物件とは?チェックポイント
医者が物件を選ぶ際に見るべき具体的なポイントを以下に沿って解説します。
- なぜ築古・木造・一棟物件が検討されやすいのか
- 築年数・構造・エリア、見るべき具体的な注意点
- 忙しい医者のための物件選定フレーム
4-1. なぜ築古・木造・一棟物件が検討されやすいのか
築古木造一棟物件は購入価格が安く、減価償却費が大きく出るため節税効果が高いとされています。
また、築古ならではの利回りの高さが投資魅力を高めています。
例えば、築30年の木造アパートを低価格で取得し、初年度の減価償却で大きな税効果を実現した医者もいます。
こうした物件は節税目的と高利回りを両立しやすい選択肢といえます。
4-2. 築年数・構造・エリア、見るべき具体的な注意点
築年数が古すぎると修繕費が膨大になるため、耐用年数と修繕計画のバランスが必要です。
木造は減価償却費が大きい一方で耐久性に劣るため、定期的な改修費用を見込む必要があります。
エリア選定では、駅近や生活利便性が高い地域を優先し、将来の需要を見据えるとよいでしょう。
こうした注意点を踏まえることで、長期運用に適した物件を選べるでしょう。
5. 医者の不動産投資成功のカギは誰に相談するかにかかっている
信頼できる相談相手を選ぶポイントを以下に沿って紹介します。
- 医者向け不動産の経験がある専門家を選ぶには?
- 顧客の意向に沿った提案ができるアドバイザーを見極める
5-1. 医者向け不動産の経験がある専門家を選ぶには?
不動産会社やコンサルタントは、医者向け実績が豊富かどうかを確認しましょう。
実績のない業者は医者特有のニーズを理解せず、適切な提案ができない可能性があります。
具体的には、医者専用の投資セミナー実績や事例数を保有する業者を選ぶと安心です。
このように、経験豊富な専門家を選ぶことが成功の第一歩となるでしょう。
5-2. 顧客の意向に沿った提案ができるアドバイザーを見極める
提案内容が画一的ではなく、個別の資産状況やライフプランに合わせているかを見極めましょう。
例えば、複数プランのシミュレーションを提示し、メリット・デメリットを明示してくれるようなアドバイザーは理想的です。
こうした提案を行うアドバイザーとなら、長期的なパートナーシップが築けるでしょう。
6. まとめ
本記事では、医者が不動産投資を始める3つの理由と現実的なメリット、陥りやすい落とし穴、物件選びのポイント、そして相談相手の選び方について解説しました。
融資の優位性や節税効果を最大限に活かしつつ、リスクを回避するための視点を持つことが重要です。信頼できる専門家と連携し、効率的なフレームを活用しながら、医者ならではの資産形成を実現していきましょう。
ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添った不動産投資のご提案を行っております。お医者様の方で、不動産投資をご検討中の方には、お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
