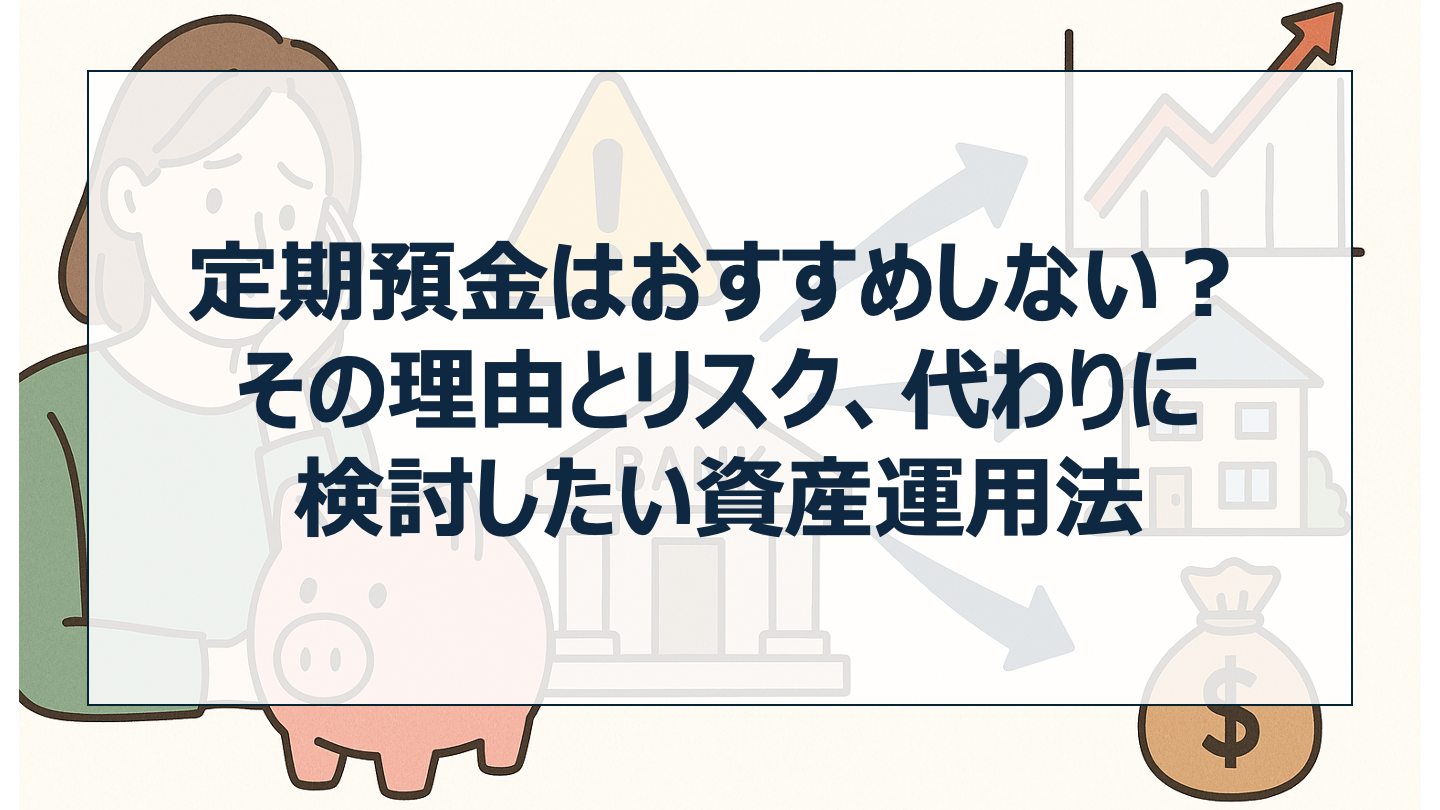
・定期預金はなぜおすすめしないのか?
・定期預金が向いている人と向いていない人について知りたい
・定期預金の代わりに検討すべき資産運用について知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
この記事を読めば、定期預金に関する不安を払拭でき、安定的に資産を増やせる運用に役立つでしょう。
目次
1-1. 普通預金より金利が高い
1-2. 元本割れのリスクがない
1-3. 預金保険制度に守られている
2-1. 金利が低く、資産が増えにくい
2-2. 満期まで自由に引き出しにくい
2-3. 元本保 証 は1,000万円+利息まで
3-1. 向いている人:資産の安全性を最優先する人
3-2. 向いていない人:資産を増やしたい人・運用に興味がある人
4-1. 高金利キャンペーンを活用する
4-2. ボーナスシーズンの特別金利を狙う
4-3. 金利や条件を比較して選択することが重要
5. 定期預金の次に考えたい安定的にお金を増やすための、おすすめ資産運用
1. 定期預金の特徴とメリット
定期預金は、安全性を保ちつつ普通預金よりも高い金利を狙えます。まずはこの基本的なメリットを押さえておきましょう。以下は、定期預金の特徴とメリットです。
・普通預金より金利が高い
・元本割れのリスクがない
・預金保険制度に守られている
それぞれ解説します。
1-1. 普通預金より金利が高い
定期預金は普通預金に比べて設定期間中の金利が高く、同じ金額を預けるなら支払われる利息が大きくなります。銀行は預かった資金を長期運用できる対価として、普通預金より高い金利を提示するためです。
例えば、とあるメガバンクの普通預金金利は約0.2%なのに対し、3年定期預金金利なら約0.35%程度です。金融機関や期間にもよりますが、ネット銀行や信用金庫等のキャンペーンを活用すると年率1%超の金利を受け取れるケースもあります。
仮に100万円を年0.35%で運用すると、1年間で3,500円の利息が得られ、これは普通預金の約2倍の利息額になります。ただし、実際には利息に対しての税金が20.315%が源泉徴収されるため、手取り額は約2,788円になることには注意が必要です。
このように、確実な安全性を保ちつつ、普通預金以上の利息を得たい人には適した方法と言えるでしょう。
1-2. 元本割れのリスクがない
定期預金は元本が保証されており、市場の変動によって預けたお金が減る心配がありません。契約期間中の元本は必ず返還され、金利のみ変動します。
中途解約した場合には金利が普通預金水準まで下がることはあるものの、元本自体が目減りすることはありません。この性質は、投資のリスクを確実に避けたい層にとって安心材料となります。
1-3. 預金保険制度に守られている
定期預金は預金保険制度の対象で、万が一預入先の銀行が破綻しても、金融機関ごとに預金者1人につき普通預金と定期預金の合計で1,000万円+破綻日までの利息が保護されます。
公的機関である預金保険機構が運営しており、金融システムの安定を目的としているため、信頼性が高い仕組みです。
たとえば、500万円を預けていた場合、利息を含めた金額が1,000万円以内なら全額保護されるため、大きな安心感を得られるでしょう。
ただし、1,000万円を超える預金分は保護対象外となるため、保護対象とするためには複数の銀行に分散する必要があります。こうした制度面のメリットも、安全性重視の人には大きな魅力です。
2. 定期預金はおすすめしない?3つのデメリット
さて、安全性の高い定期預金にも、低金利や流動性制限などの理由で「おすすめしない」と言われる3つのポイントがあります。
