
(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
| この記事は2025年6月16日にふるさと納税DISCOVERYで公開された「所得税減税で手取りを増やす!会社員が知るべき税金対策の全知識」を転載したものです。 掲載記事:所得税減税で手取りを増やす!会社員が知るべき税金対策の全知識 |
※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。
「税金、払いすぎていないか?」と感じる会社員の方へ。
毎月の給与明細をご覧になり、「これほど税金が引かれているのか」と感じたことはありませんか。
所得税は、個人の所得に対して課せられる国の税金ですが、さまざまな制度を活用することで軽減が可能です。
減税は複雑に思われるかもしれませんが、会社員の方でも利用できる制度は多く存在します。
この記事では、所得税の基本的な仕組みから、利用できる具体的な減税制度の種類、そしてそれらをどのように申請すれば良いのかまで、わかりやすく解説いたします。
税金に対する漠然とした不安を解消し、適切に手取りを増やすための知識を身につけてください。
そもそも所得税とは何か?減税の仕組みを理解する
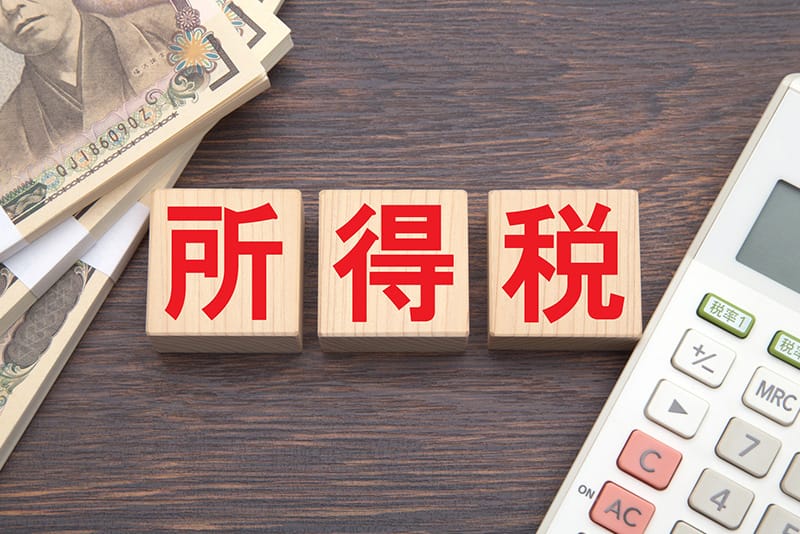
(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
所得税の基本:計算方法と課税の仕組み
所得税とは、個人の所得に課せられる国税です。会社員の場合、通常は毎月の給与から天引きされています。
所得税の計算は以下のとおりです。
- 収入金額 − 所得控除 = 課税所得
- 課税所得 × 所得税率 − 税額控除 = 所得税額
所得税には「累進課税制度」が採用されています。
たとえば、課税所得が195万円以下であれば税率は5%ですが、1,800万円を超えると40%と、所得に応じて税率が変わります。
「減税」の二つのアプローチ
所得税の「減税」には、「所得控除」と「税額控除」の二つの方法があります。
- 所得控除:課税所得を減らすことで結果的に税額を減らす
- 税額控除:算出された税額から直接金額を引く
会社員が知るべき代表的な所得税減税(所得控除)の種類

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
生命保険料控除:保険で安心、税負担も軽減
生命保険に加入している方は、「生命保険料控除」を活用することで、保険による安心だけでなく、税金の軽減というメリットも得られます。これは、1年間に支払った生命保険料に応じて、所得から一定額を控除できる制度です。
生命保険料控除は、保険契約の種類や契約日によって区分されており、次の3つの控除に分類されます。
- 一般生命保険料控除:死亡保険や学資保険などが対象
- 介護医療保険料控除:医療保険や介護保険が対象(平成24年以降の新契約のみ)
- 個人年金保険料控除:個人年金保険が対象(一定の条件を満たす必要あり)
これらの控除はそれぞれ最大4万円、合計で最大12万円まで所得から差し引くことが可能です(新契約の場合)。
医療費控除:病気や怪我が減税につながる
医療費が高額になった年は、「医療費控除」を活用することで、支払った医療費の一部を所得から差し引くことができ、所得税・住民税の軽減が期待できます。
対象になる主な費用
- 処方薬・市販薬の購入費用(治療目的)
- 入院費・手術費
- 出産費用(通院・入院費含む)
- 通院にかかる公共交通機関の交通費
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
対象外の費用
- 美容整形や予防接種など治療目的でないもの
- 健康診断・人間ドック(病気が見つかり治療に至った場合を除く)
- 通院にかかったガソリン代や自家用車の駐車料金
※セルフメディケーション税制との併用は不可
社会保険料控除:意外と見落としがちな控除対象
会社員の方が毎月の給与明細を見て実感するのが、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料が大きな金額で差し引かれていることでしょう。
これらの社会保険料は、すべて「社会保険料控除」の対象となり、支払った金額の全額を所得から控除することができます。
小規模企業共済等掛金控除:老後と税負担を同時に考える
「iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)」や「小規模企業共済」は、老後資金を準備しながら所得税・住民税の軽減が図れる制度です。
これらに支払った掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。
たとえば、iDeCoに毎月2万円(年間24万円)を積み立てた場合、課税所得から24万円が控除され、所得税率が10%の方であれば、所得税が約2万4千円、住民税も約2万4千円、合計で約4万8千円の税負担軽減効果が得られます。
なお、小規模企業共済は、個人事業主や会社役員などが加入できる制度で、掛金の全額が所得控除の対象となる点でiDeCoと同様です。
会社員の方はiDeCoを、個人事業主やフリーランスの方は小規模企業共済の活用を検討するとよいでしょう。
ただし、どちらも以下のような注意点があります。
- 元本保証はありません(iDeCoは運用商品による)
- 手数料が発生します
- 原則として一定年齢まで引き出しができません
こうした制度を正しく理解し、老後資金の形成と税負担軽減の両立を目指すことが大切です。
※元本保証なし・60歳まで引き出し不可・手数料あり
参考:iDeCo公式サイト
地震保険料控除:防災対策が税制優遇に
地震保険料控除の対象となるのは、地震保険単独の契約または火災保険とセットで加入している地震保険の部分です。
火災保険料だけでは控除の対象とはなりませんので注意が必要です。
- 年間の支払地震保険料の全額(最大5万円)を所得控除できる
扶養控除・配偶者控除:家族構成に応じた減税策
「扶養控除」は、16歳以上の扶養親族がいる場合に適用される所得控除です。
納税者と生計を一にしており、かつ所得が一定以下(合計所得金額が48万円以下)の親族が対象となります。
控除額は扶養親族の年齢などによって変わり、以下のように区分されています。
- 一般の扶養親族:38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の学生など):63万円
- 老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居老親等なら58万円)
その他の控除(寄附金・障害者控除など)
「所得控除」として認められる制度は、生命保険料控除や扶養控除などの代表的なもの以外にも多数存在します。
自身や家族の状況によって該当するケースがあるため、該当制度を漏れなくチェックすることが重要です。(以下例など)
- 寄附金控除(ふるさと納税含む)
- 障害者控除
- 寡婦控除・ひとり親控除
手取りを増やす!見落としがちな税額控除と税金軽減のポイント

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
住宅ローン控除:住宅取得時に知るべき制度
住宅ローンの年末残高に応じて、税額から直接控除。初年度は確定申告、2年目以降は年末調整可。
ふるさと納税:応援したい自治体を選んで税額控除に活用
寄附金のうち2,000円を超える部分が控除対象。
5自治体以内ならワンストップ特例制度が利用可。
NISA(つみたてNISA・新NISA):将来の税負担を軽減
運用益や配当金が非課税になる投資制度。直接的な所得控除ではないが、将来的な税負担を軽減する手段として有効。
所得税減税の各種申請について

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)
年末調整で完結できる控除一覧
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- iDeCoの掛金
- 配偶者控除
- 扶養控除
各種申告書・証明書を年末調整で提出。
確定申告が必要なケースを把握する
- 医療費控除を受ける場合
- ふるさと納税でワンストップ特例を使わない場合
- 住宅ローン控除の初年度
- 副業所得が20万円超など
国税庁サイトのe-Taxで自宅から申請可能。
申告ミスは減税機会を逃す原因に
- 書類の保管
- 提出期限の遵守
- 申告漏れの防止
不明点は税務署や専門家へ相談を。
まとめ
この記事では、所得税の基本や減税制度の種類、会社員としての申請種類について解説しました。
控除や減税の制度を知り、正しく活用することで、手取り額の増加が期待できます。
生命保険料控除、医療費控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税など、自身に合った制度を選び、今日から実践を始めてみてはいかがでしょうか。
なお、本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談には対応しておりません。
税制改正の可能性もあるため、正確な情報は必ず税務署や税理士にご確認ください。
