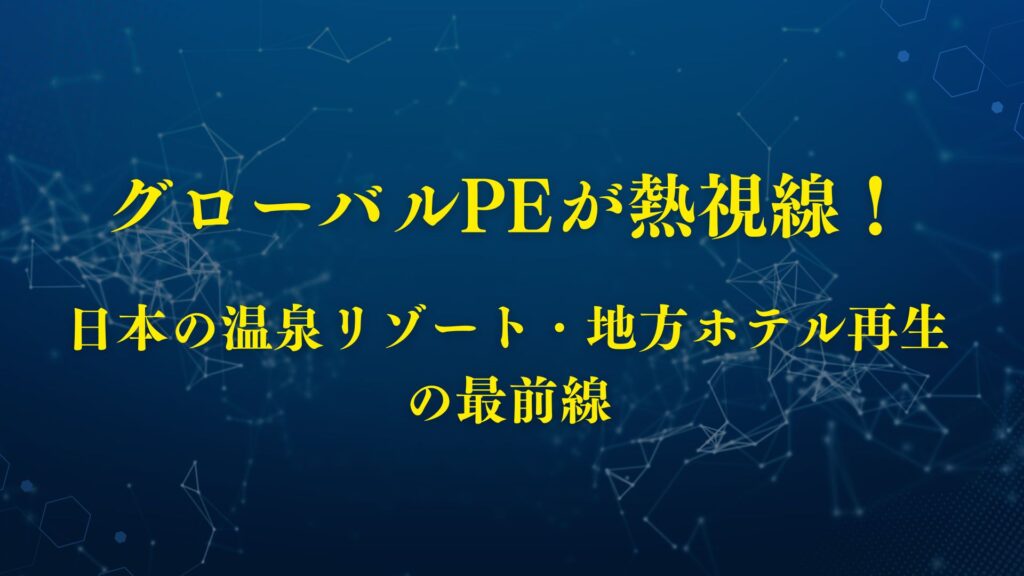
海外ファンドが日本の温泉地や地方ホテルを戦略的に買収・再生する動きが広まっています。
これは単なる投資ではなく、地域活性と投資リターンの両立を狙う取組みであり、最新動向を解説します。
1.日本のリゾート市場に吹く“海外資本”の新風
グローバルPE(プライベート・エクイティ)ファンドが日本の温泉リゾートや地方ホテルに注目し、買収・再生の動きを加速させています。
背景には円安や低金利、豊富な投資資金の存在があり、コロナ後の観光需要回復も追い風です。本記事では、海外資本がなぜ今、日本のリゾート市場に関心を寄せるのか、その魅力や投資環境の変化を事例を交えて解説します。
1-1. 海外ファンドが注目する背景にある円安、低金利、ドライパウダー(待機資金)の存在
近年、日本のリゾート市場に海外資本が流れ込む動きが目立っています。その背景のひとつが「円安」です。為替が円安で推移すると、海外投資家にとって日本の不動産やホテル資産は“割安”に映ります。
さらに、日本の低金利環境も投資を後押ししています。欧米諸国ではインフレ対策として金利が引き上げられ、不動産取得に伴う借入コストが増加しています。
一方、日本では依然として低金利が続いており、融資を活用した不動産投資が有利な環境にあります。この差は、海外ファンドにとって日本市場を選好する理由の一つとされています。
加えて、グローバルPE(プライベート・エクイティ)ファンドが抱える「ドライパウダー(待機資金)」の存在も大きい要因です。その資金を効率よく運用するには、安定収益が期待できる市場を開拓する必要があります。人口減少が進む日本においても、観光分野はまだ伸びしろがあると見られ、こうした待機資金がリゾート市場に向かう流れが加速しています。
1-2. 投資対象としての温泉地・地方ホテルの魅力(スノーリゾート・温泉地など)
海外ファンドが注目するのは、都市部のホテルだけではありません。特に人気が高いのは、伝統的な温泉地や自然豊かなスノーリゾートです。
日本各地には草津、箱根、別府、由布院といった国際的にも知名度のある温泉地が存在します。これらは長い歴史と文化的価値を有し、観光客にとって「唯一無二の体験」を提供できる資産です。さらに、温泉や和の旅館文化はアジアを中心としたインバウンド観光客に強く支持されており、海外の高級リゾートとの差別化要素になっています。
また、北海道や長野などのスノーリゾートも大きな投資対象となっています。良質なパウダースノーは世界的に知られ、特にオーストラリア、欧州、アジア圏からのスキー客に根強い人気があります。近年は富裕層向けの高級リゾート開発も進んでおり、長期滞在型の需要に応えられる可能性を秘めています。
地方ホテルの場合、都市部のホテルと比べて取得価格が相対的に低いため、改修やブランド再構築を通じて大きな付加価値を生みやすいという特徴もあります。海外ファンドにとっては「バリューアップ戦略(企業や不動産、事業などが持つ価値を高めるために行う取り組み)」が描きやすい投資対象であり、再生によるリターンの期待値が高いと考えられています。
1-3. コロナ後の観光需要回復と円安の追い風(インバウンド回復・為替効果)
新型コロナウイルスの影響で一時は大きく落ち込んだ観光市場ですが、ここにきてインバウンド需要が急速に回復しています。
訪日外国人数は2025年上半期で2,000万人を突破し、2025年8月は342万人と単月として過去最高を記録しました。観光庁の統計でも、宿泊客数や消費額の伸びが確認されており、再び観光が地域経済を支える柱となりつつあります。
この回復に円安が重なったことで、日本を訪れる外国人観光客にとって「日本は割安に楽しめる国」という印象が広がっています。宿泊費や飲食費、観光体験が自国に比べてリーズナブルであることが、さらなる訪日需要を喚起しています。
インバウンド消費の増加は、ホテルやリゾート施設の稼働率向上に直結します。特に温泉リゾートや地方ホテルは、都市部にはない魅力を持っており、観光産業の分散先として重要な役割を担い始めています。海外ファンドがこうした資産を買収・再生することで、サービス水準が国際基準に近づき、さらに観光需要を取り込む好循環が生まれる可能性があります。
加えて、コロナ禍を経て観光客の志向も変化しました。「密を避けた自然体験」「健康志向」「地域文化への関心」など、地方のリゾートや温泉地との親和性が高まっています。これに対応することで、地方ホテルや温泉地は再び脚光を浴び、海外資本の参入余地が一段と広がっているのです。
2.グローバルPEの戦略的アプローチ
海外ファンドは日本の温泉リゾートや地方ホテルを買収する際、単なる不動産投資ではなく、長期的な価値創造を意識しています。
立地やブランド力などの基準に基づいた精査に加え、施設改装やサービス改革を組み合わせ、地域と連携した再生モデルを構築するのが特徴です。本章では、グローバルPEの戦略的アプローチを具体的に見ていきます。
2-1. 買収対象選定の基準(立地・ブランド力・稼働率)
海外ファンドが日本のホテルやリゾートを検討する際には、厳格な基準に基づいた精査が行われます。
その中でも最重要となる要素のひとつが「立地」です。観光資源へのアクセスや空港や主要都市からの交通利便性は稼働率に直結します。例えば、北海道のニセコや長野の白馬は、スキーリゾートとして国際的に評価されており、交通インフラの改善も進んでいるため投資対象として高い評価を受けやすいエリアです。
次に重視されるのが「ブランド力」です。歴史ある温泉旅館や、世界的に知名度のある観光地に立地する施設は、再生後に集客効果を高めやすいという利点があります。既存のブランド認知度や信頼感は、再建時のマーケティングコスト削減にも繋がります。
さらに「稼働率」や「客単価」も重要な指標です。過去の稼働実績や予約率、平均客室単価(ADR)、売上総利益率などの指標を精査することで、投資後の収益性を試算します。安定した稼働を確保できる施設は、長期的にキャッシュフローを生み出しやすく、投資リスクを下げる要素となります。
2-2. 再生戦略(施設改装・サービス改革・ブランド再構築・ドライパウダー活用)
買収後の最大の課題は「いかに価値を高めるか」です。グローバルPEファンドは複数の戦略を組み合わせ、施設の再生を図ります。
まずは「施設改装」です。老朽化した客室や共用スペースを刷新し、最新のデザインや利便性を取り入れることで、国際基準に合った魅力的な空間を提供します。ラグジュアリー層向けのスイートルームの増設や、健康志向を意識したスパやフィットネス施設の導入も多く見られます。
次に「サービス改革」です。人材育成やITシステム導入による効率化が進められます。予約管理やチェックインのデジタル化を進めつつ、接客では日本ならではのおもてなしを活かすハイブリッド型の運営が重視されます。こうした取組みは、外国人観光客にとっても安心感を与える要素となります。
また、「ブランド再構築」も重要です。施設名やコンセプトを刷新し、国際的に通用するマーケティングを展開します。海外旅行代理店やOTA(オンライン旅行代理店)と連携することで、グローバルな販売チャネルを確保し、稼働率の安定化を図ります。
こうした施策には多額の資金が必要ですが、PEファンドが持つ「ドライパウダー(待機資金)」を活用することで、スピーディかつ大規模な改装・改善を実行できます。資金の厚みを背景に短期間で価値を引き上げるのは、PEの得意とするアプローチです。
2-3. 地域連携型モデル(雇用創出・地産地消・文化発信)
再生戦略の中で近年注目されているのが「地域連携型モデル」です。単にホテルを収益源とするのではなく、地域社会と一体となった取り組みを重視するケースが増えています。
例えば、ホテルの改装や運営に際して地元企業や職人を活用することで「雇用創出」につながります。さらに、食材調達を地域の農家や漁業者から行う「地産地消」を推進することで、地域経済全体への波及効果をもたらします。レストランでのメニュー開発に地元の特色を反映させると、観光客の体験価値も向上します。
また、地域文化や伝統芸能をホテルのプログラムに取り入れる「文化発信」も注目されています。地元の工芸品を内装に活かす、地域の祭りやアートイベントと連携する、など単なる宿泊施設を超えた「地域文化のショーケース」としての役割を果たす事例も増えています。こうした取り組みはインパクト投資の観点からも評価されやすく、ファンドの投資先としての魅力を高める要因となっています。
3.投資家にとっての魅力とリスク
日本のリゾート市場は、海外ファンドにとって魅力的な投資対象である一方、リスクも伴います。
観光需要の回復やホテル市場の成長は安定収益をもたらす可能性がありますが、為替の変動や地政学リスク、地域住民との合意形成など課題も多いのが現実です。本章では、投資家の視点から「魅力」と「リスク」の両面を整理して解説します。
3-1. 安定収益源としての観光資産(ホテル市場での高シェア)
観光資産、とりわけホテルやリゾート施設は、投資家にとって「安定した収益源」として位置づけられています。日本は四季折々の自然や文化資源に恵まれ、訪日外国人の需要と国内旅行需要の双方を取り込める市場です。
観光庁の最新データによれば、訪日外国人旅行者数はコロナ後に急速な回復を見せ、主要都市や観光地のホテル稼働率も改善しています。特に東京や大阪といった都市部に加え、京都、箱根、ニセコなどのリゾート地では高い稼働率が続いています。観光需要は地域ごとに異なるサイクルを持つため、ポートフォリオを分散させれば収益の安定性を高めることが可能です。
また、ホテル事業は一度安定稼働に乗れば、継続的なキャッシュフローを生み出しやすい特徴があります。客室単価(ADR)の改善や稼働率の上昇が収益に直結するため、施設改装やブランド戦略で競争力を高めれば、中長期的に安定した利回りを期待できるのです。
PEファンドにとって、こうした「観光資産のシェア拡大」は投資妙味が高く、ポートフォリオの一角を担う対象として注目されています。
3-2. 為替・観光需要依存リスク(円高反転・地政学リスク)
一方で、観光資産への投資は外部環境に左右されるリスクも抱えています。その代表例が「為替リスク」です。現在の円安基調は外国人投資家や観光客にとって有利な環境ですが、将来的に円高に転じれば状況は一変します。
投資家にとっては、円建て収益を本国通貨に換算する際、為替差損が生じる可能性があります。また、円高局面では訪日外国人にとって日本旅行のコストが割高となり、観光需要の減少につながる懸念もあります。
さらに、地政学リスクも無視できません。国際関係の緊張や自然災害、感染症の再拡大などは観光需要を一気に冷え込ませる可能性があります。特にインバウンド依存度の高い地域では、外部環境の変化が稼働率や収益に直結するため、投資家は慎重なシナリオ分析を行う必要があります。
観光需要は経済環境や為替動向に左右されやすい「循環性の強い資産」であることを踏まえ、複数地域への分散投資などリスク管理を講じることが求められます。
3-3. 規制・地域合意形成の課題(地域住民との意識ギャップ)
観光資産への投資で見落とされがちなリスクが「規制」と「地域住民との合意形成」です。
リゾートやホテルの開発・再生には、建築基準法や景観条例、環境保護に関する規制が多く存在します。特に温泉地や自然環境が豊かな地域では、開発行為に対する制約が厳しく、計画通りに事業を進められないケースもあります。
また、地域住民との「考えの違い」も大きな課題です。観光開発が進むことで、雇用創出や経済効果を歓迎する声がある一方、生活環境の変化や過度な観光客流入による負担を懸念する声も少なくありません。地域社会との合意形成が不十分なまま事業を進めれば、反発や抗議活動を招くリスクもあります。
このため、海外ファンドにとっては、地域社会との信頼関係を築くことが不可欠です。地元企業との協業や地産地消の推進、文化発信イベントの共催など、地域との接点を意識的に設けることで、住民の理解と支持を得やすくなります。こうした「ソーシャルライセンス(社会的許可)」の獲得が、長期的に持続可能な投資成果につながると考えられます。
4.地方創生×資産運用の未来
海外ファンドによる地方リゾートや温泉ホテルへの投資は、単なる収益追求にとどまらず、地域社会への波及効果を伴う「地方創生」の一環としても注目されています。
インパクト投資の潮流や自治体・地元企業との協業を通じて、持続可能な観光モデルを築く取り組みが進みつつあります。本章では、資産運用と地方創生が交差する未来像を探ります。
4-1. インパクト投資としての位置づけ
観光リゾートへの投資は、従来の不動産投資の延長線上にとどまらず、社会的リターンと経済的リターンを同時に目指す「インパクト投資」としての側面が強まっています。
インパクト投資とは、単に財務的な収益の獲得を目指すだけでなく、地域社会や環境に対して測定可能なポジティブな影響をもたらすことを目的とする投資手法です。温泉リゾートや地方ホテルの再生は、地域雇用の創出、観光客誘致による経済活性化、地元文化や伝統の継承など、多面的な社会的効果を伴います。
特に日本の場合、人口減少や高齢化が進む地方では、外部資本の導入が地域経済を支える重要な役割を果たす可能性があります。海外ファンドによる再生戦略が地域住民の暮らしを豊かにしつつ、投資家にとっても安定的なキャッシュフローを生むことができれば、まさにインパクト投資の典型例と言えるでしょう。
4-2. 海外ファンドと自治体・地元企業の協業モデル
成功する再生プロジェクトの多くは、ファンド単独ではなく「協業モデル」によって支えられています。特に重要なのが、自治体や地元企業との連携です。
自治体は観光政策やインフラ整備の担い手であり、地域全体のブランド構築にも大きな影響を与えます。例えば、温泉地の景観規制や環境保全施策を踏まえた施設改装は、自治体との協議を通じて実現されるケースが一般的です。ファンドにとって自治体は「規制の壁」であると同時に、信頼関係を築ければ強力なパートナーになり得ます。
一方、地元企業は日常のオペレーションや地域資源との接点を持っています。食材供給や観光プログラムの提供、伝統工芸の導入など、地元企業の参画は施設の差別化につながります。また、地元金融機関や観光協会との連携によって資金調達や販路拡大を支援できる点も見逃せません。
こうした協業モデルは、地域住民の理解を得やすくする効果もあります。外資による「買収」という印象を和らげ、「地域と共に歩む投資」へと転換することで、持続可能な事業基盤を築くことが可能になるのです。
4-3. 今後注目すべき地域と物件タイプ(スノーリゾート・温泉リゾートなど)
将来の投資対象として注目される地域や物件タイプにはいくつかの傾向があります。
まず「スノーリゾート」です。北海道ニセコ、長野白馬などは、既に国際的な知名度を獲得しており、豪州・欧州・アジアからのリピーターが多い地域です。今後もインフラ整備や高級宿泊施設の開発余地があることから、引き続き投資妙味があると見られます。
次に「温泉リゾート」です。草津、箱根、別府、由布院といった国内有数の温泉地は、長期的に安定した集客力を持っています。特に富裕層向けにラグジュアリー体験を提供する施設や、ウェルネス志向を取り入れたスパ併設型リゾートは、国際市場でも競争力を持つ可能性があります。
さらに「新しい需要を取り込む地域」も注目です。例えば、東北の自然リゾートや四国・九州の文化体験型観光地は、まだ海外観光客の知名度が低い分、成長余地が大きいと考えられます。これらの地域は投資コストが比較的低いため、再生によるバリューアップの余地が広い点が魅力です。
物件タイプでは、従来の大型ホテルだけでなく、分散型宿泊施設やサステナブル建築を活用したエコリゾートも増えています。持続可能性を重視する観点から、こうした施設への関心は今後さらに高まると予想されます。
5. まとめ
日本の温泉リゾート・地方ホテルは、円安・低金利・豊富なドライパウダーを追い風に、海外ファンドの再生投資が進みやすい環境にあります。魅力は、唯一無二の観光資産を活かしたバリューアップの余地と、改装・サービス改革・ブランド再構築による収益性の改善可能性です。
一方で、為替や地政学、需要変動、規制・地域合意といった不確実性は小さくありません。成功の鍵は、立地・ブランド・稼働の精査、分散と為替ヘッジ、段階的投資とKPI管理(ADR、RevPAR、回収期間など)、そして自治体・地元企業との協働です。インパクト投資の観点を取り入れ、地域の雇用や文化発信と両立させながら、持続可能な収益モデルを丁寧に設計していく姿勢が重要と考えられます。
ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。富裕層の方に対して、状況に応じた最適なアドバイスをいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
