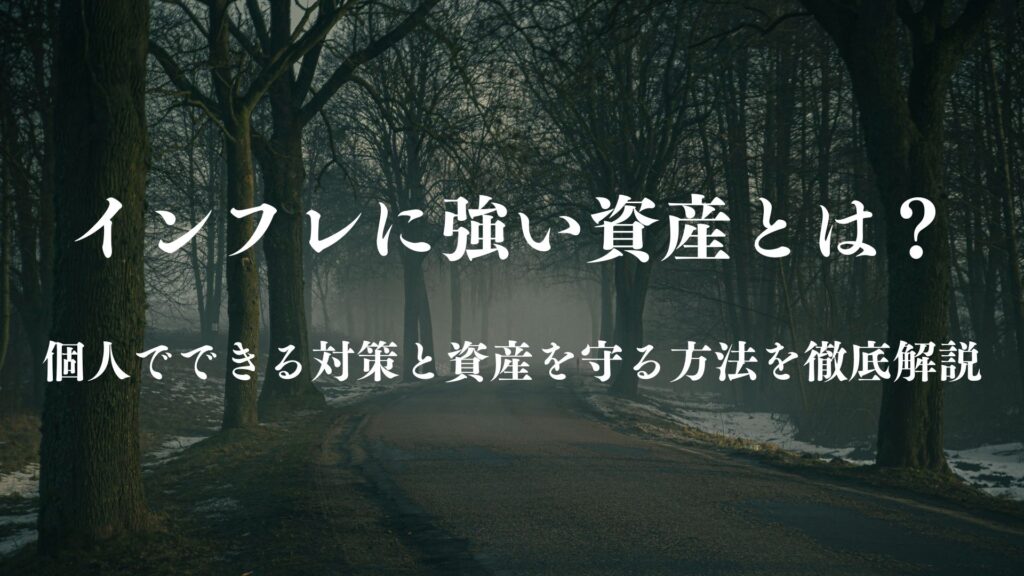
- 個人でできるインフレ対策が分からない
- インフレの定義や生活への影響を知りたい
- インフレに強い資産は何かが気になる
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では資産運用の視点から、個人が取り組めるインフレ対策について解説します。
この記事を読むと、インフレに対する基本的な理解が深まり、将来へ向けた資産防衛のヒントを得られることでしょう。
1. 改めてインフレとは何か?
インフレ(インフレーション)とは、モノやサービスの価格が全体的に上昇し、相対的にお金の価値が下がる現象を指します。
一般的に好況期の需要増加(ディマンド・プル・インフレ)や原材料や人件費の高騰などによる供給コストの増加(コスト・プッシュ・インフレ)が主な原因とされています。
例えば、原油価格の高騰によりガソリン代が上がると、輸送コストの増加に伴い物価も値上がりします。また、石油を原材料とする多くの製品価格も連鎖的に上昇します。その結果、同じ金額で購入できるものの量が減るため、実質的なお金の価値が目減りしてしまうのです。
インフレは一定の範囲であれば経済成長の一環ともいえますが、急激に進行すると家計や企業経営に深刻な影響を及ぼします。
2. インフレが個人に与える影響
それでは、具体的にインフレが個人に与える影響を見ていきましょう。
インフレは家計に幅広い負担を与える可能性があるため、早めの対策が求められます。
- 生活必需品や光熱費の上昇
- 現預金の実質的な価値の目減り
- 賃上げが物価上昇に追いつかないケース
それぞれについて解説します。
2-1. 生活必需品や光熱費の上昇
物価上昇はまず生活必需品や光熱費に反映されやすく、家計への負担が大きくなります。
特に食料品や電気・ガス料金などは毎月の支出に直結するため、わずかな値上げでも家計に影響が出やすくなります。
こうした負担を放置することで貯蓄を取り崩す必要が生じ、長期的な資産形成に支障をきたすおそれがあります。
家計でできる対応策として、支出内容を把握し、固定費の見直しを検討することが大切です。
2-2. 現預金の実質的な価値の目減り
現預金はインフレに対して弱い資産であり、預金金利よりも物価上昇率のほうが高いと実質的な価値が目減りします。
例えば、年利0.1%の普通預金に100万円を預けても、1年間で得られる利息は約1000円にとどまり、そこから税金も差し引かれます。これに対し、物価上昇率が2%の場合、同じ100万円で購入できるものやサービスの量は1年後に実質2万円分減ることになります。
現預金だけで資産を保有すると、知らず知らずのうちに資産価値が減少してしまうリスクを抱えてしまうのです。
2-3. 賃上げが物価上昇に追いつかないケース
たとえ名目賃金が上昇しても、物価上昇率のほうが高ければ実質賃金は低下します。
実際、日本では2025年4月時点で実質賃金が4カ月連続で減少し、前年比1.8%の下落を記録しました。物価が4.1%上がる中で名目賃金は2.3%しか伸びておらず、購買力は依然として押し下げられています。
こうした背景から、生活水準を維持するためには副業収入の確保、資産運用などといった対策を組み合わせることが重要といえます。
※参考「厚生労働省発表の「毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果確報」
3. 個人で考えられるインフレ対策① 投資を行う
投資はインフレ対策として多くの人が取り入れている方法の一つです。
インフレに比較的強いとされる資産に資金を移すことで、資産価値が目減りするリスクを一定程度抑えつつ、将来的なリターンも期待できます。
例えば、株式や投資信託は、企業が製品・サービスの価格を上げて収益を伸ばすことで、株価や分配金にも好影響を及ぼします。それでは、以下で具体的に投資の方法を見ていきましょう。
- インフレに強いとされるセクターや銘柄の株式や投資信託へ投資する
- 少額から始める積立投資のメリット
- インフレに弱い資産(例:現預金)との違い
3-1. インフレに強いとされるセクターや銘柄の株式や投資信託へ投資する
株式は、インフレに対して一定の耐性を持つと考えられる資産です。
インフレ下でも価格転嫁することにより収益を維持・拡大できる場合、株価の上昇要因となるためです。例えば、食品メーカーでは原材料費が上昇しても販売価格に転嫁できるため、インフレ局面でも株価が堅調に推移する事例が見られます。
投資信託なら複数の企業や資産クラスに分散投資でき、インフレに耐性のある資産へまとめて投資できる点がメリットです。ポートフォリオ全体の価格変動リスクを抑え、リターンの安定化にも寄与します。
3-2. 少額から始める積立投資のメリット
積立投資は毎月一定額を自動的に投資に回す方法で、ドル・コスト平均法を活用することにより購入価格を平準化する効果を得ることができます。
例えば毎月1万円ずつ投資信託を購入すると、市場が下落したタイミングでも多くの口数を買付けすることができ、上昇局面での利益を享受しやすくなります。
少額から始められるため、投資初心者が無理なく継続しやすい点も魅力です。
3-3. インフレに弱い資産(例:現預金)との違い
現預金は「安全資産」と呼ばれるものの、インフレ下では実質的な購買力が低下しやすい点が大きなデメリットです。
日本は低金利の状況が続いており、物価の上昇に追いつかず、実質的に価値が目減りすることがあります。
一方で、投資には価格変動等のリスクは伴いますが、長期的な視点ではインフレ率を上回るリターンが得られる可能性もあります。安全性と収益性のバランスを考慮しながら、資産配分の見直しを検討することも一つの方法です。
4. 個人で考えられるインフレ対策② 海外資産を保有する
通貨を分散することはインフレや円安の影響を軽減する手段の一つとされています。
全ての資産を円建てだけで保有すると、円安が進行した際に資産価値が目減りする可能性がありますが、一部を米ドルやユーロなど他通貨建て資産に分散することでその影響を緩和できます。
海外資産の具体的な方法を見ていきましょう。
- 通貨分散によるリスクヘッジ
- 外貨預金・外国株式・海外ETFなどの選択肢
- 為替変動リスクとその管理方法
4-1. 通貨分散によるリスクヘッジ
異なる通貨で資産を分散保有すると、ある通貨が急落した場合でも、他の通貨建て資産でその影響を一部緩和できる可能性があります。
例えば、資産の一部を米ドルやユーロに分けることで、円建てのみの場合に比べて為替による資産価値の変動が抑えられます。通貨分散はポートフォリオの安定性を高めるための一つの選択肢といえるでしょう。
4-2. 外貨預金・外国株式・海外ETFなどの選択肢
外貨預金は円建て定期預金と比べて金利が高い傾向があり、さらに円安局面では為替差益が発生する場合もあります。
外国株式や海外ETFは、米国株をはじめとする多彩な銘柄やインデックスに直接投資することができ、地域分散効果と成長性の両方が期待できます。ただし、手数料や為替スプレッドが発生するため、コスト比較を忘れずに行いましょう。
4-3. 為替変動リスクについて
海外資産には為替変動リスクが伴います。
為替相場の変動は、資産の円換算額に直接影響するので注意が必要です。
例えば、1ドル=130円から120円に円高が進むと、1,000ドルの資産は円換算で13万円から12万円に減少し、1万円のマイナスになります。
投資信託やETFなどの中には、為替ヘッジ付きの商品もありますが、ヘッジコストがかかる分、運用成績が低くなったり、円安局面では為替差益を得られないなどのデメリットがあります。自分の投資目的や、許容リスクに合わせてヘッジ有無を選択してください。
5. 個人で考えられるインフレ対策③ 実物資産を保有する
金や不動産などの実物資産は、通貨の価値変動に影響されにくい特性があります。
インフレ局面では金価格や不動産価格が上昇する傾向があり、特に不動産投資では賃料収入(インカムゲイン)だけでなく価格上昇益(キャピタルゲイン)を通じたリターンも期待できます。
こうした資産をポートフォリオに組み込むことで、インフレ耐性が高まります。
次に、実物資産の具体的なポイントを確認します。
5-1. 分散保有と流動性のバランス
実物資産、特に先に挙げた不動産は一般的に売却までに時間を要することが多く、流動性が低い点は注意が必要ですが、一方で資産価値の安定性は高い傾向にあります。
すべての資産を現物資産に集中させると、急な資金ニーズに対応できないことがあるため注意してください。
そこで、流動性の高い金融資産と組み合わせて保有し、バランスを取ることが重要です。この組み合わせにより、インフレリスクを意識しつつも、日常的な資金需要への対応力を保つことができるでしょう。
5-2. 初心者が実物資産に投資する際の注意点
実物資産を保有する場合、購入価格に加えて、保管や維持に必要なコスト、税金等が発生します。
例えば、金を現物で保有する場合、売買手数料のほか保管料や保険料がかかるケースもあり、不動産では固定資産税や管理会社への手数料のほか、修繕費用なども必要です。また、賃料下落や空室による収入減少リスクを伴います。投資前にトータルコストをシミュレーションし、余裕資金での運用を心がけるとよいでしょう。
6. 投資が不安な人はどうすればいい?
投資に対して不安がある場合は、いきなり大きな資金を動かすのではなく、段階的な取り組みを心がけることが大切です。具体的なステップを紹介します。
6-1. 証券会社やIFAなど専門家に相談する
投資の無料相談窓口は銀行・証券会社・IFAが代表的で、いずれも専門知識を持ったスタッフからアドバイスが受けられます。
特にIFAは中立的な立場で商品提案を行うため、自社商品の偏りが少なく長期的なサポートを期待できます。無料相談を利用して、自分に合った商品選びやポートフォリオ構築の第一歩としましょう。
6-2. 自分の目的とリスク許容度を明確にする
投資を始める前に、何のためにいくら必要か、そしてどれだけの損失を許容できるかを整理します。
老後資金、教育資金、住宅購入資金など資金の目的は異なるため、投資目的を明確化することで投資戦略が立てやすくなります。オンラインのリスクプロファイリングツールを活用して、数値的に可視化する方法もあります。
把握したうえで相談すると、より的確なアドバイスが得られます。
6-3. まずは少額から投資をスタートする
最初は積立投資や少額の買付サービスを利用し、数千円から1万円で始めるとリスクを抑えられます。
損失が出ても精神的ダメージが小さく、経験を積みながら投資感覚を養えます。ネット証券各社では1円単位で積立できる商品もあり、生活費口座とは別に「投資用口座」を設定しておくと管理が楽になるでしょう。小さな一歩が、将来の大きな安心につながることでしょう。
7. まとめ
インフレが長期化する局面では、ひとつの手段だけで資産を守るのは難しい場合があります。
株式・投資信託への投資、外貨建資産の保有、実物資産の組み入れといった多角的なアプローチを組み合わせることで、リスクを分散しやすくなります。
また、専門家への相談や自己分析、少額スタートといったステップを踏むことで、不安を軽減しながら資産形成に取り組むことも可能です。
ぜひ今から自分なりのポートフォリオを見直し、インフレ時代に負けない資産づくりを始めていきましょう。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案をしております。インフレ対策の資産運用について、お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機に一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
