- M&Aで会社がなかなか売れない
- 会社が売れない理由が分からない
- 会社が売れるようになる方法を知りたい
上記のようなお悩みを解決する記事を執筆しました。
多数のM&A実績があるプロが、「なぜ会社が売れないのか」について解説します。
この記事を読むと、M&Aでなかなか買い手がつかなかった会社が売れるようになります。
1. M&Aで会社が売れない理由
売り手としてM&Aで会社が売れない理由は以下のようなものが挙げられます。
| No. | 理由 |
| 1 | 利益をあげられていない |
| 2 | 売り手の会社構造に問題がある。 |
| 3 | 買収した際のシナジー(相乗効果)がない |
| 4 | 事業規模が小さい |
| 5 | 財務管理が不透明 |
| 6 | 法律上の問題がある |
以下でそれぞれ解説していきます。
1-1. 利益をあげられていない

利益を出せてなく成長が期待できない企業は、買い手側から魅力を感じにくいです。
過去数年にわたって安定的に利益を出せていないと、将来の収益面でも不安が残り譲渡が難しくなります。たとえば売上自体はある程度確保できていても、経費が膨らみすぎて赤字が続いている場合などは、買収後に立て直すためのコストが大きくなる可能性が高いです。このような状況を放置すると、M&Aの場で十分な評価を得ることが難しくなります。
また、業界自体が縮小傾向にある場合も買い手は魅力を感じにくくなります。
業界縮小は、将来性がないと判断されてしまうためです。
ただ一方で、利益があげられておらず赤字が続いている会社であっても、M&Aが必ず成功しないわけではありません。例えば、業界として拡大傾向であったり、その会社独自の製品を持っているなど、成長性(伸びしろ)がある場合は、そこを魅力的に感じた会社とM&Aが成立する可能性があります。。
1-2. 売り手の組織構造に問題がある
組織構造に問題があると、売れない原因になります。
組織体制が不透明だと、買い手側はスムーズな経営引き継ぎを想像しにくくなるからです。
社内のコミュニケーションが滞っていたり、経営者だけが情報を握っている場合は特に注意が必要です。
たとえば小規模事業者で役職や権限が曖昧なままだと、買収後の管理体制を再編する手間が増えるでしょう。また、ワンマン経営で経営者だけが情報を握っている場合も、組織体制が不透明でリスクが大きいと買い手に思われてしまいます。
引き継ぎに伴うリスクが想定されるため、買収価格にネガティブな影響を及ぼしかねません。
1-3. 買収した際のシナジー(相乗効果)がない
買い手は、買収後に事業を拡大できるかどうかを見極めています。
本業との関連が薄い企業を買収しても、追加の売上やコスト削減などが見込めない場合、M&Aを行うメリットがないからです。
たとえば、まったく異なる業界で経験や技術面に関連がなく、顧客の共有も難しい場合はシナジー(相乗)効果が生まれづらいです。
M&Aにおいて求められているシナジー効果とは、単に2つ以上の事業を組み合わせることで生まれる足し算の結果ではなく、想定よりも大きくなることを指します。そのため、買収することによって、売り手の顧客基盤や技術等を、買い手の事業に活用できるなどのメリットを提示する必要があります。
買い手が期待するメリットを提示できないと、結果として「買おう」という意思を持つ企業が見つからず、売れ残ってしまいます。
1-4. 事業規模が小さい
ビジネスとして成り立っていても、あまりにも規模が小さいとM&Aのターゲットから外されがちです。
買収後に拡大を見込む投資家や企業にとっては、それに見合うリターンを得るのが難しいと映るからです。
たとえば従業員がごく少数で、設備や顧客リストも小規模にとどまっている場合、買い手にとって新たに参入するコストがメリットを上回るかどうかが厳しく見極められます。また、経営者が抜けるとすぐに事業が回らなくなるリスクも発生します。
その結果、ほかに有望な買収先がある場合は、そちらに目が向いてしまいます。
1-5. 財務管理が不透明

会計処理や帳簿の管理がきちんと行われているかは、買い手にとって大きな不安要素となります。
黒字決算と聞いていても、中身を精査すると経費処理の基準が曖昧だったり、税務リスクが潜んでいるケースもあるでしょう。
たとえば領収書や請求書が未整理のまま長期間放置されていると、売上や利益が正確に把握できない状態に陥りかねません。
財務面の信頼性が損なわれれば、買い手が手を引く可能性が高まってしまいます。
1-6. 法律上の問題がある

労働法や業種特有の規制など法律を守れていない会社は、買収後に法的リスクを抱えこむ危険性があります。
許認可の不備やコンプライアンス違反が判明すれば、買い手にとっては余計なコストや信用失墜につながりやすいでしょう。
たとえば、「株式の所在が分からない」、「過去に不正行為・違法行為が行われたことがある」、「株主総会・取締役会の内容がない」などは、会社法に抵触する可能性があります。
そうしたリスクを払拭できないと、どんなに事業が魅力的でも売却が成立しにくくなります。
2. M&Aで会社が売れるようになる方法
| No. | 方法 |
| 1 | 会社の財務状況を改善する |
| 2 | 買い手の候補を多く募る |
| 3 | 事業の将来性を考える |
| 4 | シナジー効果を得られる買い手企業を選ぶ |
| 5 | 他社にない強みを把握する |
| 6 | 優先順位をつける |
| 7 | 売却の時期を逃さない |
| 8 | 実績があるM&Aのプロに相談する |
2-1. 会社の財務状況を改善する
M&Aでは売上や利益、キャッシュフローなどの財務状況を測る指標が安定していると、会社が売れやすくなります。また、金融機関などからの借入が少なく、高収益であることも評価される点となります。
そのため、交渉のスタート地点である財務状況が整備されていると、買い手は安心して検討を進められます。
採算が悪い事業の利益率の改善や固定費の見直しなどに着手しておけば、将来の見通しがポジティブになるでしょう。
たとえば固定費削減として、無駄な在庫管理コストやオフィスの家賃を削減し、余った資金を成長投資に振り向けると、さらに好印象を与えられます。
健全な財務が示されると、企業価値を高められ、売却の成功率も上がります。
2-2. 買い手の候補を多く募る
一社だけに売却交渉を絞り込むと、交渉力が弱くなりがちです。
なぜなら、相手が提示する条件を飲まざるを得なくなる可能性が高まるからです。
たとえば複数の買い手候補に同時に検討してもらえば、提示される金額や条件を比較しながら交渉を進められるメリットがあります。買い手の提示条件を比較することで、買い手同士の競争で価格が上昇することもあるでしょう。
より多くの買い手とやり取りすることは負担も増えますが、満足いくM&A取引につながりやすくなります。
2-3. 事業の将来性を考える

売却時点だけでなく、その先の事業の成長性(伸びしろ)が大きいかどうかが重要になります。
成長市場をターゲットにしている事業や、高い技術力で市場をリードできる領域を持っていれば、買い手が長期的な投資価値を期待できるからです。
たとえば、最近流行りのデジタルトランスフォーメーション(DX)関連のサービスや、AIなど新規技術との親和性が高い場合は、将来的に大きく成長する可能性をアピールできます。
また、その他に安定した利益を出していることも、事業の成長性を買い手に与えることができます。事業で安定した利益がでているということは、安定した顧客基盤があり、実績を十分に備えていることとなるため、売り手にとって大きな強みです。
将来像が明確だと、買い手にとっても安心かつ魅力的な投資先になります。
2-4. シナジー効果を得られる買い手企業を選ぶ
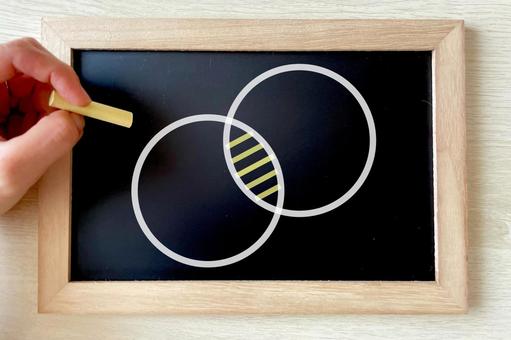
買い手の事業と組み合わせることで得られるシナジー効果(相乗効果)を具体的に示すことが大切です。
互いの強みを組み合わせれば、単独では実現できない売上やコスト削減の可能性が高まり、買い手にとってM&Aが魅力的となるからです。
たとえばソフトウェアを自社で開発し、それを買い手企業の販売チャネルに載せることで新規顧客を獲得できるなどが典型的な例といえます。
こうした根拠を買い手に分かりやすく示せると、相手も買収後のメリットを鮮明にイメージできます。
2-5. 他社にない強みを把握する
他社にない強みを把握することで、買い手へのアピール材料となります。
差別化要因が明確であればあるほど、買い手企業は自社にない強みを手に入れられるメリットを感じます。
一般的には専門知識や独自技術、優良顧客層の存在などが大きな強みとして挙げられます。
たとえば同業他社が真似しにくい製造技術や、高く評価される特許を保有している場合などは、大きなアピール材料になります。
こうした競合優位性を数値や事例で示すと、買い手側の興味をグッと引き寄せられます。
2-6. 優先順位をつける
売り手がすべての条件にこだわりすぎると、交渉がまとまらなくなります。
大事なポイントと、譲ってもよい部分を事前に仕分けておけば、条件調整がスムーズに進みやすくなります。たとえば価格面はある程度譲れるが、従業員の雇用維持だけは絶対に譲れないなど、優先順位を事前に決めておくことがポイントです。メリハリをつけた交渉は、買い手にも安心感を与え、より良い結果に繋がりやすいです。
2-7. 売却の時期を逃さない
売り手側の事業のピーク時や業績が上向きのタイミングで売却に踏み切ると、評価を高く得られます。逆に言えば、下降局面に入ってから売ろうとすると買い手は慎重になり、条件が下がりやすくなります。。
たとえば、新商品が好調で注目を集めている時期や、経済全体が活発で投資意欲が高いときに売りに出すと、より有利な交渉が期待できます。また、売り手の経営者に意欲がある時に行うべきです。経営者が高齢になり、体力や意欲、健康面が悪くなった際に、M&Aを進めるのは体力的にも精神的にも大きな負担になります。
そのため、タイミングを逃さず行動すると、高値での売却も狙いやすくなるでしょう。
2-8. 実績があるM&Aのプロに相談する
M&Aのプロに相談することで、売却のためのアドバイスを受けることができます。
豊富な経験を持つ専門家は、業界の相場や買い手との交渉ノウハウを熟知しています。
複雑な手続きや法務問題などをスムーズに進めてくれるため、M&Aの失敗リスクを下げられます。
たとえば、過去の同業界M&Aに詳しいコンサルタント、仲介会社、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に依頼することで、理想的な買い手を素早く見つけられる場合も多いです。
頼れるプロの力を借りると、交渉から契約締結までの道のりもスピーディーになります。
ファーストパートナーズでは、数多くのM&A実績を元に、M&Aの初期検討から成約までワントップのサポートを行っております。
これを機に、M&Aの相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
3. 会社がM&Aで売れない時の相談先

| No. | 相談先 | 特徴 |
| 1 | 事業承継・引き継ぎ支援センター | ローカルなネットワークに強みをもつ |
| 2 | 金融機関 | 取引のある金融機関の場合、財務内容を把握しており、相談しやすい |
| 3 | M&A仲介会社 | 買い手と売り手の間に入り、M&Aの成立に注力してくれる。中立的な立場の意見がほしい方におすすめ |
| 4 | M&Aアドバイザリー会社 | 契約した側の利益を最大化するよう尽力してくれる。第3者の視点から意見を欲しい方におすすめ |
3-1. 事業承継・引き継ぎ支援センター
中小企業庁に設置された公的機関として中小企業の引き継ぎをサポートしており、手厚い相談対応をしてくれます。料金面も抑えられ、初期的な相談窓口としても頼りになります。
たとえば事業規模が小さくて民間の仲介会社に相手にされなかった場合でも、幅広い地域ネットワークを活用して相談に乗ってくれます。国や自治体の支援もあるため、初めてのM&Aで戸惑っている企業にはハードルが低い選択肢です。
3-2. 金融機関
銀行や信用金庫などの金融機関は、企業の財務状況をよく把握しているので話が通じやすいです。
銀行の場合、融資のほかにも事業承継やM&Aの情報提供に力を入れているところが多く見受けられるようになってきています。普段から金融機関と取引している場合には、まず相談してみることをおすすめします。
既存の顧客とのネットワークを活用して、買い手を紹介してくれるケースもあるため、相談してみる価値は十分にあるからです。資金繰りに関するアドバイスも得られるので、経営状態を改善しながら売却に備えることも可能です。
3-3. M&A仲介会社
専門の仲介会社は、売り手と買い手をつなぐ事に長けており、幅広い業界の案件を扱っている会社が多くあります。
中小企業向けのマッチング実績が豊富な仲介会社なら、希望条件に合う買い手を効率よく見つけてくれるでしょう。
たとえば複数の候補からベストな企業を選べるように比較検討資料を作成してくれるなど、総合的なサポートを受けられます。ただし手数料や成功報酬などが発生するため、契約前にしっかり条件を確認することが大切です。
3-4. M&Aアドバイザリー会社
仲介会社とよく比較される存在ですが仲介とは異なり、売り手側・買い手側のどちらか一方に付き、担当した側利益の最大化を目的に交渉を進めます。
交渉戦略やM&A後のリスク管理など、クライアントの立場に合わせたコンサルティングを提供します。IFAなどのM&Aアドバイザリー会社は、第三者的な立場からM&Aに関するアドバイスをしてくれます。
たとえば買い手との条件交渉で、どこを譲り、どこを守るべきかを詳細にアドバイスしてくれるので、安心して進められます。
自社の代わりに交渉の最前線に立ってくれるので、本業に集中しながら売却手続きを進められます。
4. まとめ
M&Aで会社が売れ残ってしまう原因は、利益体質の弱さや買収後のシナジーが薄いと判断されることなど、さまざまです。
しかし、タイミングの見極めや妥協点の設定、将来性のアピールなどを戦略的に行えば、売却の成功率は大きく向上します。
もし思うように話が進まない場合は、事業承継・引き継ぎ支援センター、金融機関、IFAなどのM&Aの仲介を行っている会社への相談から始めるのも良いでしょう。
適切なサポートを得ながら進めることで、自社の魅力をよりよく伝え、希望に近い形でのM&Aを実現しやすくなります。
Iファーストパートナーズでは、数多くのM&A実績を元に、M&Aの初期検討から成約までワントップのサポートを行っております。
これを機に、M&Aの相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
