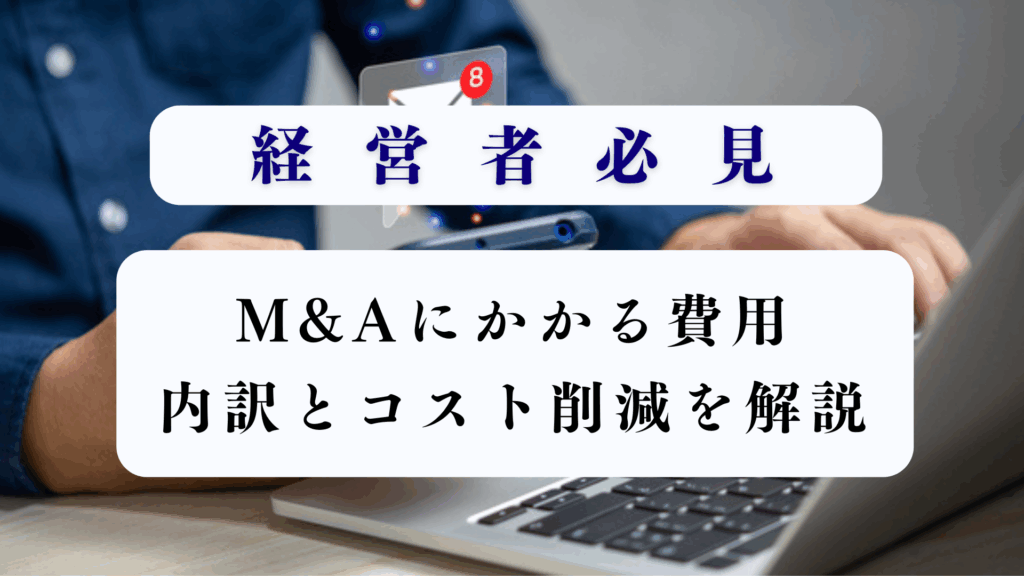
M&Aでは、売り手・買い手それぞれに費用が発生します。
M&Aにかかる費用は、取引の規模や複雑さによって大きく変動し、企業の財務に大きな影響を与えます。
本記事では、M&Aに関する費用の基本概念から種類、相場、コスト削減方法まで、包括的に解説します。
1.M&Aにかかる費用の種類

M&Aではさまざまな費用が発生します。
ここでは、売り手と買い手それぞれの費用の内訳をみていきましょう。
1-1.売り手(売却側)の主な費用
a. アドバイザー報酬
M&Aのアドバイザー(仲介業者やフィナンシャル・アドバイザーなど)に支払う費用です。
一般的には、譲渡が成立したタイミングで報酬を支払う「成功報酬型」が多く採用されていますが、場合によっては契約締結時の着手金や、取引の進捗に合わせた中間金が設定されることもあります。
b. 弁護士・税理士など専門家への報酬
M&Aにおける契約書や譲渡スキームの検討、税務アドバイス、譲渡対価の最適化などで、弁護士や税理士など専門家のサポートを受ける場合に発生する費用です。
M&Aのアドバイザー会社を通じて一括で依頼できるケースもあります。
c. デューデリジェンス関連費用
M&Aにおいてデューデリジェンスとは、買収前に対象企業の事業などの実態を調査し、価格や取引について適切に判断するための調査の事をいいます。一般的に買い手が主導してデューデリジェンスを行いますが、売り手側も資料整備や専門家対応などに費用を要する場合があります。
企業内のデータや資料の準備、内見・説明会の開催なども含め、売り手が負担すべきコストが追加で発生する可能性がある点に留意が必要です。
d. 税金関連の費用
株式譲渡によって得られた売却益には、譲渡所得税が課されます。
個人が大株主の場合、 売却益は所得税・住民税の対象です。法人が保有する株式であれば、 売却益が法人税の課税対象となります。
1-2.買い手(譲受側)の主な費用
a.アドバイザー報酬
買い手側もM&Aのアドバイザー、投資銀行などに対して報酬を支払う場合があります。
b.DD(デューデリジェンス)費用
買い手はM&Aの意思決定にあたり、対象会社の財務・税務・法務・ビジネスなどを多角的に調査します。
そのため、公認会計士・税理士・弁護士・コンサルタントなど複数の専門家を起用する場合が多くあります。こうした調査は比較的大きなコストを伴うため、予め費用を見込んでおく必要があります。
c.弁護士・税理士など専門家への報酬
買い手は、投資契約書や株式譲渡契約書の作成・レビューなどを主導するため、弁護士費用が発生するケースが一般的です。
これは法的リスクのヘッジや契約条件の適正化を図るうえで欠かせない作業となります。
また、DD(デューデリジェンス)の延長として、税理士や会計士との顧問契約やスキーム検討にかかる報酬が生じることも多いです。
買収後の税務・会計処理を含め、全体最適を図るためのアドバイスやシミュレーションが必要になるため、専門家費用はあらかじめ見込んでおきましょう。
d.買収資金の調達関連費用(ファイナンスコスト)
M&Aの際に必要な買収資金を、銀行融資やVC投資、社債発行などで調達する場合、
それらに伴う利息や発行費用といった費用が発生します。
特に、LBO(レバレッジド・バイアウト)のような高レバレッジ手法を採用する場合、アレンジメントフィーやデットファイナンスに関する諸経費が追加コストとしてかかるケースもあります。
e.PMI(Post Merger Integration)関連費用
M&Aが成立した後、買収先企業とのシステム統合や人事制度調整、ブランド戦略の再構築などを行う際に発生する費用です。
これらの統合作業をスムーズに進めるため、コンサルタントや専門家の継続的なサポートを受ける場合があり、その分の追加コストを見込む必要があります。
スポーツメルマガ用2.M&Aにかかる費用の相場

一般的に、中小企業のM&Aでは数百万円から数千万円程度、大企業の案件では数億円以上かかることがあります。
費用の主な内訳は、仲介手数料、アドバイザリー費用、デューデリジェンス費用、法務・税務関連費用などです。相場を把握することで、適切な予算設定と費用対効果の検討が可能になります。
2-1.業種別の費用の違い
M&A費用は業種によっても大きく異なります。製造業では工場や設備の評価に専門知識が必要なため、デューデリジェンス費用が高くなる傾向があります。
一方、IT業界では知的財産権の評価がポイントとなり、特許や技術の価値算定に費用がかかります。
小売業では店舗網の評価や在庫の精査が必要で、それに伴う費用が発生します。金融業では規制対応や顧客資産の評価に多くの時間と費用がかかる傾向があります。
医療・介護業界では、許認可や人材の評価がM&Aにかかわるため、特殊な専門知識を持つアドバイザーが必要となるため、費用が高くなることもあります。
このように、業種特有の要因が費用に大きく影響するため、事前に業界に精通した専門家に相談すると良いでしょう。。
2-2.規模別の費用の相場
小規模なM&A(売上高1億円未満の企業)では、総費用が1,000万円程度から始まることが多く、主に仲介手数料とデューデリジェンス費用が中心です。
中規模案件(売上高1億円から10億円程度)では、3,000万円から1億円程度の費用が一般的で、より詳細な調査や複数の専門家の関与が必要となります。
大規模案件(売上高10億円以上)になると、1億円を大きく超える費用が発生し、複雑な法務・税務対応や国際的な調整が必要となることもあります。
いずれも、案件の複雑さや当事者間の交渉状況によって大きく変動する可能性があります。
2-3.海外M&Aと国内M&Aの費用比較
海外M&Aの場合、言語の違いによる翻訳・通訳費用、異なる法制度や会計基準への対応費用、海外渡航費用などが必要となります。
国内M&Aと比べて1.5倍から2倍程度の費用がかかることが一般的です。
また、国際的な税務や法務の専門家の関与が必須となるため、アドバイザリー費用も高額になります。為替リスクへの対応や文化的な違いを埋めるためのコンサルティング費用なども多めに見積もっておくことが必要です。
3:M&A費用のコスト削減方法

ここでは、M&A費用を抑えるための主な方法について説明します。自社でできるコスト削減、パッケージサービスの活用がおすすめです。
3-1.:自社でできるコスト削減
決算書類、固定資産台帳、会計ソフトデータなどの財務関連資料を事前に整えておくことで、専門家への依頼時間を短縮し、コストを抑えることができます。
また、自社の強みや課題を明確にし、企業概要書を自社で作成することも効果的です。
予めM&A実行時のリスクを事前に把握し、対策を講じておくことで、デューデリジェンスの費用を抑えることもできます。
3-2.パッケージサービスの活用
近年、中小企業向けのM&Aパッケージサービスが登場しており、これを活用することでM&A費用を大幅にカットすることが可能です。
M&Aプロセス全体をカバーし、定額制や成功報酬型の料金体系を採用しているケースが多いですが、個別で専門家に依頼するよりも全体的な費用を抑えられる可能性があります。
4.まとめ

M&Aには買い手側、売り手側共にさまざまな費用がかかることを紹介してきました。M&Aを検討する際には、これらを理解して無駄な費用が発生しない様、複数の専門家に相談したり、担当者を見極める必要があります。
まずは無料相談可能なIFAを頼ってみてはいかがでしょうか。
ファーストパートナーズ・グループには、大手金融機関出身者が多数在籍し、高いスキルを持つ各分野のエキスパートが揃っています。スタートアップ企業の資金調達支援や事業拡大支援、M&Aによる事業承継やIPOの実現など、幅広いサポートを行っており、M&A成立後も、運用戦略の提案や資産増大の支援など、長期的なサポートを提供しています。
ぜひこれを機に相談を検討いただけたら幸いです。
