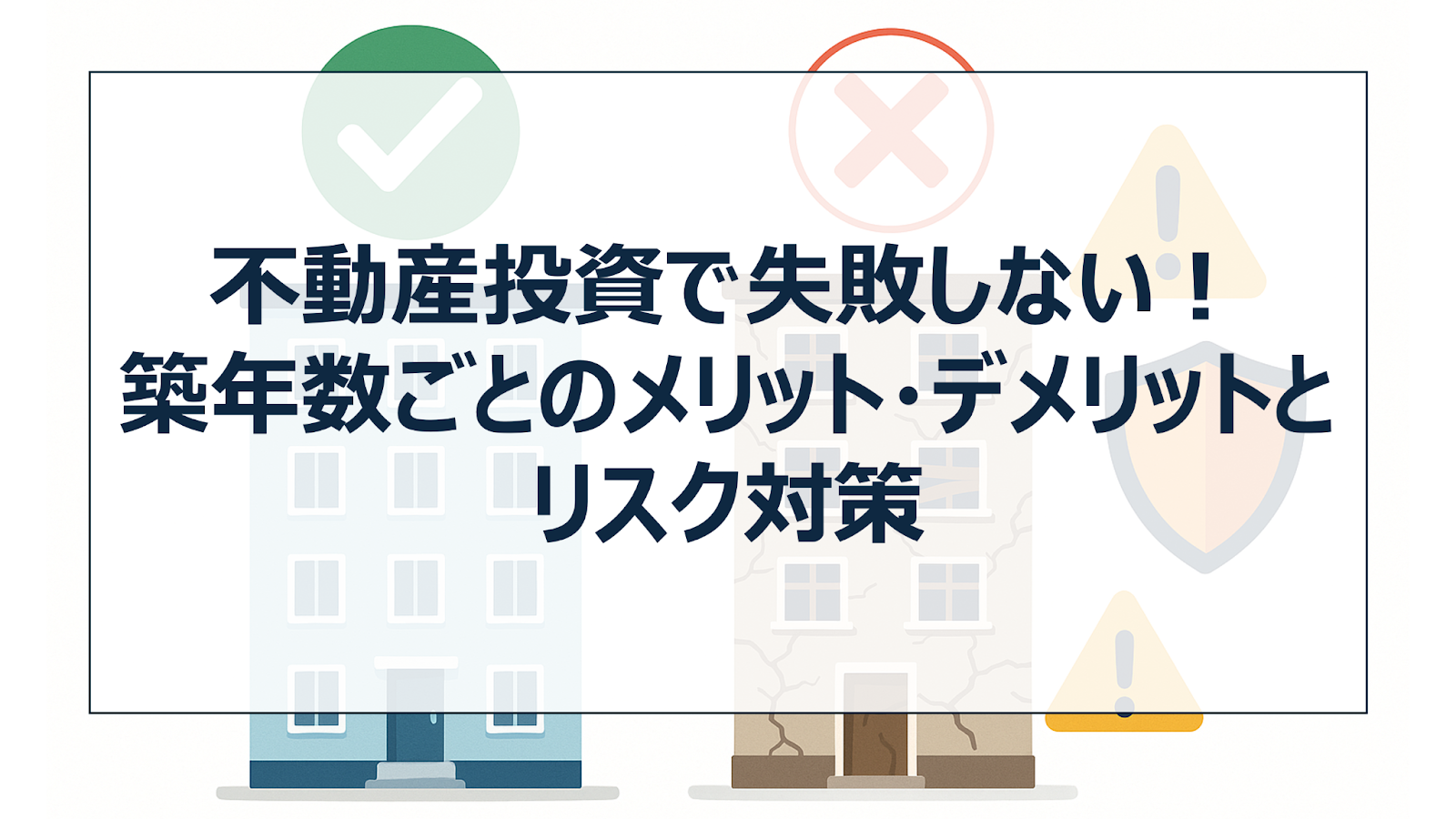
- 不動産投資の物件選びで築年数をどう考慮したら良いか分からない
- 不動産投資で物件築年数の重要性が分からない
- 不動産投資で物件築年数ごとのメリット、注意点が分からない
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。不動産投資のプロが、不動産投資における物件の築年数について解説します。
この記事を読むことで、物件の築年数に関する不安や疑問を解消し、物件選びの軸を持つことができるでしょう。
1. 不動産投資における「築年数」の基礎知識と重要性
不動産投資では、「築年数」が投資判断に与える影響は非常に大きく、物件選びの重要な評価軸のひとつとなります。まずは築年数が投資判断に与える基本的な影響を確認しましょう。
- 築年数が物件価値に与える影響
- なぜ「築年数」が投資の成否を分けるのか
- 「法定耐用年数」と「実際の建物寿命」の違い
以下で、それぞれについて解説します。
1-1. 築年数が物件価値に与える影響
一般的に、築年数が進むほど物件の資産価値は下がる傾向にあると言われています。
新築時が最も高い評価を受け、その後は築年数の経過と共に下落率が緩やかになりながらも、建物の経年劣化と共に価値の減少が進みます。
その背景には、建物は老朽化に伴い外壁や設備の性能が低下し、法定耐用年数を過ぎると税務上の評価も下がるためです。
例えば、東日本不動産流通機構の調査を元にした推計では、首都圏の中古マンションでは築10年で新築価格から約5%、築20年では約20%程度資産価値が下がる傾向があるとされています。地方の木造戸建ての場合ですと、築20年を越えると資産価値がほぼゼロになることも考えられます。
築年数は物件価値を見極める上で欠かせない指標となります。購入前には必ず築年数を確認しましょう。
1-2. なぜ「築年数」が投資の成否を分けるのか
築年数が不動産投資の成否に大きく影響する理由として、運用可能期間や修繕費の負担、入居者のニーズ変化が挙げられます。これらは中長期的なキャッシュフローに直結するため、表面的な利回りだけでは判断できない重要な要素となります。
とくに築古物件では、建物や設備の劣化により、突発的な修繕費用が必要になる場合がある点に注意が必要です。
例えば、築数十年以上の物件では給排水管の交換や外壁補修など、数百万円規模の工事が必要になる可能性があり、こうした支出は事前に織り込んでいないと、収支シミュレーションにズレが生じ、黒字運用が困難になるケースもあります。こうした理由から、築年数は購入判断時に必ず加味し、無理のない運用計画を立てることが求められるでしょう。
1-3. 「法定耐用年数」と「建物寿命」の違い
法定耐用年数とは、建物の構造ごとに国が定めた年数で、減価償却費を算出する際の税務上の基準となるものです。税務上の計算に用いられる客観的な基準です。
一方で建物寿命とは「実際に居住や利用が可能な期間」を指すもので、公的な定義はありません。これは建物の構造、施工品質、管理状態、メンテナンス履歴などによって左右されるため、実際の使用可能年数は、法定耐用年数を超える場合も少なくありません。
具体例として、鉄筋コンクリート造のマンションは法定耐用年数47年ですが、住宅性能表示制度の劣化対策等級3であれば75~90年は使えるとされています。
このように税務上の法定耐用年数と実際の建物寿命は異なるため、投資判断には両者をしっかり区別して理解しておきましょう。
2. 築年数別による物件の特徴と見極め方
ここからは築年数帯ごとの一般的な特徴を押さえ、どのように物件を見極めるかを解説します。
- 築年数ごとの分類とそれぞれの一般的な定義
- 築年数別に見る物件の人気・家賃・入居率
- 築年数帯で考慮すべき投資戦略の立て方
以下で、それぞれについて解説します。
2-1. 築年数ごとの分類とそれぞれの一般的な定義
不動産投資において、物件は主に「築10年未満」「築10~20年」「築20年以上」の3つの築年数帯に分類されます。この分類は修繕などによる利回り変化や融資条件の目安にもなるためです。
築10年未満の物件は設備が新しく、入居需要も高い傾向があります。築10~20年の物件では、新築時を比較し、物件価格は下がるものの家賃が安定する傾向があります。
築20年以上の物件になると、物件を安価で購入できる一方、空室リスクや修繕負担が増す点に注意が必要です。
このように、築年数帯ごとに異なる特徴やリスクがあるため、自身の投資目的や資金計画に合わせて築年数帯を決めることが大切です。
2-2. 築年数別に見る物件の人気・家賃・入居率
築10年未満の物件は、最新の設備やデザイン性が評価されやすく、入居希望者の需要が強いため、家賃水準・入居率ともに高水準で推移する傾向があります。満室時のキャッシュフローが安定しやすいのが魅力となります。
築10~20年の物件は、購入価格が築浅よりも低いため物件購入者からの人気が高いです。家賃や入居率は、築浅と比べ、低くなる傾向があります。
築20年の物件は人気が一般的に低く、賃貸住宅の空き家の7割が築20年以上というデータがあります。家賃や入居率は、築10~20年の物件と比べ、さらに低くなる傾向となっています。
築年数帯によって家賃と入居率の特性が異なるため、自身の融資条件や運用プランに合う物件を選びましょう。
2-3. 築年数帯で考慮すべき投資戦略の立て方
築浅物件はキャピタルゲイン狙いの短期売却戦略が立てやすい一方、築古物件はキャッシュフロー重視の長期保有戦略が向いています。目的によって取るべき戦略は大きく変わります。
築10年未満は値下がりリスクが小さいため、「運用益+売却益」を狙う短期戦略に適しやすいでしょう。ただ、設備修繕のリスクは低いですが、家賃が高くなるため、利回りは低くなる可能性があります。
築10~20年の物件は、家賃が安定するため、運用益メインの中長期戦略がおすすめです。
築20年以上は割安なため「リノベーション+高利回り運用」を検討できるでしょう。
例えば、築古アパートを一棟リノベーションし、付加価値を高めて賃料を上げることで、築浅物件並みの収益を狙う手法があります。ただ、予期せぬ修繕等で費用が増えることや空室リスクがあるため、注意が必要です。
築年数帯に応じた戦略を明確にすることで、無駄なリスクを抑えつつ目標とする収益を得やすくなります。
3. 新築・築浅・築古物件どれを選ぶ?:タイプ別のメリットと注意点
物件タイプごとに具体的な長所短所を比較し、自分に合ったものを選びましょう。
- 新築物件のメリットと注意点
- 築浅物件のメリットと注意点
- 築古物件のメリットと注意点
以下で、それぞれについて解説します。
3-1. 新築物件のメリットと注意点
新築物件は最新の設備や内装を備えており、、入居希望者からの人気が高く、空室が埋まりやすいというメリットがあります。安心して長く運用できる点も魅力です。
ただし購入価格が高額なためキャッシュフローが圧迫されやすく、利回りが低く出るケースが多いのがデメリットです。
例えば、築浅物件に比べて購入価格が10%ほど高いこともあるため、手持ち資金や借入金利によっては収支計画が厳しくなる可能性があります。
また、空室が埋まるまでは、想定したキャッシュフローにならず、返済原資を見積る必要もあります。
したがって、新築物件を選ぶ際は融資条件や自己資金のバランスを慎重に検討しましょう。
3-2. 築浅物件のメリットと注意点
築浅物件は新築に近い設備や外観などの魅力を維持しつつも、新築よりは価格が下がり始める時期に購入できるため、コストパフォーマンスが高いのが特徴です。入居率も比較的安定しやすく、収益の予測が立てやすいでしょう。
一方で築浅物件でも設備や内装の老朽化が始まるため、将来的には修繕費がかかることを想定する必要があります。
具体例として、築10年の物件は外壁補修等の大規模修繕のタイミングがまだ先である一方、給湯器やエアコンの交換時期が迫ってくるケースが考えられるでしょう。
購入後の修繕計画をあらかじめ立てることで、予期せぬ費用増を抑えられます。
3-3. 築古物件のメリットと注意点
築古物件は購入価格が相対的に低いため自己資金や借入額を抑えやすく、高い表面利回りを狙える点が魅力です。
しかし空室リスクや設備老朽化による修繕費の増加が課題となります。
例えば、築20年以上の物件では給排水管全交換や外壁補修といった大規模修繕が必要になる可能性が高いため、修繕費用の見積もりが外れると収支が大きくブレる可能性があります。
築古物件を検討する際は、リノベーションによる付加価値向上や物件管理の手間を見越した利益シミュレーションが欠かせないでしょう。
4. 築年数によるリスクを最小限に抑える対策と物件選びのコツ
築年数別のリスクを理解した上で、実際にどのように対策すればよいかを見ていきます。
4-1. 物件の状態を見極めるデューデリジェンスの重要性
物件購入時には設備や建物の劣化状況を専門家が調査する「デューデリジェンス(DD)」の実施が重要です。これが不測の支出を減らす第一歩となります。
専門家による現地調査で給排水管、外壁、屋根の劣化状況を確認し、将来的な大規模修繕計画を立てることが重要です。
例えば、築25年のアパートでは事前調査で配管の孔食、劣化が見つかり、数百万円超の改修費用が必要と判明する可能性もあるでしょう。
こうした調査結果をもとに購入価格交渉や修繕費積立計画を練ることで、収支計画のズレを防げる可能性があります。
4-2. 適切な修繕計画と資金計画
不動産投資では、長期的な視点での修繕計画と、それを支える資金計画の両立が不可欠です。定期的に修繕積立金を確保し、長期修繕計画(LCC)を作成すると安心です。築年数に応じた修繕タイミングを把握し、余裕をもって資金を準備しましょう。
共用部や主要設備の交換時期をあらかじめ把握し、積立金と借入のバランスを取ることで資金ショートのリスクを抑えられます。
例えば、国土交通省のガイドラインの目安では、築20年超のマンションでは大規模修繕が12~15年ごとに必要となるため、それに向けて毎年数十万円の積立が必要になることがあります。
修繕と資金の両面から計画を立てることが、長期運用の安定につながります。
4-3. 融資の受けやすさと金融機関の評価ポイント
不動産投資における融資の審査では、耐用年数に対して残存年数がどれだけあるかを重視します。一般的に築10~20年以内だと評価額が高く、長期融資を組みやすい傾向があります。
融資申請時には耐用年数残存年数や立地条件、入居率データを提出し、物件の収支安定性を示すことが重要になるでしょう。
築年数を踏まえた融資戦略を立てることで、自己資金を効率的に活用できます。
4-4. 築年数のデメリットを「立地力」でカバーする戦略
築古物件でも駅近や都市部など高需要エリアを選べば空室リスクを低く抑えられます。立地の利便性が高いほど投資寿命が延びると言えるでしょう。
例えば、都心近郊の築20年超マンションでも駅徒歩3分の物件は入居者が途切れにくく、修繕費を賄うだけの家賃が見込める可能性もあります。
このように築年数で劣る点は立地で補い、収益性を維持する戦略が良いでしょう。
5. まとめ
築年数は不動産投資の成否に直結する重要な要素です。
物件価値、修繕費、融資条件、入居需要に大きく影響するため、基礎知識を押さえた上で築年数別の特徴を理解し、適切な戦略を立てることが肝心です。
新築・築浅・築古それぞれのメリットと注意点を比較し、デューデリジェンスや資金計画、立地戦略を組み合わせてリスクを最小化しながら安定収益を目指しましょう。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添った不動産投資のご提案を行っております。不動産投資での失敗を避けたい方には、お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
