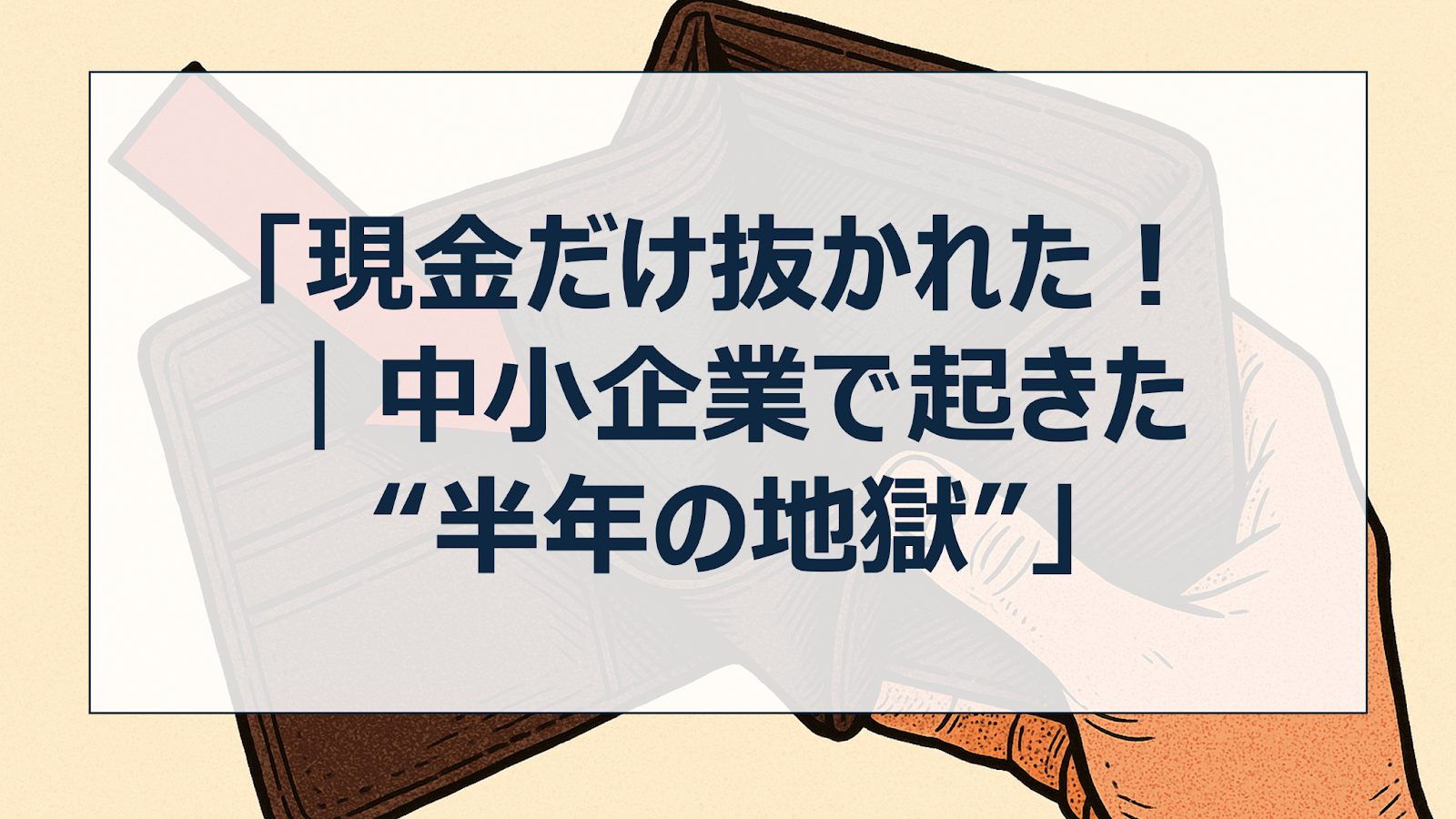
- 資産だけを奪われてしまうM&Aについて知りたい
- 資産だけ抜かれるM&Aの具体的な事例について知りたい
- 中小企業経営者が会社を守るためにできる対策を知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。M&Aのプロが、資産だけを奪うM&A買収スキームの実態について解説します。
この記事を読むと、悪質なM&Aスキームへの不安を解消し、騙されずに会社を守る方法がわかります。
目次
1. 資産だけを奪われる買収とは?仕組みと狙い
1-1. なぜ中小企業が標的にされるのか?
1-2. ターゲットにされる企業の“共通条件”
2. ケース①:資金繰りに悩んだ経営者が見た“救済”の罠
3. ケース②:「M&Aはチャンス」と思ったら“帳簿だけの価値”を狙われた
4. ルシアン事件から見る“吸血型”M&Aの特徴
4-1. なぜ第三者が資金を移動できたのか
4-2. 契約書・取締役構成・口座権限の盲点
5. 警鐘:これはM&Aではなく“合法的収奪”だ法のグレーゾーンで行われる手口の実態
6. 経営者が自分の会社を守るためにできること
6-1. スキームの知識を持つことが最大の防衛策
6-2. 「相手が何を得たいか」を見抜く眼を持つ
7. まとめ
1. 資産だけを奪われる買収とは?仕組みと狙い
悪質なM&Aの中には「資金管理の効率化」などを理由に、流動資産(現金・在庫・売掛金など)を買収後すぐに子会社の口座を親会社の管理下に移すことで口座を掌握するという手口があります。
このような資金移動が繰り返され、かつ返金が遅れたり止まったりすると、給与遅延や取引停止が連鎖し、子会社側の企業は数カ月で資金ショートに陥ります。こうした事態は国内の報道や弁護士解説でも具体的に指摘されています。
口座や承認権限の移管、送金指示の常態化、資金戻しの恣意的運用が重なると、子会社側は支払期日に資金が足りなくなります。
さらに「保証解除」などの約束が履行されないと、売り手側の経営者に個人補償などのリスクが残る場合も有る為、事前の契約確認が重要です。
早期に「資金・権限の一括移管」を求める提案は、事業再生ではなく資産回収が狙いのサインである可能性もあると見て警戒すべきです。
1-1. なぜ中小企業が標的にされるのか?
中小企業はガバナンスや人員が限られていることが多く、買収提案を短期間で精査する体制が整っていないケースがあります。
金融機関や仲介者、顧問士業など周りの助言に依存しやすい状況が、買い手側の資金管理スキームを通しやすくしている一因になっています。
また、意思決定フローが口頭やメールで済まされていたり、取締役会の開催・議事録整備が形式的になっていると、権限移譲や口座変更の判断が属人的に行われ、チェック機能が働かない恐れがあります。
例えば「取引先に不安を与えないように今日中に送金をしてほしい」などと急かされ、十分なリーガルチェックをせずにグループ口座への送金指示に応じてしまうケースもあります。こうした対応に連鎖して支払遅延が起き、取引先の信用が落ち込みます。
時間的余裕がない状況ほど第三者の専門家を介して、資金・権限の移転条件を明文化・合意することがリスク管理上重要といえます。
1-2. ターゲットにされる企業の“共通条件”
買収の対象として狙われやすいのは、現預金が潤沢、売掛金回収が順調、棚卸資産が多いのに規模の割に管理体制が弱い企業です。赤字や債務超過でも「帳簿上の流動資産」が目当てにされます。
資産を移せば短期で現金化でき、買い手側の資金繰りに使えるからです。さらに、保証解除や負債整理など“救済”の言葉が並ぶと、売り手は条件をのみやすくなります。
「退職金支払い」「保証解除」を前提に安値譲渡へ誘導し、クロージング直後に倉庫在庫の一部を別会社へ移し替えるよう求めるケースが想定されます。戻し条件や対価精算のルールが不明確だと、在庫評価損や資産毀損につながるリスクが高まります。
資産の移動条件と対価精算の仕組みを曖昧にしたままのM&Aは、危険度が高いと判断すべきです。
2. ケース①:資金繰りに悩んだ経営者が見た“救済”の罠
資金繰りに苦しむ企業に対して「グループ本社が一時的に資金を管理し、必要な時に返す」という提案がされるケースがあります。
