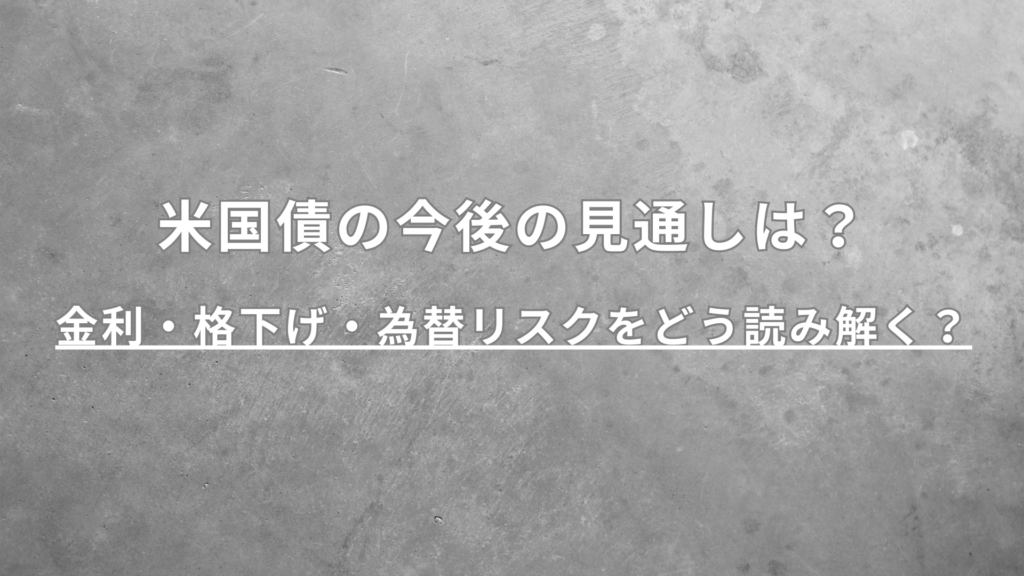
米国債は世界最大の債券市場であり、安全資産としての地位を長く維持してきました。
しかし近年は、インフレや金利上昇、米国の格付け見直し、さらには為替リスクといった新たな要因が絡み、価格変動への注目が高まっています。
本記事では、米国債の今後の見通しを多角的に整理し、投資判断のヒントを探ります。
1. なぜ今、米国債に注目が集まっているのか?背景を押さえよう
1-1. インフレ・金利・地政学リスクなど環境変化による関心の高まり
1-2. 「安全資産」のはずの米国債にも価格変動リスクがある理由
1-3. 円安トレンドを受けて、為替差益を狙う投資家も増加中
3-1. 金利と債券価格の相関関係
3-2. 長期債と短期債どちらが価格変動に敏感か?
4-1. 政治リスク
4-2. インフレ再燃リスク
4-3. 為替リスク
5. 米国債を買うならいつがいい?米国債の「タイミング」の見極め方
1. なぜ今、米国債に注目が集まっているのか?背景を押さえよう
米国債は世界最大の債券市場であり、国際金融において「基軸資産」とも呼ばれる存在です。
通常、リスクを回避したい投資家にとって米国債は最も信頼度の高い選択肢の一つとされてきました。しかし、近年の経済環境は大きく変化しており、米国債が改めて投資家の注目を集めています。
その背景には、インフレや金利動向、地政学リスク、さらには為替市場の変動といった複数の要因が絡み合っています。ここでは、なぜ今米国債に視線が集まるのかを整理してみましょう。
1-1. インフレ・金利・地政学リスクなど環境変化による関心の高まり
まず大きな要因となっているのが、インフレと金利動向です。米国では2021年以降、パンデミック後の需要回復や供給制約、エネルギー価格の高騰などを背景に物価が大きく上昇しました。
これを抑制するため、米連邦準備制度理事会(FRB)は急速な利上げを進め、短期間で政策金利を大幅に引き上げています。この結果、米国債の利回りは数年ぶりの高水準に達し(10年債利回り4.25% 8月22日時点)、「安全資産でありながら高い金利を享受できる商品」として投資家の関心を呼んでいます。
加えて、地政学リスクの高まりも米国債の注目度を押し上げています。
たとえばここ数年のウクライナ情勢の悪化、中東の不安定化、台湾海峡を巡る緊張のように、国際政治のリスクが増すような状況が訪れると、リスク回避の動きとして「ドル資産」に資金が流入する傾向が見られます。
そのリスク回避先のドル資産の代表格が米国債です。世界の中央銀行や機関投資家は、こうした局面では米国債を保有することでポートフォリオ全体の安定性を確保しようとするのです。
さらに、このような米国債への資金流入の背景の1つとして、世界経済の減速懸念も挙げられます。
成長が鈍化する局面では、株式よりも比較的安定した債券への資金シフトが起こりやすくなります。特に米国債は市場規模が大きく流動性も高いため、短期間に巨額の資金を動かす機関投資家にとって、安心して取引できる選択肢となっています。
1-2. 「安全資産」のはずの米国債にも価格変動リスクがある理由
「安全資産」とされる米国債にも無視できないリスクがあります。典型的なのが金利変動に伴う価格リスクです。
通常、債券の価格は金利と逆の動きをするため、FRBが利上げを行うと既発債券の価格は下落します。たとえば、固定利率で発行された米国債を保有している場合、市場金利が上昇すれば、新たに発行される債券の利回りの方が魅力的になり、既存の債券価格は相対的に下がってしまうのです。
また、近年は米国の信用力そのものへの懸念も浮上しています。2023年には格付け会社フィッチが米国債の格付けを引き下げました。理由として、財政赤字の拡大や政治的な債務上限問題への懸念が挙げられます。
米国は、基軸通貨ドルを発行できるためデフォルトリスクは極めて低いと考えられているものの、「財政規律への不安」という形で市場の心理に影響を及ぼしました。
さらに、投資家にとって注意が必要なのは長期債の価格変動リスクです。10年債や30年債といった長期国債は、金利の変化に対して短期債よりも敏感に反応します。利回りが上昇すれば価格下落幅が大きくなり、含み損を抱える可能性が高まります。
そのため、「安全資産」とはいえ、保有期間や投資目的に応じてリスクを認識しておく必要があるのです。
1-3. 円安トレンドを受けて、為替差益を狙う投資家も増加中
日本の個人投資家や機関投資家にとって、米国債への投資を考える上で重要なのが為替リスクです。米国債はドル建てであるため、円とドルの為替変動がリターンに直結します。
ここ数年、日本円は歴史的な円安局面を迎えており、1ドル=160円を超える場面も見られました。円安が進む局面では、米国債をドル建てで保有している投資家にとって、為替差益を得られる可能性があります。
このため、単に利回りを確保するだけでなく、為替益を含めたトータルリターンを狙う投資家が増えています。特に外貨建て資産をほとんど持っていない投資家にとっては、分散投資の観点からも米国債は魅力的な選択肢となります。
反対に円高が進むと為替差損が発生するリスクがあるため、為替ヘッジ付きの商品を選んで為替リスクを抑える、という選択も可能です。しかし、為替の方向性は予測が難しいため、投資家によっては一部をヘッジ付きで、一部をヘッジ無しで保有するなど、バランスをとった運用を行うケースもあります。
2. 米国債の価格は何をもとに動く?カギを握る2つの要因
米国債は「世界で最も安全な資産」と言われることもありますが、その価格は常に一定ではなく、市場環境によって大きく変動します。
