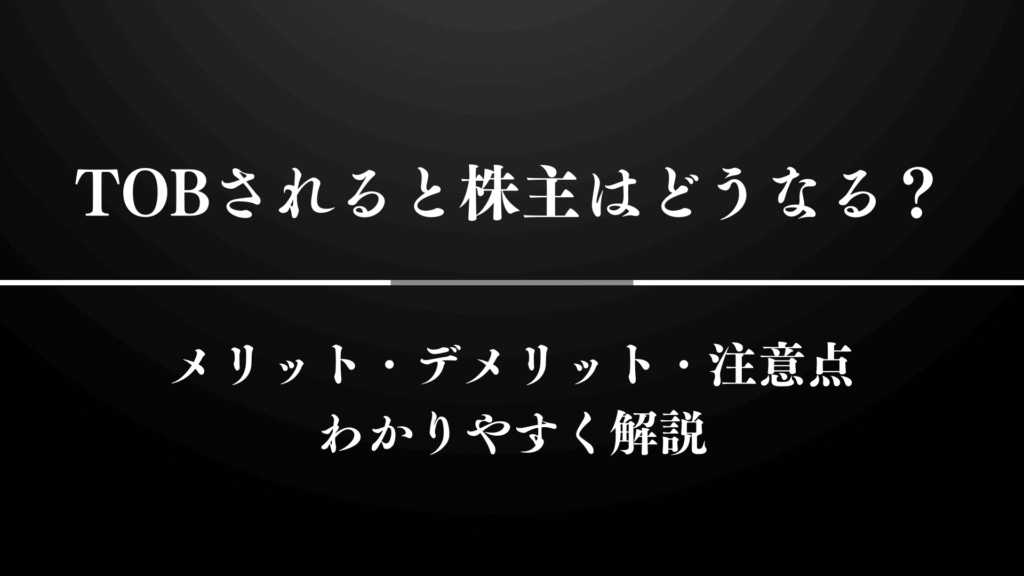
TOB(株式公開買付け)が発表されると、株主は「応募する・市場で売る・持ち続ける」の判断を短期間で迫られます。
本記事では、TOBの基本から株主のメリット・デメリット、公開買付け価格や株価の動き、手続き上の注意点までをわかりやすく解説します。判断の際の参考材料としてご活用ください。
1. 株主が知っておくべきTOB(株式公開買付け)の基本
株式投資をしていると、ニュースで「〇〇社がTOBを発表」といった見出しを目にすることがあります。TOBとは「Take Over Bid」の略で、日本語では「株式公開買付け」と呼ばれる仕組みです。
これは、ある企業や投資ファンドなどが特定の会社の株式を市場外で一括して買い付けることを指します。通常の株式売買は証券取引所を通じて行われますが、TOBは証券取引所を介さず、株主に対して「一定の価格で、一定の期間に、まとまった株数を買います」と公に提示して行われます。
なぜTOBが行われるのかというと、大きく二つの目的があります。
一つは「企業買収」です。ある会社が他社を子会社化したり、完全子会社にしたりするために発行済み株式の過半数を取得するケースです。もう一つは「持ち分拡大」です。
すでに筆頭株主である企業や投資家がさらに持株比率を高めたい場合に使われます。これにより経営への影響力を強めたり、将来的に上場廃止(非公開化)を見据えるケースもあります。
TOBの特徴は「提示価格が市場価格より高く設定されることが多い」という点です。
通常より高い価格で買い取ることで、株主に株式を手放してもらいやすくするためです。例えば、株価が1,000円の銘柄に対して「1株1,200円で買い付けます」と発表されれば、多くの株主は「市場で売るより有利だ」と判断する可能性が高くなります。そのため、TOBが発表されると対象企業の株価が急上昇することも珍しくありません。
一方で、TOBには株主にとって注意すべき点もあります。
まず、TOBに応じるには通常の証券口座からの売却ではなく、“公開買付代理人”に指定された特定の証券会社を通じて手続きを行う必要があります。また、TOBの応募期間が決まっており、その期間を過ぎてしまうと公開買付価格で売却できなくなります。さらに、買付が成立するかどうかは条件付きの場合もあり、最終的にTOBが不成立に終わる可能性もあります。
株主にとってTOBとは、自分の保有株を有利に売却できるチャンスである一方、その後の会社の経営体制や株主構成に大きな変化をもたらす重要な出来事です。
とくに上場廃止が絡むTOBでは、応じなかった株主が株式を持ち続けても市場で売れなくなるリスクがあります。したがって、TOBが発表された際には「なぜこのTOBが行われるのか」「公開買付価格は妥当か」「自分は株主としてどのような立場を取りたいのか」を冷静に判断することが大切です。
2. TOBが株主にもたらすメリット
TOB(株式公開買付け)が発表されると、株主にとって大きなチャンスが訪れる場合があります。
普段の株式投資では、株価の変動は市場の動きに左右されます。しかし、TOBでは買い手が「一定の価格で株式を買います」と明確に提示してくれるため、通常より有利な条件で株式を売却できる可能性があるのです。ここでは株主にとっての主なメリットを二つの観点から見ていきましょう。
2-1. 通常より高い価格で株式を売れるチャンスがある
最も大きなメリットは、株式を市場で売却するよりも高い価格で売却できるケースが多いことです。
TOBを仕掛ける側としては、多くの株主に応募してもらわなければ目的を達成できません。そのため、提示価格は通常の株価よりも一定のプレミアム(上乗せ)をつけるのが一般的です。
例えば、市場での株価が1,000円前後で推移している企業に対し、買い手が「1株1,200円で買い付けます」と発表すれば、株主は市場より20%も高い価格で売却できることになります。特に長期保有していた株式が思うように値上がりしていなかった場合でも、TOBによって予想外の利益を得られるケースがあります。
また、TOBの発表直後には市場価格そのものが公開買付価格に近づいて上昇する傾向があります。市場での売却でも利益を得られる場合がありますが、提示価格まで完全に届かないことも多いため、TOBへの応募がより有利となるケースが見受けられます。
2-2. 判断次第で大きな利益を得られる可能性も
ただし、必ずしも全てのTOBで大きな利益が得られるわけではありません。
公開買付価格の上乗せ幅が小さい場合や、競合相手が現れない場合には市場価格との乖離が限定的にとどまることもあります。とはいえ、通常の株式投資では、短期間で利益を確定するのは容易ではない一方で、TOBでは、あらかじめ提示された価格で株式を売却できるため、条件が合えば利益を確定できるという点が株主にとっては大きな魅力といえるでしょう。
3. TOBが株主にもたらすデメリット
TOB(株式公開買付け)は株主にとって「高値で株式を売れるチャンス」というメリットがある一方で、いくつかのデメリットやリスクも存在します。
特に「TOBに応じなかった場合にどうなるか」という点や、「株主としての立場の変化」には注意が必要です。ここでは株主が知っておきたい代表的なデメリットを解説します。
3-1. TOBに応じないと株式が売りにくくなるリスク
最大のリスクは、TOBに応じないことで株式が売却しにくくなる可能性があることです。
公開買付者が大量の株式を取得して支配権を握ると、その後の市場での流動性が大きく低下します。つまり、市場で株式を買いたい投資家が減ってしまい、売りたいときに思うように売れない状況に陥るのです。
特に、TOBの目的が「完全子会社化」である場合は注意が必要です。買付者が一定割合以上の株式を取得すると、上場廃止手続きに進むケースがあります。上場廃止になれば証券取引所での売買はできなくなり、少数株主は事実上、会社からの買取請求に応じるか、株式を保有し続けるしかなくなります。保有しても市場での換金手段がなくなるため、投資資金を回収できなくなるリスクが高まります。
また、TOBの成立後に市場で株式を売却しようとしても、株価が公開買付価格を下回ることも多く、「あのときTOBに応じておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。
3-2. 株主としての発言力が弱まることがある
もう一つのデメリットは、株主としての発言力が弱まる可能性がある点です。
TOBによって公開買付者が経営権を握ると、株主総会での議決権のバランスは大きく変わります。たとえば、過半数の株式を取得した買付者が主要な議案を決定できるようになれば、少数株主が反対票を投じても経営方針に影響を与えるのは難しくなります。
さらに、公開買付者が90%以上の株式を取得した場合には「スクイーズアウト(少数株主排除)」が行われることもあります。これは、少数株主が強制的に株式を買い取られる仕組みで、株主としての存在自体が消滅するケースです。
もちろん買取価格は法律上の基準に基づいて算定されますが、自分の意志で保有を続けたい株主にとっては不本意な結果となりかねません。
株主にとって「議決権」や「経営への参加機会」は会社に関与できる貴重な権利です。しかしTOB後には、その権利が大幅に制限され、株主としての発言力を失う可能性があることを理解しておく必要があります。
4. TOBの発表で株主と株価はどう動く?
TOB(株式公開買付け)が発表されると、株主や株価には大きな変化が表れます。
普段の株式投資では、業績や景気動向によって株価が動きますが、TOBの発表はそれとは別次元の「特別な出来事」として市場に影響を与えます。では、具体的にどのような反応が起きるのでしょうか。
株価は公開買付価格に近づく傾向がある
TOBが発表されると、まず株価は公開買付価格に向かって大きく動きます。
たとえば、市場で1株1,000円で取引されていた企業に対し、「1株1,300円で買付けます」と発表された場合、多くの投資家が「今市場で買ってTOBに応募すれば利益が出る」と考え、株式を買いに走ります。その結果、株価は急騰し、発表直後に公開買付価格に近い水準まで上昇するのが一般的です。
ただし、株価が必ずしも公開買付価格と同じになるわけではありません。買付が成立しないリスクや、応募手続きの手間などを考慮して、市場価格はやや低めで推移することもあります。逆に、競合相手による「上乗せTOB」への期待が高い場合には、公開買付価格を超えて株価が上昇することもあります。
株主の心理と行動の変化
既存の株主にとっては、「高値で売れるチャンス」となるため応募を検討する動きが強まります。
特に長期保有してきた株式が思うように値上がりしていなかった場合、TOBの発表は利益を確定できる好機と映るでしょう。
一方で、「会社の将来性に期待しているから売りたくない」「親会社の傘下に入ればさらに成長するかもしれない」と考える株主は、あえて応募せず保有を続ける選択をすることもあります。つまり、TOB発表後の株主の行動は、「売るか、残るか」をめぐって二極化する傾向があります。
短期投資家の参入も増える
TOB発表は短期的な投資チャンスと捉えられるため、発表後には新たな投資家が参入してきます。
市場価格と公開買付価格の差を狙った売買(いわゆる“TOB狙い”の投資手法)によって、対象銘柄の出来高が急増するのが特徴です。このような動きは株価をさらに押し上げる要因となりますが、同時に発表直後の値動きが荒くなることもあります。
発表後の株価の安定と変化
TOB期間中は、市場価格が公開買付価格付近で安定するケースが多いです。
しかし、最終的にTOBが成立するかどうかによって、その後の株価は大きく変わります。成立すれば市場での売買が縮小し、上場廃止に向かうケースでは保有株が強制的に現金化される可能性があります。一方、不成立になった場合は「期待が外れた」として株価が急落することもあり、投資家の失望売りが広がることも少なくありません。
5. TOB発表後、株主が取れる3つの選択肢
TOB(株式公開買付け)が発表されると、株主は自分の株式をどうするか選択を迫られます。
選択肢は大きく分けて「TOBに応募して株式を売る」「市場で株式を売却する」「そのまま保有し続ける」の3つです。それぞれにメリットとデメリットがあり、投資目的や状況によって最適な判断は変わります。ここでは3つの行動パターンを詳しく見ていきましょう。
5-1. TOBに応募し株式を売却
最もオーソドックスな選択肢が、TOBに応募して提示価格で株式を売る方法です。TOBでは、通常より高い価格が提示されることが多く、応募すれば市場より有利な条件で株式を売却できる可能性があります。
例えば、株価が1,000円で推移しているときに「1,200円で買付けます」と発表された場合、TOBに応募すれば20%のプレミアムを得られます。長期保有で含み益が出ていなかった株でも、一気に利益確定できるチャンスになります。
ただし、TOBに応募するには手続きが必要です。通常の売却のように簡単に売却できるわけではなく、公開買付代理人に指定された特定の証券会社を通じて書類を提出する必要があります。さらに、買付株数に上限がある場合、応募が殺到するとすべての株式が買い取られず、一部だけ成立するケースもあります。
それでも、TOBに応募することで「条件が合えば利益を確定できる」という安心感が得られるため、多くの株主が選ぶ方法です。
5-2. 市場で株式を売却
二つ目の選択肢は、証券取引所で市場売却する方法です。TOBが発表されると、対象株の株価は通常、公開買付価格に近づいて上昇していく傾向があります。そのため、TOBに応募せずとも市場で売却して利益を確定できる場合があります。
市場で売却するメリットは「手続きが簡単」な点です。普段の売買と同じように、証券会社の取引画面から株式を売るだけで済みます。TOBに応募する際に必要な書類の記入や、代理人証券会社への対象株式の移管などの手間を避けられるのは大きな利点です。
また、売却代金も数日で口座に入金されるため、資金を素早く別の投資に回したい人に向いています。
一方でデメリットは、売却価格が必ずしもTOBの公開買付価格と同じにはならない点です。通常、市場価格はTOB価格より少し安い水準で推移するため、TOBに応募した方が得になるケースが多いのです。さらに、TOBが不成立になるリスクを織り込んで市場価格が下落することもあり、「早めに売っておけば良かった」と後悔する可能性もあります。
短期投資家や手続きの煩雑さを避けたい投資家には、市場売却という選択肢が現実的といえるでしょう。
5-3. 現状のまま株式を保有
三つ目の選択肢は、TOBに応じず株式をそのまま持ち続ける方法です。買付者が一定の割合に達しない限り、株主としての地位は維持できるため、「会社の将来性を信じて売りたくない」という株主にとっては有力な選択肢となります。
たとえば、TOBの目的が経営権の安定化や持ち分比率の引き上げであり、上場廃止を前提としていない場合、TOB成立後も株式は市場で取引可能です。この場合、株主は引き続き配当を受け取ることができ、将来の株価上昇を狙うこともできます。
しかし、保有を続ける場合にはリスクもあります。買付者が過半数以上の株式を取得すれば、株主総会での議決権はほぼ買付者の意向に従う形となり、少数株主の発言力は弱まります。
さらに、買付比率が90%を超えると「スクイーズアウト」と呼ばれる制度で少数株主が強制的に株式を買い取られる場合もあります。その場合、提示される価格がTOB価格と同水準であることが多いですが、必ずしも株主にとって有利とは限りません。
また、TOBが上場廃止を目的としている場合には注意が必要です。上場廃止になれば市場で売買ができなくなり、換金性は著しく低下します。株式を保有し続けたい株主にとっても、実質的には選択肢が限られることになります。
6. TOB成立後に株主に起こる変化と株価の動向
TOB(株式公開買付け)が成立すると、株主と株価の状況は大きく変わります。成立した時点で、買付者が一定の株式を取得することが確定し、企業の経営体制や市場での位置づけが大きく動き出すからです。ここでは、TOB成立後に株主が直面する変化と、株価がたどる一般的な流れを解説します。
6-1. 株主に起こる変化
まず、TOBに応募して株式を売った株主は、成立後に代金を受け取り、株主名簿から外れることになります。提示された公開買付価格で売却できるため、これ以上の変化はありません。大切なのは、成立後に確実に資金が入金されることです。
一方、TOBに応募せず株式を保有し続けた株主には、大きな変化が訪れることがあります。買付者が過半数以上の株式を取得すれば、経営権を握ることになり、株主総会での議決権は実質的に買付者側が支配します。そのため、少数株主は経営方針に影響を与えることが難しくなり、発言力は弱まります。
さらに、「スクイーズアウト」と呼ばれる制度により、少数株主が強制的に株式を買い取られるケースもあります。この場合、株主として会社に残ることはできず、事実上すべての株主が退出することになります。
また、上場廃止が前提のTOBであれば、成立後に株式は証券取引所での取引が停止され、非公開会社へ移行します。株式を持ち続けることはできても、市場で売却できなくなり、換金性が著しく低下するため、実質的には現金化する選択を迫られるのです。
6-2. 株価の動向
TOB成立後の株価は、通常は大きな動きを見せなくなります。なぜなら、市場で取引される株の流通量が減り、また公開買付価格が基準として強く意識されるためです。多くの場合、株価はTOB価格付近で安定し、出来高も減少します。
ただし、TOBが不成立に終わった場合は状況が一変します。市場は「期待が外れた」として売りが殺到し、株価が急落するケースも少なくありません。逆に成立後であっても、競合による追加買付けや新たな戦略的提携の報道が出れば、株価が再び動意づくこともあります。
上場廃止が決まった場合は、株価はやがて公開買付価格と一致する方向に収束します。市場で売買できるのは廃止までの限られた期間であり、株主はその間にどう行動するか判断を迫られることになります。
7. 株主が知っておくべきTOBのリスクと注意点
TOB(株式公開買付け)は、株主にとって「通常より高い価格で株式を売却できるチャンス」となる一方で、必ずしも安心して臨めるわけではありません。
手続きの方法や売却のタイミング、そして想定外のリスクを理解していなければ、思わぬ損失や不便につながる可能性があります。ここでは、株主が知っておくべき代表的な注意点を4つに分けて解説します。
7-1. 公開買付代理人(特定の証券会社)を通じて手続きが必要
通常の株式売買は、普段利用している証券会社の取引画面から簡単に行えます。しかしTOBの場合は、買付者が指定する「公開買付代理人」と呼ばれる証券会社を通じて手続きをする必要があります。
例えば、自分が普段ネット証券を利用していても、その証券会社が公開買付代理人に指定されていない場合は、公開買付代理人である証券会社に株式を移管してから応募する必要があります。この場合、株式の移管手続きや必要書類の提出など、時間と手間がかかる点に注意が必要です。応募期限が限られているため、手続きの遅れが原因で応募できなくなるリスクもあるのです。
したがって、TOBの発表があった場合に応募の意向があるならば、まず対象株式を保有している証券会社が公開買付代理人に含まれているかを確認し、含まれていない場合は速やかに移管を進めることが重要です。
7-2. 応募期間を過ぎるとTOB価格で売却できない
TOBには必ず「応募期間」が設定されています。多くの場合、1か月前後の期間が設けられていますが、この期限を過ぎてしまうと、提示された価格で株式を売却することはできません。
特に注意すべきなのは、「気づいたときには締め切られていた」というケースです。TOBは発表から成立までの流れが比較的短期間で進むため、株主が情報を見逃すと対応できないまま終わってしまう可能性があります。
応募期間を過ぎても市場で売却は可能ですが、その時点では株価が公開買付価格を下回っていることが多く、「TOBに応じていれば得られたはずの利益」を逃してしまうリスクがあります。情報収集と期限管理が何より大切です。
7-3. 税金や口座振替(移管)手数料が発生する場合がある
TOBに応募して株式を売却し、利益が出た場合は、通常の株式の売買と同じように譲渡益として課税対象となります。
また、TOBの応募自体に手数料はかかりませんが、口座振替(移管)をする際に手数料がかかる場合があります。証券会社ごとに扱いが異なりますので、事前に確認しておくことが大切です。
7-4. TOBが不成立になるリスク
TOBは発表されたからといって、必ずしも成立するわけではありません。買付条件として「〇%以上の株式が応募された場合に成立」といった下限条件が設けられていることが多く、必要な株数が集まらなければ不成立となります。
不成立になった場合、TOB価格で売却することはできず、市場に株式が戻ることになります。このとき、市場価格はTOB発表前の水準に逆戻りしたり、場合によってはそれ以下に下落するケースもあります。株主にとっては「高値で売れるはずだったのに、結局売れずに含み益が消えてしまった」という結果になりかねません。
そのため、TOBに応募する際には「成立の可能性が高いかどうか」を見極める視点も必要です。過去の事例を見ると、親会社による完全子会社化など明確な意図がある場合は成立しやすい一方、敵対的買収のように対象企業が反対しているケースでは不成立に終わることもあります。
8.まとめ
TOBは、市場価格にプレミアムが乗ることが多く、適切に手続きすれば利益確定の機会になる可能性があります。一方で、応募期限・公開買付代理人・税金・不成立のリスク、さらに上場廃止や議決権の希薄化といった影響への配慮も欠かせません。重要なのは、ご自身の目的(短期の利益確定、長期保有等)と条件(買付価格、買付比率、買付意図)を整理し、無理のない選択を行うことです。迷う点があれば、証券会社や専門家へ早めに相談し、期日管理と必要書類の確認を進めておくことが重要です。
ファーストパートナーズでは、お客様一人ひとりの状況に寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。
富裕層・資産形成層の方々に向け、金利環境や市場動向を踏まえた最適なアドバイスを提供いたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。
