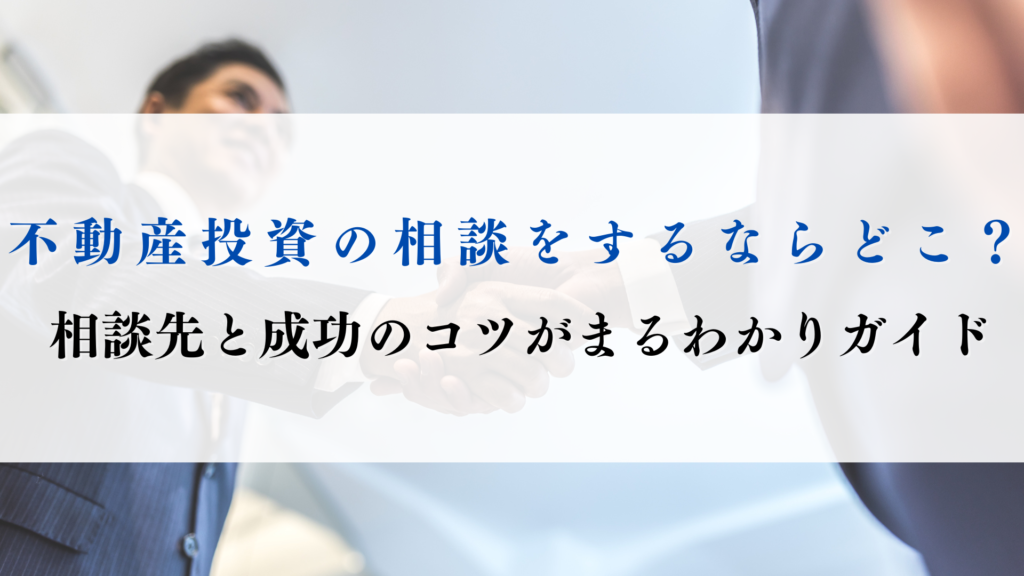
- 不動産投資の相談先が分からない
- 不動産投資の相談前に何を準備すれば良いか分からない
- 不動産投資で失敗しないための方法を知りたい
このようなお悩みで困ることはないでしょうか。
不動産投資のプロが、不動産投資のコツや相談先について解説します。
この記事を読むと、不動産投資の不安を解消でき、将来の資産形成に役立つこと間違いなしです。
1. 不動産投資する時の主な相談先6選
不動産投資をする時に代表的な相談先を6つ紹介します。
| 相談先 | こんな方におすすめ |
| 不動産投資家 | 知り合いに不動産投資の経験者がいる人 |
| 不動産仲介会社 | 相場情報をリアルタイムに見たい人 |
| 税理士 | 会社に顧問税理士がいる人 |
| 不動産投資会社 | 物件紹介から管理までワンストップで依頼したい人 |
| 金融機関 | 融資を利用して不動産投資をしたい人 |
| IFA | 特定の金融機関には属さない中立的な立場の意見を聞きたい人 |
1-1. 不動産投資家

不動産投資をこれから始めるなら、すでに実践経験を持つ投資家にアドバイスを求めることは非常に重要です。
実績のある投資家は具体的な数字をもとに失敗と成功の両面から話してくれるため、現場のリアル感がつかみやすいからです。
たとえば、地方の築古物件を数戸保有している投資家は、リフォーム費用の交渉術や空室対策の実践方法を教えてくれることがあります。
そうした実例は、検索しても見つからない現場感があり、決断に迷った際には大きな後押しとなるでしょう。
自分の身の回りに、不動産投資をしている人がいれば、ぜひ話を聞いてみると良いです。
経験者からの生の声を取り入れると、投資全体の流れやリスク管理を肌で感じることができます。
1-2. 不動産仲介会社
不動産仲介会社に相談すると、市場に出回る物件の相場情報をリアルタイムで把握できるメリットがあります。
物件の選択肢が広がるうえに、売主との価格交渉に慣れたスタッフがサポートしてくれるため、適正価格を理解しやすいからです。
たとえば、同じエリアでも駅徒歩5分以内の物件と10分以上の物件とでは家賃相場や需要層が大きく変わります。
そうした差を正しく認識できれば、投資計画を組む段階で収支の精度が高まり、失敗を減らすことができるでしょう。
仲介会社を活用することで、物件探しにかける時間や労力を効率的にコントロールできます。
1-3. 税理士

税理士も不動産投資の相談先の一つです。
不動産投資で利益が出れば、確定申告や節税対策は避けて通れません。
税理士に相談すれば、家賃収入や経費計上の仕方に関して正確なアドバイスを得られるため、不安を減らせるからです。
たとえば、減価償却費の計上方法や青色申告特別控除を適切に活用できるかどうかで、実際の手取り収入が大きく変わるケースがあります。
小さな見落としが将来的に大きな税負担につながる可能性があるので、早めにプロに意見を求める必要性は高いでしょう。
特に、会社に顧問税理士がいる場合は、内情にも詳しいので、税理士はおすすめの相談先です。
税理士のサポートを受けると、複雑な手続きをスムーズに進められ、本来の投資活動に集中しやすくなります。
1-4. 不動産投資会社

ワンストップで物件紹介から管理まで請け負う不動産投資会社に相談するのは、手間を軽減したい投資家にとっておすすめな相談先です。
不動産投資会社は、投資用不動産の販売・仲介を行い、購入後の管理や運用サポートも提供する企業です。資産形成のコンサルティングや融資のアレンジを手掛ける会社もあり、投資家の状況に応じた幅広い支援を受けられます。
投資初心者でもサポート体制が整っている場合が多く、購入後の管理に関しても一定のノウハウが期待できるためです。
たとえば、物件の入居者募集や家賃回収といった管理業務を一括で行ってくれる会社なら、本業が忙しい人でも効率的に資産を増やせるでしょう。
ただし、提供されるサービス内容や手数料体系は各社で異なるため、複数社から見積もりを取り比較する必要があります。
自分に合った不動産投資会社を見つけることができれば、長期的なパートナーとして心強い存在となるでしょう。
1-5. 金融機関
融資を利用して投資を進めるなら、金融機関に相談して適切なローンの選択肢を探ることが大切です。
金利や返済期間、担保評価など、投資の収益性にダイレクトに影響を与える条件を精査する必要があるからです。
たとえば、変動金利ローンを選べば初期コストを抑えられるものの、市場金利の上昇リスクを負う点には注意しなければなりません。
一方で固定金利ローンなら利息は安定しますが、返済総額が変動金利より高くなる可能性もあります。
また、会社経営者の場合、本業とは別に不動産投資で金融機関から資金調達をした場合、本業での資金調達に影響を及ぼす可能性があるので、注意が必要です。
自分のリスク許容度や投資計画に合った資金調達方法を選択することをおすすめします。
1-6. IFA

銀行や証券会社とは独立した立場で顧客の資産運用をサポートしてくれるのがIFA(※)であり、不動産投資でも中立的な意見を得やすい存在です。
特定の金融機関の商品に縛られず、より幅広い選択肢の中から最適な提案をしてもらえる利点があります。
金融機関に相談した場合、自社の商品に偏った紹介をされることがあるかもしれません。しかし、IFAであれば、投資目的に合わせて株式・債券などの金融商品と不動産投資を組み合わせるポートフォリオを提案してくれるケースも少なくありません。
その結果、資産全体でリスクを分散しながら、長期的な収益を狙いやすいのがIFAの魅力でしょう。
IFAに相談することで、単なる物件売買にとどまらない包括的な資産運用プランを組み立てるヒントが得られます。
※Independent Financial Advisorの略で、独立系ファイナンシャルアドバイザーや金融商品仲介業者です。特定の金融機関(例えば、証券会社や銀行)に所属せず、中立的な立場から顧客の資産運用をサポートする専門家です。
2. 不動産投資の相談前に必ず整理しておくべきポイント
不動産投資について相談する前に、整理しておくべきポイントを解説します。
| ポイント | 具体例 |
| 不動産投資の目的 | ・キャッシュフロー狙い・売却益狙い・節税効果 |
| 不動産投資の一般的知識 | ・不動産投資のメリット・リスク・利回り・コスト |
| 自分の資産状況 | ・自分の現在のキャッシュフロー |
それぞれ以下で解説します。
2-1. 不動産投資の目的

不動産投資を始める前には、まず自分が何を達成したいのかを明確にしておく必要があります。
目的が曖昧だと、物件選びや資金計画の基準がぶれやすくなり、無駄な出費や機会損失につながるからです。
具体的には、キャッシュフローを得たいのか、キャピタルゲインを狙いたいのか、あるいは節税効果を重視したいのかをはっきりさせましょう。
たとえば、キャッシュフローを優先するなら立地条件が良い物件を長期保有し、節税を目的とするなら減価償却費が多く取れる築古物件を狙うという選択肢もあります。
事前にゴールを設定すれば、不動産投資の専門家に相談する際も明確な意見をもらいやすくなるはずです。
2-2. 不動産投資の一般知識

最低限の専門用語や市場の仕組みを理解しておくと、相談時に相手の説明をスムーズに理解できます。
知識がない状態だと、契約書やローンの細かい条項を正しく把握できず、思わぬリスクに気づけない可能性があるからです。
たとえば、表面利回りと実質利回りの違い、管理費や修繕積立金の概念、エリア特性による家賃の相場変動などは把握しておく価値があります。
これらの基本的な情報を押さえておくと、相談する際に具体的かつ踏み込んだ質問を投げかけられるようになるでしょう。
不動産投資の専門家とのやり取りが深まり、より的確なアドバイスを得られるようになります。
2-3. 自分の資産状況
自己資金やローン返済に充てられる月々の余裕額など、自分の資産状況を正確に把握しておくことは重要です。
投資に回せる額と生活に支障が出るラインを混同してしまうと、予定外の支出でローン返済が苦しくなるリスクが高まるからです。
また、会社経営の場合、本業が赤字であるにも関わらず、不動産投資でも赤字を出してしまうとさらに資金繰りが悪くなることに繋がります。
そういった事態を回避するには、家計や会社の現状や将来の収支見込みを客観的に把握し、焦らずに投資判断を下すことが大切でしょう。
自分の資産をきちんと整理することで、相談相手からも具体的な提案を得やすくなります。
3. 不動産投資が抱えるリスク

不動産投資をする際に生じる5つのリスクについて解説します。
| リスク | 詳細 |
| 物件選びで失敗するリスク | 購入した物件に需要がなく、資産価値がない |
| 空室リスク | 物件の空室率が高く、家賃収入が減ってしまう |
| 修繕リスク | 外壁補修などで大きな出費が発生する可能性がある |
| 滞納リスク | 家賃滞納によって、入居者との交渉の手間がかかるまた、家賃収入が減ってしまう |
| 売却価格リスク | 購入価格よりも価値が下落することで損失となる |
3-1. 物件選びで失敗するリスク
不動産投資は、購入する物件の選定を誤ると収益が伸びないばかりか、資産価値も想定以上に下落するリスクがあります。
立地や築年数、構造、周辺環境などの要素を総合的に判断できないと、入居率が低迷して家賃収入が得られにくくなるからです。
たとえば、人気のないエリアの物件を安さだけを理由に購入すると、需要が少なく空室が長引く懸念があります。
思わぬ欠陥や修繕コストが必要になるケースもあるため、事前調査や専門家の意見を取り入れることが重要です。
物件選びを慎重に進めることは、不動産投資の成功を左右する鍵とも言えます。
3-2. 空室リスク
家賃収入が途絶えてしまい不動産投資の収益構造を揺るがす要因となります。
入居者がいない期間もローン返済や固定資産税、管理費などの支出は継続するため、キャッシュフローが悪化しやすくなるからです。
たとえば、単身者向けワンルームなら賃貸需要が安定している都市部を選ぶことで空室期間を短縮する工夫ができますし、ファミリー向け物件なら学校や商業施設の有無が大きく影響します。
空室リスクを抑えたいなら、物件購入時にターゲット層を明確にし、賃貸の募集戦略をしっかり考える必要があるでしょう。
適切なエリア選定と魅力的な物件づくりが、空室対策の要となります。
3-3. 修繕リスク
建物は経年とともに老朽化するため、定期的な修繕費を見込んでおかないと予想外の出費が投資計画を圧迫する可能性があります。
屋根や外壁の補修、設備の交換など、大きなメンテナンスが重なると一時的にキャッシュフローが悪化しやすいからです。
たとえば、築古のマンションを購入して数年後に大規模修繕が決定し、思っていた以上のコストを請求されるケースも珍しくありません。
そうした負担を回避するには、建物の状態を事前にしっかり調査し、区分所有であれば修繕積立金の状況、一棟所有であれば修繕履歴の状況や今後の修繕計画を確認しておくことが大切でしょう。
メンテナンス費用を考慮に入れた投資計画を立てることで、安定した収益管理が期待できます。
3-4. 滞納リスク
入居者が家賃を滞納すると、家賃収入が途絶えるだけでなく、回収業務に手間と費用を要する恐れがあります。
適切な審査を行わずに入居を許可してしまうと、長期的に家賃未払いが続き回収不能になるリスクが高まるからです。
たとえば、連帯保証人を設定しないまま契約してしまうケースや、保証会社を利用していない場合はオーナーが直接交渉しなければならない場面もあるでしょう。
こうした手続きを避けるためには、入居希望者の信用力を見極める仕組みと、トラブル発生時に迅速に動ける体制を整える必要があります。
最近では、滞納リスクに備えて保証会社の導入が一般的となっており、リスクヘッジの面でも有効です。
3-5. 売却価格リスク
将来的に売却を検討する場合、購入時よりも相場が下落していれば想定通りの利益を得られないリスクがあります。
不動産の価値は景気変動やエリアの人気度合いに左右されるため、予測が難しいからです。
たとえば、再開発計画が延期や中止になったエリアでは需要が低下し、買い手がつきにくくなるケースもあるでしょう。
購入後のマーケット変化をある程度想定し、中長期保有で家賃収入を得ながら価値向上を図る戦略も検討すればリスクは緩和されやすくなります。
売却価格リスクを念頭に置きながら、投資期間や出口戦略を明確にすることが失敗回避につながるでしょう。
4. 不動産投資で失敗しないための対策
| リスク | 対策 |
| 物件選びで失敗するリスク | 物件を選ぶ正しい観点を持つ |
| 空室リスク | ①空室にしないノウハウを身につける ②サブリース契約を結ぶ |
| 修繕リスク | 事前に専門家に建物リスクを評価してもらう |
| 滞納リスク | 入居者には保証会社への加入を求める |
| 売却価格リスク | 中長期的に保有する |
| リスク全般 | 不動産投資のプロに相談する |
不動産投資で失敗しないための対策を、以下でそれぞれ解説します。
4-1. 物件を選ぶ正しい観点を持つ
投資の成否は物件選びに大きく左右されるため、立地や物件種別、間取りなどの要素を総合的に評価すること不可欠です。
価格だけで飛びついてしまうと、後々の空室や修繕コストで苦労するリスクが高まるからです。
たとえば、都心部の中古マンションは価格が高くても需要が安定しており、結果的に収益を確保しやすいケースが多いでしょう。
一方、地方の築古アパートは購入費が安い半面、エリア次第では長期間の空室が発生する可能性も否定できません。
自分の投資方針やリスク許容度に合った選定基準を作り、複数の物件を比較検討したうえで慎重に判断することが重要です。
4-2. 空室にしないノウハウを身につける
不動産投資で安定収入を得るには、空室期間をできるだけ短くするノウハウが鍵となります。
集客力のある管理会社を選んだり、適切なリフォームを施したりして物件の魅力を高めることで、入居希望者を確保しやすくなるからです。
たとえば、内装をシンプルかつ清潔感あるデザインにしたり、インターネット無料設備を導入することでターゲット層のニーズに合う物件に仕上げる方法があります。
立地が多少不便な物件でも、他物件にはない特色があれば魅力を感じてもらいやすいでしょう。
空室リスクを軽減する取り組みを継続して行うことで、長期的に安定した家賃収入が期待できます。
4-3. サブリース契約を結ぶ
空室リスクを回避する手段として、家賃保証付きのサブリース契約(※)を検討する投資家は少なくありません。
契約期間中は一定の家賃が保証されるため、景気や需要の変動に左右されにくいのが利点です。
たとえば、物件をサブリース会社に一括で貸し出す形をとれば、入居者募集やトラブル対応を代行してもらえるため手間も減らせるでしょう。
ただし、保証賃料が相場より低めに設定されることや、契約更新時に条件が見直されるリスクもある点には注意が必要です。
メリットとデメリットをよく比較し、自分の投資戦略に合ったサブリース利用かどうかを見極めることが大事です。
※賃貸物件を不動産会社が借り上げ、その物件を第三者に転貸する契約です
4-4. 事前に専門家に建物リスクを評価してもらう
購入予定の物件に見えない欠陥や大規模修繕の必要性が潜んでいないか、専門家による調査を依頼することも対策の一つです。
外観だけではわからない構造的な問題がある場合、修繕費が想定以上に膨らむ可能性があるからです。
たとえば、建築士や不動産鑑定士による建物診断を受ければ、耐震性や給排水管の劣化状況などを詳細にチェックしてもらえます。
その結果、後から高額な修繕費を請求される事態を防ぎ、値引き交渉などにも役立てられるでしょう。
物件の安全性を確認しておけば、投資後のストレスや不安を大幅に軽減できます。
4-5. 入居者には保証会社への加入を求める
家賃滞納リスクを抑えるために、入居者に保証会社の利用を案内することは重要です。
連帯保証人がいないケースでも保証会社が間に入ることで、家賃未払い時の補填や回収手続きを代行してくれるからです。
たとえば、若年層の単身者や外国人留学生は保証人を立てにくいことが多く、保証会社を利用することで契約がスムーズに進むケースもあります。
保証料の負担をどちらが持つかといった条件交渉は必要ですが、オーナー側のリスクヘッジとしては非常に効果的です。
安定した家賃回収体制を整えることで、投資の収支管理が一段と堅実になります。
4-6. 中長期的に保有する
不動産投資は、短期的な転売益を狙うよりも中長期保有で家賃収入を積み上げることでリスクを抑えることができます。
価格変動の波をある程度やり過ごしつつ、ローン返済を進めて資産を増やす戦略が王道と考えられるからです。
たとえば、10年以上同じ物件を保有し続ければ、ローンの元本が減る一方で家賃収入は維持されるため、キャッシュフローが拡大しやすくなります。
短期売却を目的とすると、景気後退やエリアの需要変化により、想定通りの利益を得られないリスクが大きいでしょう。
着実に利益を積み上げたいなら、長い目で物件価値を高めながら安定的な収入を確保する方が得策です。
4-7. 不動産投資のプロに相談する
不動産投資に慣れていない場合や迷いが多いときは、専門家からのアドバイスを得ることで不動産投資の計画を明確にしやすいです。
独自に判断して進めると見落としや思い込みが生じやすく、後戻りできない場面で大きな損失を被る可能性が高まるからです。
たとえば、複数の物件で投資実績を持つコンサルタントや、さまざまな不動産会社の情報を扱うIFAなどから意見を聞く方法も考えられます。
自分だけでは情報不足の領域があっても、プロと連携すれば多角的な検証ができるため、投資判断の精度は上がるでしょう。
最終的に、専門知識を活用することでリスクコントロールもしやすくなり、安心感を高めながら投資を進められます。
5. まとめ
不動産投資において失敗を避け、安定した利益を得るためには、相談先の選択や事前準備が極めて重要です。
それぞれの専門家や投資家が異なる視点とノウハウを持っているため、複数の情報を組み合わせることで総合的に判断しやすくなります。
実際に投資目的や資産状況を整理してから話を聞けば、より具体的なアドバイスを引き出せるでしょう。
さらに、利回り計算やリスク対策などの基本を押さえたうえで行動すれば、物件選定や運営方針を決める際の迷いが減るはずです。
さまざまな視点と知識を積み重ねながら、一歩ずつ堅実に不動産投資の成功を目指してみてはいかがでしょうか。
IFAのファーストパートナーズでは、相続対策やキャッシュフロー拡大、資産規模拡大や、償却・節税、所有目的のため、資産防衛など、不動産を軸にしてさまざまな提案が可能です。不動産投資でお困りの方は、一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
