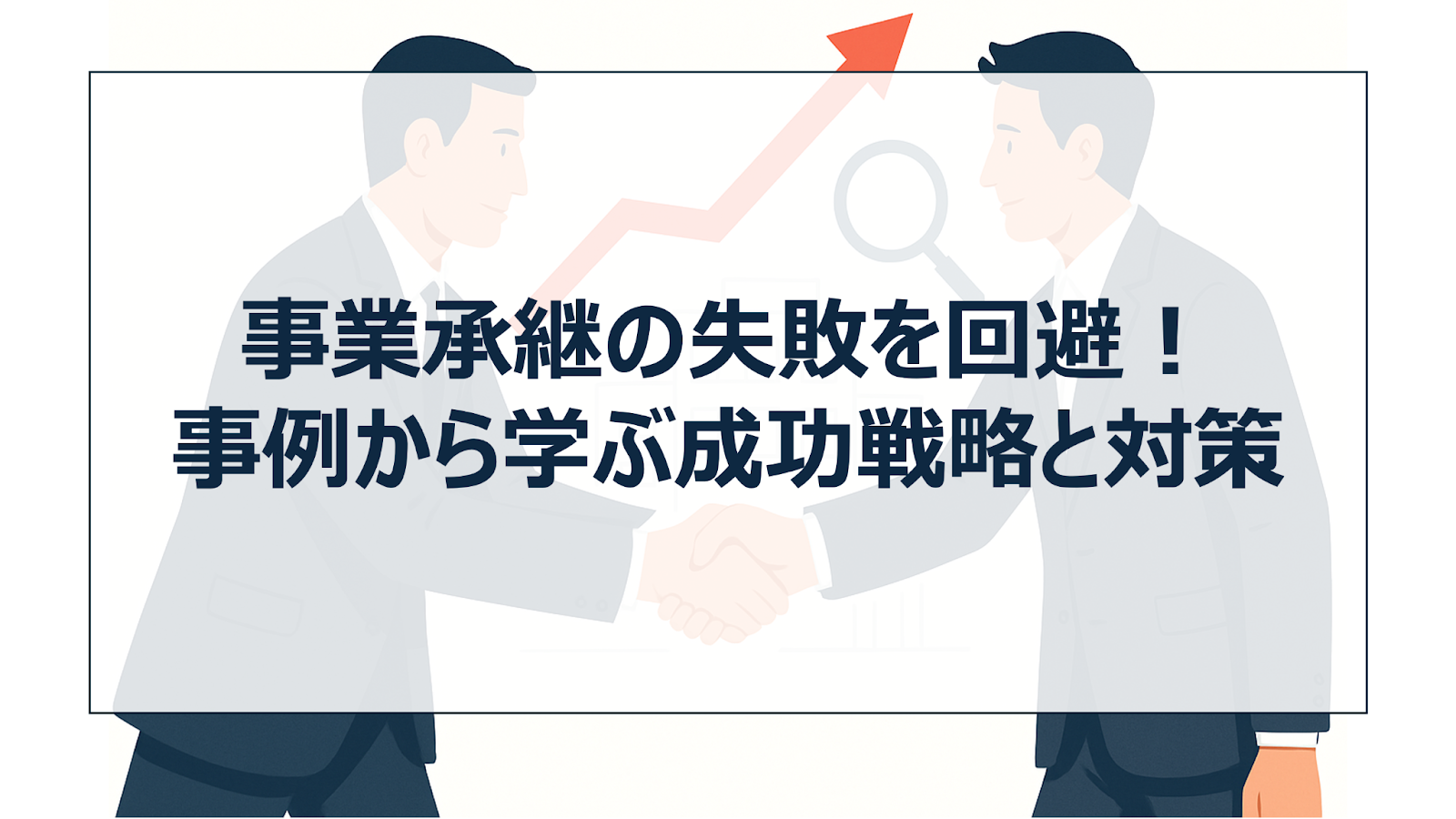
- 事業承継の失敗を回避したいけど、どうすればいいか分からない
- 事業承継の失敗事例について知りたい
- 事業承継の失敗要因とその対策について知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
本記事では、事業承継の失敗回避策について解説します。
1. 事業承継の失敗とは
事業承継の失敗とは、経営者から後継者への権限移譲が適切に行われず、企業が継続的に運営できなくなる状態を指します 。
これは、後継者選定の誤りや引継ぎ期間の不足、関係者間の情報共有不足などが背景にあります。
例えば、社長が急逝し、後継者に十分な準備がないまま代表に就任せざるを得なくなるケースが考えられ、この場合、後継者は企業文化や事業内容を把握しきれておらず、社内が混乱してしまうことがあります。
そのような事態を防ぐためには、事前の準備と関係者間の綿密なコミュニケーションが不可欠です。
適切な計画があれば、失敗リスクを大きく軽減できるでしょう。
2. 事業承継の失敗事例6選
事業承継の失敗事例について解説します。
- 計画不足が社内の混乱を招いたケース
- 後継者が経営権を確立できなかったケース
- 社内の対立により後継者が孤立・排除されたケース
- 後継者が見つからず事業継続が困難になったケース
- 内部分裂が会社資産の流出を招いたケース
- 前経営者が引退後も強い影響力を持ち続けたケース
2.1 計画不足が社内の混乱を招いたケース
計画不足による社内の混乱は、事業承継が円滑に進まない典型的な事例です。
新経営者への引継ぎ内容が曖昧だと、従業員は何を優先して動くべきか判断に迷います 。
例えば、明確なスケジュールや引き継ぎマニュアルがなかったことにより、今までと異なる方針を示してしまい、混乱が生じるケースが考えられます 。
こうした状況では、業務効率が低下し、従業員の不安や離職が発生しやすくなります 。
したがって、詳細な承継計画を策定し、双方で認識を合わせることが重要です 。
2.2 後継者が経営権を確立できなかったケース
後継者が正式な経営権を確立できないまま承継が進むと、組織内に明確なリーダーが不在の状態が生まれます。
これは、株式や議決権の移譲が不十分であることが理由となる場合が多いです。
例えば、親族内承継で株式の分散が解消されず、新旧オーナーが同時に意思決定権を行使するケースなどが想定されます。その結果、経営判断が二転三転し、取引先や従業員からの信頼を失う恐れがあります。
経営権移譲の手続きを早期に完了させ、明確な権限区分を設定する必要があります。
2.3 社内の対立により後継者が孤立・排除されたケース
社内の派閥対立が後継者の孤立や排除を招くことがあります。
これは、株式や役職を巡る親族間トラブルが引き金になることが多いです。
例えば、新経営者の権限を快く思わない一部の従業員が、旧経営者側に寄り集まり圧力をかけるケースが考えられます。こうした状況では、後継者が孤立し、結果的に経営判断に関与できなくなる恐れがあります。
親族や幹部との事前調整を徹底し、対立を未然に防ぐことが重要です。
2.4 後継者が見つからず事業継続が困難になったケース
後継者不在の企業は将来的に廃業を余儀なくされます。
地方の中小企業では、頼みの後継者候補の子供たちは都市部に移住し、他の親族にも従業員にも承継できる者がいないケースがあります。都市部への人口流出が続いている現状からすると、これは今後も増加していくと考えられます。
こうなると、企業の資産や技術が地域社会から失われる恐れがあるため、第三者承継やM&Aの活用を早期に検討する必要があります。
2.5 内部分裂が会社資産の流出を招いたケース
社内派閥争いが資金流出を引き起こす場合があります。
これは、株式を持つ親族間で派閥が形成されることが背景にあります。
例えば、長男派と次男派に分かれ、次男派が退職時に多額の退職金や株式買い取り請求を行うケースが考えられます。その結果、企業の運転資金が枯渇し、日常的な経営に支障を来す恐れがあります。
株式構成や退職条件を事前に調整し、過度な資金流出を防ぐことが求められます。
2.6 前経営者が引退後も強い影響力を持ち続けたケース
前経営者が退任後も経営に介入すると、新経営者の判断が揺らぎます。
例えば、定年退職した社長が経営会議に参加し続け、新方針を覆すケースが想定されます。このような介入は、従業員に混乱をもたらし、新体制への信頼を損なう恐れがあります。
退任後の役割を明確にし、運営から距離を置いてもらう取り決めも必要です 。
3. 事業承継が失敗に終わる主な5つの要因
事業承継が失敗に終わる5つのおまな要因を解説いたします。
- 後継者選定の誤り
- 計画の不備
- コミュニケーション不足
- 社内分裂
- 外部環境の変化への対応不足
3.1 後継者選定の誤り
後継者選定の誤りは、能力や意欲を見誤ることで生じます。
十分な資質や経験を持たない人を選ぶと、経営が停滞する可能性があります。
例えば、親族の情で決めたものの、経営経験が乏しく組織をまとめられないケースが考えられます。必要な外部研修や社内の指導体制が間に合わなかったり、重要な意思決定の場面で判断を誤ったりし、社内に混乱を招く可能性は高いでしょう。
適性を見極めた上で候補者を複数挙げ、育成期間を設けることが重要です。
3.2 計画の不備
計画の不備は、時期や内容の曖昧さが原因です。
実行スケジュールが不明確だと、関係者の準備が追いつかなくなります。
例えば、承継時期を決めずに準備だけ進めていた場合、事業環境が急変して計画が形骸化するリスクが想定されます。こうなると、計画をリアルタイムで修正できず、承継失敗のリスクが高まります。
具体的な期限とマイルストーンを設定し、定期的にスケジュールを見直す必要があります 。
3.3 コミュニケーション不足
関係者間で目標や課題が共有できないと、承継後に齟齬が生じやすいです。
例えば、新旧の経営者間で事業ビジョンが異なり、後継者がこっそり異なる方針を進めたケースが考えられます。これは、従業員からの信頼を損ない、内部分裂に発展する恐れがあります。
定期的なミーティングやワークショップを通じて、情報を透明化することが大切です。
3.4 社内分裂
社内分裂は、勢力争いが引き金となる場合があります。
派閥間の対立が激化すると、後継者が孤立しやすくなります。例えば、株式保有比率を巡って社内派閥が対立し、経営意思決定が停滞するケースが考えられます。
結果として、投資判断や業務執行が遅れ、市場競争力を失う恐れがあります。公平な手続きと外部監査を導入し、リスクを軽減しましょう。
3.5 外部環境の変化への対応不足
外部環境の変化を見落とすと、計画が時代の流れにそぐわなくなる可能性があります。
市場動向や法規制の変化に適応できないまま承継すると、業績が悪化するかもしれません。例えば、デジタル化の波に乗り遅れ、旧来のビジネスモデルに固執したケースが想定されます。
こうなると、新経営者は短期間で大幅な改革を迫られ、その結果従業員の反発を招く恐れがあります。定期的に環境分析を行い、計画に反映させることが求められます。
4. 事業承継の失敗を未然に防ぐ対策
以下の対策を講じることで、失敗リスクを大幅に軽減できます。
- 早期からの計画策定と準備
- 後継者育成
- 関係者との円滑なコミュニケーション
- 専門家への相談と活用
4.1 早期からの計画策定と準備
早期の計画策定は、段階的な準備を可能にします。
承継時期の数年前から準備を始める企業は、準備不足による混乱を避けられる傾向にあります。
例えば、中小企業庁のガイドラインを参照しながらマイルストーンを設定するケースが効果的です。準備期間中に必要な法務・財務チェックを進めることで、後継者は安心して経営に専念できます。
適切なタイムラインを設け、お互いに進捗を共有することが重要です。
4.2 後継者育成
後継者育成は、実務経験やリーダーシップ研修を通じて行います。
OJTや外部セミナーを組み合わせることで、経営判断力を養えます。
例えば、取引先訪問や財務分析の実践を通じて、経営感覚を身につけるプログラムが有効です。育成計画を定期的に見直し、フィードバックを行うことで成長を促すことができ、結果として、後継者は自信を持って経営に臨めるでしょう 。
4.3 関係者との円滑なコミュニケーション
定期的な会議やワークショップで情報共有を徹底するようにしましょう。
また、全従業員向け説明会やQ&Aセッションを設けると、不安解消につながります。新経営者のビジョンや承継プロセスを丁寧に説明し、透明性を高めることで、従業員の理解と協力を得やすくなります。
継続的にコミュニケーションチャネルを維持することが大切です。
4.4 専門家への相談と活用
税理士や弁護士などの専門家は、複雑な手続きをサポートしてくれます。
また、M&A仲介会社を活用すると、第三者承継のマッチングがスムーズです。専門家との定期的な打ち合わせでリスクを早期に発見できます。
外部の目線を取り入れることで、計画の精度が向上するでしょう。
5. 後継者不在・不安がある場合の事業承継
以下の解決策を検討しましょう。
- M&A(第三者承継)による解決策
- 従業員への事業承継を検討する
5.1 M&A(第三者承継)による解決策
第三者承継は、後継者がいない場合に有力な手段といえます。
企業価値評価に基づく公正な価格設定が重要となります。例えば、同業他社への売却により、従業員雇用を維持しながら承継を実現するケースがあります。
M&Aアドバイザーを通じて適切な買い手を選定することで、条件交渉が円滑になります。外部ノウハウを取り入れることで、承継後の成長も見込めるでしょう。
5.2 従業員への事業承継を検討する
従業員への承継は、企業文化を維持しやすいといえます。
従業員持株会やストックオプションを活用すると、経営参画意欲を高められます。例えば、コーポレートガバナンスを整備し、従業員代表を取締役に登用するケースがあります。
内部の人材育成体制が整っていれば、外部人材を後継者とする場合に比べて、よりスムーズに移行できる可能性があります。安定的な承継と企業価値向上を両立できる手法といえます。
6. 事業承継の失敗を回避するための相談先
事業承継の失敗を回避するための相談先として、以下の専門機関の活用を検討しましょう。
- 金融機関
- 税理士・弁護士
- M&A仲介会社
6.1 金融機関
金融機関へは、納税資金などの資金調達面で相談するといいでしょう。
融資条件や返済シミュレーションを専門家と相談しながら策定するのがポイントです。例えば、長期固定金利ローンを組むことで、承継後の負担を軽減できます。
条件交渉にあたっては、事前に事業計画を具体化しておくと有利になります。地域金融機関と連携を強化し、地元企業としての信頼を高めましょう。
6.2 税理士・弁護士
税理士は相続税・贈与税の対策をサポートしてくれます。
また、弁護士は契約書作成や株式移転手続きで法的リスクを低減してくれるでしょう。
例えば、事業承継税制を活用した特例適用の申請サポートを受けるなど、専門家の指導を得ながら、円滑に手続きを進めましょう。
定期的な顧問契約を結び、継続的なサポートを得るのが望ましいといえます。
6.3 M&A仲介会社
M&A仲介会社は、買い手候補の発掘から交渉まで一括で支援します。
市場動向や類似事例の知見を提供し、最適な条件でマッチングを実現します。
さらに、非公開情報の取り扱いや交渉プロセスにおいても、秘密保持契約(NDA)の締結をはじめとした管理体制を整備し、安全な取引環境を構築します。法務面を含めた包括的な支援によりスムーズな交渉が可能となります。
信頼できる仲介会社を選ぶことで、成功確率が高まるでしょう 。
7. まとめ
本記事では、事業承継の失敗事例を紹介し、主な要因と対策を体系的に解説しました。
早期の計画策定や後継者育成、関係者との円滑なコミュニケーション、専門家の活用が成功の鍵となります。
加えて、後継者不在時にはM&Aや従業員承継といった代替手段も視野に入れることが重要です。信頼できる相談先の助言を受けながら準備を進めることで、事業承継の成功率を大きく高められるでしょう。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添った事業承継のご提案を行っております。お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。
ご相談はこちらから。

