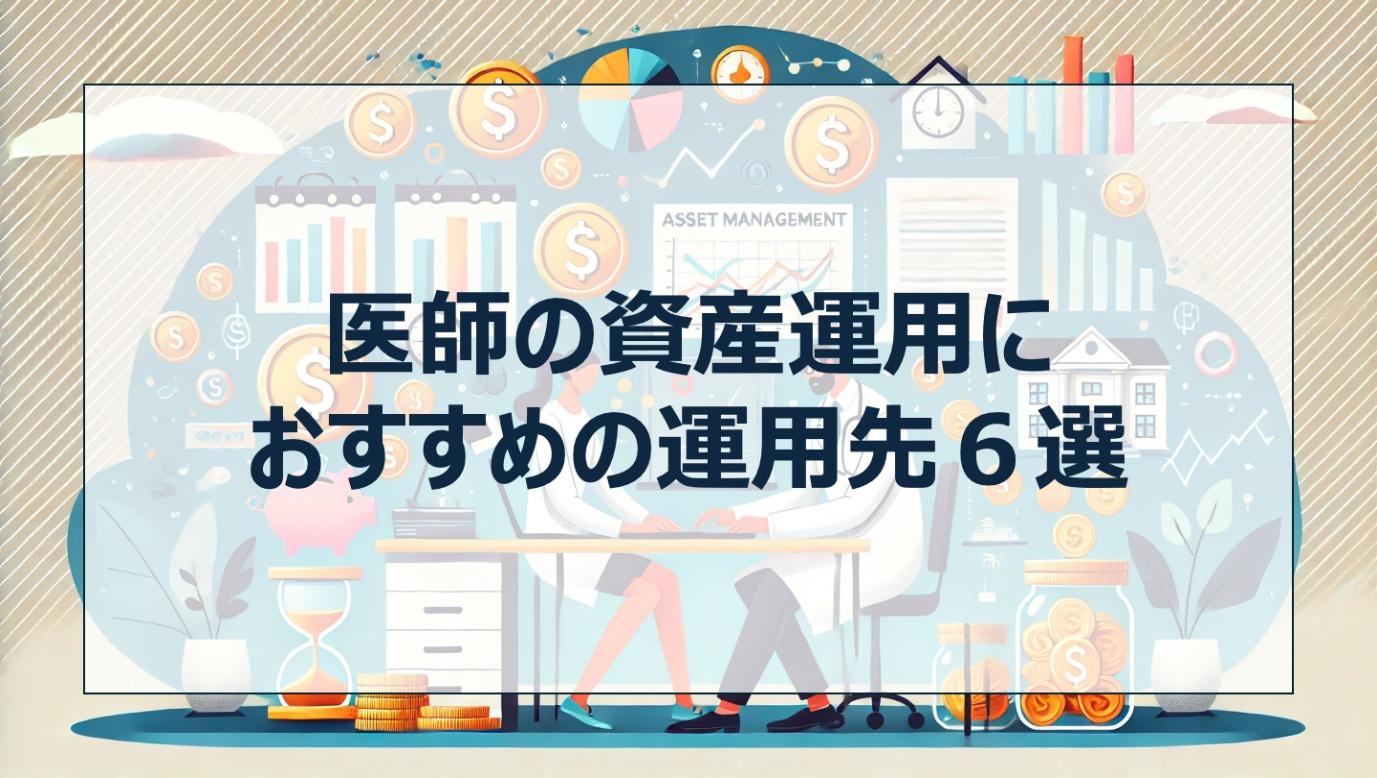
- 医師に向いている資産運用方法が分からない
- 勤務医と開業医における資産運用の違いがあるのか知りたい
- 医師の資産運用でよくある失敗と対策を教えて欲しい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。資産運用のプロが、医師の資産運用について解説します。
この記事を読むと、医師の資産運用に関する不安を解消でき、医師に適切とされる資産運用ができるでしょう。
1. 医師に向いている資産運用とは?高収入だからこそ知っておきたいポイント
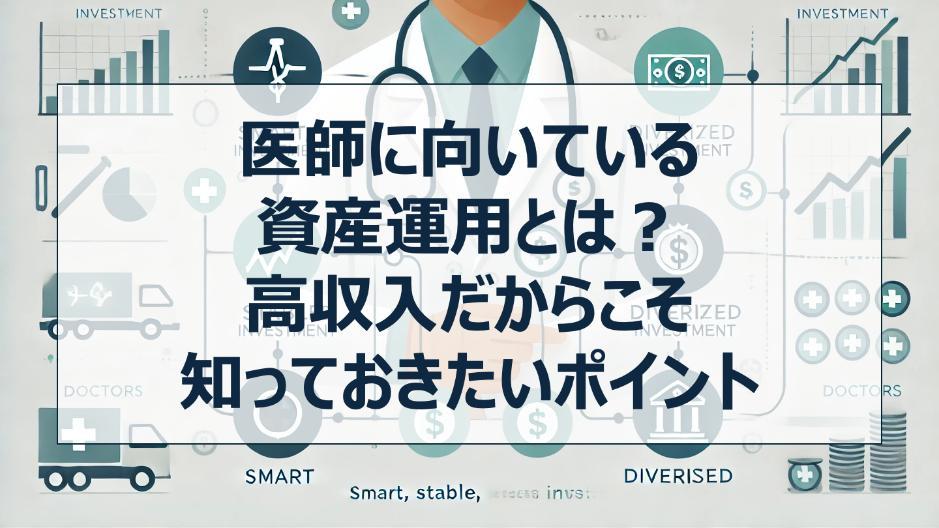
医師は専門性の高さにより比較的高収入であることから、他業種と比較して余裕資金を確保しやすい一方で、勤務時間が長く、資産運用に充分な時間を割きにくいという傾向があります。
そのため、運用先の選定にあたっては、税や日常的な管理のしやすさが重要な判断材料となります。これらは運用方法を選ぶ際の基本でもあり、失敗を避けるために慎重に検討すべきポイントです。
ここでは以下の2つの観点から医師にとって適した資産運用手法を解説します。
- 課税負担と軽減策の重要性
- 管理しやすい運用方法
以下でそれぞれを解説します。
1-1. 課税負担をいかに抑えるか
所得が増えるほど税率も上がる累進課税のもとでは、高収入である医師にとって課税負担が重くなる傾向にあります。
そのため、税金対策が資産運用を行う上で重要な要素となり、運用利益を非課税または低く抑えられる制度の活用が有効な選択肢となります。
例えば、新NISA(小額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの税制優遇制度を利用すれば、本来であれば課税対象となる所得や運用の一部を一定の条件下で非課税とすることが可能です。
こうした制度を上手く取り入れることで、医師としての収入を活かしながら、将来に向けた資産形成をより効率的に進めることができるでしょう。
1-2. 管理しやすい運用方法を選ぶのが鍵
医師は多忙な日常業務に追われることが多く、投資の管理に十分な時間を割くのが難しいケースも少なくありません。
したがって、シンプルで自動化された運用方法を選ぶことが、投資の継続性を高めるために重要なポイントです。
例えば、定期積立や再投資で投資信託を購入すると、個別のタイミングを見極める手間を省けます。相場の変動に一喜一憂することなく長期的な資産形成を目指せる仕組みを構築することで、忙しい医師でも無理なく資産運用を継続できる環境が整いやすくなると考えられます。
2. 医師におすすめの資産運用6選
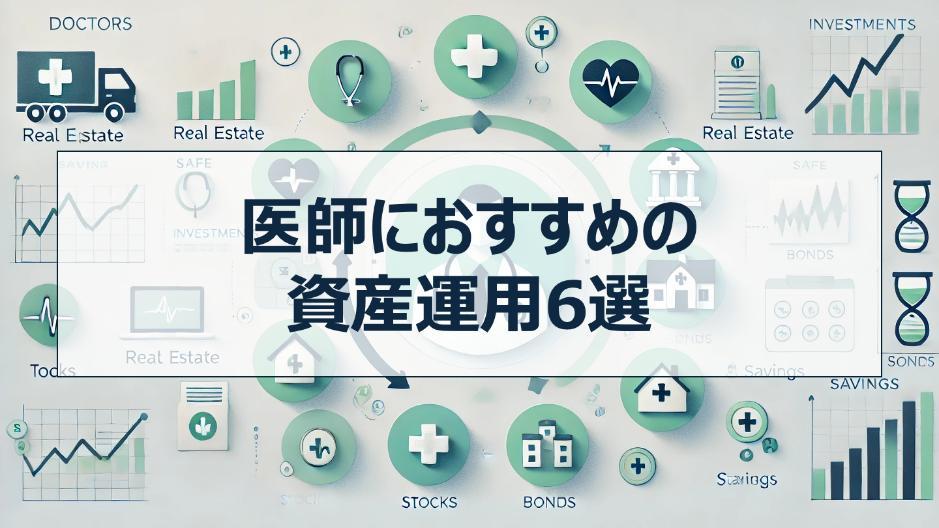
医師が資産運用方法を選ぶ際は、リスクとリターンのバランスが取れていることに加え、課税負担が少ないことや管理のしやすさを兼ね備えていることも重要なポイントです。ここでは、医師におすすめの資産運用を6つ紹介します。
- 株式投資
- 債券
- 投資信託
- 保険
- 確定拠出年金(iDeCo)
- 不動産投資
以下で、それぞれについて解説します。
2-1. 株式投資
株式投資は、企業の成長性に伴う値上がり益(キャピタルゲイン)や配当収入を通じて資産の増加を目指す運用方法です。
たとえば、安定した配当を出している企業の株式と国内外の大手企業の株式をポートフォリオに一定割合組み入れることで、市場全体の成長による恩恵を受けやすくなるでしょう。
2-2. 債券
債券は、満期まで保有していれば額面金額が戻ってくる仕組みのものが多く、安定した利子収入が得られるため、比較的リスクの低い金融商品と言われています。
たとえば、長期にわたり固定金利が支払われる債券を保有することで、市場変動の影響を受けにくい運用が可能となります。複数の債券を組み合わせることで、投資リスクのさらなる軽減を図ることにもなるでしょう。
リスク回避を重視する方にとって、債券投資は安定性を重視した資産運用の選択肢として適しています。
2-3. 投資信託
投資信託は専門家が分散投資を行うので、個人で銘柄選定を行う手間が省け、時間的制約の多い医師にとって魅力的な選択肢といえるでしょう。
毎月一定額を自動で積み立てることで、購入タイミングを分散し、取得単価を平均化する効果も期待できます。
このような手法は「ドルコスト平均法」と呼ばれ、価格変動リスクの低減や、投資タイミングを気にしなくてよいといったメリットがあるとされており、忙しい医師にとっても無理なく継続できる運用手段の一つとしておすすめです。
2-4. 保険
保険商品、特に貯蓄性のある終身保険や養老保険は、単なる保障機能にとどまらず、資産運用と税負担の軽減の両面から活用が検討できます。
高所得層である医師の場合、所得税や住民税の負担が相対的に大きくなりやすいため、保険料控除による税務上の優遇を意識するケースもあります。
例えば、一定期間が経過した後に解約返戻金が増加する仕組みを活用すれば、老後資金の準備としても有効な手段となるでしょう。実際に、掛け捨て型の保険を見直して貯蓄型保険に切り替えることで、将来の資産形成と税効果の改善を図る方もいます。
このように、保険商品は保障性と資産形成の両立を目指す医師の資産運用における有力な選択肢のひとつとなり得るでしょう。
2-5. 確定拠出年金(iDeCo)
確定拠出年金、特に個人型確定拠出年金(iDeCo)は、老後資金の準備に特化した制度として医師にもおすすめです。
掛金の全額が所得控除の対象となるため、税負担の軽減が期待できる点が最大の魅力です。
雇用形態により拠出できる金額の制限はありますが、その金額分は所得控除の対象とすることができるため、所得税・住民税の軽減効果があります。
さらに、運用益も非課税であるため、長期間にわたって再投資を行えば複利効果も期待できるでしょう。
このようにiDeCoは将来に向けた安定的な資金形成を意識する方にとって有力な制度の一つといえるでしょう。
2-6. 不動産投資
不動産投資は、家賃収入(インカムゲイン)や売却益(キャピタルゲイン)を通じて収益を目指すことができるほか、税務上の優遇措置を活用できる場合もあるため、有効な資産運用の手段として検討される運用先です。
とくに医師のように信用力の高い職業では、ローン審査も比較的有利に進む場合が多く、収益物件を取得しやすい環境にあるといえるでしょう。具体例として、賃貸物件を所有し管理会社に委託することで、手間を抑えつつ収益を得ているケースも報告されています。
また、不動産は相続税評価額を圧縮しやすいという特性があるため、相続対策の一環としても検討できます。このように、不動産は収益性と資産保全の両面を意識する医師にとって効果的な資産運用方法として位置付けられます。
3. 勤務医と開業医における資産運用とポートフォリオの違い
勤務医と開業医は、収入源や業務形態に大きな違いがあるため、資産運用の戦略やポートフォリオの組み方にも差が生じます。
どちらの場合も長期的な視点での資産形成が必要ですが、具体的な運用先や管理手法には特色があるため、両者の違いを理解することが大切です。
- 勤務医:安定収入を活かした積立運用と長期的な資産形成
- 開業医:収入変動や事業リスクを考慮した運用と法人活用
- 両者共通の注意点:税金対策・ライフステージ別の設計
以下でそれぞれについて解説します。
3-1. 勤務医:安定収入を活かした積立運用と長期的な資産形成
勤務医は日々の給与収入が安定しているため、毎月一定額を積み立てる資産運用が現実的な戦略として有効となるでしょう。
安定した収入を背景に、積立投資や自動引き落としによる運用がしやすい点は、投資のタイミングに悩まずに済むという意味でも、長期的な資産形成に適していると考えられます。
たとえば、勤務医がつみたてNISAや投資信託を利用して、毎月決まった金額を自動で投資する手法は、実際に継続的な資産形成に繋がっている事例も見受けられます。
将来の退職後の備えとして資産の土台を築く上でも有効であり、安心して資産運用を継続しやすいといえます。
3-2. 開業医:収入変動や事業リスクを考慮した運用と法人活用
開業医は、事業収入の変動や経営リスクを抱える為、個人での資産運用に加えて、医療法人を活用した投資戦略を検討すると良いでしょう。
ただし、医療法人による投資活動には一定の制限や注意点があるため、節度をもった運用が求められます。医療法上、医業の継続を妨げない範囲での資産運用は認められており、安全性の高い投資については、医療法人で取り入れられている場合もあります。
開業医においては、医療法人という枠組みを適切に活かした運用戦略が、将来の資産形成に寄与する可能性があると考えられます。
なお、実際の運用にあたっては税理士や専門家の助言を得ながら進めることが重要です。
3-3. 両者共通の注意点:税金対策・ライフステージ別の設計
勤務医と開業医の双方に共通して重要なのは、税負担の軽減やライフステージに合わせた資産運用設計をすることです。
高収入であるがゆえに所得税や住民税の負担が重くなりやすいため、新NISAやiDeCoなどの制度を上手く活用することで、税効率を改善できる可能性があります。
また家族構成や今後のライフイベントに応じて運用計画を立てることで、過度なリスクを回避しながらも確実な資産形成を実現できる可能性が高まります。つまり、どちらの働き方でも、個々の状況に応じたポートフォリオの最適化が、資産運用を成功へと導く鍵となるでしょう。
4. よくある失敗とその対策
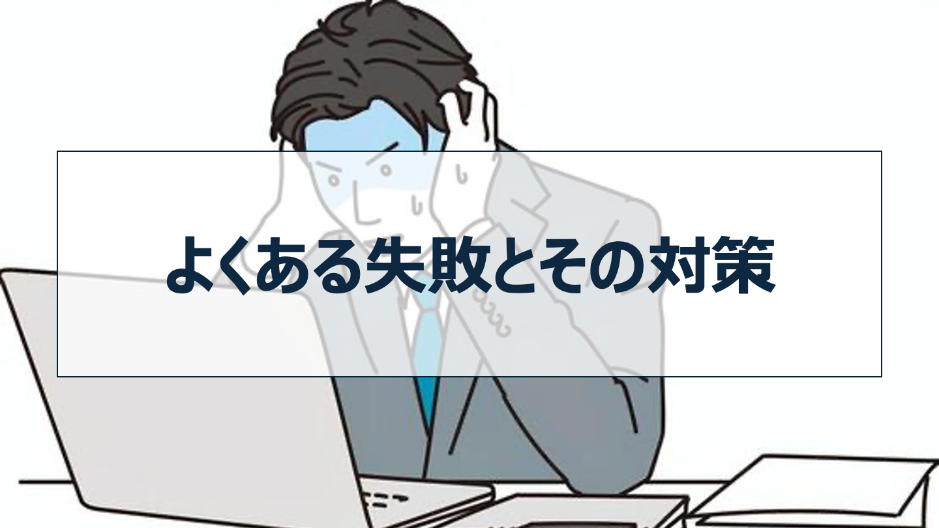
資産運用における失敗には単一の原因だけでなく、複数の要因が絡み合っている場合が多いです。
比較的多く見られる代表的な失敗例は以下の4つです。失敗を未然に防ぐためには、正確な知識と冷静な判断力が重要です。
- 節税目的で高額な保険に偏る
- 知識が不十分なまま投資を始めてしまう
- 他人からの投資話に安易に乗ってしまう
- 運用状況を長期間見直さず放置してしまう
以下で、それぞれの失敗について解説します。
4-1. 節税目的で高額な保険に偏る
高額な保険商品にばかり資金を割いてしまうと、必要以上にコストが嵩み、資産運用全体のリターンが低下する恐れがあります。
高所得である医師の場合、節税効果を狙うあまり、リスク分散が不十分な高額保険に偏るケースが挙げられます。
たとえば、保険料控除を狙いながらも契約手数料や解約返戻金が悪影響を及ぼすことがあるため、十分な検討が必要となるでしょう。
その対策としては、保険以外の運用先とのバランスを考え、全体のポートフォリオ内での適正な比率を維持することが重要です。
結論として、節税効果を狙いつつも、保険に偏りすぎない多角的な資産運用が必要となっています。
4-2. 知識が不十分なまま投資を始めてしまう
十分な知識や情報収集をせずに資産運用を始めると、市場の急激な変動やリスクの高い商品による損失といったトラブルに直面する可能性があります。
医師は本業が多忙であるため、投資に関する知識を習得する時間が確保しづらく、準備が不十分なまま運用を始めてしまうケースも少なくありません。
例えば、手数料やリスクを正確に理解しないまま投資を実行してしまい、後から損失が発覚するといった事例も報告されています。まずは基礎知識を身に着け、信頼できる専門家やアドバイザーに相談しながら投資を進めることが重要な対策となるでしょう。
4-3. 他人からの投資話に安易に乗ってしまう
周囲や勧誘業者からの「今が買い時」といった話に飛びついてしまうと、自分の資産運用方針やリスク許容度と合わない投資案件に手を出してしまう危険性があります。
実際に、無理な投資話に乗り、大幅な損失を経験した例は決して少なくありません。
例えば、口コミや宣伝文句に惑わされて本質的なリスク分析をせずに投資し、後に予想外の下落で大きな損害を被ったケースが挙げられます。
こうした失敗を防ぐためには、必ず自分自身で情報を確認し、判断材料を整理した上で投資を行うことが必要となります。
他人の意見を鵜呑みにせず、しっかりと自分の資産運用計画に合致するかを検証して判断する姿勢が大切です。
4-4. 運用状況を長期間見直さず放置してしまう
資産運用は一度設定して終わりではなく、定期的な見直しが不可欠です。
市場環境や自身のライフステージの変化に応じた調整を行わずに放置してしまうと、せっかくの運用効果が最大限に発揮されず、結果として資産の増加が停滞してしまう可能性があるからです。
たとえば、長期間同じポートフォリオを維持していると、市場の構造変化に対応できずにリスクが偏る場合があるため、定期的な資産の再評価が必要です。定期的に資産運用状況をチェックし、必要に応じたリバランスを実施することをおすすめします。
5. 医師の資産運用は専門家に相談すべき?
資産運用は専門的な知識や最新の市場動向の理解が求められる場面も多くあり、医師自身が全てを独力で判断するのは現実的に難しいケースも少なくありません。
信頼できる専門家のアドバイスを受けながら投資を進めることで、無理のない運用計画が立てやすく、失敗リスクを低減することにも繋がります。
具体的には、以下の専門家との相談をおすすめします。
- 銀行
- 証券会社
- IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
以下でそれぞれについて解説します。
5-1. 銀行
銀行は長年の実績と信頼性を背景に、預金や債券、さらには各種金融商品の相談窓口として資産運用初心者でも利用しやすい存在です。とくに定期預金や個人向け国債は、手続きが比較的シンプルで、リスクを抑えた運用を希望する方にとっても取り入れやすい商品です。
実際、こうした商品を利用して、資産の一部を安全性重視で保有することにより、急な資金ニーズに対応しやすい体制を整えている例も見受けられます。
銀行での相談は、信頼性の高いサービスや商品提供を受けられる点に加え、資産運用の基盤づくりにも役立つため、基本的な相談先の一つとして有用です。
銀行を活用することで、リスク管理や流動性の確保といった点でバランスの取れた運用が実現しやすいといえます。ただし、株式の運用が出来ないなど、購入できる商品が限られる点には注意が必要です。
5-2. 証券会社
証券会社は、株式や投資信託など幅広い金融商品を取り扱っており、それに加え市場の最新情報や運用戦略に関する情報提供を行っています。
高所得層であり、多忙な職業である医師が、資産運用の幅を広げるための情報源や助言の窓口として、証券会社を活用することは有用な選択肢の一つとなるでしょう。
例えば、各種市場レポートやアナリストによるリサーチ資料を活用しながら、自分のリスク許容度や目的に合った投資先の選定がしやすくなる点もメリットの一つです。
証券会社のサポートを受けることで、医師のような多忙な方でも、判断に役立つ材料を得ながら無理のない資産運用を進める一助となる可能性があります。
5-3. IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
IFAは、銀行や証券会社と異なり、特定の金融機関に縛られることなく、より中立的な立場からアドバイスを提供するため、個々の医師の状況に合わせた最適なポートフォリオ設計が可能です。
IFAに相談することで、税制優遇制度の活用や市場動向に沿った効率的な資産配分など、専門的な視点がもたらすメリットを享受できます。
IFAのアドバイスを受けることは、医師にとって専門的かつ中立的な資産運用のサポートを得るための有力な手段となり、結果的に安心して資産運用を進めるための鍵となるでしょう。
6. まとめ
医師として高収入を活かしながらも、将来の不確実性に備えて資産運用を実施することは、重要なライフプランの一部です。
これまで紹介した内容は、税効率の向上や運用管理のしやすさに加え、勤務医と開業医それぞれの特性に応じた運用戦略の違いを踏まえた、適切なポートフォリオ設計の必要を示しています。
具体的には、株式、債券、投資信託、保険、確定拠出年金(iDeCo)、不動産投資といった選択肢を、目的やリスク許容度に応じてバランス良く組み合わせることが、安定した資産形成を支える一つの方法と考えられます。また、定期的な見直しを行うことや信頼できる専門家と連携することで想定外のリスクを回避しやすくなるでしょう。
さらに、自分自身のライフステージや家族構成、価値観に合わせた柔軟な運用戦略と、信頼できるアドバイザーとの協力関係を構築することによって、医師としてのキャリアと個人の財務面をともに支える資産運用が実現しやすくなります。
IFAのファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添った資産運用のご提案をしております。医師が行う資産運用について、お客様の状況に合わせて、的確にサポートいたします。
これを機に一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
