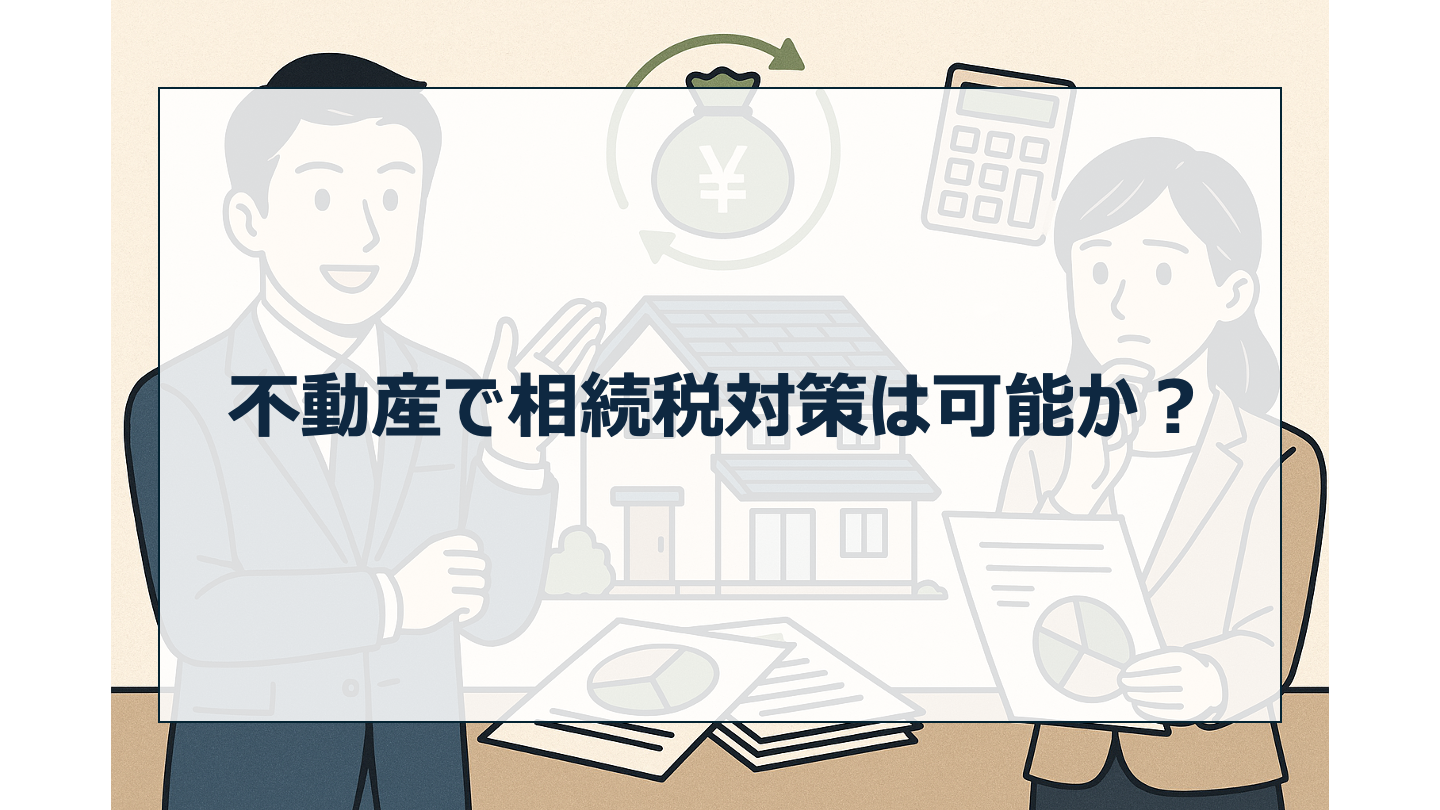
- 不動産で相続税対策ができるのか分からない
- 相続税対策に有用な不動産の特徴について知りたい
- 不動産で相続税対策する際の注意点を知りたい
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
不動産のプロが、不動産を使った相続税対策について解説します。
この記事を読むと、不動産の相続税対策に関する悩みを解消でき、相続税を抑えられるでしょう。
1. 不動産が相続税対策に役立つ理由
なぜ不動産が相続税の節税効果に役立つのかという疑問を持たれる方がいるかと思います。不動産が相続税対策に役立つ理由について解説します。
- 現金を不動産へ換えることで評価額が低くなるケースがある
- 不動産を第三者に貸し出すことで活用できる評価減の仕組み
- 借入を併用することで資産評価額をさらに圧縮できる方法
以下で各仕組みを順に見ていきましょう。
1-1. 現金を不動産へ換えることで評価額が低くなるケースがある
現金を賃貸用不動産に替えるだけで相続税評価額を圧縮できるケースがあります。
というのも、土地や建物は時価ではなく、路線価・固定資産税評価額で算定され、エリアにもよりますが低く評価されるケースがあるからです。
例えば時価1億円の土地が、路線価評価で7,000万円と認定されるケースが挙げられます。
また新築建物は工事費の60%前後で評価されるため、現金を建物建設に充てるだけで約40%の評価減が期待できるでしょう。
この評価ギャップにより、本来の資産価値を損なわずに相続税負担を軽減できるのが大きなメリットとなります。
1-2. 不動産を第三者に貸し出すことで活用できる評価減の仕組み
不動産を第三者に貸し出すことでも相続税評価額を圧縮できます。
建物を貸家にすると、借家権割合(概ね30%)が評価額から控除され、さらに土地が貸家建付地として20%程度評価減されます。
具体例として、固定資産税評価額1.8億円の建物を賃貸に出すと、さらに30%控除で1.26億円まで評価額を下げられる可能性があります。
さらにその土地部分も貸家建付地扱いとなり、約20%引き下げが可能となるでしょう。
建物と土地の二重の評価減を組み合わせることで、評価額の大幅圧縮が期待できます。
1-3. 借入を併用することで資産評価額をさらに圧縮できる方法
不動産取得時に借入金を活用すると、借入金は相続税上マイナス評価として控除されます。
相続税評価額は債務を差し引いた純資産額で評価が行われるため、資産総額を減らせるからです。
例えば1億円借り入れを利用した場合、その分だけ相続財産の評価額が圧縮されます。
ただし返済能力や利回りを考慮しないと返済不能リスクを抱えるため、収支計画を立てておくことが大切です。
返済計画を綿密に立て、リスクマネジメントを徹底することで、借入による節税効果を受けられるでしょう。
2. 相続税対策に有効な不動産の特徴
次に、節税効果を最大限発揮するために選ぶべき不動産の条件を確認しましょう。
- 時価と相続税評価額の差が大きい物件
- 流動性が高く換金しやすい立地・規模
- 利回りが高く“保有しながらキャッシュフローも生み出せる”物件
2-1. 時価と相続税評価額の差が大きい物件
時価(※)と評価額に大きな乖離がある物件ほど、評価圧縮効果が高まります。
路線価や倍率地域の設定により、物件によって評価割引率が異なるためです。
例えば都心の築浅中古マンションでは、時価と評価額に20%前後の差が出ることがあります。地域や築年数、建物性能も評価ギャップに影響するため、個別に評価額シミュレーションを行いましょう。
こうした物件を選定することで、より大きな節税効果を狙える可能性があります。
※不動産の時価とは、その物件が市場で取引が成立している価格のことです。
2-2. 流動性が高く換金しやすい立地・規模
相続発生時に迅速に現金化できる物件を選ぶことで、安心につながります。
駅近ワンルームマンションなど需要が高い小規模物件は、短期間での売却が比較的容易となる傾向があります。
一方、郊外の大型倉庫や山林などは買手が限られ、換金に数年かかるケースもあります。
売却手数料や仲介期間も考慮し、納税期限(相続発生から10ヶ月)に間に合う換金性を重視しましょう。
流動性を優先することで、相続後の資金繰りリスクを大幅に抑えられるでしょう。
2-3. 利回りが高く“保有しながらキャッシュフローも生み出せる”物件
利回りが高い投資用物件は、家賃収入で相続税納付資金を賄いやすくなります。
継続的なキャッシュフローがあると、換金せずとも納税資金を確保できるからです。
利回り5%以上の地方RCマンションは、運用しながら負担なく収益を得やすい例です。
ただし高利回り物件は修繕費や管理コストが上昇しやすいため、将来の維持費も勘案することが重要です。
収益性と維持コストのバランスを検討し、有効なキャッシュフローを見込める物件を選びましょう。
3. 不動産活用時の注意点
一方で、不動産による節税にはリスクや留意点も伴います。
以下で主要なポイントを整理します。
- 購入は本人の意思で行う必要性
- 明らかな節税目的と判定される場合のリスク
- 利回りが低い物件に関する維持費の課題
- 流動性の低い物件による資金確保の難しさ
- 遺産分割を考慮しない資産構成が引き起こすトラブル
以下でそれぞれ解説します。
3-1. 購入は本人の意思で行う必要性
不動産取得は節税のみを目的とせず、本人による合理的な投資判断が必要です。
なぜなら、節税目的だけと判断されると、税務署に否認される恐れがあるためです。
相続開始前3年以内に購入した物件は特例が適用されない場合がある点も注意しましょう。収益予測や投資計画を事前に作成し、自らの意思で選定した証拠を残すことが有効です。
専門家の助言を得て、意思決定プロセスを記録することでリスクを低減できます。
3-2. 明らかな節税目的と判定される場合のリスク
節税のみを目的とした取引は、税務署による精査・否認のリスクが高まります。
特に収益性が乏しい物件を相続税対策のためだけに取得すると、調査対象になりやすいからです。
そのため取得前に収益試算やリスク分析を実施し、節税以外の合理的根拠を示すことが重要となります。書類上だけの取引と判断されると特例適用が取り消されるかもしれないので、注意しましょう。
投資価値を有する物件選びを心がけ、節税以外の効果も担保しましょう。
3-3. 利回りが低い物件に関する維持費の課題
利回り2%前後の築古戸建てなどは、維持費負担が収益を上回る場合があります。
固定資産税や修繕費用は年数経過とともに増大する傾向があるからです。
具体例として、老朽化した給排水設備の修繕で数百万円単位の出費が生じるケースもあります。将来の維持管理計画を立案し、長期的なコストを含めた収支シミュレーションを行いましょう。
維持費負担を見越した物件選定が、安定的な節税対策に繋がります。
3-4. 流動性の低い物件による資金確保の難しさ
需要が限られる工業用地や山林は、売却までに数年を要することがあります。
なぜなら、相続発生から納税期限の10ヶ月以内に資金を確保する必要があるためです。
納税猶予制度も活用可能ですが、要件や保証が必要となるケースが多い点に注意しましょう。換金性の高い物件と組み合わせ、総合的な資産配分を検討することが大切です。
流動性リスクを抑えることで、相続後の資金繰り不安を軽減できます。
3-5. 遺産分割を考慮しない資産構成が引き起こすトラブル
不動産は共有持分での分割が難しく、相続人間で評価額算定や管理方法でもめやすいです。
共有名義の山林や賃貸ビルをめぐって、売却や管理方針で紛争が発生する事例があります。
事前に遺言書や信託を活用し、分割方法を明示しておくとトラブルを未然に防げます。指定分割や共有持分の買い取り方法を決めておくことで、相続手続きが円滑になります。
分割対策を講じることが、スムーズな相続実現に繋がるでしょう。
4. まとめ
不動産を活用することで、時価と評価額のギャップや賃貸評価減、借入併用による純資産圧縮といった三つの仕組みを駆使して相続税を大きく圧縮できます。
適切な物件選びでは、評価ギャップが大きく流動性・利回りに優れるものを選ぶことが重要です。
一方で、節税目的のみでは否認リスクや維持費負担、遺産分割トラブルなどの留意点もあります。
購入時には本人の合理的意思や投資計画を明確にし、専門家の助言を得てリスク管理を徹底しましょう。こうした準備を踏まえれば、不動産は有力な相続税対策手段となるでしょう。
ファーストパートナーズ・グループでは、お客様のニーズに寄り添い不動産のお悩みに関するサポートをしております。不動産を利用した相続税対策について、お客様の状況を鑑みながら、的確にアドバイスいたします。
これを機に一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はこちらから。
